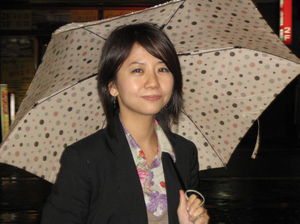「ガンダーラ映画祭」や「背徳映画祭」など、最近はインディーズ映画の特集上映が盛んに行われ、そうしたイベントの中から傑出した作品が出てくることもしばしばです。今回取り上げる「桃まつりpresents真夜中の宴」は、そもそも映画美学校の同期だった女性たちが開いた上映会から始まった企画。2度目に当たる今回はメンバーを増強し、上映規模も拡大しての開催となります。参加しているのは瀬々敬久監督の『ユダ』や『泪壺』などの脚本家・佐藤有記、エロス番長シリーズの一編『ともしび』の監督・吉田良子、前作『犬を撃つ』がカンヌ映画祭シネ・フォンダシオン部門に招待された木村有理子などの精鋭ぞろい。というわけで、前回からの中心メンバーであり、普段はユーロスペースで映画製作を担当している大野敦子さんに「桃まつり」の見所を伺いながら、映画界に生きる女性の本音を探ってみました。
――大野さんはユーロスペースで働いてるそうですが、どんな仕事をしてるんですか。
普段は製作を担当していて、最近では松井良彦監督の『どこに行くの?』やレオス・カラックスの短編(オムニバス『TOKYO!』の一篇)に関わっています。
――そもそも映画を意識するようになったきっかけはなんだったんですか。
元々、映画には一観客として接してたんです。大学を出た後、一般企業に就職したんですけど、たまたま映画館でイメージフォーラムのチラシを見て夏期講習に通ったりしていて。それが終わった頃にちょうど美学校の募集があったので応募したという感じなんです。みんなで一緒に何かを作るというのが面白かったんですね。
――美学校にはコアな映画好きが集まっていたと思いますが、違和感はなかったですか。
わたしは二期生だったんですけど、一期生には美学校のような場所を待ち望んでいた人たちが多かったらしくて、講師からは「それに比べておまえらはなんだ。映画を観ていないし、志は低いし」と散々言われました(笑)。もちろんたくさん映画を観ている人もいたんですが、そんな空気だったのであまり違和感はなかったですね。
――美学校で大きな出会いなんかはありましたか。
直接ではないんですが、当時は講師の塩田(明彦)さんが『どこまでもいこう』を撮ったり、青山(真治)さんが『ユリイカ』を撮ったりする前後の時期だったので校内に熱気がありましたね。生徒たちにも「次は俺だ」みたいな高揚感はあったと思います。
――それからユーロスペースに入った経緯はどんな感じだったんでしょう。
今回『daughters』という作品を撮っている木村有理子が、卒業制作で撮った『犬を撃つ』がカンヌのシネ・フォンダシオン部門に招待されて。それは美学校としても初めてのことだったので、英語ができるという理由だけでわたしもお手伝いとして付いていったんですね(笑)。そこでユーロの社長の堀越と知り合って、いろいろとお世話になったんです。わたし自身、当時の仕事に限界を感じていて、映画のことが面白くなっていた時期だったので、堀越に相談してみたら「うちに来れば?」ということになって。
『granite』 大野敦子
――入社当初から製作担当だったんですか。
入った当時は部署そのものがない状態で、個人的には事務的なアシスタントをするのかと思ってたんです。ただ、堀越は製作にも興味を持っていて、ジャン=ピエール・リモザンの『TOKYO EYES』やダニエル・シュミットの『書かれた顔』など、日本で外国人監督の映画を製作していたんですね。それで入社後しばらくしてから、オリヴィエ・アサヤスが日本で撮りたがってるという話があって、それならおまえがやれ、と言われまして。それが『DEMONLOVER』という作品ですね。当時は会社が渋谷にあったんですけど、美学校の地下に部屋をもらって一人でそこに通ってました(笑)。
――ユーロの製作部を立ち上げた形になるんですね。
でも、いまだに一人しかいないんですけどね(笑)。
――現場を直接仕切ることもあるんですか。
それは規模によりますね。例えば冨永昌敬監督の『コンナオトナノオンナノコ』では、車の運転から何からやりました。予算の大きな作品は制作のプロにお任せして、わたしは現場に行っても役に立たないんですけど(笑)。
――男社会の業界に入っていくことの苦労は感じませんでしたか。
やっぱり体力勝負なところがあるので、一制作部として入ったら辛かったと思います。わたしは少し外れた立場だったので、まだ楽ではありましたけど。ただ、男性顔負けの体力でがんばってる女性の方もいるので一概には言えないですね。体力面以外では、女性ゆえの苦労というのはないと思います。
――逆に利点はなかったですか。
ないですね。例えば女性的なきめ細やかさなんかは、わたしにはないほうなんです。それを求められると困ってしまう。むしろ業界の男性は女性に優しくしてくれていると思いますよ。それは甘く見られているということと表裏ではあると思いますけど。
――表現者としての部分についても伺いたいんですが、大野さんは今回監督として二本撮っていますよね。作家として、女性の強みや弱みは何だと思いますか。
それは観てくれた方に聴きたいですね。今回『桃まつり』の感想としては、「女性が撮っているのに、こうも女性を描かないのか」ということをすごく言われたんです。恋愛もないし、なんでこんなに女らしくないんだと。ただ敢えて言えば、今の二十代後半から三十代の女性の撮りたいものが恋愛ではないというのが現実なんだろうと思います。
――『桃まつり』の企画が立ち上がるまでの経緯を教えてください。
今回参加している木村有理子、笹田留美、竹本直美、深雪の四人はわたしと美学校の同期で、誕生会仲間なんです(笑)。十人くらいのメンバーで、卒業してからもそれぞれの誕生日に集まるということをずっとやっていて。そのうち、これだけ美学校の卒業生がいるんだから誕生会以外のことをしようということになって、去年の三月に五作品で『桃祭』という上映会をやったんですね。そのときは美学校の第一試写室と第二試写室を開けて一回ずつ上映したんですが、両方とも満員になって。それでユーロ支配人の北條にも観てもらったら、うちでやってみたらどうかという話になったんです。
――今回の『桃まつり』はメンバーも増やして上映規模も大きくなりますよね。せっかく女性監督が集まったんだから「女」を強調していこうという話にはならなかったんですか。
それはなかったですねぇ(笑)。そもそも女らしさなんてないだろうと思っている人たちが集まってるってこともあるんですけど、一方で、女が集まっても結局こんな感じだよっていう気持ちもあります。今回のチラシにしても、もっとかわいいものにも出来たと思うんですけど、お酒を飲みながら鍋をつつきあってる写真を使ったのは、それが女の現実だというニュアンスがあったりもするんですね。
桃まつりのチラシ
――たしかに色気はないですね…(笑)。ということは今回、方向性をつけたり、全体を統括するような立場の人はいなかったということですか。
内容に口を出すことはしませんでした。やっぱり自主映画として監督自身がプロデューサーであるという基本は守りたかったんです。あらかじめ決めていたのは、二十分くらいの尺で、上映形態はDV-CAMになるっていうことだけで、あとは内容も撮影期間も予算も、まったく好きなようにやってもらいました。
――今回新たに参加した監督はやっぱり誕生会仲間なんですか。
そこは広げました(笑)。前回やってみて、あまりにも作品の傾向が似てたんですね。それはお互いに親しすぎるのが原因かもしれないということで、新しい血を入れようと。結果的にはみんな美学校の卒業生になってしまったんですけど、吉田良子や佐藤有記とは仕事のうえで以前から面識がありまして。片桐絵梨子に関しては「面白い人がいるよ」と人に紹介してもらったんです。
――結果的に前回より作品の幅は広がりましたか。
それがやっぱり同じことを指摘されてるんです。女らしくないということもそうですけど、みんな何かひとつの出来事があってそれをどう克服していくかということを描いているんですね。
――では改めて伺いますが、『桃まつり』の見所はなんでしょう。
こんな真面目なことを言っていいのかわかりませんけど(笑)、人はどう生きていけばいいのか、どう現実と対峙したらいいのかという主題を、それぞれ自分なりの方法で模索した作品群になっていると思います。
――そういう社会性のある目線で作品を作るのは自分の女性的な問題が解決していないからなんでしょうか。例えば漫画家の岡崎京子や魚喃キリコのように女性性を前面に出してドラマを構築していくという方法もありますよね。
監督ごとに違うと思うんですが、わたしの場合はその問題が片付いていないから目を向けたくないんでしょうね。ただ木村はずっと女性目線の作品を撮ってきた人で、元々は『桃まつり』も彼女ありきで生まれた企画なんですよ。そういう部分をもっと売りにしていけばいいのかもしれませんが、スタンスの取り方は様々だと思うんです。例えば吉田は以前『ともしび』という、女性の執拗な片思いの話を撮りましたけど、今回彼女がどうして男性主体で撮ったのかといえば、そういうものを撮ったことがなかったからという理由なんです。
『きつね大回転』片桐絵梨子
――でも、女性らしさという以前に男性が主人公になっている作品が多いですね。
そうなんです。わたし自身は男性主人公で二本撮ったんですが、それはそのほうが客観的になれるというか…。だから「おまえに男の何がわかるんだ」と言われれば、「いや、わかりません」という感じなんですけど。
――それは男性を描きたいというより、自分の中にあるものを男性に投影して描きたいということですよね。でも、観た人の反応としては女らしくないということになってしまう?
それも人によってなんですが、例えば塩田さんには自主映画でこんなにたくさんのしっかりとした作品ができるんだと驚いていただけました。
――『桃まつり』の今後の展開は考えてますか。
できれば毎年やっていきたいと思っています。毎年三月には女性監督の短編が上映されるらしいという評判を作るところから始めて、将来的には長篇を製作できるシステムを作っていきたいですね。
――女性が集まると大変な面もあるんじゃないかと思うんですが、ドロドロしたものはないんですか(笑)。
ありますよ(笑)。ある程度はみんな大人なんですけど、やっぱり監督だから我が強いんですね。時には喧嘩をして罵詈雑言を浴びせ合うこともあります。それでも自分の作品を劇場にかけたいという思いをみんなが持っているので何かあっても一つになれる。あと、劇場の意見を加味するとこうだからってわたしが説明すると、納得していなくても最終的には首を縦に振ってもらえます(笑)。
――必然的に大野さんが統括的な立場になるわけですね。そうすると、陰でこそっと言われたり?(笑)
あるかもしれませんが、でもそれは知らないふりをして(笑)。あとは時々お酒を飲んで暴れます。そうするとみんなが「大野さん、こんなに壊れちゃった」と優しくしてくれる(笑)。ただ、知り合いの方が低予算の映画できちんと宣伝までやっているのを見てきたので、自分にもできると思っちゃったんですよね。諍いが起きると思ってもいませんでしたし…。でも、監督も映画を作るだけじゃなくて、自分の作品を人に届けるために、宣伝も含めてもっと戦略的に考えていいと思いますね。それはきっと後々の財産になりますから。
――作家が自分たちの力で配給や宣伝もできるようになれば、もっと業界の風通しがよくなるでしょうね。
作家が直接宣伝をしたほうがいいのかは場合によるでしょうけど、「どう撮るか」だけでなく「どう見せるか」を意識的に考えていけたらいいのかなと。そうしていけるようにがんばります。
『emerger』佐藤有記
(取材・構成:平澤竹識/構成協力:大嶋 絢子)
『桃まつり 真夜中の宴』
3月29日(土)~4月11日(金)連日21時10分より渋谷ユーロスペースにて
〈上映作品〉
『明日のかえり路』 監督・脚本 竹本直美
『座って!座って!』 監督・脚本 笹田留美
『emerger』 監督・脚本 佐藤有記
『感じぬ渇きと』 監督・脚本 大野敦子
『きつね大回転』 監督・脚本 片桐絵梨子
『daughters』 監督・脚本 木村有理子
『あしたのむこうがわ』 監督・脚本 竹本直美
『希望』 監督・脚本 深雪
『たんぽぽ』 監督・脚本 深雪
『granite』 監督・脚本 大野敦子
『みかこのブルース』 監督・脚本 青山あゆみ
※日によって上映作品が異なりますので、詳細は下記のURLにてご確認下さい