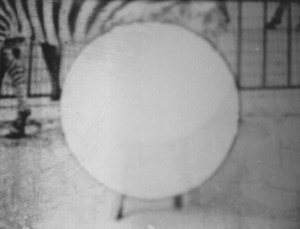飯村隆彦はドナルド・リチー、大林宣彦、高林陽一とならび日本の実験映画の草分けである。他の三人がその後、文学研究者や劇映画の監督など、実験映像以外の道へ進んでいったのに対し、飯村隆彦は六〇年代以降もビデオ・アート、メディアアート、映像インスタレーションを発表し続け、一貫して実験映像の道を探求している。国内での評価だけではなく、海外の映画祭、美術館、大学、シネマテークにおいて数知れぬほどの上映、パフォーマンス、講演活動をこなしている。日本が生んだ世界的な実験映像作家として、海外の研究者たちからも熱い視線を送られている。
飯村隆彦は六〇年代に盛んであった赤瀬川原平、小杉武久、土方巽らネオ・ダダ文化のなかから颯爽と登場し、詩と美術への関心に裏打ちされた実験映画を制作していった。六〇年代半ばに、アメリカのアンダーグラウンド映画の洗礼を浴びて、本場のニューヨークへ渡った。オノ・ヨーコ、ナム・ジュン・パイク、フルクサスのメンバーら前衛芸術家と親交を結び、ジョナス・メカス、アンディ・ウォーホル、スタン・ブラッケージ、ジャック・スミスら世界的な実験映画作家たちと交流して、アンダーグラウンド・シーンのなかで自身の実験映画を次々に発表していった。七〇年代以降はビデオ・アート、メディアアートの主導的な作家として活動し、ニューヨークと東京を拠点としながら文字通り世界中で上映、パフォーマンス、講演活動を精力的に行っている。
(聞き手・構成/金子遊 写真/nashino 協力/原將人、岩崎孝正)
六〇年代前半の実験映画
――飯村隆彦さんの著書『実験映像のために』や『パリ=東京 映画日記』によれば、飯村さんは大学を出た後、就職をせずに、ニュース映画会社でアルバイトを経験し、PR映画の助監督をやっていたそうですね。映画のプロではなく、個人的で芸術的な映画へと向かわれたきっかけは何かあったのですか。
僕が慶應高校へ通っていた頃、ダダイストの高橋新吉や萩原恭次郎の詩に興味がありました。そこにはただの活字ではなく、視覚的に詩を見せるという行為があったのです。自分でも詩を書いていました。最初の詩は「目」というタイトルで、飛び降り自殺をテーマにしたものでした。ページの上に「目」というタイトルがあって、その下は全くの空白で、ページの一番下に「目」が横向きに倒れている、これは漢字の数字の四で、死を意味したものです。普通の詩ではなく、具体詩(コンクレート・ポエム)のように視覚的な効果(と音読による意味の転換)に興味を覚えたのです。高校のときは日吉キャンパスに通っていましたが、隣接する大学の社研について行って、共産党の山村工作隊に加わって田植作業を手伝ったこともあります。
慶應の大学生になってからは視覚的なものに興味が出、廃物彫刻やアクション・ペインティング(フランス語ではアンフォルメル)など、ネオ・ダダや新しい潮流の現代美術に興味を持ちました。実際に三点ほど絵画作品を描いてみたこともあります。僕は詩や現代美術の方から映画や映像へ向かったので、最初から物語的な映画の方向には興味がなかったのです。
――まだ六〇年代前半ですと、ヨーロッパの前衛映画やアメリカの実験映画は日本に紹介されてなかったんですよね。
まだ紹介されてない。ただニュースでは六二、三年に、ニューヨークにアンダーグラウンド映画が、アンディ・ウォーホルがエンパイア・ステイト・ビルを延々と撮ったとかそういう話題が入ってきて、友人のドナルド・リチーが向こうの雑誌を見せてくれた。
――社会へ出るまでは映画を撮っていなかったのですか。
ええ。映画に携わるようになったのは、大学を卒業してからです。記録映画作家・野田新吉さんの紹介で、月給一万円で日映新社という朝日新聞系のニュース映画やPR映画を製作している会社に入りました。演出部の雑用をこなすアシスタントの仕事でした。最初から会社の映画には何の幻想もなかったので、自分で八ミリフィルムのカメラと映写機を買い、好きなものを撮りはじめたのが六二年のことです。
最初から実験映画に興味を持っていました。六〇年代前後では、まだヨーロッパの昔の前衛映画や当時のアメリカのアンダーグラウンド映画は日本に紹介されていませんが、雑誌などを通じてニュースとしての情報は入っていました。実験映画は僕にとって詩と絵画の中間にある、もう一つのメディアだと思えたんですね。
『くず』
――最初に撮った『くず』(62、レギュラー八ミリ、一六ミリブローアップ、一二分、音楽:小杉武久)[DVD『60s Experiments』に収録]という映画には、何かお手本にできるような実験映画があったわけではないんですね
六二年に撮った『くず』が、一種の映画詩ですけど、処女作にあたります。特にお手本となるような前衛映画や実験映画はありませんが、映画よりは当時の美術シーンで流行していたジャンクアートの影響はありました。『くず』は東京の晴海海岸に転がる、無数の廃棄物や動物の死骸にカメラを向けた作品です。それと同時に、死んでしまった物体を、映像のなかで甦らせるというアニミズムのような観点もあります。今で言えば、エコロジーのようなものです。晴海埠頭へは七日間ほど通い、八ミリフィルムで撮影して編集しました。『くず』には子供たちが何人も登場しますが、あれは晴海周辺にあったバタヤ部落の子供たちで、海岸に打ち捨てられた廃棄物、動物の死骸、部落の子供たちをただ単に風景として記録するのではなく、その風景のなかにカメラを持って「自分もジャンクにすぎない」という観点から、その一部として参加していくということを考えていました。
エルモのカメラを使っていましたが、レギュラー八ミリで、カメラはゼンマイ式だったので、一カットは最大で一五秒くらいしか撮れませんでした。映画のなかでは、海岸の砂浜を走ったり、フレームのなかに自分の足を出したり、廃棄物を引っ張って動かしてみたり、砂に埋もれたズボンを立ち上がる人間のように見せかけたりしました。それらが一見、シュールにみえますが、私にとっての参加の方法であり、映像にとってそれらは「もの」として立ち現れます。シュールレアリスティックな幻想を使うのではなく、現実のなかにある「もの」たちの唄を歌いあげようとしました。
――詩という観点と同時に、飯村さんの特徴は同時代の美術シーンに強く反応しているところですね。
六二年には身のまわりでハイレッドセンターの様々な前衛的な美術運動やハプニングなどが起きていました。当時のネオ・ダダというと赤瀬川原平、荒川修作、篠原有司男らが参加していた「読売アンデパンダン展」もありました。僕自身はそこには参加しなかったけど、よく彼らとは会って、特に美術家の中西夏之と仲良くなりました。彼とは『ONAN』(62、一六ミリ、モノクロ、七分、音楽:刃根康尚)という映画を撮っています。映画のなかで本人が出演し、彼が作った卵のオブジェを使いました。これは六四年のブリュッセル国際実験映画祭で、特別賞をもらいました。
中西がたまたま現像所で、アメリカの子供のための性教育映画のぼろぼろのフィルムを見つけて、僕に見せてくれました。これを『視姦について』(62、モノクロ、十分、サイレント)[DVD『60s Experiments』に収録]という映画に二人で仕立て上げました。教育映画のフィルムに直接パンチで穴を開け、悪戯書きをし、フィルムをスクラッチして色々な手法を加えていきました。まだ日本でファウンド・フッテージの利用などなかった時に、ダダ的な手法を映画でやったわけです。また、パンチで開けた穴のところに、日本のポルノ写真を入れて陰部を黒く塗られたものを瞬間挿入して、サブリミナルの実験もしています。それが僕のパンチとね、ポジネガの関係にあるわけだけど、当時の国家権力による検閲へのプロテスト行動という意味合いをこめました。つまり、一度検閲された写真を、こちらで検閲し直す、パンチの穴を開けるという行為です。また、植物が勾配するセックスにあたる部分や、生物が細胞分裂するシーンなど、顕微鏡の丸い穴にあわせて性に関わるところにパンチで穴を開けています。六二年は、いろいろアイデアがあふれて、五、六本撮っています。
『視姦について』
――その年には、男女の性行為をどこか写っているか分からないほどクローズ・アップして撮った『LOVE』(62、レギュラー八ミリ、一六ミリブローアップ、モノクロ、一五分、音楽:オノ・ヨーコ)[DVD『60s Experiments』に収録]という映画も作っていますね。この映画を気に入ったオノ・ヨーコが、ニューヨークへ行ってジョナス・メカスへ見せたら絶賛されて、「飯村の『Love』は美しさとオリジナリティと、ありきたりのニセのシュール・レアリズムの映像ではない映画詩において際立っている。詩的で、肉体の感覚的な冒険であり、流れるようで、直載であり、美しい」とメカスが書いたそうですね。
僕はまだクロースアップ・レンズが買えなかったので、虫眼鏡を自分で取りつけて撮影しました。一センチ四方の範囲の身体の一部が、スクリーンに拡大されます。人間の身体というものを即物的に扱い、具体的な映像だけれど同時に、抽象的な表現になります。
もう一つには、前に実際に経験してるんですけど、完全なヌードだと、検閲に引っかかり、陰部が写っていると現像所からフィルムが返ってこないのです。そんな権限どこにあるんだと思うんですけど。しかし、あれだけクローズ・アップしてしまえば、実際に何が写っているか分からないという戦術でした。それ以上に男女の区別なく、部分と部分が自由に出会い、交わるという、アンドレ・ブルトンの「自由な結合」の詩に同感していました。局所信仰のポルノには反対で、あえて実際の性行為のシーンはありません。後年、ニューヨークへ渡ってから八ミリフィルムでは上映しづらいという問題があり、一六ミリフィルムへブローアップしました。その結果、劇的なまでに黒と白のコントラストが強調されて、粒子が荒れるというグラフィカルな効果が出ました。
――オノ・ヨーコさんが『LOVE』のサウンドトラックにノイズ音のような音楽をつけていますね。
その頃、オノ・ヨーコが草月ホールでジョン・ケージたちとパフォーマンス(当時はハプニング)をやるということで、帰国したんですね。そのときにサイレントだったこの作品を見て、一度で彼女は気に入り、ニューヨークで上映した方がいいと言ってくれました。当時、彼女は渋谷のマンションの一三階にキョウコちゃんという娘と暮らしていました。そこへ訪ねていき、音をつけてくれるように頼んだら、その部屋の窓からいきなりマイクを突き出して風の音やノイズを録音したんです。「これ、あなたにあげる」って言って。ところどころ、自動車のサイレンとかが入ってるんですけどね。それが『LOVE』に使われている不可思議なノイズ音のようなサウンドトラックとなりました。
『LOVE』
ネオ・ダダと暗黒舞踏
――当時のネオ・ダダの美術運動というと、あらゆる作品を同列に扱う「読売アンデパンダン展」が開かれていた頃ですね。また飯村さんは六〇年代前半に大林宣彦、高林陽一、ドナルド・リチー、石崎浩一郎と「ジャパン・フィルム・アンデパンダン」を組織しています。これらの経緯を教えてください。またゲリラ的な自主上映をしていたそうですが、具体的にはどのような上映形態だったのですか。
荻窪にVAN映画研究所があって、若手の日大出身の映画人の溜まり場になっており、僕が住んでいる高円寺からも自転車で行ける距離でした。そこに赤瀬川、中西、高松次郎、僕なんかも出入りしていました。まだ赤瀬川の千円札事件の前です。中西とはアンデパンダンのときに会って、銀座で道路清掃をするハプニングなど、彼のパフォーマンスを見ていました。自分のアート作品としては「読売アンデパンダン」でドキュメントした『ダダ’62』(六二年)という映画を撮っています。イベントの紹介や記録というよりは、全編をクローズ・アップで撮っていき、オブジェとオブジェの境目が分からなくなるように撮影した作品です。八ミリフィルムでそのような映画を撮ることが、僕のネオ・ダダに対する参加の方法でした。
六四年に紀伊国屋ホールで日本最初の実験映画祭「ジャパン・フィルム・アンデパンダン」を組織し、赤瀬川、刀根、大林、リチーなども参加しました。二分映画という形で作品を募集し、誰でも参加できるようにしました。当時の読書新聞に「一切の商業的・政治的なものに束縛されない自由な映画」という「自由な映画を!」というマニフェストを発表し、大林宣彦、ドナルド・リチー、高林陽一、佐藤重臣、石崎浩一郎も参加したのです。足立正生も顔を出していました。そういうグループを作って映画祭を開催したのですが、私の渡米もあって、一回だけで終りました。
――その頃の飯村さんには『シネ・ダンス[映像舞踏]:土方巽暗黒舞踏 ―あんま―』(63-2001、モノクロ、八ミリ、サイレント、二〇分、完成版)[DVD『CINE DANCE: The Butoh of Tatsumi Hijikata』に収録]というドキュメント作品がありますね。出演は土方巽、大野一雄、大野慶人、笠井叡といった舞踏界の豪華な顔ぶれです。これはいわゆる記録映像ではなく、飯村作品としか呼びようのない作品になっています。
暗黒舞踏の創始者である土方巽さんの暗黒舞踏に興味を持って、稽古場へ何度か出入りしました。六三年に草月会館ホールで上演された歴史的な舞台「あんま」と、六五年に日本青年会館ホールで上演された「バラ色ダンス」の舞台を撮影したんです。土方巽からどのように、どの部分を撮ってほしいとか、事前の打ち合わせは一切ありませんでした。僕が好きなように撮ったんです。
一つの狙いとしては、単なる記録的なドキュメンタリーにするのではなく、僕自身も暗黒舞踏の作品のなかに参加するということでした。これは後年「シネ・ダンス」という映画とダンスを結合した言葉で呼ぶようになりました。外側から撮るという客観的な記録に対する疑いがありましたから、その場で自分の目が見ることができたものだけを撮り、自分の視線を記録するという方法を試みたんです。ダンサーにかなり近づいて撮るので、その身体は非常に抽象化されて、カメラを手の延長として使ったので、これを「カメラ・マッサージ」と名づけました。そのすぐ後に、マーシャル・マクルーハンが「カメラは身体の延長である」と言いました。カメラは目の延長であると同時に手の延長でもあるという意味ですが、今思えば、そのような考え方を先取りしていた映画でもあったのではないか、と思っています。
『シネダンス』
――ジョナス・メカスがリビング・シアターを撮るために、一六ミリの機材を背負って舞台にあがって撮影した『営倉』という映画が六三年です。ほぼそれと同時期にあたりますね。実際に舞台にあがって、お客さんに観られながら撮影している、と。
それに比べたら、『あんま』のとき僕は八ミリのカメラを持って、草月会館ホールのステージの上にあがっていたので身軽でした。カメラを振り回して撮っていたから、観客席から見れば、ダンサーの一人のように見えたことでしょう。ゼンマイ式のカメラでワンカットが一五秒しか撮れないので、常にゼンマイを巻き直していました。踊る舞踏家たちは、僕のために待ってくれないので、追っかけました。最初から舞台上で起きるすべてを記録するのは不可能だと分かっていましたから、僕が舞台に参加した身体の痕跡が映像として残ればいいという考えでした。カット割りやアクション繋ぎは全く無視して撮っています。いわばカメラによるコレオグラフィー(振付)ということで、自分自身がダンスをしながら、映像作品を撮るというパフォーマンスの一種です。
『あんま』の後半のシーンでは、大野一雄さんの着物のシーンと洋服のシーンが激しいカメラの運動のなかで、行ったり来たりフラッシュバックする構成になっています。それは舞台にはない映画的な効果として作り出したものです。いわゆる劇映画のフラッシュバックではない、物語形式ではない形でその技法を使用しました。「あんま」という舞踏作品は、東北の非常に貧しく、生活の厳しい村落を舞台にしています。大野一雄さんが演じるのは、村落共同体のアウトサイダーの人物で、彼は少年たちがボールに興じるなかで阿呆を演じます。そして村祭りの舞踏を通してのみ、村の人々の仲間に入れてもらえるという物語なのです。この村祭りのシーンでは、本物の三味線弾きが演奏し、大衆的な歌謡も使われました。しかし、この舞台の音楽については何も記録していません。最初のバージョンは六三年に完成しましたが、後に未使用のフィルムを大幅に追加して完成版を二〇〇一年に作りました。
――六五年には『シネ・ダンス[映像舞踏]:土方巽暗黒舞踏 バラ色ダンス』(65-2001、モノクロ、八ミリ、サイレント、一三分、完成版))[DVD『CINE DANCE: The Butoh of Tatsumi Hijikata』に収録]を作っていますね。出演は同じく土方巽、大野一雄、大野慶人、石井満隆、笠井叡など錚々たる顔ぶれです。
『バラ色ダンス』は『あんま』の二年後に撮影しました。土方は映画撮影について無頓着でした。『バラ色ダンス』は日本青年館という広いホールで行なわれ、舞台の上に大きな二階席があったので、二階でロングショットを撮ったり、舞台に戻ってきて近接して撮ったり、撮影に関しては結構忙しかったです。ひとりで八ミリフィルムを回しながら、ロングとアップが行ったり来たりするようにしたのです。ただ、露出過剰などの技術的な失敗もありましたが、それも使っています。
――それはお一人で撮っていたんですね。舞台の見せ場は土方さん、大野さんのデュエット、ゲイダンスですね。
『バラ色ダンス』は『あんま』よりもずっと西洋的な舞台で、『あんま』のような物語性もなかった。振付に関しても、より西洋的なモダンダンスに近いものでした。『バラ色ダンス』の見せ場の一つが、土方巽と大野一雄のデュエットであるゲイ・ダンスです。二人は親密に絡み合いながら、野蛮なゲイと優しいゲイをそれぞれ表現していました。この頃の暗黒舞踏の舞台は、写真は随分と撮られていましたが、映画は誰も撮っておらず、映像記録としてもこの二本しかないので非常に貴重なものとなりました。
『あんま』『バラ色ダンス』は度々、細江英公が少し前に撮った『臍と原爆』(六二年)や、また、僕の提唱した「シネ・ダンス」は、マヤ・デレンがダンスと映画撮影を結合しようとした行為と比べられることもあります。確かに細江の『臍と原爆』は見ていましたが、彼はほとんどのショットを静止的なカメラで撮影しました。それが僕のシネ・ダンスという方法論との大きな違いです。同じことはマヤ・デレンについても言えて、当時は彼女の映画はまだ見ることができなかったのですが、彼女がカメラを振り付けるというときも固定したカメラで撮影しています。それは撮影者の身体の運動の痕跡が映る、僕のシネ・ダンスやカメラ・マッサージとは違うと思っています。シネ・ダンスは単にひとつの撮影技法という以上に、イメージと身体を一体化する考えに基づいており、最近の映像身体論をほぼ半世紀以前に試みたと言えるのではないしょうか。
六〇年代後半のニューヨーク
――飯村さんは六六年にニューヨークへ渡米します。当時の海外では『くず』『ai(love)』『視姦について』『リリパット王国舞踏会』[いずれもDVD『60s Experiments』に収録]など、ご自身の初期作品はどのように評価されましたか。
当時、まだ僕の実験映画は誰も取り上げないというか、日本ではほとんど評価されていませんでした。そこでオノ・ヨーコが『LOVE』をニューヨークへ持っていってくれて、ジョナス・メカスに見せたのです。彼が僕の映画を見てヴィレッジ・ヴォイス誌やフィルム・カルチャー誌で映画評を書いてくれたので、非常に勇気づけられました。それでニューヨークに行きたいという気にもなったんです。僕の先輩に写真家の金坂健二さんがいて、紹介されて応募してみたら、六六年にボストンのハーバード大学の夏季の国際セミナーに招待されました。それが初渡米です。このセミナーは芸術分野に限らず、教育やジャーナリズムなど広い分野から人間を集めていました。僕は自分の実験映画を持って行ったのですが、性的にきわどい描写が多いので学生には見せられないと言われ、先生たちだけの会で見せました。
その渡米のときに『LOVE』をイェール大学で上映したことがありました。その頃のイェールはまだ男子校で、興奮した学生たちがこの映画を見せろと言って押し寄せたんです。翌日のニューヨーク・タイムスの記事は、こんな風に報じました。ぼくもびっくりしたんですけど。「昨夜興奮した暴徒のために、イェール大学のアートギャラリーで日本の実験映画の上映が妨害された。警察の発表によると暴徒の数は千人にものぼる。上映は二〇時半からの予定だったが、一時間前にはギャラリーに通じるストリートの前に群集が集まりはじめた。二〇時頃には群集の騒ぎは大きくなり、通りに人があふれだした。タクシーがクラクションを鳴らして通ると、人々はブーイングで応じますます殺気立つ。何組かの学生グループは、道を開けろ、ポルノ映画だぞ、と叫ぶ。二〇時四五分に五人の警官がドアの前に並び、誰もビルの中に入れないようにした。通りは大混乱になった。紙くず、ビン、ビール缶が辺りに飛び散った」と。
――大変、好評を博したようですね(笑)。その後、ニューヨークに着いて最初の上映会は、タイムズスクエア近くの地下劇場で、ジョナス・メカスが主催するシネマテークにて、『くず』『いろ』『LOVE』などの八ミリ作品、一六ミリ作品の『リリパット王国舞踏会』を本場ニューヨークの観客たちに見せたのですね。観客席は満席で、八万円もの上映料をもらって驚いたということですが、これはどのような経緯で上映に至ったのですか?
ニューヨークに着いて、すぐにジョナス・メカスに会いにフィルムメーカーズ・シネマテークを訪ねました。彼はシネマテークを主宰すると同時に、モギリも一緒にやってました。すでにメカスは僕の『LOVE』をオノ・ヨーコの紹介で見ていましたが、その他の作品も見てもらいました。そして、彼が「近いうちに個展をやろう」と言って握手をしました。最初は八ミリでやったんですけど、八ミリへの差別があるどころか、積極的に取り上げていました。その上映の告知がヴィレッジ・ヴォイス誌などにも出たので、彼らからしたら名前を聞いたことのない僕のような作家の映画会に多くの観衆が集まってくれたのです。それが最初です。
――その後はずっとニューヨークで活動していたのですか。
そこでジャパン・ソサエティの客員芸術家として二年半を過ごしました。それから本場のアンダーグラウンド映画をたくさん見て、自分自身の作品も多少は撮影しました。そういえば、こんなことがありました。最初ニューヨークでイースト・ヴィレッジのロフトに住んでいるオノ・ヨーコを訪ねたんです。そうしたら、彼女が玄関の前にしゃがみこんでいるので、どうしたのかと尋ねました。娘のキョウコちゃんのミルクを買う金がないので、日本領事館にかけあったところ、領事館の人がミルクを持ってきてくれることになり、それを待っているんだと言いました。どうしてオノさんみたいな金持ちの娘が、ミルクにも困るような生活をしているのか、と驚きましたね。後で聞いたら、親のあらゆる援助を断って、そんな生活をしていたということです。その頃のオノ・ヨーコはフルクサスという伝説的なパフォーマンス・グループの初期からのメンバーでしたが、そんな芸術活動を続けるために、ヴェジタリアン専用のレストランでウェイトレスをしていたこともあったそうです。
ニューヨークで最初に撮った映画は『ニューヨーク・シーン』(67)です。これは当時の八ミリフィルムで五〇フィートのワンロールで一本の映画と撮るというコンセプトでした。なるべくファインダーを覗かずに、目とは別のところで、身体で映像を撮るということを試したのですが、あまりうまくいきませんでしたが、この経験から『フィルムメーカース』[DVD『Filmmakers』に収録](67-68)ができました。
『フィルムメーカース』
――『フィルムメーカース』は実験映画史の観点から見ても、非常に重要な記録映像であると言えます。
ええ。『ニューヨーク・シーン』の後で『フィルムメーカース』を撮りました。アメリカの代表的なアンダーグラウンド映画作家たち、すなわちアンディ・ウォーホル、ジャック・スミス、ジョナス・メカス、スタン・ヴァンダービーク、スタン・ブラッケージ、そして自分自身を撮りました。一人の作家のポートレートをそれぞれ二百フィ-ト(約五分)で撮るというコンセプトで、無編集のままで完成しました。各アーティストを撮るときに、その映画作家のスタイルや特徴の模倣を試みました。たとえば、ヴァンダービークのときは三六〇度のパンを含む、カメラワークを試み、メカスのときはカメラのスピードを実験的に変えてコマ撮りを多用し、ウォーホルの場合は長撮りのあとにカット替わりの白いフラッシュの使用をするといった具合です。これらはインサイダー・ジョークですが、彼らの撮影スタイルを紹介する効果もあると思います。
ウォーホルに関しては実際に会わずに、というのも、ウォーホルは自分の作品がすべてであり、その背後には何もないと言っていたので、本人を撮影するより、言葉通りに彼の映画を映画館へ行って再撮影しました。また、スタン・ブラッケージを撮るために、コロラドの山奥にある彼の家へ訪ねました。もちろん『ドッグ・スター・マン』(61-64)を見ていたので、あの映画と本当に同じ風景のなかに住んでいるのだと実感しました。森、山、窓、子供たち、ドンキーなどのブラッケージ映画的なキーワードを撮りました。サウンドトラックは全編に、英語のレッスンのように、画面に見えるものの単語を発音しました。言葉による異化作用です。
――スタン・ヴァンダービークにも会いに行ったんですね。
スタン・ヴァンダービークの撮影では、マンハッタンから車で二時間くらい離れた、芸術家たちが住んでいるコミュニティを訪ねました。彼は家の敷地に大きなドーム状の「ムービードローム」を自分で建てて、そこで色々な多元映写を試していました。後の科学万博などで使われたドームでの先駆的な実験で、スタン・ヴァンダービークは数台の映写機を設置して、機械仕掛けではなく、その間を行ったり来たりしながら手動で操作し、ドーム状のスクリーンへ自在に映像を投影していました。観客は彼と一緒にドームのなかに入り、座ってみたり寝転んでみたりしました。特にシナリオがあるというわけでもなく、大、小の映像が半ば即興的に演奏されて上映されました。これはニューヨーク映画祭でそのようなツアーが行なわれ、参加しました。
ジャック・スミスを撮影したときは、彼のロフトを訪問しました。私の『フィルムメーカース』の映像にあるように、部屋のなかに大きな祭壇があり、ガラクタを集めたようなオブジェが並んでいて、アラビアンナイトのような衣装と花が飾ってあり、火をつけた蝋燭が複数立っていました。OKをもらって撮ったんですが、「ボクにも少し残して!」と蚊の泣くような声で言われました。常に自分の世界に陶酔しているようなところがありましたが、声をかければ、ストレートに反応は返ってきました。また、『ニューヨーク・シーン』では彼の代表作である『燃え上がる生物』を撮影したそのロフトで、その映画を上映しながら、ジャック・スミスにスクリーンの前に座ってもらい撮影しました。彼は居心地が悪そうで、頭を動かして落ち着きがなかったけれど、忍耐強い人でした。
※本稿を作成するにあたり、武蔵野美術大学イメージライブラリーの多大な協力を得ましたので、ここに御礼を記しておきます。(金子)
※このインタビューは、2011年1月初旬に刊行予定の『個人映画のつくり方』(アーツアンドクラフツ刊)に収録される予定です。
http://www.webarts.co.jp/book/menu/forthcoming.htm
Blog(Japanese) http://takaiimura.sblo.jp/
Blog(English) http://takahikoiimua.sblo.jp/
HP(English&Japanese) http://www.takaiimura.com/
※尚、このインタービュウに出てくる映画とビデオの作品の多くはDVDでお求めになれます。
<DVD作品のリスト>
http://www.takaiimura.com/salej.html
<ご購入出来るお店>
NADiff a/p/a/r/t 恵比寿本店
NADiff x10 写真美術館・恵比寿
NADiff contemporary 東京都現代美術館・木場
gallery 5 オペラシティ・ギャラリー・初台
NADiff愛知 愛知芸術センター・名古屋
NTTインターコミュニケーション・センター・新宿
<ネット通信販売> ※★は@に変換してご入力ください
「art media K.Y.(アムキー)」 http://amky.org/japanese/store/index.html
メール amky★amky.org
「ユーフォニック」Plexus http://www.d-plexus.com/
「imageF/イメージ エフ」 http://www.imagef.jp/ 畠山順メール jun★imagef.jp
「飯村映像研究所」http://www.takaiimura.com/ メール iimura★gol.com