孤高の天才
映画作家・原將人。彼は1968年
麻布高校の在学中、16ミリ映画『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を撮影・完成し、第1回東京フィルムフェスティバル グランプリ、ATG賞を同時受賞。新聞にも大々的に取りあげられ、自主映画・8ミリ映画ブームの火をつけた。それから40余年。自身が「映画になること」を夢見て、
古事記に登場する日本最古の
天皇神話に自身を重ねながら、日本列島を重層的に撮った『初国之知所
天皇』(73)。
松尾芭蕉と
曾良の
奥の細道の旅を、父と子の私的な
ロードムービーに置き換えた『百代の過客』(93)など、孤高の傑作群を創出し続けている。
09年からは、
8ミリフィルム映写機による三面マルチ画面に、電子ピアノとゲストミュージシャンによる生演奏を重ねる独自の形態で『マテリアル&メ
モリーズ』の上映運動を全国で展開。10年からは有志による「原將人全映画上映」という1年がかりの企画上映もスタート。ニューアルバムのレコーディング、原將人ドキュメンタリーの制作が開始されるなど、身辺が賑やかになっている。劇映画第2弾『天翔る(あまかける)』の公開も控える作家に、自由に映画半生を語ってもらった。
(聞き手・構成・写真/金子遊 構成協力/春日洋一郎 協力/
若木康輔)
 『東京戦争戦後秘話』
『東京戦争戦後秘話』
――それでは『東京戦争戦後秘話』の話に入りましょう。1969年の10・21国際
反戦デーの新宿周辺における街頭闘争にて、『自己表出史・
早川義夫編』の撮影をしていた原さんとカメラマンの亘真幸さんが、同じく撮影クルーを出していた
大島渚さんと創造社の方々に出くわした話を聞きました。それ以前には、
大島渚さんとは面識はあったんですか。
大島さんとは、ぼくの方はお顔を拝見したことはありましたけど、面識というほどではなくて、その時に初めて話しました。
足立正生さんは、よく知ってました。その時も「原クン」って声をかけてきてくれましたから。清順共闘で面識があったんです。
――清順共闘と言うと
鈴木清順さんの…?
そうです。
鈴木清順さんの日活首切り問題に端を発した、
鈴木清順問題共闘会議、いわゆる清順共闘です。ぼくもメンバーだったシネクラブ研究会の100回記念で、
鈴木清順の連続上映を計画したんです。その前にも
草月会館の
シネマテークが
鈴木清順特集をやっていたので、日活の会社が
鈴木清順にこんなに多くの映画ファンがいて、人気があるのだということを認識したようなのです。そういう人気を背景に、清順さんも自分のスタイルでいこうということで『殺しの烙印』を撮った。当時の日活社長・
堀久作さんが『殺しの烙印』を見て「こんな訳の分からない映画を撮るなんて」と呆れたのと、シネクラブ研究会が日活に
鈴木清順全作品上映のオファーをした時期が重なり、堀さんが「映画青年向きの芸術映画を撮っている監督はうちにはいらない」ということで清順さんを首にした。それが
鈴木清順問題共闘会議のはじまりです。
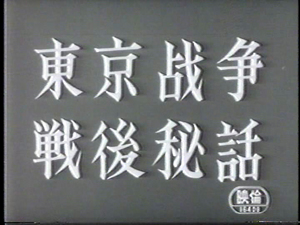
――『殺しの烙印』の公開年は67年ですが、その一連のできごとは68年のことですか。
そうです。68年です。『殺しの烙印』は67年で、シネクラブ研究会が『殺しの烙印』を含む全作品の上映をオファーしたのが68年なんです。それでぼくが新宿で大島さんや足立さんと会ったのが69年です。新宿で大島さんたちと会ったことと、清順共闘とは『東京戦争戦後秘話』と密接な関係があるんで整理しますと、まず、68年の10.21、国際
反戦デーがあります。ぼくは直接には目撃してはいないんですが、10.21の新宿の街頭闘争で、戦後初めて
騒乱罪が適用されました。新宿っていうのは、
ベトナム戦争の真っただ中、背後に立川基地や
横田基地を控え、
北ベトナムを爆撃する飛行機に燃料や弾薬を補給する貨物列車の
ターミナル駅だったから、
国鉄、まだJRじゃなかったから
国鉄、つまり
日本国有鉄道の労働者たちも国際
反戦デーの呼びかけに呼応して、
ストライキにうってでたし、西口広場では
ベトナム反戦のフォークゲリラで盛り上がっていて、野次馬たちを巻き込んで、
ベトナム反戦をアピールするには最適な場所だったんで、
学生運動の各
セクトも最大の戦闘拠点としていたわけです。そんなこんなで、68年には盛り上がって、
騒乱罪が適用された。
そのときの証拠物件として、
国学院の映画研究会が、公安に、撮影していたフィルムを差し押さえられるという事件があった。
鈴木清順問題共闘会議では、その頃に起きている映画のトピックスを全部取り上げていたから、
国学院の映研の連中を呼んで話を聞いて、もし問題があるようなら清順共闘もそれに対して動こうとした。ぼくもちょうど『おかしさに彩られた悲しみのバラード』で賞をもらった頃だったので、行きましたよ。たしか、その時に大島さんもいたと記憶しています。でも、直接話をする機会はなかった。そういうことがあって、その1年後の69年の10.21の新宿で
大島渚さんと会い、その数ヵ月後に大島さんから映画の脚本を書かないかというオファーを貰ったときに、ぼくはその
国学院映研の事件のようなエピソードを入れ込んだ『東京战争戦後秘話』のア
イデアを思いついたんです。

――当時の政治運動的な背景を知らないと、なかなか理解しにくい部分があるんですね。
それなら、もう少し、付け加えておきますと、69年の10.21は前年以上に過激な街頭闘争が行われたんです。
全学連の
セクトのなかには、機動隊と対決するにあたって角材や火炎瓶だけでなく、パイプ爆弾と呼ばれる火薬を詰めた新型爆弾を用意していた
セクトもあった。
赤軍派なんですけどね。10.21と11月の佐藤首相の訪米阻止までを、東京戦争、大阪戦争と称して、漢字で書くと戦争の戦は、占うに戈(ほこ)ですね、街頭で国家権力と闘うということです。でも、もうここまでくると
武装蜂起と
紙一重になってしまい、大量の逮捕者を出すし、民衆からの支持も失って、実際、10月と11月で三千人を超える逮捕者を出して、運動は急速に収束してしまう。
そして69年の佐藤首相の訪米で
日米安全保障条約の自動延長は決まってしまい、後から考えると、もうここで70年の
安保闘争は終わっていたんです。70年になると
大阪万博が始まり、もう時代の雰囲気はすっかり変わっていた。3月には関西の
赤軍派による
日航の
よど号ハイジャック事件があり、運動は、あとは
赤軍派の海外拠点設立と、国内では
連合赤軍の
あさま山荘事件に至るわけです。だから、こういうことを踏まえて、60年安保を闘った大島さんは70年安保に対するレクイエムとして『東京戦争戦後秘話』という題名を付けたんだと思います。

――原さんとグループ・ポジポジの人たちが、大島さんの創造社へ一緒に呼ばれたんですよね。
その経緯を少し詳しく話しますと、まず69年の3月に、僕と福間雄三くんで第1回全国高校映画連盟の上映会を開催した。第2回は70年の3月に
上野高校でやった。そのときに、後藤和夫くんたちのグループ・ポジポジが『天地衰弱説』という映画を上映し、すごく評判が良かった。そのとき賞はなかったんだけど、上映が終った後の拍手の大きさで、自分たちの映画が観客賞だったと彼らは言っていました。そのときに、1年先輩による映画の特別上映というような形で、ぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』も上映された。
大島渚さんと脚本家の
田村孟さんが『天地衰弱説』とぼくの映画の両方を見て、ちょっと相談があるから創造社に来てくれと言ったんですよね。
大島瑛子さんから連絡をもらって、赤坂の創造社に出向きました。「映画で遺書を残した男の物語」という主題が提示されて、その主題に添って何か話を考えてみてくれということでした。ぼくは、起承転結があって、映画で遺書を残して死ぬというよりは、最初に「映画で遺書を残した男」がいたということから始めたら面白いのではないかと閃いた。でも、そこからその謎を解いていくのでは、
倒叙法ということだけで、結局同じ事になってしまうので、「映画で遺書を残した男」がいたことを現実か幻想かというドラマのレベルの、それを超えたところ、まあメタレベルっていうのか、
ロブ=グリエのような
ヌーヴォー・ロマンの叙述のレベルっていうのかな、そういうところに置けばどうかと、そんなことを話したら、面白そうだから10枚くらい書いてきてくれないかということになったんです。後で、僕が脚本担当で、グループ・ポジポジが出演することに決まりました。
 『東京戦争戦後秘話』と創造社
『東京戦争戦後秘話』と創造社
――それで『東京戦争戦後秘話』のシナリオを、原さんと
佐々木守さんで書くことになったんですね。ホン書きはどうやって進めていったんですか。
1週間くらいかけて、ぼくと佐々木さんで書いていった。ぼくが持っているア
イデアを話し、それを守さんが咀嚼して脚本的にはこうしよう、ああしようと言う。そして、それを実際に書き下ろすのはぼくの仕事でした。
佐々木守さんは当時ものすごい売れっ子の脚本家だったので、テレビのシナリオを書きすぎて利き手が腱鞘炎だったんです。ぼくにとって、ラッキーだったのは守さんが箱を作らずにシナリオを書くタイプだったことですね、いや、実際は箱を作って構成を立ててから書くこともできたんでしょうが、ぼくに合わせてくれていたのかな。
――1週間で書き上げたんですか?
第1稿で110枚くらいだったんで、180枚にまで膨らまそうということで、それからさらに2週間くらいかけて完成稿にまでもっていきました。守さんはテレビをやっているから、どんどん具体的なシーンとセリフが出て来る。でも実際に、書いていくのはぼくなので、納得しないと書かない。そこで理屈をこねて、
フッサールや
メルロ=ポンティまで持ち出して、自分のア
イデアを通そうとする。守さんはそれを根気よく噛み砕いてくれる。後で、
キネ旬に「くそ生意気なガキに哲学講義されて発狂寸前だった」と書いてはいますがね。守さんは面倒見のいいお兄さんでした。まあ、僕にとってはすごくいいペースで作業できました。

――
大島渚さんは、いろいろな才能の人間を取り入れるのが上手い方ですよね。
そうですね。大島さんがぼくと守さんの資質を見抜いていたんでしょう。二人を組ませたら面白いって。そういう意味では、大島さんは、監督らしい監督です、本当に。映画に関わるスタッフを全員、野球でいえば、選手みたいな感じで扱い、それぞれのポジションで力を発揮させる。そういう映画監督ですね。
佐々木守さんはすごく頭の柔らかい人でした。それから、美術の戸田重昌さんも本当に凄い人だと思いました。創造社ではシナリオ・ライターがロケハンに付き合うのが慣例で、守さんはテレビの方で忙しくて行けなかったんで、ぼくが戸田さんとロケハンに同行しました。
戸田さんは、メインとして使う部屋を決めたら、その場でガラス屋を呼んで、窓の擦りガラスを全部透明なガラスに替えてしまった。結局、実際の撮影のときはその窓を取り払ってしまったけれど、そうやって具体的に自分のイメージを確認していくという作業を即座にやって、それを積み重ねていくんです。これはちょっと、すごいことだと思いました。ロケハンの段階で美術的な仕込みを始めちゃえば後が楽と言うか、スタート
ダッシュ決めて好タイム記録してしまうみたいなことできるでしょ、低予算でも。それと、『東京戦争戦後秘話』では脚本の他に予告編の監督もやりました。

――じゃあ、現場にも立ち会っていたんですか?
いやいや、基本的には、現場にいませんでした。まあ、現場に行くと見学だけじゃ済まなくなりそうだし、「大島さん、こうした方がいいんじゃないですか!」って言いたい時、それを我慢するのもすごくつらいものがあるんで。だから、撮影現場には、予告編用のカット撮らせてもらう時だけ行こうって自己限定して、予告編用に撮りたいときに現場へ行き、チーフ助手に頼んで別撮りさせてもらいました。編集は浦岡敬一さんです。浦岡さんとの編集作業は大変勉強になりました。ここを1コマ足したり引いたりするとどうなるか、というのを全部編集しながら逐一見せてくれました。本当に編集の特別授業を受けていた感じですよ。論理的だけど感覚的な人。
小林正樹監督の『
東京裁判』は浦岡さんがいなければできなかったと思います。

――予告編の監督をやったときの雰囲気をもう少し教えてください。
「キタロウ、原クンが予告編用に撮りたいって言うからカメラ回してやってくれ」と撮影監督の成島東一郎さんが言うと、チーフ助手のキタロウこと手持ちの得意な兼松さんは、嬉々としてやってくれました。だから、予告編用の撮影はすべてキタロウさんによる手持ちでした。時間に余裕がある時は、大島さんにも出演してもらい、その日の撮影現場をドキュメンタリー風に再現したりもした。例えばですね、映画の登場人物の元木と泰子が絡みながら「あいつ」がいるの、いないの、というやり取りをしたシーンの撮影後という設定で、元木役の後藤くんに大島さんへ質問をぶつけてもらいました。「監督!あいつって、いたんですか?いなかったんですか?」と。大島さんには「いるんだよ!そして、いないんだ!」と、解釈を拒絶する回答を頼みました。
現実か虚構か、現実か幻想か、という二項対立を超えた多層性をアピールしたかったんですけど、まあ、大島さんは、それをどう使うのか、どういう予告編を作るのかなんて、あまり深く追求しないで、役者に徹して、ぼくが言う通りやってくれて、ああ、任されてるなって感じがして感動的だったですね。音楽を担当した
武満徹さんが創造社に登場した頃には、ぼくはその予告編の編集に取り掛かっていました。クランク・アップする頃には予告編を劇場で流さなければならなかったんです。そこでぼくは武満さんに、予告編にはテーマ曲の他に「弦楽のためのレクイエム」も使わせてほしいとお願いしたんです。

――そのテーマ曲っていうのが、先ほどおっしゃっていた、原さんがリク
エストした
ビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォー
エヴァー」にそっくりな曲だったんですね。
そうです。そうです。それで「弦楽のためのレクイエム」っていうのは、本当に正統的な映画音楽っていう感じで大好きな曲だったんですけど、武満さんが映画音楽の師であった
早坂文雄さんを追悼した曲だったんですね。つい最近知ったことですが。
――『東京戦争戦後秘話』の中で「東京風景戦争」という、何の変哲もない住宅街を撮った風景映画が映画内映画として差し挟まれています。つまり、遺書としての映画ですね。それを学生たちが見ながら「あいつは何でこんなものを撮っていたんだ」と話し合うシーンがあります。あれは、原さんのア
イデアですか。
そうですね。あれはぼくがア
イデアを出して、佐々木さんも当時、
足立正生さんたちと『略称 連続射殺魔』という風景映画を撮っていたときだったので「ああ、いいんじゃない」と自然にまとまっていったのだと思います。でも、実際に撮影されたものは、撮影した成島さんの美意識が絡んでしまっているんで、かなり違うという違和感を感じて、それが後でぼくが自分で撮ることになる『初国知所之
天皇』(はつくに
しらすめらみこと)へと繋がっていきましたね。

――ラストシーンがおもしろいですね。映画の冒頭で飛び降りた男の死体の横に足が映っている。良く考えると、ぐるりと円環構造でまた冒頭に戻ってしまうような迷宮性を持っている。誰がこの映画を撮影したのかわからない、幻想なのか現実なのか分からないという構造ですね。
あれは、最後に大島さんがそういう構造にしたんです。ぼくと佐々木さんが書いた脚本には、そこまで書き込んではなかった。ぼくと佐々木さんが書いたシナリオでは次のようになっています。
○路上
象一の死体が転がっている。
カメラを握った手の下から血が流れ出してくる。
群衆がその回りに集まってくる。
と、何者とも知れぬ手が伸びて、象一の手のカメラをひったくるようにして消える。
 以上の写真は『東京戦争戦後秘話』
以上の写真は『東京戦争戦後秘話』
このカメラをひったくるところを、大島さんは何者かの足元を入れ込んで撮っている。その足元は死体の象一と全く同じ黒いスニーカーなんですね。すると、何者かは象一かもしれない。いや、象一なんでしょう。そこに、遠慮がちにではあるが「映画で遺書を残して死んだ男の物語」という
大島渚によって提示された主題に即して書かれたシナリオを、
大島渚自身の手でもう一度ひっくり返した形跡があるんです。
それと、DVDになってから見返して驚いたのは、車がらみの撮影をほとんどぶっつけ本番でやっているみたいなんですけど、迫力というか勢いがあるなと思いました。電車の線路の中に入ってしまうシーンとか、みんなぶっつけ本番で撮っていたんでしょう。それでも、実際のところ、ぼくはそれにも関わらず、やっぱり
大島渚といえども、脚本通りにしか映画を撮らないのかなという疑問を感じていた。それは
松本俊夫さんの『
薔薇の葬列』に助監督として入ったときと同じ印象です。撮影の現場では、結局、段取りをこなしていくという形でしか撮影することができないのか、と疑問に思った。それは或る予算のなかで、スタッフを組んで撮る以上、どう仕様もないことなんですが、自分で撮る時は何とかそうではない撮り方を模索しようと思いました。それは、商品としてのパッケージのなかに、そこからはみ出る力と運動をいかに詰め込むことができるのか、という二律背反した問いかけのわけで、ぼくにとっては永遠の課題ですね。それに答えるために今も走り続けています。
『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)
――『東京戦争戦後秘話』の制作が70年の夏に終り、翌年の71年からついに『初国知所之
天皇』の撮影をはじめるんですよね。
『東京戦争戦後秘話』のなかの風景映画では、さっきも言ったように、成島東一郎さんの撮り方に不満があったんです。成島さんは風景を自分の美意識を入れて、かっちりしたプロフェッショナルな撮り方でやっている。でも、風景というのは、そこに偶然存在するぼくたちにとって、よそよそしいものでなければならない、
存在論と言うか、不在証明と言うか、わりと広い画で撮らないといけないと思った。そういう風景として、古代から現代まで歴史そのものを、文明そのものを、虚構だろとか、冗談だろって言えるような視点で日本を見てみようかと思ったんです。
――それと同時に、撮影現場を経験した
松本俊夫や
大島渚の製作プロセスを見て、彼らほどの才人ですら、ベルトコンベアーで製品を組みあげていくように、段取り的に映画を撮っている。そうではない方へ向かいたい、というのがあったんでしょうね。それが原さんの映画評論の言葉でいう、見る=見られるの関係で形成される「映画の肉体」ということでしょうか。文学や演劇と違う、映画らしさとは何なのか。映画だけにしかできない、映画固有のおもしろさとは何か。そのように考えたとき、原さんは反シナリオ中心主義というか「映画の生命」を見つける旅へ出られたわけですよね。
うん、そうですね。ぼくにとって、映画を撮るということは
シャーマニズムです。映画の神様を降ろしてくることなんですね。それが
古事記や
日本書紀の
天孫降臨の神話からインスパイアされることにもなり、
二重写しになって『初国知所之
天皇』を撮る行為になっていったのです。
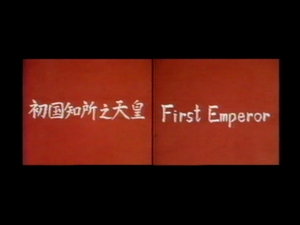
――『初国知所之
天皇』は、もともとは16ミリフィルムによる劇映画の構想だったそうですね。どのような映画になる予定だったんですか。
騎馬民族日本征服説を象徴するような男が、馬で北海道から『
イージー・ライダー』のように、延々と日本列島を南下して、
天孫降臨の神話の謎を解明すべく、鹿児島までやって来るという話です。
騎馬民族日本征服説と
天孫降臨説が、日本列島の風景のなかで、どのようにぶつかるのか、ということを
ロードムービーでやってみようと思った。それはジェイムス・
ジョイスの小説「
ユリシーズ」のような世界を、「
古事記」をベースにして日本列島でやるというア
イデアからはじまっています。
だけど、そう考えながら撮影を進め、挫折を繰り返していくうちに、単なる劇映画にするのではなく、自分がカメラを持って全国を回るスタイルの方が、むしろ最初の構想に近いということに気がついた。よりドキュメンタリーに近いというか、日記映画のようなスタイルになっていった。それで、16ミリフィルムで撮影した劇映画的な部分は、日記映画スタイルのなかに引用するだけに留めて、基本的には
8ミリフィルムのカメラで、自分が旅して見ているものを撮影するという形で完成することになりました。もし、あのまま16ミリフィルムの劇映画として完成していたら、
ジム・ジャームッシュの『デッドマン』みたいな映画になっていたでしょうね。
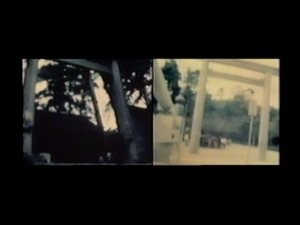
――当時は新聞でも紹介されて、話題になったんですよね。高校を卒業したばかりの天才映画少年が、北海道から馬を連れて旅をしながら映画撮影を続けていると。旅の佳境は、やはり歴史の古い京都、奈良、出雲あたりでしょうか。最初から九州を南下して鹿児島まで行く計画だったんですか?
コンセプトとしては、最終的には宮崎、鹿児島まで行き、
天孫降臨の謎を解明するというのがありましたが、そこまでシナリオは詰めてなかった。ブロック、ブロックで組み立てながら連作風に続けていこうと思っていました。それで、北海道の後は、東北で
芭蕉と一緒に旅することを考えていたところで挫折しましたね。
芭蕉の「
奥の細道」をなぞるような旅というかね。結局、この映画では東北へは行かなかったんだけど、それは後に『百代の過客』(93)という映画で、ぼく自身と中学生の息子の2人旅を、
芭蕉と
曾良になぞらえて撮った
ロードムービーへと繋がって行くことになりました。

――原さんには、神話や文学をベースにする発想がありますよね。それと同時に『初国知所之
天皇』で面白いのは、一種のロケーション・ハンティングという行為が延長されて、そのまま映画になっているところがあります。最初、「私が私の映画の主人公になってしまった」と当惑気味なナレーションが入りますが、旅をしている途中で「おれこそが初国知所之
天皇だ」とそれが確信に変わる瞬間があります。あれが凄い。また、劇映画の構想のときに北海道から馬を借りて日本列島を南下しようとしたという挿話がありますね。資金的に行き詰まってその馬を返してしまい、さて撮影を続けるというときに、
8ミリフィルムによる
ロードムービーへ転換するという発想になったのでしょうか。
もちろん客観的にはそうなんですけど、途中で
8ミリフィルムで撮りきれるという確信が湧きましたね。迷ってるときは「ああでもない、こうでもない」と頭で迷いますけど、カメラを日常的に手にしていると、「これで映画作品として成立する」というような確信というか、閃きのようなものが、カメラを持つ手とカメラポジションを探す足を通じて、身体的に天から降りてきたんですね。
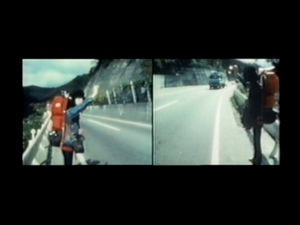
――『初国知所之
天皇』はもの凄い映画であり、インディペンデント・個人映画系の映画としては唯一、「
キネマ旬報」のオールタイム・ベスト100の1本に入っている伝説の作品です。この映画が凄いことの要素の1つとして、約8時間という上映時間があります。「約」というのは、要するに、8ミリ映写機と16ミリ映写機の2台でマルチ・プロジェクション、スローモーション上映をするので、一定の決められた上映時間はなく、そのときの上映環境によって上映時間が変わる、変えられるということですね。マルチ画面は常にズレを生むわけです。まさに毎回上映される内容が偶然性によって決定づけられ、二度と同じことができないという一回性の上映形態です。
『初国』の場合、やはり、最も画期的だったのが、スローモーション映写の発見なんですよね。撮影したものを一本につないで、映写機で何度も見直したんです。そうしたら、映像が速過ぎちゃって、これは違う、これでは映画として成立しないのではないかと思えてきた。とにかく時間の流れが撮っている時と違う。撮っている時は、ものすごいハイテンションで、意識も身体も撮ることに集中してしまっているんで、時間の流れが滅茶苦茶ゆっくりなんです。それを再現できない限り、映画にはならないなと思えたんです。そこで、とにかくスローモーションにするレバーを入れてみたら、まさに、撮っている時の時間の流れがそのスローモーションだったんです。この映画はこのように上映されるために撮られたんだ、ということが初めて理解できたんです。

――日記映画のスタイルの中で、わりとスローモーションにするっていうのはありますよね。
ジョナス・メカスもそうですし、
かわなかのぶひろさんもそうだし。手持ちのカメラで撮影している風景が、手ブレで、ズレて残像を生み出していく感じが、スローモーションだとはっきりと分かります。イメージが見た目と違う世界になりますよね。その他に『初国』の場合、この列島の風景も私自身の一部だ、私の延長なのだ、という原さんに特有の発想があります。そこから、風景映画を撮ることが自己を撮る行為へとなって行ったのでしょうか。
もう少し逆説的ですけどね。
――逆説的と言いいますと?
その風景のどこにも自分はいない。「いま、ここにいるってことは、たまたま、いま、ここにいるだけで、いま、ここの風景のどこにも自分はいない」ってことです。そして、それは魂の浮遊性につながってくる。可能性としては「私は遍在するのだ、ありとあらゆるところにいるのだ」ということになってくる。その身体の遍在性と魂の浮遊性の二極分解のなかから、日々新たに世界を発見していこうということになるわけ。それがスケージュールによって移動する旅行ではない、「旅」のもたらすものなんです。
芭蕉が言っている「軽み」というものもそういうものではなかったかと思います。風景に向けていたカメラをゆっくり自分の方に向けると、不在証明としての風景から不在証明としての自画像になっていくわけです。
『初国』の旅は、撮影と言っても、30キロのリュックを背負って実家を出て、放浪生活のような旅だったんです。当時は携帯電話もないし、家族とは全く連絡もなかったですね。でも、或る日、風景と自画像を撮影していると、30キロの赤いリュックというのは、戦争のときに中国で歩兵となり、重い背嚢を背負って行軍していた父親だったんだな、ということに気がつく。リュックの赤は日の丸の赤だったんだと気付くわけです。そういう風に世界と家族と自分との絆を発見してしまったということがありました。金沢のくだりですけど。
71年に『初国』のロケハンで北海道へ行ったとき、初めて
ヒッチハイクをしました。それで、ものすごく
ヒッチハイクという行為自体が気に入りました。まあ、道路というのは、近代国家によって敷設されていった鉄道と違って、太古からの移動する身体と浮遊する魂の行き交いを象徴するもので、まさに『初国』のテーマとも符合するものだったんです。そのことに気がつきました。実際、北海道へ行くと、もう
ヒッチハイクしか旅行手段がない。北海道だと車もよく止まってくれるんです。ただ路上で指を立てて車をキャッチするんです。オートバイも停まってくれましたね。これがまた楽しい。
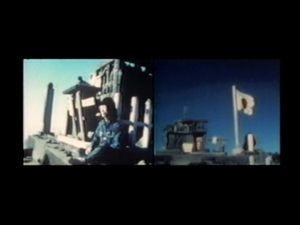 以上の写真は『初国知所之天皇』
以上の写真は『初国知所之天皇』
――『初国』の映画のなかでも、
ヒッチハイクのシーンが多くありますよね。トラックなどに乗せてもらうときに、自分のことを「学生ではなく、映画関係の仕事をしているが、その勉強をかねて旅していると言った方がいい」というナレーションがありますね。
まず、そう言うと車内で自由に撮影できるんです。運ちゃんにカメラを向けても全く気にしない。そうするうちに、食事を奢ってくれるんですよ。とにかく学生というより社会人と言う方が断然受けがよかった。
『東京戦争戦後秘話』
1970年/35mmフィルム/94分/モノクロ
監督:
大島渚 脚本:原正孝(原將人)、
佐々木守 予告編演出/原正孝
『初国知所之天皇』
1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映
監督:原將人
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人(映画作家)インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史 早川義夫編』
原將人公式サイト
【原將人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・
早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原將人監督とゲストによる
トークあり
詳細
http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図
http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★
gmail.com ※★を@にしてご入力ください
 『東京戦争戦後秘話』
――それでは『東京戦争戦後秘話』の話に入りましょう。1969年の10・21国際反戦デーの新宿周辺における街頭闘争にて、『自己表出史・早川義夫編』の撮影をしていた原さんとカメラマンの亘真幸さんが、同じく撮影クルーを出していた大島渚さんと創造社の方々に出くわした話を聞きました。それ以前には、大島渚さんとは面識はあったんですか。
大島さんとは、ぼくの方はお顔を拝見したことはありましたけど、面識というほどではなくて、その時に初めて話しました。足立正生さんは、よく知ってました。その時も「原クン」って声をかけてきてくれましたから。清順共闘で面識があったんです。
――清順共闘と言うと鈴木清順さんの…?
そうです。鈴木清順さんの日活首切り問題に端を発した、鈴木清順問題共闘会議、いわゆる清順共闘です。ぼくもメンバーだったシネクラブ研究会の100回記念で、鈴木清順の連続上映を計画したんです。その前にも草月会館のシネマテークが鈴木清順特集をやっていたので、日活の会社が鈴木清順にこんなに多くの映画ファンがいて、人気があるのだということを認識したようなのです。そういう人気を背景に、清順さんも自分のスタイルでいこうということで『殺しの烙印』を撮った。当時の日活社長・堀久作さんが『殺しの烙印』を見て「こんな訳の分からない映画を撮るなんて」と呆れたのと、シネクラブ研究会が日活に鈴木清順全作品上映のオファーをした時期が重なり、堀さんが「映画青年向きの芸術映画を撮っている監督はうちにはいらない」ということで清順さんを首にした。それが鈴木清順問題共闘会議のはじまりです。
『東京戦争戦後秘話』
――それでは『東京戦争戦後秘話』の話に入りましょう。1969年の10・21国際反戦デーの新宿周辺における街頭闘争にて、『自己表出史・早川義夫編』の撮影をしていた原さんとカメラマンの亘真幸さんが、同じく撮影クルーを出していた大島渚さんと創造社の方々に出くわした話を聞きました。それ以前には、大島渚さんとは面識はあったんですか。
大島さんとは、ぼくの方はお顔を拝見したことはありましたけど、面識というほどではなくて、その時に初めて話しました。足立正生さんは、よく知ってました。その時も「原クン」って声をかけてきてくれましたから。清順共闘で面識があったんです。
――清順共闘と言うと鈴木清順さんの…?
そうです。鈴木清順さんの日活首切り問題に端を発した、鈴木清順問題共闘会議、いわゆる清順共闘です。ぼくもメンバーだったシネクラブ研究会の100回記念で、鈴木清順の連続上映を計画したんです。その前にも草月会館のシネマテークが鈴木清順特集をやっていたので、日活の会社が鈴木清順にこんなに多くの映画ファンがいて、人気があるのだということを認識したようなのです。そういう人気を背景に、清順さんも自分のスタイルでいこうということで『殺しの烙印』を撮った。当時の日活社長・堀久作さんが『殺しの烙印』を見て「こんな訳の分からない映画を撮るなんて」と呆れたのと、シネクラブ研究会が日活に鈴木清順全作品上映のオファーをした時期が重なり、堀さんが「映画青年向きの芸術映画を撮っている監督はうちにはいらない」ということで清順さんを首にした。それが鈴木清順問題共闘会議のはじまりです。
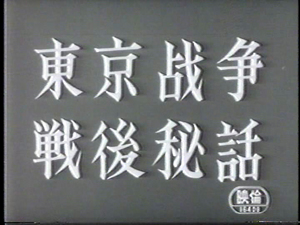 ――『殺しの烙印』の公開年は67年ですが、その一連のできごとは68年のことですか。
そうです。68年です。『殺しの烙印』は67年で、シネクラブ研究会が『殺しの烙印』を含む全作品の上映をオファーしたのが68年なんです。それでぼくが新宿で大島さんや足立さんと会ったのが69年です。新宿で大島さんたちと会ったことと、清順共闘とは『東京戦争戦後秘話』と密接な関係があるんで整理しますと、まず、68年の10.21、国際反戦デーがあります。ぼくは直接には目撃してはいないんですが、10.21の新宿の街頭闘争で、戦後初めて騒乱罪が適用されました。新宿っていうのは、ベトナム戦争の真っただ中、背後に立川基地や横田基地を控え、北ベトナムを爆撃する飛行機に燃料や弾薬を補給する貨物列車のターミナル駅だったから、国鉄、まだJRじゃなかったから国鉄、つまり日本国有鉄道の労働者たちも国際反戦デーの呼びかけに呼応して、ストライキにうってでたし、西口広場ではベトナム反戦のフォークゲリラで盛り上がっていて、野次馬たちを巻き込んで、ベトナム反戦をアピールするには最適な場所だったんで、学生運動の各セクトも最大の戦闘拠点としていたわけです。そんなこんなで、68年には盛り上がって、騒乱罪が適用された。
そのときの証拠物件として、国学院の映画研究会が、公安に、撮影していたフィルムを差し押さえられるという事件があった。鈴木清順問題共闘会議では、その頃に起きている映画のトピックスを全部取り上げていたから、国学院の映研の連中を呼んで話を聞いて、もし問題があるようなら清順共闘もそれに対して動こうとした。ぼくもちょうど『おかしさに彩られた悲しみのバラード』で賞をもらった頃だったので、行きましたよ。たしか、その時に大島さんもいたと記憶しています。でも、直接話をする機会はなかった。そういうことがあって、その1年後の69年の10.21の新宿で大島渚さんと会い、その数ヵ月後に大島さんから映画の脚本を書かないかというオファーを貰ったときに、ぼくはその国学院映研の事件のようなエピソードを入れ込んだ『東京战争戦後秘話』のアイデアを思いついたんです。
――『殺しの烙印』の公開年は67年ですが、その一連のできごとは68年のことですか。
そうです。68年です。『殺しの烙印』は67年で、シネクラブ研究会が『殺しの烙印』を含む全作品の上映をオファーしたのが68年なんです。それでぼくが新宿で大島さんや足立さんと会ったのが69年です。新宿で大島さんたちと会ったことと、清順共闘とは『東京戦争戦後秘話』と密接な関係があるんで整理しますと、まず、68年の10.21、国際反戦デーがあります。ぼくは直接には目撃してはいないんですが、10.21の新宿の街頭闘争で、戦後初めて騒乱罪が適用されました。新宿っていうのは、ベトナム戦争の真っただ中、背後に立川基地や横田基地を控え、北ベトナムを爆撃する飛行機に燃料や弾薬を補給する貨物列車のターミナル駅だったから、国鉄、まだJRじゃなかったから国鉄、つまり日本国有鉄道の労働者たちも国際反戦デーの呼びかけに呼応して、ストライキにうってでたし、西口広場ではベトナム反戦のフォークゲリラで盛り上がっていて、野次馬たちを巻き込んで、ベトナム反戦をアピールするには最適な場所だったんで、学生運動の各セクトも最大の戦闘拠点としていたわけです。そんなこんなで、68年には盛り上がって、騒乱罪が適用された。
そのときの証拠物件として、国学院の映画研究会が、公安に、撮影していたフィルムを差し押さえられるという事件があった。鈴木清順問題共闘会議では、その頃に起きている映画のトピックスを全部取り上げていたから、国学院の映研の連中を呼んで話を聞いて、もし問題があるようなら清順共闘もそれに対して動こうとした。ぼくもちょうど『おかしさに彩られた悲しみのバラード』で賞をもらった頃だったので、行きましたよ。たしか、その時に大島さんもいたと記憶しています。でも、直接話をする機会はなかった。そういうことがあって、その1年後の69年の10.21の新宿で大島渚さんと会い、その数ヵ月後に大島さんから映画の脚本を書かないかというオファーを貰ったときに、ぼくはその国学院映研の事件のようなエピソードを入れ込んだ『東京战争戦後秘話』のアイデアを思いついたんです。
 ――当時の政治運動的な背景を知らないと、なかなか理解しにくい部分があるんですね。
それなら、もう少し、付け加えておきますと、69年の10.21は前年以上に過激な街頭闘争が行われたんです。全学連のセクトのなかには、機動隊と対決するにあたって角材や火炎瓶だけでなく、パイプ爆弾と呼ばれる火薬を詰めた新型爆弾を用意していたセクトもあった。赤軍派なんですけどね。10.21と11月の佐藤首相の訪米阻止までを、東京戦争、大阪戦争と称して、漢字で書くと戦争の戦は、占うに戈(ほこ)ですね、街頭で国家権力と闘うということです。でも、もうここまでくると武装蜂起と紙一重になってしまい、大量の逮捕者を出すし、民衆からの支持も失って、実際、10月と11月で三千人を超える逮捕者を出して、運動は急速に収束してしまう。
そして69年の佐藤首相の訪米で日米安全保障条約の自動延長は決まってしまい、後から考えると、もうここで70年の安保闘争は終わっていたんです。70年になると大阪万博が始まり、もう時代の雰囲気はすっかり変わっていた。3月には関西の赤軍派による日航のよど号ハイジャック事件があり、運動は、あとは赤軍派の海外拠点設立と、国内では連合赤軍のあさま山荘事件に至るわけです。だから、こういうことを踏まえて、60年安保を闘った大島さんは70年安保に対するレクイエムとして『東京戦争戦後秘話』という題名を付けたんだと思います。
――当時の政治運動的な背景を知らないと、なかなか理解しにくい部分があるんですね。
それなら、もう少し、付け加えておきますと、69年の10.21は前年以上に過激な街頭闘争が行われたんです。全学連のセクトのなかには、機動隊と対決するにあたって角材や火炎瓶だけでなく、パイプ爆弾と呼ばれる火薬を詰めた新型爆弾を用意していたセクトもあった。赤軍派なんですけどね。10.21と11月の佐藤首相の訪米阻止までを、東京戦争、大阪戦争と称して、漢字で書くと戦争の戦は、占うに戈(ほこ)ですね、街頭で国家権力と闘うということです。でも、もうここまでくると武装蜂起と紙一重になってしまい、大量の逮捕者を出すし、民衆からの支持も失って、実際、10月と11月で三千人を超える逮捕者を出して、運動は急速に収束してしまう。
そして69年の佐藤首相の訪米で日米安全保障条約の自動延長は決まってしまい、後から考えると、もうここで70年の安保闘争は終わっていたんです。70年になると大阪万博が始まり、もう時代の雰囲気はすっかり変わっていた。3月には関西の赤軍派による日航のよど号ハイジャック事件があり、運動は、あとは赤軍派の海外拠点設立と、国内では連合赤軍のあさま山荘事件に至るわけです。だから、こういうことを踏まえて、60年安保を闘った大島さんは70年安保に対するレクイエムとして『東京戦争戦後秘話』という題名を付けたんだと思います。
 ――原さんとグループ・ポジポジの人たちが、大島さんの創造社へ一緒に呼ばれたんですよね。
その経緯を少し詳しく話しますと、まず69年の3月に、僕と福間雄三くんで第1回全国高校映画連盟の上映会を開催した。第2回は70年の3月に上野高校でやった。そのときに、後藤和夫くんたちのグループ・ポジポジが『天地衰弱説』という映画を上映し、すごく評判が良かった。そのとき賞はなかったんだけど、上映が終った後の拍手の大きさで、自分たちの映画が観客賞だったと彼らは言っていました。そのときに、1年先輩による映画の特別上映というような形で、ぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』も上映された。大島渚さんと脚本家の田村孟さんが『天地衰弱説』とぼくの映画の両方を見て、ちょっと相談があるから創造社に来てくれと言ったんですよね。
大島瑛子さんから連絡をもらって、赤坂の創造社に出向きました。「映画で遺書を残した男の物語」という主題が提示されて、その主題に添って何か話を考えてみてくれということでした。ぼくは、起承転結があって、映画で遺書を残して死ぬというよりは、最初に「映画で遺書を残した男」がいたということから始めたら面白いのではないかと閃いた。でも、そこからその謎を解いていくのでは、倒叙法ということだけで、結局同じ事になってしまうので、「映画で遺書を残した男」がいたことを現実か幻想かというドラマのレベルの、それを超えたところ、まあメタレベルっていうのか、ロブ=グリエのようなヌーヴォー・ロマンの叙述のレベルっていうのかな、そういうところに置けばどうかと、そんなことを話したら、面白そうだから10枚くらい書いてきてくれないかということになったんです。後で、僕が脚本担当で、グループ・ポジポジが出演することに決まりました。
――原さんとグループ・ポジポジの人たちが、大島さんの創造社へ一緒に呼ばれたんですよね。
その経緯を少し詳しく話しますと、まず69年の3月に、僕と福間雄三くんで第1回全国高校映画連盟の上映会を開催した。第2回は70年の3月に上野高校でやった。そのときに、後藤和夫くんたちのグループ・ポジポジが『天地衰弱説』という映画を上映し、すごく評判が良かった。そのとき賞はなかったんだけど、上映が終った後の拍手の大きさで、自分たちの映画が観客賞だったと彼らは言っていました。そのときに、1年先輩による映画の特別上映というような形で、ぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』も上映された。大島渚さんと脚本家の田村孟さんが『天地衰弱説』とぼくの映画の両方を見て、ちょっと相談があるから創造社に来てくれと言ったんですよね。
大島瑛子さんから連絡をもらって、赤坂の創造社に出向きました。「映画で遺書を残した男の物語」という主題が提示されて、その主題に添って何か話を考えてみてくれということでした。ぼくは、起承転結があって、映画で遺書を残して死ぬというよりは、最初に「映画で遺書を残した男」がいたということから始めたら面白いのではないかと閃いた。でも、そこからその謎を解いていくのでは、倒叙法ということだけで、結局同じ事になってしまうので、「映画で遺書を残した男」がいたことを現実か幻想かというドラマのレベルの、それを超えたところ、まあメタレベルっていうのか、ロブ=グリエのようなヌーヴォー・ロマンの叙述のレベルっていうのかな、そういうところに置けばどうかと、そんなことを話したら、面白そうだから10枚くらい書いてきてくれないかということになったんです。後で、僕が脚本担当で、グループ・ポジポジが出演することに決まりました。
 『東京戦争戦後秘話』と創造社
――それで『東京戦争戦後秘話』のシナリオを、原さんと佐々木守さんで書くことになったんですね。ホン書きはどうやって進めていったんですか。
1週間くらいかけて、ぼくと佐々木さんで書いていった。ぼくが持っているアイデアを話し、それを守さんが咀嚼して脚本的にはこうしよう、ああしようと言う。そして、それを実際に書き下ろすのはぼくの仕事でした。佐々木守さんは当時ものすごい売れっ子の脚本家だったので、テレビのシナリオを書きすぎて利き手が腱鞘炎だったんです。ぼくにとって、ラッキーだったのは守さんが箱を作らずにシナリオを書くタイプだったことですね、いや、実際は箱を作って構成を立ててから書くこともできたんでしょうが、ぼくに合わせてくれていたのかな。
――1週間で書き上げたんですか?
第1稿で110枚くらいだったんで、180枚にまで膨らまそうということで、それからさらに2週間くらいかけて完成稿にまでもっていきました。守さんはテレビをやっているから、どんどん具体的なシーンとセリフが出て来る。でも実際に、書いていくのはぼくなので、納得しないと書かない。そこで理屈をこねて、フッサールやメルロ=ポンティまで持ち出して、自分のアイデアを通そうとする。守さんはそれを根気よく噛み砕いてくれる。後で、キネ旬に「くそ生意気なガキに哲学講義されて発狂寸前だった」と書いてはいますがね。守さんは面倒見のいいお兄さんでした。まあ、僕にとってはすごくいいペースで作業できました。
『東京戦争戦後秘話』と創造社
――それで『東京戦争戦後秘話』のシナリオを、原さんと佐々木守さんで書くことになったんですね。ホン書きはどうやって進めていったんですか。
1週間くらいかけて、ぼくと佐々木さんで書いていった。ぼくが持っているアイデアを話し、それを守さんが咀嚼して脚本的にはこうしよう、ああしようと言う。そして、それを実際に書き下ろすのはぼくの仕事でした。佐々木守さんは当時ものすごい売れっ子の脚本家だったので、テレビのシナリオを書きすぎて利き手が腱鞘炎だったんです。ぼくにとって、ラッキーだったのは守さんが箱を作らずにシナリオを書くタイプだったことですね、いや、実際は箱を作って構成を立ててから書くこともできたんでしょうが、ぼくに合わせてくれていたのかな。
――1週間で書き上げたんですか?
第1稿で110枚くらいだったんで、180枚にまで膨らまそうということで、それからさらに2週間くらいかけて完成稿にまでもっていきました。守さんはテレビをやっているから、どんどん具体的なシーンとセリフが出て来る。でも実際に、書いていくのはぼくなので、納得しないと書かない。そこで理屈をこねて、フッサールやメルロ=ポンティまで持ち出して、自分のアイデアを通そうとする。守さんはそれを根気よく噛み砕いてくれる。後で、キネ旬に「くそ生意気なガキに哲学講義されて発狂寸前だった」と書いてはいますがね。守さんは面倒見のいいお兄さんでした。まあ、僕にとってはすごくいいペースで作業できました。
 ――大島渚さんは、いろいろな才能の人間を取り入れるのが上手い方ですよね。
そうですね。大島さんがぼくと守さんの資質を見抜いていたんでしょう。二人を組ませたら面白いって。そういう意味では、大島さんは、監督らしい監督です、本当に。映画に関わるスタッフを全員、野球でいえば、選手みたいな感じで扱い、それぞれのポジションで力を発揮させる。そういう映画監督ですね。佐々木守さんはすごく頭の柔らかい人でした。それから、美術の戸田重昌さんも本当に凄い人だと思いました。創造社ではシナリオ・ライターがロケハンに付き合うのが慣例で、守さんはテレビの方で忙しくて行けなかったんで、ぼくが戸田さんとロケハンに同行しました。
戸田さんは、メインとして使う部屋を決めたら、その場でガラス屋を呼んで、窓の擦りガラスを全部透明なガラスに替えてしまった。結局、実際の撮影のときはその窓を取り払ってしまったけれど、そうやって具体的に自分のイメージを確認していくという作業を即座にやって、それを積み重ねていくんです。これはちょっと、すごいことだと思いました。ロケハンの段階で美術的な仕込みを始めちゃえば後が楽と言うか、スタートダッシュ決めて好タイム記録してしまうみたいなことできるでしょ、低予算でも。それと、『東京戦争戦後秘話』では脚本の他に予告編の監督もやりました。
――大島渚さんは、いろいろな才能の人間を取り入れるのが上手い方ですよね。
そうですね。大島さんがぼくと守さんの資質を見抜いていたんでしょう。二人を組ませたら面白いって。そういう意味では、大島さんは、監督らしい監督です、本当に。映画に関わるスタッフを全員、野球でいえば、選手みたいな感じで扱い、それぞれのポジションで力を発揮させる。そういう映画監督ですね。佐々木守さんはすごく頭の柔らかい人でした。それから、美術の戸田重昌さんも本当に凄い人だと思いました。創造社ではシナリオ・ライターがロケハンに付き合うのが慣例で、守さんはテレビの方で忙しくて行けなかったんで、ぼくが戸田さんとロケハンに同行しました。
戸田さんは、メインとして使う部屋を決めたら、その場でガラス屋を呼んで、窓の擦りガラスを全部透明なガラスに替えてしまった。結局、実際の撮影のときはその窓を取り払ってしまったけれど、そうやって具体的に自分のイメージを確認していくという作業を即座にやって、それを積み重ねていくんです。これはちょっと、すごいことだと思いました。ロケハンの段階で美術的な仕込みを始めちゃえば後が楽と言うか、スタートダッシュ決めて好タイム記録してしまうみたいなことできるでしょ、低予算でも。それと、『東京戦争戦後秘話』では脚本の他に予告編の監督もやりました。
 ――じゃあ、現場にも立ち会っていたんですか?
いやいや、基本的には、現場にいませんでした。まあ、現場に行くと見学だけじゃ済まなくなりそうだし、「大島さん、こうした方がいいんじゃないですか!」って言いたい時、それを我慢するのもすごくつらいものがあるんで。だから、撮影現場には、予告編用のカット撮らせてもらう時だけ行こうって自己限定して、予告編用に撮りたいときに現場へ行き、チーフ助手に頼んで別撮りさせてもらいました。編集は浦岡敬一さんです。浦岡さんとの編集作業は大変勉強になりました。ここを1コマ足したり引いたりするとどうなるか、というのを全部編集しながら逐一見せてくれました。本当に編集の特別授業を受けていた感じですよ。論理的だけど感覚的な人。小林正樹監督の『東京裁判』は浦岡さんがいなければできなかったと思います。
――じゃあ、現場にも立ち会っていたんですか?
いやいや、基本的には、現場にいませんでした。まあ、現場に行くと見学だけじゃ済まなくなりそうだし、「大島さん、こうした方がいいんじゃないですか!」って言いたい時、それを我慢するのもすごくつらいものがあるんで。だから、撮影現場には、予告編用のカット撮らせてもらう時だけ行こうって自己限定して、予告編用に撮りたいときに現場へ行き、チーフ助手に頼んで別撮りさせてもらいました。編集は浦岡敬一さんです。浦岡さんとの編集作業は大変勉強になりました。ここを1コマ足したり引いたりするとどうなるか、というのを全部編集しながら逐一見せてくれました。本当に編集の特別授業を受けていた感じですよ。論理的だけど感覚的な人。小林正樹監督の『東京裁判』は浦岡さんがいなければできなかったと思います。
 ――予告編の監督をやったときの雰囲気をもう少し教えてください。
「キタロウ、原クンが予告編用に撮りたいって言うからカメラ回してやってくれ」と撮影監督の成島東一郎さんが言うと、チーフ助手のキタロウこと手持ちの得意な兼松さんは、嬉々としてやってくれました。だから、予告編用の撮影はすべてキタロウさんによる手持ちでした。時間に余裕がある時は、大島さんにも出演してもらい、その日の撮影現場をドキュメンタリー風に再現したりもした。例えばですね、映画の登場人物の元木と泰子が絡みながら「あいつ」がいるの、いないの、というやり取りをしたシーンの撮影後という設定で、元木役の後藤くんに大島さんへ質問をぶつけてもらいました。「監督!あいつって、いたんですか?いなかったんですか?」と。大島さんには「いるんだよ!そして、いないんだ!」と、解釈を拒絶する回答を頼みました。
現実か虚構か、現実か幻想か、という二項対立を超えた多層性をアピールしたかったんですけど、まあ、大島さんは、それをどう使うのか、どういう予告編を作るのかなんて、あまり深く追求しないで、役者に徹して、ぼくが言う通りやってくれて、ああ、任されてるなって感じがして感動的だったですね。音楽を担当した武満徹さんが創造社に登場した頃には、ぼくはその予告編の編集に取り掛かっていました。クランク・アップする頃には予告編を劇場で流さなければならなかったんです。そこでぼくは武満さんに、予告編にはテーマ曲の他に「弦楽のためのレクイエム」も使わせてほしいとお願いしたんです。
――予告編の監督をやったときの雰囲気をもう少し教えてください。
「キタロウ、原クンが予告編用に撮りたいって言うからカメラ回してやってくれ」と撮影監督の成島東一郎さんが言うと、チーフ助手のキタロウこと手持ちの得意な兼松さんは、嬉々としてやってくれました。だから、予告編用の撮影はすべてキタロウさんによる手持ちでした。時間に余裕がある時は、大島さんにも出演してもらい、その日の撮影現場をドキュメンタリー風に再現したりもした。例えばですね、映画の登場人物の元木と泰子が絡みながら「あいつ」がいるの、いないの、というやり取りをしたシーンの撮影後という設定で、元木役の後藤くんに大島さんへ質問をぶつけてもらいました。「監督!あいつって、いたんですか?いなかったんですか?」と。大島さんには「いるんだよ!そして、いないんだ!」と、解釈を拒絶する回答を頼みました。
現実か虚構か、現実か幻想か、という二項対立を超えた多層性をアピールしたかったんですけど、まあ、大島さんは、それをどう使うのか、どういう予告編を作るのかなんて、あまり深く追求しないで、役者に徹して、ぼくが言う通りやってくれて、ああ、任されてるなって感じがして感動的だったですね。音楽を担当した武満徹さんが創造社に登場した頃には、ぼくはその予告編の編集に取り掛かっていました。クランク・アップする頃には予告編を劇場で流さなければならなかったんです。そこでぼくは武満さんに、予告編にはテーマ曲の他に「弦楽のためのレクイエム」も使わせてほしいとお願いしたんです。
 ――そのテーマ曲っていうのが、先ほどおっしゃっていた、原さんがリクエストしたビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」にそっくりな曲だったんですね。
そうです。そうです。それで「弦楽のためのレクイエム」っていうのは、本当に正統的な映画音楽っていう感じで大好きな曲だったんですけど、武満さんが映画音楽の師であった早坂文雄さんを追悼した曲だったんですね。つい最近知ったことですが。
――『東京戦争戦後秘話』の中で「東京風景戦争」という、何の変哲もない住宅街を撮った風景映画が映画内映画として差し挟まれています。つまり、遺書としての映画ですね。それを学生たちが見ながら「あいつは何でこんなものを撮っていたんだ」と話し合うシーンがあります。あれは、原さんのアイデアですか。
そうですね。あれはぼくがアイデアを出して、佐々木さんも当時、足立正生さんたちと『略称 連続射殺魔』という風景映画を撮っていたときだったので「ああ、いいんじゃない」と自然にまとまっていったのだと思います。でも、実際に撮影されたものは、撮影した成島さんの美意識が絡んでしまっているんで、かなり違うという違和感を感じて、それが後でぼくが自分で撮ることになる『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)へと繋がっていきましたね。
――そのテーマ曲っていうのが、先ほどおっしゃっていた、原さんがリクエストしたビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」にそっくりな曲だったんですね。
そうです。そうです。それで「弦楽のためのレクイエム」っていうのは、本当に正統的な映画音楽っていう感じで大好きな曲だったんですけど、武満さんが映画音楽の師であった早坂文雄さんを追悼した曲だったんですね。つい最近知ったことですが。
――『東京戦争戦後秘話』の中で「東京風景戦争」という、何の変哲もない住宅街を撮った風景映画が映画内映画として差し挟まれています。つまり、遺書としての映画ですね。それを学生たちが見ながら「あいつは何でこんなものを撮っていたんだ」と話し合うシーンがあります。あれは、原さんのアイデアですか。
そうですね。あれはぼくがアイデアを出して、佐々木さんも当時、足立正生さんたちと『略称 連続射殺魔』という風景映画を撮っていたときだったので「ああ、いいんじゃない」と自然にまとまっていったのだと思います。でも、実際に撮影されたものは、撮影した成島さんの美意識が絡んでしまっているんで、かなり違うという違和感を感じて、それが後でぼくが自分で撮ることになる『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)へと繋がっていきましたね。
 ――ラストシーンがおもしろいですね。映画の冒頭で飛び降りた男の死体の横に足が映っている。良く考えると、ぐるりと円環構造でまた冒頭に戻ってしまうような迷宮性を持っている。誰がこの映画を撮影したのかわからない、幻想なのか現実なのか分からないという構造ですね。
あれは、最後に大島さんがそういう構造にしたんです。ぼくと佐々木さんが書いた脚本には、そこまで書き込んではなかった。ぼくと佐々木さんが書いたシナリオでは次のようになっています。
○路上
象一の死体が転がっている。
カメラを握った手の下から血が流れ出してくる。
群衆がその回りに集まってくる。
と、何者とも知れぬ手が伸びて、象一の手のカメラをひったくるようにして消える。
――ラストシーンがおもしろいですね。映画の冒頭で飛び降りた男の死体の横に足が映っている。良く考えると、ぐるりと円環構造でまた冒頭に戻ってしまうような迷宮性を持っている。誰がこの映画を撮影したのかわからない、幻想なのか現実なのか分からないという構造ですね。
あれは、最後に大島さんがそういう構造にしたんです。ぼくと佐々木さんが書いた脚本には、そこまで書き込んではなかった。ぼくと佐々木さんが書いたシナリオでは次のようになっています。
○路上
象一の死体が転がっている。
カメラを握った手の下から血が流れ出してくる。
群衆がその回りに集まってくる。
と、何者とも知れぬ手が伸びて、象一の手のカメラをひったくるようにして消える。
 以上の写真は『東京戦争戦後秘話』
このカメラをひったくるところを、大島さんは何者かの足元を入れ込んで撮っている。その足元は死体の象一と全く同じ黒いスニーカーなんですね。すると、何者かは象一かもしれない。いや、象一なんでしょう。そこに、遠慮がちにではあるが「映画で遺書を残して死んだ男の物語」という大島渚によって提示された主題に即して書かれたシナリオを、大島渚自身の手でもう一度ひっくり返した形跡があるんです。
それと、DVDになってから見返して驚いたのは、車がらみの撮影をほとんどぶっつけ本番でやっているみたいなんですけど、迫力というか勢いがあるなと思いました。電車の線路の中に入ってしまうシーンとか、みんなぶっつけ本番で撮っていたんでしょう。それでも、実際のところ、ぼくはそれにも関わらず、やっぱり大島渚といえども、脚本通りにしか映画を撮らないのかなという疑問を感じていた。それは松本俊夫さんの『薔薇の葬列』に助監督として入ったときと同じ印象です。撮影の現場では、結局、段取りをこなしていくという形でしか撮影することができないのか、と疑問に思った。それは或る予算のなかで、スタッフを組んで撮る以上、どう仕様もないことなんですが、自分で撮る時は何とかそうではない撮り方を模索しようと思いました。それは、商品としてのパッケージのなかに、そこからはみ出る力と運動をいかに詰め込むことができるのか、という二律背反した問いかけのわけで、ぼくにとっては永遠の課題ですね。それに答えるために今も走り続けています。
『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)
――『東京戦争戦後秘話』の制作が70年の夏に終り、翌年の71年からついに『初国知所之天皇』の撮影をはじめるんですよね。
『東京戦争戦後秘話』のなかの風景映画では、さっきも言ったように、成島東一郎さんの撮り方に不満があったんです。成島さんは風景を自分の美意識を入れて、かっちりしたプロフェッショナルな撮り方でやっている。でも、風景というのは、そこに偶然存在するぼくたちにとって、よそよそしいものでなければならない、存在論と言うか、不在証明と言うか、わりと広い画で撮らないといけないと思った。そういう風景として、古代から現代まで歴史そのものを、文明そのものを、虚構だろとか、冗談だろって言えるような視点で日本を見てみようかと思ったんです。
――それと同時に、撮影現場を経験した松本俊夫や大島渚の製作プロセスを見て、彼らほどの才人ですら、ベルトコンベアーで製品を組みあげていくように、段取り的に映画を撮っている。そうではない方へ向かいたい、というのがあったんでしょうね。それが原さんの映画評論の言葉でいう、見る=見られるの関係で形成される「映画の肉体」ということでしょうか。文学や演劇と違う、映画らしさとは何なのか。映画だけにしかできない、映画固有のおもしろさとは何か。そのように考えたとき、原さんは反シナリオ中心主義というか「映画の生命」を見つける旅へ出られたわけですよね。
うん、そうですね。ぼくにとって、映画を撮るということはシャーマニズムです。映画の神様を降ろしてくることなんですね。それが古事記や日本書紀の天孫降臨の神話からインスパイアされることにもなり、二重写しになって『初国知所之天皇』を撮る行為になっていったのです。
以上の写真は『東京戦争戦後秘話』
このカメラをひったくるところを、大島さんは何者かの足元を入れ込んで撮っている。その足元は死体の象一と全く同じ黒いスニーカーなんですね。すると、何者かは象一かもしれない。いや、象一なんでしょう。そこに、遠慮がちにではあるが「映画で遺書を残して死んだ男の物語」という大島渚によって提示された主題に即して書かれたシナリオを、大島渚自身の手でもう一度ひっくり返した形跡があるんです。
それと、DVDになってから見返して驚いたのは、車がらみの撮影をほとんどぶっつけ本番でやっているみたいなんですけど、迫力というか勢いがあるなと思いました。電車の線路の中に入ってしまうシーンとか、みんなぶっつけ本番で撮っていたんでしょう。それでも、実際のところ、ぼくはそれにも関わらず、やっぱり大島渚といえども、脚本通りにしか映画を撮らないのかなという疑問を感じていた。それは松本俊夫さんの『薔薇の葬列』に助監督として入ったときと同じ印象です。撮影の現場では、結局、段取りをこなしていくという形でしか撮影することができないのか、と疑問に思った。それは或る予算のなかで、スタッフを組んで撮る以上、どう仕様もないことなんですが、自分で撮る時は何とかそうではない撮り方を模索しようと思いました。それは、商品としてのパッケージのなかに、そこからはみ出る力と運動をいかに詰め込むことができるのか、という二律背反した問いかけのわけで、ぼくにとっては永遠の課題ですね。それに答えるために今も走り続けています。
『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)
――『東京戦争戦後秘話』の制作が70年の夏に終り、翌年の71年からついに『初国知所之天皇』の撮影をはじめるんですよね。
『東京戦争戦後秘話』のなかの風景映画では、さっきも言ったように、成島東一郎さんの撮り方に不満があったんです。成島さんは風景を自分の美意識を入れて、かっちりしたプロフェッショナルな撮り方でやっている。でも、風景というのは、そこに偶然存在するぼくたちにとって、よそよそしいものでなければならない、存在論と言うか、不在証明と言うか、わりと広い画で撮らないといけないと思った。そういう風景として、古代から現代まで歴史そのものを、文明そのものを、虚構だろとか、冗談だろって言えるような視点で日本を見てみようかと思ったんです。
――それと同時に、撮影現場を経験した松本俊夫や大島渚の製作プロセスを見て、彼らほどの才人ですら、ベルトコンベアーで製品を組みあげていくように、段取り的に映画を撮っている。そうではない方へ向かいたい、というのがあったんでしょうね。それが原さんの映画評論の言葉でいう、見る=見られるの関係で形成される「映画の肉体」ということでしょうか。文学や演劇と違う、映画らしさとは何なのか。映画だけにしかできない、映画固有のおもしろさとは何か。そのように考えたとき、原さんは反シナリオ中心主義というか「映画の生命」を見つける旅へ出られたわけですよね。
うん、そうですね。ぼくにとって、映画を撮るということはシャーマニズムです。映画の神様を降ろしてくることなんですね。それが古事記や日本書紀の天孫降臨の神話からインスパイアされることにもなり、二重写しになって『初国知所之天皇』を撮る行為になっていったのです。
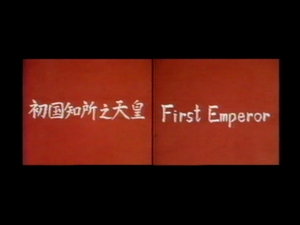 ――『初国知所之天皇』は、もともとは16ミリフィルムによる劇映画の構想だったそうですね。どのような映画になる予定だったんですか。
騎馬民族日本征服説を象徴するような男が、馬で北海道から『イージー・ライダー』のように、延々と日本列島を南下して、天孫降臨の神話の謎を解明すべく、鹿児島までやって来るという話です。騎馬民族日本征服説と天孫降臨説が、日本列島の風景のなかで、どのようにぶつかるのか、ということをロードムービーでやってみようと思った。それはジェイムス・ジョイスの小説「ユリシーズ」のような世界を、「古事記」をベースにして日本列島でやるというアイデアからはじまっています。
だけど、そう考えながら撮影を進め、挫折を繰り返していくうちに、単なる劇映画にするのではなく、自分がカメラを持って全国を回るスタイルの方が、むしろ最初の構想に近いということに気がついた。よりドキュメンタリーに近いというか、日記映画のようなスタイルになっていった。それで、16ミリフィルムで撮影した劇映画的な部分は、日記映画スタイルのなかに引用するだけに留めて、基本的には8ミリフィルムのカメラで、自分が旅して見ているものを撮影するという形で完成することになりました。もし、あのまま16ミリフィルムの劇映画として完成していたら、ジム・ジャームッシュの『デッドマン』みたいな映画になっていたでしょうね。
――『初国知所之天皇』は、もともとは16ミリフィルムによる劇映画の構想だったそうですね。どのような映画になる予定だったんですか。
騎馬民族日本征服説を象徴するような男が、馬で北海道から『イージー・ライダー』のように、延々と日本列島を南下して、天孫降臨の神話の謎を解明すべく、鹿児島までやって来るという話です。騎馬民族日本征服説と天孫降臨説が、日本列島の風景のなかで、どのようにぶつかるのか、ということをロードムービーでやってみようと思った。それはジェイムス・ジョイスの小説「ユリシーズ」のような世界を、「古事記」をベースにして日本列島でやるというアイデアからはじまっています。
だけど、そう考えながら撮影を進め、挫折を繰り返していくうちに、単なる劇映画にするのではなく、自分がカメラを持って全国を回るスタイルの方が、むしろ最初の構想に近いということに気がついた。よりドキュメンタリーに近いというか、日記映画のようなスタイルになっていった。それで、16ミリフィルムで撮影した劇映画的な部分は、日記映画スタイルのなかに引用するだけに留めて、基本的には8ミリフィルムのカメラで、自分が旅して見ているものを撮影するという形で完成することになりました。もし、あのまま16ミリフィルムの劇映画として完成していたら、ジム・ジャームッシュの『デッドマン』みたいな映画になっていたでしょうね。
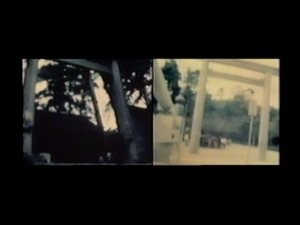 ――当時は新聞でも紹介されて、話題になったんですよね。高校を卒業したばかりの天才映画少年が、北海道から馬を連れて旅をしながら映画撮影を続けていると。旅の佳境は、やはり歴史の古い京都、奈良、出雲あたりでしょうか。最初から九州を南下して鹿児島まで行く計画だったんですか?
コンセプトとしては、最終的には宮崎、鹿児島まで行き、天孫降臨の謎を解明するというのがありましたが、そこまでシナリオは詰めてなかった。ブロック、ブロックで組み立てながら連作風に続けていこうと思っていました。それで、北海道の後は、東北で芭蕉と一緒に旅することを考えていたところで挫折しましたね。芭蕉の「奥の細道」をなぞるような旅というかね。結局、この映画では東北へは行かなかったんだけど、それは後に『百代の過客』(93)という映画で、ぼく自身と中学生の息子の2人旅を、芭蕉と曾良になぞらえて撮ったロードムービーへと繋がって行くことになりました。
――当時は新聞でも紹介されて、話題になったんですよね。高校を卒業したばかりの天才映画少年が、北海道から馬を連れて旅をしながら映画撮影を続けていると。旅の佳境は、やはり歴史の古い京都、奈良、出雲あたりでしょうか。最初から九州を南下して鹿児島まで行く計画だったんですか?
コンセプトとしては、最終的には宮崎、鹿児島まで行き、天孫降臨の謎を解明するというのがありましたが、そこまでシナリオは詰めてなかった。ブロック、ブロックで組み立てながら連作風に続けていこうと思っていました。それで、北海道の後は、東北で芭蕉と一緒に旅することを考えていたところで挫折しましたね。芭蕉の「奥の細道」をなぞるような旅というかね。結局、この映画では東北へは行かなかったんだけど、それは後に『百代の過客』(93)という映画で、ぼく自身と中学生の息子の2人旅を、芭蕉と曾良になぞらえて撮ったロードムービーへと繋がって行くことになりました。
 ――原さんには、神話や文学をベースにする発想がありますよね。それと同時に『初国知所之天皇』で面白いのは、一種のロケーション・ハンティングという行為が延長されて、そのまま映画になっているところがあります。最初、「私が私の映画の主人公になってしまった」と当惑気味なナレーションが入りますが、旅をしている途中で「おれこそが初国知所之天皇だ」とそれが確信に変わる瞬間があります。あれが凄い。また、劇映画の構想のときに北海道から馬を借りて日本列島を南下しようとしたという挿話がありますね。資金的に行き詰まってその馬を返してしまい、さて撮影を続けるというときに、8ミリフィルムによるロードムービーへ転換するという発想になったのでしょうか。
もちろん客観的にはそうなんですけど、途中で8ミリフィルムで撮りきれるという確信が湧きましたね。迷ってるときは「ああでもない、こうでもない」と頭で迷いますけど、カメラを日常的に手にしていると、「これで映画作品として成立する」というような確信というか、閃きのようなものが、カメラを持つ手とカメラポジションを探す足を通じて、身体的に天から降りてきたんですね。
――原さんには、神話や文学をベースにする発想がありますよね。それと同時に『初国知所之天皇』で面白いのは、一種のロケーション・ハンティングという行為が延長されて、そのまま映画になっているところがあります。最初、「私が私の映画の主人公になってしまった」と当惑気味なナレーションが入りますが、旅をしている途中で「おれこそが初国知所之天皇だ」とそれが確信に変わる瞬間があります。あれが凄い。また、劇映画の構想のときに北海道から馬を借りて日本列島を南下しようとしたという挿話がありますね。資金的に行き詰まってその馬を返してしまい、さて撮影を続けるというときに、8ミリフィルムによるロードムービーへ転換するという発想になったのでしょうか。
もちろん客観的にはそうなんですけど、途中で8ミリフィルムで撮りきれるという確信が湧きましたね。迷ってるときは「ああでもない、こうでもない」と頭で迷いますけど、カメラを日常的に手にしていると、「これで映画作品として成立する」というような確信というか、閃きのようなものが、カメラを持つ手とカメラポジションを探す足を通じて、身体的に天から降りてきたんですね。
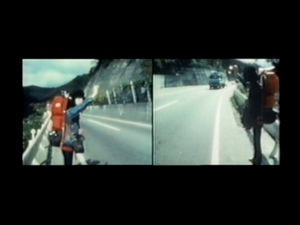 ――『初国知所之天皇』はもの凄い映画であり、インディペンデント・個人映画系の映画としては唯一、「キネマ旬報」のオールタイム・ベスト100の1本に入っている伝説の作品です。この映画が凄いことの要素の1つとして、約8時間という上映時間があります。「約」というのは、要するに、8ミリ映写機と16ミリ映写機の2台でマルチ・プロジェクション、スローモーション上映をするので、一定の決められた上映時間はなく、そのときの上映環境によって上映時間が変わる、変えられるということですね。マルチ画面は常にズレを生むわけです。まさに毎回上映される内容が偶然性によって決定づけられ、二度と同じことができないという一回性の上映形態です。
『初国』の場合、やはり、最も画期的だったのが、スローモーション映写の発見なんですよね。撮影したものを一本につないで、映写機で何度も見直したんです。そうしたら、映像が速過ぎちゃって、これは違う、これでは映画として成立しないのではないかと思えてきた。とにかく時間の流れが撮っている時と違う。撮っている時は、ものすごいハイテンションで、意識も身体も撮ることに集中してしまっているんで、時間の流れが滅茶苦茶ゆっくりなんです。それを再現できない限り、映画にはならないなと思えたんです。そこで、とにかくスローモーションにするレバーを入れてみたら、まさに、撮っている時の時間の流れがそのスローモーションだったんです。この映画はこのように上映されるために撮られたんだ、ということが初めて理解できたんです。
――『初国知所之天皇』はもの凄い映画であり、インディペンデント・個人映画系の映画としては唯一、「キネマ旬報」のオールタイム・ベスト100の1本に入っている伝説の作品です。この映画が凄いことの要素の1つとして、約8時間という上映時間があります。「約」というのは、要するに、8ミリ映写機と16ミリ映写機の2台でマルチ・プロジェクション、スローモーション上映をするので、一定の決められた上映時間はなく、そのときの上映環境によって上映時間が変わる、変えられるということですね。マルチ画面は常にズレを生むわけです。まさに毎回上映される内容が偶然性によって決定づけられ、二度と同じことができないという一回性の上映形態です。
『初国』の場合、やはり、最も画期的だったのが、スローモーション映写の発見なんですよね。撮影したものを一本につないで、映写機で何度も見直したんです。そうしたら、映像が速過ぎちゃって、これは違う、これでは映画として成立しないのではないかと思えてきた。とにかく時間の流れが撮っている時と違う。撮っている時は、ものすごいハイテンションで、意識も身体も撮ることに集中してしまっているんで、時間の流れが滅茶苦茶ゆっくりなんです。それを再現できない限り、映画にはならないなと思えたんです。そこで、とにかくスローモーションにするレバーを入れてみたら、まさに、撮っている時の時間の流れがそのスローモーションだったんです。この映画はこのように上映されるために撮られたんだ、ということが初めて理解できたんです。
 ――日記映画のスタイルの中で、わりとスローモーションにするっていうのはありますよね。ジョナス・メカスもそうですし、かわなかのぶひろさんもそうだし。手持ちのカメラで撮影している風景が、手ブレで、ズレて残像を生み出していく感じが、スローモーションだとはっきりと分かります。イメージが見た目と違う世界になりますよね。その他に『初国』の場合、この列島の風景も私自身の一部だ、私の延長なのだ、という原さんに特有の発想があります。そこから、風景映画を撮ることが自己を撮る行為へとなって行ったのでしょうか。
もう少し逆説的ですけどね。
――逆説的と言いいますと?
その風景のどこにも自分はいない。「いま、ここにいるってことは、たまたま、いま、ここにいるだけで、いま、ここの風景のどこにも自分はいない」ってことです。そして、それは魂の浮遊性につながってくる。可能性としては「私は遍在するのだ、ありとあらゆるところにいるのだ」ということになってくる。その身体の遍在性と魂の浮遊性の二極分解のなかから、日々新たに世界を発見していこうということになるわけ。それがスケージュールによって移動する旅行ではない、「旅」のもたらすものなんです。芭蕉が言っている「軽み」というものもそういうものではなかったかと思います。風景に向けていたカメラをゆっくり自分の方に向けると、不在証明としての風景から不在証明としての自画像になっていくわけです。
『初国』の旅は、撮影と言っても、30キロのリュックを背負って実家を出て、放浪生活のような旅だったんです。当時は携帯電話もないし、家族とは全く連絡もなかったですね。でも、或る日、風景と自画像を撮影していると、30キロの赤いリュックというのは、戦争のときに中国で歩兵となり、重い背嚢を背負って行軍していた父親だったんだな、ということに気がつく。リュックの赤は日の丸の赤だったんだと気付くわけです。そういう風に世界と家族と自分との絆を発見してしまったということがありました。金沢のくだりですけど。
71年に『初国』のロケハンで北海道へ行ったとき、初めてヒッチハイクをしました。それで、ものすごくヒッチハイクという行為自体が気に入りました。まあ、道路というのは、近代国家によって敷設されていった鉄道と違って、太古からの移動する身体と浮遊する魂の行き交いを象徴するもので、まさに『初国』のテーマとも符合するものだったんです。そのことに気がつきました。実際、北海道へ行くと、もうヒッチハイクしか旅行手段がない。北海道だと車もよく止まってくれるんです。ただ路上で指を立てて車をキャッチするんです。オートバイも停まってくれましたね。これがまた楽しい。
――日記映画のスタイルの中で、わりとスローモーションにするっていうのはありますよね。ジョナス・メカスもそうですし、かわなかのぶひろさんもそうだし。手持ちのカメラで撮影している風景が、手ブレで、ズレて残像を生み出していく感じが、スローモーションだとはっきりと分かります。イメージが見た目と違う世界になりますよね。その他に『初国』の場合、この列島の風景も私自身の一部だ、私の延長なのだ、という原さんに特有の発想があります。そこから、風景映画を撮ることが自己を撮る行為へとなって行ったのでしょうか。
もう少し逆説的ですけどね。
――逆説的と言いいますと?
その風景のどこにも自分はいない。「いま、ここにいるってことは、たまたま、いま、ここにいるだけで、いま、ここの風景のどこにも自分はいない」ってことです。そして、それは魂の浮遊性につながってくる。可能性としては「私は遍在するのだ、ありとあらゆるところにいるのだ」ということになってくる。その身体の遍在性と魂の浮遊性の二極分解のなかから、日々新たに世界を発見していこうということになるわけ。それがスケージュールによって移動する旅行ではない、「旅」のもたらすものなんです。芭蕉が言っている「軽み」というものもそういうものではなかったかと思います。風景に向けていたカメラをゆっくり自分の方に向けると、不在証明としての風景から不在証明としての自画像になっていくわけです。
『初国』の旅は、撮影と言っても、30キロのリュックを背負って実家を出て、放浪生活のような旅だったんです。当時は携帯電話もないし、家族とは全く連絡もなかったですね。でも、或る日、風景と自画像を撮影していると、30キロの赤いリュックというのは、戦争のときに中国で歩兵となり、重い背嚢を背負って行軍していた父親だったんだな、ということに気がつく。リュックの赤は日の丸の赤だったんだと気付くわけです。そういう風に世界と家族と自分との絆を発見してしまったということがありました。金沢のくだりですけど。
71年に『初国』のロケハンで北海道へ行ったとき、初めてヒッチハイクをしました。それで、ものすごくヒッチハイクという行為自体が気に入りました。まあ、道路というのは、近代国家によって敷設されていった鉄道と違って、太古からの移動する身体と浮遊する魂の行き交いを象徴するもので、まさに『初国』のテーマとも符合するものだったんです。そのことに気がつきました。実際、北海道へ行くと、もうヒッチハイクしか旅行手段がない。北海道だと車もよく止まってくれるんです。ただ路上で指を立てて車をキャッチするんです。オートバイも停まってくれましたね。これがまた楽しい。
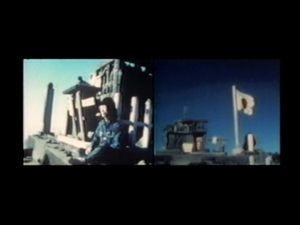 以上の写真は『初国知所之天皇』
――『初国』の映画のなかでも、ヒッチハイクのシーンが多くありますよね。トラックなどに乗せてもらうときに、自分のことを「学生ではなく、映画関係の仕事をしているが、その勉強をかねて旅していると言った方がいい」というナレーションがありますね。
まず、そう言うと車内で自由に撮影できるんです。運ちゃんにカメラを向けても全く気にしない。そうするうちに、食事を奢ってくれるんですよ。とにかく学生というより社会人と言う方が断然受けがよかった。
『東京戦争戦後秘話』
1970年/35mmフィルム/94分/モノクロ
監督:大島渚 脚本:原正孝(原將人)、佐々木守 予告編演出/原正孝
『初国知所之天皇』
1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映
監督:原將人
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人(映画作家)インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史 早川義夫編』
原將人公式サイト
【原將人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原將人監督とゲストによるトークあり
詳細 http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図 http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★gmail.com ※★を@にしてご入力ください
以上の写真は『初国知所之天皇』
――『初国』の映画のなかでも、ヒッチハイクのシーンが多くありますよね。トラックなどに乗せてもらうときに、自分のことを「学生ではなく、映画関係の仕事をしているが、その勉強をかねて旅していると言った方がいい」というナレーションがありますね。
まず、そう言うと車内で自由に撮影できるんです。運ちゃんにカメラを向けても全く気にしない。そうするうちに、食事を奢ってくれるんですよ。とにかく学生というより社会人と言う方が断然受けがよかった。
『東京戦争戦後秘話』
1970年/35mmフィルム/94分/モノクロ
監督:大島渚 脚本:原正孝(原將人)、佐々木守 予告編演出/原正孝
『初国知所之天皇』
1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映
監督:原將人
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人(映画作家)インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史 早川義夫編』
原將人公式サイト
【原將人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原將人監督とゲストによるトークあり
詳細 http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図 http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★gmail.com ※★を@にしてご入力ください