孤高の天才
映画作家・原將人。彼は1968年
麻布高校の在学中、16ミリ映画『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を撮影・完成し、第1回東京フィルムフェスティバル グランプリ、ATG賞を同時受賞。新聞にも大々的に取りあげられ、自主映画・8ミリ映画ブームの火をつけた。それから40余年。自身が「映画になること」を夢見て、
古事記に登場する日本最古の
天皇神話に自身を重ねながら、日本列島を重層的に撮った『初国之知所
天皇』(73)。
松尾芭蕉と
曾良の
奥の細道の旅を、父と子の私的なロードームービーに置き換えた『百代の過客』(93)など、孤高の傑作群を創出し続けている。
09年からは、
8ミリフィルム映写機による三面マルチ画面に、電子ピアノとゲストミュージシャンによる生演奏を重ねる独自の形態で『マテリアル&メ
モリーズ』の上映運動を全国で展開。また、劇映画第2弾『天翔る(あまかける)』の公開も控える作家に、自由に映画半生を語ってもらった。
(聞き手・構成・写真/金子遊 構成協力/春日洋一郎 協力/
若木康輔)
 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
――これが作品として編集したのは初めての作品ですか?
さっきちょっと話したように、その前に8ミリで習作みたいに撮ってたんですが、映写されるスピード感も、映像の質感も納得できなかったのと、
8ミリフィルムだと結構長くまわしてしまい、だらだらした感じに仕上がってしまう。編集に関しても、
8ミリフィルム用のビュワーを持っている人が周囲にいなかった。映写機にかけて見て、直接フィルムを眼で見て、カットしていくしかなかったんだけど、
8ミリフィルムだとフィルムの一コマが小さくて、細かいところまで見えないから、見当をつけて、大雑把に編集するしかない。だから編集というよりもNG抜きですよね。それに比べれば16ミリは夢のようでした。面積として4倍ありますからね。ほぼフィルムを透かして見ると肉眼で何が写ってるか分かる。だから、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』もビュワーは使わなかった。ラッシュを映写機にかけて、あとは肉眼で確認して、切り分けて、部屋に紐をはって、切り分けた断片を、洗濯バサミで次から次へとぶら下げていきました。それで、これ繋いで、あれ繋いで、これ繋いでという風に順序を並べ替えて、まあ、洗濯紐と洗濯バサミで編集していくんですよ。それで納得がいけば実際にスプライサーで繋いで、映写機にかけて見る。気に入らなかったらまたばらして、洗濯紐に並べていく、という作業をくりかえした。それが初めてちゃんと映画を編集したときになるのかな。まあ、肉眼で見える最低の大きさの16ミリというのは編集を覚えるには最適なメディアなんです。だから、話は飛びますが、『初国知所之
天皇』で再び8ミリに戻った時には、8ミリでの編集の困難さを知っていましたから、撮影するときに編集する、編集しながら撮影するということが最初からできたと言うか、8ミリはそうするしかないということが分かっていたから、そう撮影したんです。

――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の撮影はご自分でやられたんですか?
ええ、自分が登場しないところは自分でやって、それ以外のところは、
麻布高校の友人に頼んでやってもらった。器用な友達に、三脚を立ててアングルを決めて、カメラの操作を一通り教えて、回してもらったんです。
――これは「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」(68)のグランプリ作品ですね。
草月
シネマテークが「第1回東京実験映画祭」を開催したのが僕が高校2年の時で、その後、草月
シネマテークが中心になって「フィルムアート」という雑誌を創刊した。それに合わせて2回目が開催されたので、実験映画祭から名前を変えたんですよ。だから、厳密にいえば映画祭として2回目だけど、名前を変えたからまた第1回ということで「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」となったんですね。そこで、グランプリとATG賞と両方をもらいました。
――いま見ても新鮮な映画ですよね。カットが短く、テンポも早く、のっけから様々な映画からのパロディや引用があり、劇中劇も入っている。とても高校生が作った作品とは思えません。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の第一章が「地獄の季節」となっていますが…。
小林秀雄訳の
アルチュール・ランボーの『地獄の季節』がすごい好きでした。
岩波文庫版が高校生たちのバイブルみたいになっていて、みんな読んでいましたね。星ひとつ(*4)の50円だったし。
この『おかしさに彩られた悲しみのバラード』という映画の成り立ちから話しますと、シナリオはこの映画の途中で出てくる『黄金時代‘68』、劇中劇というか、映画内映画として組み込まれている映画なんですけど、その分しか書いていませんでした。と言うか、そもそも最初は『黄金時代’68』という映画を作ろうとしたんです。ぼくは、映画館ばかり通っていた高校生でしたが、映画を製作するとなると友人に協力を頼まなくてはならないので、急に学校へちゃんと通いはじめた。そして、授業中にシナリオをスタッフやってくれる友人たちに回し読みしてもらい、休み時間になるとみんなで集まって、シナリオのどこをどう直そうかと相談した。そうやって『黄金時代‘68』のシナリオを書いたんだけど、あまり評判が良くなかったんです。

――かなり政治的な内容の部分もありますからね。原っぱで「
ベトナム戦争ごっこ」をする場面は、
ゴダールの引用だとわかりますが、高校生には少し難しいでしょう。
いや、評判が良くなかったというのは、難しいということではなかったんです。政治意識と政治的な主体っていうのかな。その立場の問題なんです。当時の先鋭的な高校生の政治意識はみんな
全共闘運動のところまで行ってましたからね。ぼくとしては、一応、
反戦運動を問い直すという政治的なメッセージを『黄金時代‘68』というシナリオに込めたつもりでした。例えば
ベ平連がやっている
市民運動は、
ベトナムで戦争で行われてる非道に対して、人道的に反対する声を集約していくだけではないか。そういう
反戦運動のあり方に対して、それは少し違うと考えていた。やはり自分の置かれている状況から運動を始めなくてはいけないのではないか、と。その頃には東大や早稲田大で闘争が起き始めていた頃でした。だから、そのような無媒介的に
ヒューマニズムで
反戦を唱えるというのは違うのではないか、と考えていたわけで、それを、そういうメッセージをそのシナリオに入れて書いたつもりだったんです。でも、みんな、甘いって言うんです。
みんなも同じような事を考えていた。自分たちの置かれた状況から出発することを考えていた。だから、シナリオを検討しているうちに、
反戦運動の批判が描かれているだけじゃだめだ、そこで自分たちが主体的に何をするかが描かれていないと仕様がないと、みんな言うんですよ。「映画なんか撮ってる場合じゃない! 今すぐ休み時間に机を積み上げて
バリケード封鎖しよう!」とか言いだす奴もいました。やっぱり高みに立った状況批判だけじゃなくて、そのなかでどうすべきなのかということを描かなければだめなんだと、ぼくも自分で書いたものがまだツメが甘いと思ってたし、みんなの批判を真摯に受けとめたんですが、でも、どうしたらいいか分からず困ってしまったんです。へたをすると、安易な
プロパガンダに流れてしまう。困った、困った、と。その時ひらめいたんですね。このような状況そのものを映画にしたらいいんじゃないか、ということにぼくは気づきました。映画が降りて来たんですね。この時が映画が降りて来た初めての経験です。それが春休みのはじまる直前でした。「分かった!任せてくれ!だいたい構想はできたから」と言って、とにかく朝の集合場所と時間だけ決めて、その日の撮影分のシナリオは当日の朝までに書いて渡すという形で納得してもらい、高校2年から3年になる春休みに、とにかく撮りはじめたのが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』なんです。1968年という政治的な状況があって、
アメリカという
帝国主義国家によって
ベトナム戦争が行われていて、ぼくたちが生まれ育った日本という国家はそれに協力している。そのなかで自分たちは何をしたらいいのか分からない。映画を撮るにしてもどんな映画を撮ったらいいのか分からない。それでも映画だけは撮った!というのがこの映画に込められたメッセージだと思います。だからこのメッセージは自分たちにも突きつけられた。高校生としての自分たちの置かれた位置は、国家の構成員を育成する
教育機関のレールの上を走っている、走らされているだけということは分かっていた。だから、レールを走り続けてその先の大学まであえて行くのかという問いが、みんな、この映画を撮る事によって突きつけられてしまった。だから大学へ行かなかったのがぼくを含めて何人かいました。

――創作の秘密と言いますか、一番お聞きしたかったところに入ってきていると思います。一章、二章という風に繋がっていきますが、撮影は章ごとに行なったんですか?
そうです。順番に撮っていました。そういうシナリオ無しのような撮り方をすると順撮りしてかないと分からなくなってしまうので。頭のなかでいろいろな映画の記憶が繋がっていってね、それを整理していかなければならなかったんです。劇中劇にあたる『黄金時代‘68』の部分は
ルイス・ブニュエルの『黄金時代』からの引用というか
本歌取りなんです。
朝鮮人の少年のリンチのシーンがありますが、あれは
大島渚の『絞首刑』からの引用ですね。大島さんの60年代後半の映画も、創造社になってからの『白昼の通り魔』からはすべてリアルタイムで見ていますね。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』では、そのリンチされた
朝鮮人の少年が逃げるところまでは事前に考えていました。その後は
トリュフォーの『
大人は判ってくれない』のラストシーンのように浜辺で撮ろうと考えていました。本当のラストシーンの「僕たちはこの夏に映画をつくった」というところは、
大林宣彦の『いつか見たドラキュラ』の終わり方のパロディですね。
編集作業はひとりでやりました。ラッシュで編集を始めてプリントを焼くまでに、4月から7月まで4ヶ月かかっていますね。まあ、そこまでひとりでやったのだから、間違いなく僕の作品だといえますが、そこにいたるまでの製作プロセスを考えれば麻布の友人たちとの総力戦じゃないですか。現像は市ヶ谷に読売現像所といういいラボがあって、普段はニュース映画しかやってないようなところなんですが、法政大学の映研などがよく使っていたところです。
志村喬と
森繁久彌を足して割ったような、森田さんという凄くいいおじさんがいました。その後の作業手順をすべて教わりました。「ラッシュ編集をしてくれば、ネガ編は格安でしてあげるよ」と言ってくれて、プリントをあげて、それに磁気コーティングをして、ぼくたちがオープンリールテープに
宅録した音源を微調整して入れてくれました。賞をもらった後にプリントを何本か作ることになってからも、シネテープから音ネガを作って焼いた方が安いということになって、その作業もその読売現像所でやってくれました。ラボがそこまでやってくれるというのは考えられない事です。ニュース映画を中心にやっていた所だったんでそれができたんでしょうが、ラッキーでした。

――プリントは2種類あったということですか。音楽は
エリック・ドルフィーから
ビートルズまで、さまざまな楽曲を使っていますね。
ええ、好きな音楽を入れました。受賞式のパー
ティーで
武満徹さんに怒られましたけどね。音楽には
著作権があるんだといわれて。ATG賞をもらったので新宿文化で上映する予定だったのだけど、
著作権料を到底払い切れないということで上映できなくなってしまった。そうしたら、
武満徹さんが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』用に音楽を作り直してあげるって、言ってくれたんです。でも、断っちゃったんですよ(笑)。
――何で断ったりするんですか、もったいない!
若さゆえ、と言うか、ロック少年だったので、クラシックの
武満徹とロックの
ビートルズを差別化する意識があったんでしょうね。僕が映画のなかで使った
ビートルズの曲よりも良い曲を武満さんが作れるのか、みたいな。まあ、メチャメチャとんがっていましたから。でも武満さんは全然クラッシックというような領域意識のある人ではなかったんですね。非常にフラットで
オルタナティブな人だった。後になって武満さんにお願いすればよかったと悔やまれました。亡くなられた今思いますと、それこそ弟子入りして譜面の清書でもさせてもらえばよかったという感じですよね。若いということにはそういう二面性がありますね。
これは後の話ですが、『東京战争戦後秘話』のとき、武満さんが音楽を担当することになり「原クン、どういう音楽が欲しいかね」と聞いてきてくれたんです。僕がシナリオを書いた映画でしたから。僕はその時に「
ビートルズの『
ストロベリーフィールズ・フォー
エバー』にしましょう」と言ったんです。武満さんはとても喜んで「僕も
ビートルズは大好きだよ」といって、そのような曲を作ってきてくれました。でも、それは後で考えるともう少し複雑な話です。どうやら
大島渚さんが武満さんに「原クンがシナリオ書いているから、音楽のことも原クンに直接相談してもらった方がいいだろう」と言ったようなんです。大島さんが武満さんに「音楽は
ビートルズでいきましょう」なんて言えば、武満さんは怒っちゃいますよね。僕が言ったから通った話なんです。その辺は、大島さんは裏でちゃんと計算していて、そういう人の使い方がうまい監督なんですね。
黒澤明の『乱』で武満さんが音楽を担当したとき、黒澤さんに「
マーラーのような音楽でいきたい」と言われて、しかもその
マーラーを聴かされて、武満さんが怒ったというのは有名な話ですけど、選手の力をすべて引き出して勝つ試合をする監督という意味では、大島さんは黒澤さんよりも優れていましたね。

――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の章のタイトルが入るときに、イラストレーションを使っていますね。
あれはビアズレーが好きな室井伸二クンという友人が描いてくれたんです。デザインのプロになって、今は自分でデザイン事務所やっています。とにかく、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、審査員の方も観客もみんなおもしろがってくれました。
――原さんの著書『見たい映画のことだけを』に「映画の肉体」という言葉がありますが、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、まさに映画の肉体を持った「眼の映画」ですよね。物語でぐいぐい引っ張るのではなく、映像で惹きつける視覚的要素の強い映画です。
実はぼくは、『バラード』を撮った後、仕事をして家を出たかったということもあって、東京フィルムアート・フェスティバルの審査員だった
松本俊夫さんに頼んで『
薔薇の葬列』の演出部につけてもらったことがあるんですが、たとえば、
松本俊夫さんにしても、
ゴダールやレネが良いと言っていても、自分で劇映画を撮るとなるとシナリオをちゃんとあげて、スタッフをちゃんと従えてシナリオどおりに撮ることになってしまう。それに初めてのスタッフ、キャスト同士が多くて、そうするとコミュニケーションは言葉で行き交う領域だけになってしまい、シナリオを中心に言語で了解できる領域でやりとりしてしまう。撮影という作業が段取りになってしまう。すると映画が肉体を持たなくなってしまうんですね。そういうことを感じました。その後、
溝口健二と
小津安二郎を集中的に見ました。二人とも頑固に自分のスタイルを守り通しているんですが、それは
シャーマニズムではないかと思いました。巫女として映画の神様を降ろしているんだと。それが映画の肉体だと思って「映画の肉体」という文章を書きました。おそらく溝口さん、小津さんのスタッフは、そういうことが分かっていて、一緒に祈祷していたんでしょうね。そういう意味では、「映画の肉体」は、無意識的な部分でスタッフが如何に映画の神様を降ろすという
シャーマニズム的部分を共有できるかという問題かもしれない。『バラード』はけっこう追いつめられた状況で作ってましたから、それができたのかもしれない。
 ※以上の写真は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
『自己表出史 早川義夫編』
※以上の写真は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
『自己表出史 早川義夫編』
――高校は卒業されたんですか。
高3のときの担任の先生が、いい人だったというか、理解があったので卒業はさせてくれました。大学受験も考えましたが、とにかく受験勉強をしていなかったし、僕が受けるときは東大闘争で東大の入試が中止になった年でした。それで、親も息子が大学へ行って
学生運動をやるよりは、まだ映画でもやっていてくれる方がいいと判断したんです。
麻布高校では学園闘争はありませんでしたが、都立大付属高校には、
反戦高協という
中核派の拠点ができていました。その翌年の69年になると、高校まで学生組織がおりて来たんですよ。ほとんど学校へは行かずに、
松本俊夫さんの『
薔薇の葬列』でフォースの助監督を経験したのが高3の三学期だったんです。松本さんに「もう大学行かないことに決めて、映画の仕事してみたいのでつけて下さい」と頼んだ。松本さんは僕が商業映画に関しては何も知らなくて戦力にならないだろうということで、ちゃんとした仕事をくれなかった。『
薔薇の葬列』の現場では、サード助監督までいれば充分だったので、フォース助監督の仕事なんてほとんど無かったんです。現場では、カメラを置く度にファインダーを覗かせてもらっていた(笑)。そのことが照明部から大顰蹙を買いました。スタッフはプロフェッショナルで、カメラマンが
鈴木達夫さん、照明もちゃんとした劇映画のスタッフでした。現場では、モブ(群衆)シーンで若いのが必要なときに、友だちに電話しまくって、集めてくるような仕出し屋のような仕事をしていました。『
薔薇の葬列』は時間軸が交錯する迷宮的な構造を持っている映画ですが、現場では、
松本俊夫ともあろう作家がただシナリオ通りに撮っているのが不満でした。それで納得できなくて「これはこう撮った方がいいんじゃないですか」みたいなことを言った。監督に意見するフォース助監督ということで、スタッフの人たちから顰蹙を買いました。とにかく、照明部がいちばんきつかったかな。
高校を卒業する前後でもうひとつ忙しくしていたと言うか、動いていたことがありまして、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を上映したいと言ってきた高校生たちがいて、彼らも映画を撮っていたんです。彼らと連絡取っているうちに「全国高校映画連盟」というのが出来ていった。ちょっとまた川喜多さんたちのシネクラブ研究会の話になりますが、その頃、シネクラブ研究会の百回記念に、
鈴木清順全作品の連続上映を企画して、川喜多さんが日活にフィルムを借りに行ったら、拒否され、おまけに、うちにはそんな映画青年たちに人気のあるような芸術映画を撮るような監督は要らないということで、清順さんが日活を首になったという事件がありました。それからシネクラブ研究会が母体となって、
鈴木清順問題共闘会議が発足したんです。清順共闘は、週に一度、撮影所の助監督や独立プロの監督やプロデューサーなどが中心に集まって、
松田政男さんや
河原畑寧さんなどの批評家、
足立正生さんなんかも常連で、清順さんの不当解雇問題だけでなくて、当時の映画界を取り巻くあらゆる問題を取り上げて話し合っていたんです。そこにもぼくはというか、『バラード』に主演した瀬川元秀クンなんかも一緒に顔を出すようになった。戦後初めて
騒乱罪が適用された10・21の国際
反戦デーで
国学院の映画研究会の当日の記録映像がその
騒乱罪を立件するための証拠物件として警察に差し押さえられたという事件があって、
国学院の映研が清順共闘で報告すると言うんで、ぼくたちも話を聞きに行ったんですけど、闘争を記録する事が闘争だみたいな感じで、大学生ってバカだなと思ったこともあって、高校生たちの映画のレベルの方が圧倒的に高いんですね。変に左翼かぶれしてないんで、作品として自立しているわけ。ぼくたちの置かれている状況が感覚的に描かれているわけ。それもあって、「全国高校映画連盟」の結成にはかなり力を注ぎました。松本さんのところでも助監督してたので、忙しかったですね。それこそ学校へ行っている暇もなかった。でも、卒業はさせてもらったんです。
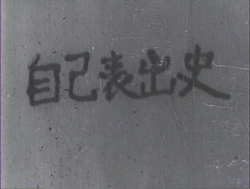
――『自己表出史
早川義夫編』の話に入りましょうか。
卒業した後、やっぱり「全国高校映画連盟」の関係で、
ドキュメンタリー映画作家の
野田真吉さん(*5)の息子の亘真幸(わたりまさゆき)クンと友達になりました。それで
野田真吉さんの家へよく遊びに行っていた。当時の野田さんは神奈川ニュースで仕事をしたり、
新日鉄などの企業PRフィルムを作ったりしていました。野田さんには息子のように可愛がられました。遊びに行く度に、仕事部屋に通してくれていろんな映画の話をしてくれました。帰りには、「この本読むといいよ」と本を貸してくれたり、「このフィルムを使いなよ」と仕事で余った16ミリフィルムをくれました。現像も仕事の企業PRフィルムを現像するときに、一緒に現像してやるよ、という言う事で、次に行く時には、ラベルに野田プロダクション『自己表出史』と書いて撮影済みフィルムを持っていって現像までしてもらいました。そういうわけで、
野田真吉さんがこの映画をプロデュースしてくれたようなものなんです。
――元々、ジャックスの音楽が好きだったんですか。
ええ、そうです。いつどこでジャックスの音楽と出会ったかは定かではないんですが、日本語のバンドとしては、
ビートルズや
ストーンズに匹敵する唯一のバンドだと思って、とにかくジャックスの映画を撮ってみたいと思ったんです。それで、やっぱり、それも「全国高校映画連盟」のつながりなんですけど、詩人・
福間健二さんの弟の福間雄三クンと仲良くなりました。福間雄三クンは
日野高校にいたんですが、8ミリで私的で詩的、ワタクシ的でポエチックな素晴らしい映画を撮っていて、彼とぼくとが「全国高校映画連盟」をまとめあげる中心人物のようになっていった。それで、組織の旗揚げに全国高校映画祭をやろうかみたいな相談で、ずいぶん雄三クンの家に行って泊めてもらったりしたこともあって、
福間健二さんと知り合いになったんですけど、
福間健二さんは、
若松孝二監督の
若松プロに出入りしていました。ジャックスのリーダー、
早川義夫さんも若松監督の映画に出演したり、『腹貸し女』の
サウンドトラックを担当したりして、
若松プロと付き合いがあった。それで
福間健二さんに早川さんを紹介してもらったんです。

――ジャックスの音楽性は、それまでの
グループサウンズとは全然違いますよね。もとはフォーク・ミュージックですが、有名な「マリアンヌ」という曲では、
サイケデリックなギターソロが入っていたり、早川さんの情念的なヴォーカルであったり、日本語ロックの草分けの存在として現在も評価が高いバンドですね。
ジャックスは
ザ・タイガースなどに比べると、圧倒的に
ビートルズや
ストーンズに近いロック的な音楽性です。作詞・作曲も自分たちの手で担当しています。
ザ・タイガースや、
テンプターズでは、
かまやつひろしが多少は自分で曲を書いていたみたいですが、やはり作曲は、
すぎやまこういちなんかが担当していて、歌
謡曲の人がロックっぽい曲を作っていたわけです。
グループサウンズの音楽はロックと言っても、
ビートルズや
ストーンズのような「ロック」とは全然違うのです。ロックの要素が入った歌
謡曲といった感じで、
美空ひばりの「真っ赤な太陽」なんかと同じですよ。
本牧には
ゴールデンカップスという上手いバンドもいましたが、彼らはR&Bのカバーをちゃんとやっていましたが、さほどオリジナリ
ティーはなかった。そのような意味で、ジャックスが日本できちんと自分たちのロックをやっていた唯一のバンドに思えました。
――
早川義夫さんがジャックスを解散したときに、撮りはじめたんですか。
早川さんに会って「ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいんですけど」と言ったら、「ああ、ジャックスは解散しましたよ」と返された。これからはソロでやっていくというので、「じゃ、それを撮らせて下さい」と言って撮り始めたんです。アルバムを製作しているときの早川さんのURCレコードの事務所での様子、ライヴステージ、それに新宿の街を歩いている姿などを撮影しました。

――構想としては、ライヴ映画を撮る予定だったそうですね。早川さんの『かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう』(69)のアルバム制作過程とライヴを撮影して、両方を合わせていわゆる音楽映画を作ろうとした、というわけでは勿論ないんですよね?
そう。ライヴの撮影も、ちゃんと一曲全部を撮影するというような撮り方ではなかった。まあ、演奏しているところをそのまま撮るなんて考えられなかったんですね。フィルムがもったいなくてと言うか、映像は映像として見る音楽、眼の音楽なんだから音楽に従属すべきじゃないと考えていた。最初、ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいと思った時も、
リチャード・レスターの撮った『
ビートルズがやってくるヤア!ヤア!ヤア!』みたいなものを漠然と考えていました。だから、69年の10・21国際
反戦デーの街頭デモとか、当時の色々な要素を映画のなかに入れ込みながら、全体を早川さんの歌とインタビューで繋げば、それで映画として成立するではないか、という直観がありました。『自己表出史
早川義夫編』では、これといってモデルにした映画はありません。『バラード』とはまったく違う作り方でした。撮影した素材と録音したテープから構成した映画です。撮影は
野田真吉さんの息子の亘クンが担当してくれて、ぼくとカメラを持った彼と2人で動いていました。
早川さんへのインタビューは、早川さんの自宅へうかがって、そのときはカメラを持たずにテープレコーダーだけで一日がかりでインタビューを録音しました。その早川さんの声をバックに、早川さんが銀座を歩いている映像や当時撮影していた映像を当て嵌めていきました。
それと『自己表出史
早川義夫編』の前に、何本か撮ろうとして撮れなかった映画企画が何本かあった。『自己表出史
早川義夫編』の序章には、「理絵の巻」という短編が組み込まれています。高校生の女の子が、学校の屋上で売春をするストーリーです。高校という空間そのものを否定するような映画を作りたかったんです。女子高生が屋上でキスしたり、男の子と絡みあったりする姿を撮影し、それに
オーネット・コールマンの「ロンリー・ウーマン」というジャズ・ミュージックを重ねました。そのテーマでは、
足立正生が『噴出祈願 15歳の売春婦』という傑作を作っていますがね。

――他にはどのような映画企画があったんですか。
大江健三郎の「セブン
ティーン」という小説をモチーフにした映画を撮ろうとして、友だちを集めて、キャストも決めて、シナリオなしで撮影を始めました。モチーフにしているだけなので、大江さんの許可を得たわけではないですが。ところが、撮影したフィルムを現像してみたら、カメラの水平軸が全部傾いていたんです。使ったボレックスのカメラのファインダーとプリズムがズレていた。かっちりとした劇映画を撮ろうとしていたので、それで嫌になって中止してしまった。そうしたら、亘君がア
リフレックスを持ってきてくれた。とにかく
早川義夫を撮り始めて、それまで撮ったフィルムで使える分を『自己表出史
早川義夫編』に入れていったんです。
――この辺りで、原さんの音楽性の確立についてお聞きしたいですね。
早川義夫さんが一番の先生ですよ。早川さんにインタビューへ行ったら、早川さんは全然レコードを持っていなかったんです。
ビートルズの古いアルバムが自宅に何枚か置いてあっただけ。その頃の流行のロック、たとえばジミヘンやクリーム、
ストーンズやドアーズも持っていない。早川さんにどうしてか聞いたら「他の人の音楽はあまり聴かない」と言うんです。「どうやって作曲をするんですか」と尋ねると、映画の中のインタビューでも答えていますが「僕は作曲の仕方を知らないから、なるべく他の人の音楽を聴かないようにしていると、すると段々とメロディーが湧いて来る。他の音楽を聴くとそれしか浮かんでこなくなっちゃうから、とにかく他の音楽を聴かずに、湧いて来るのを待つ」という方法論を教えてくれた。コード進行をコピーしたり、またコード進行を決めてから曲を作る事もしないと言うんです。「それをやると他人の真似になるから、とにかく音楽は聴かない方がいいよ」と言うんです。そうして、僕の作曲スタイルも決まりました。「早川さんみたいにすればいいんだ」と思ったんです。『初国知所之
天皇』のために、半年くらい
ヒッチハイクをしながら日本列島を撮影していたとき、ほとんどテレビも見ないしラジオも聞かなかったんですが、ピアニカだけは持ち歩いていました。それをリュックの中に入れておいて、ピアニカで浮かんだメロディーをひたすらノートに書きつづる形で作曲をするようになりました。その後、そのメロディーにコードをつけていったんです。

――早川さんと原さんは、最近でもお付き合いあるんですか。
早川さんの『たましいの場所』というエッセイ集があるんだけど、それが素晴らしい話ばかりで、特に明治生まれのお母様の臨終のエピソードなどは涙無しには読めないんですが、そのエピソードを中心に映画にしたいという思いがあるんで、連絡を取り合っています。もう、シナリオもあがっています。早川さんは川崎で書店をなさった後、90年代に店をたたんでまた活発に音楽活動をしています。いまも作詞・作曲を自分でやっていますが、復活してからの新曲がすごく良いんですよ。ヴォーカルのスタイルは変わっていませんね。
――タイトルの「自己表出史」という言葉は、
吉本隆明から来たんですか。
そうです。『言語にとって美とは何か』です。一人の個の深いところを突き詰めていくと、普遍性ではないけれども、何か本質的なものにぶつかる。早川さんでいえば、すべての音楽を聴かないで、降りるのを待つという姿勢がまさに彼の「自己表出」だと思いました。
ビートルズを聴いて、それを真似してみようとなると一種の指示表出になってしまいますからね。
――この映画の一つの魅力は、当時、一種の祝祭空間と化していたという
新宿駅周辺の雰囲気をドキュメントしているところです。1500人が逮捕された新宿デモの騒乱、10・21の国際
反戦デーを撮影していたのは、創造社の
大島渚のグループと原さんだけだったんですよね。
新宿の街は、
学生運動の
セクトやゲリラで溢れていました。あの映画における一つの成果は、1969年のあの日を映像で記録したことかもしれない。駐車していた車が次々に横倒しにされて、炎上し、その炎が、雨に濡れた道路やずらりと並ぶ機動隊の盾に反射していました。夜遅くまで、そんな光景をカメラに収めていきました。早川さんの「作曲しているともう日常じゃ無くなるんだよ」というコメントをバックに、この10・21の映像をぶつけたんです。早川さんがインタビューで話してくれたことが、その映像ともマッチして、時代の雰囲気を伝えるのに効果を上げたんだと思います。また当時は、東京の風景が急速に変わっていく時期でした。
東京オリンピックの後にどんどん
路面電車がなくなっていきました。そんな街の風景を記録している面もあります。
ぼくたちは
大島渚さん、
足立正生さん、仙元誠三さんらに街角で会いました。
大島渚さんの創造社の撮影クルーは、二班にわけて撮影していたようです。もう一班は、
田村孟さん、吉岡康弘さん、戸田重昌さんの3人。僕は大島さんたちの班に出くわしました。大島さんも10・21の撮影に来ているのは自分たちだけだろう、創造社だけだろうと思っていたらしく、僕たちが来ていたのですごく喜んでいました。そんなこともあって、僕が脚本を書いて
大島渚さんが監督した『東京战争戦後秘話』へと繋がっていったんです。
 ※以上の写真は『自己表出史 早川義夫編』
[注]
*4 岩波文庫
※以上の写真は『自己表出史 早川義夫編』
[注]
*4 岩波文庫は、消費税が導入された1989年までは、定価を金額ではなく星印の数で表示していた。当時は星印一つあたり50円だった。
*5 野田真吉 1916年愛媛県生まれ。
早稲田大学在学中
中原中也に私淑、詩作を始める。卒業後、
東宝の前身だったP.C.L.に入社。文化映画部に配属され40年監督に昇進。ほどなく召集され敗戦まで陸軍に所属。戦後、
東宝に復帰し、
東宝争議に参加し、49年退社。
日本記録映画作家協会結成の中心的な役割を担う。その一方、
大島渚、
吉田喜重らの「映画批評の会」、
安部公房、
島尾敏雄らの「現在の会」、
花田清輝、
佐々木基一らの「記録芸術の会」、長谷川龍生、
黒田喜夫、
関根弘らの「現代詩の会」などに関わり、『忘れられた土地』(58)『マリン・スノー』(60)『
モノクロームの画家 イブ・クライン』(64)などを発表。64年、
松本俊夫、
土本典昭、
黒木和雄、
小川紳介とともに「映像記録の会」を結成。67年、「杉並シネクラブ」を結成。その交流の広さから、様々なジャンルの人々から相談を受け、ジャンルを超えて人々を結び付けた、戦後の前衛的な文化を創出した核たる人物のひとりである。代表作に『冬の夜の神々の宴 遠山の
霜月祭』(70)『ゆきははなである 新野の
雪まつり』(80)『生者と死者のかよい路 新野の盆おどり・神送りの行事』(91)の「民俗神事芸能三部作」がある。また、
大島渚監督『
愛のコリーダ』(76)の撮影現場をドキュメントしており、おでん屋の店主として出演もしている。1993年没。
「おかしさに彩られた悲しみのバラード」
1968年/16mmフィルム/12分/モノクロ
監督:原將人
第1回フィルムアート・フェスティバル グランプリ&ATG賞
「自己表出史 早川義夫編」
1970年/16mmフィルム/29分/モノクロ
監督:原將人 撮影:亘真幸
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人公式サイト
【原将人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・
早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原将人監督とゲストによる
トークあり
詳細
http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図
http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★
gmail.com ※★を@にしてご入力ください
 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
――これが作品として編集したのは初めての作品ですか?
さっきちょっと話したように、その前に8ミリで習作みたいに撮ってたんですが、映写されるスピード感も、映像の質感も納得できなかったのと、8ミリフィルムだと結構長くまわしてしまい、だらだらした感じに仕上がってしまう。編集に関しても、8ミリフィルム用のビュワーを持っている人が周囲にいなかった。映写機にかけて見て、直接フィルムを眼で見て、カットしていくしかなかったんだけど、8ミリフィルムだとフィルムの一コマが小さくて、細かいところまで見えないから、見当をつけて、大雑把に編集するしかない。だから編集というよりもNG抜きですよね。それに比べれば16ミリは夢のようでした。面積として4倍ありますからね。ほぼフィルムを透かして見ると肉眼で何が写ってるか分かる。だから、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』もビュワーは使わなかった。ラッシュを映写機にかけて、あとは肉眼で確認して、切り分けて、部屋に紐をはって、切り分けた断片を、洗濯バサミで次から次へとぶら下げていきました。それで、これ繋いで、あれ繋いで、これ繋いでという風に順序を並べ替えて、まあ、洗濯紐と洗濯バサミで編集していくんですよ。それで納得がいけば実際にスプライサーで繋いで、映写機にかけて見る。気に入らなかったらまたばらして、洗濯紐に並べていく、という作業をくりかえした。それが初めてちゃんと映画を編集したときになるのかな。まあ、肉眼で見える最低の大きさの16ミリというのは編集を覚えるには最適なメディアなんです。だから、話は飛びますが、『初国知所之天皇』で再び8ミリに戻った時には、8ミリでの編集の困難さを知っていましたから、撮影するときに編集する、編集しながら撮影するということが最初からできたと言うか、8ミリはそうするしかないということが分かっていたから、そう撮影したんです。
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
――これが作品として編集したのは初めての作品ですか?
さっきちょっと話したように、その前に8ミリで習作みたいに撮ってたんですが、映写されるスピード感も、映像の質感も納得できなかったのと、8ミリフィルムだと結構長くまわしてしまい、だらだらした感じに仕上がってしまう。編集に関しても、8ミリフィルム用のビュワーを持っている人が周囲にいなかった。映写機にかけて見て、直接フィルムを眼で見て、カットしていくしかなかったんだけど、8ミリフィルムだとフィルムの一コマが小さくて、細かいところまで見えないから、見当をつけて、大雑把に編集するしかない。だから編集というよりもNG抜きですよね。それに比べれば16ミリは夢のようでした。面積として4倍ありますからね。ほぼフィルムを透かして見ると肉眼で何が写ってるか分かる。だから、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』もビュワーは使わなかった。ラッシュを映写機にかけて、あとは肉眼で確認して、切り分けて、部屋に紐をはって、切り分けた断片を、洗濯バサミで次から次へとぶら下げていきました。それで、これ繋いで、あれ繋いで、これ繋いでという風に順序を並べ替えて、まあ、洗濯紐と洗濯バサミで編集していくんですよ。それで納得がいけば実際にスプライサーで繋いで、映写機にかけて見る。気に入らなかったらまたばらして、洗濯紐に並べていく、という作業をくりかえした。それが初めてちゃんと映画を編集したときになるのかな。まあ、肉眼で見える最低の大きさの16ミリというのは編集を覚えるには最適なメディアなんです。だから、話は飛びますが、『初国知所之天皇』で再び8ミリに戻った時には、8ミリでの編集の困難さを知っていましたから、撮影するときに編集する、編集しながら撮影するということが最初からできたと言うか、8ミリはそうするしかないということが分かっていたから、そう撮影したんです。
 ――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の撮影はご自分でやられたんですか?
ええ、自分が登場しないところは自分でやって、それ以外のところは、麻布高校の友人に頼んでやってもらった。器用な友達に、三脚を立ててアングルを決めて、カメラの操作を一通り教えて、回してもらったんです。
――これは「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」(68)のグランプリ作品ですね。
草月シネマテークが「第1回東京実験映画祭」を開催したのが僕が高校2年の時で、その後、草月シネマテークが中心になって「フィルムアート」という雑誌を創刊した。それに合わせて2回目が開催されたので、実験映画祭から名前を変えたんですよ。だから、厳密にいえば映画祭として2回目だけど、名前を変えたからまた第1回ということで「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」となったんですね。そこで、グランプリとATG賞と両方をもらいました。
――いま見ても新鮮な映画ですよね。カットが短く、テンポも早く、のっけから様々な映画からのパロディや引用があり、劇中劇も入っている。とても高校生が作った作品とは思えません。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の第一章が「地獄の季節」となっていますが…。
小林秀雄訳のアルチュール・ランボーの『地獄の季節』がすごい好きでした。岩波文庫版が高校生たちのバイブルみたいになっていて、みんな読んでいましたね。星ひとつ(*4)の50円だったし。
この『おかしさに彩られた悲しみのバラード』という映画の成り立ちから話しますと、シナリオはこの映画の途中で出てくる『黄金時代‘68』、劇中劇というか、映画内映画として組み込まれている映画なんですけど、その分しか書いていませんでした。と言うか、そもそも最初は『黄金時代’68』という映画を作ろうとしたんです。ぼくは、映画館ばかり通っていた高校生でしたが、映画を製作するとなると友人に協力を頼まなくてはならないので、急に学校へちゃんと通いはじめた。そして、授業中にシナリオをスタッフやってくれる友人たちに回し読みしてもらい、休み時間になるとみんなで集まって、シナリオのどこをどう直そうかと相談した。そうやって『黄金時代‘68』のシナリオを書いたんだけど、あまり評判が良くなかったんです。
――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の撮影はご自分でやられたんですか?
ええ、自分が登場しないところは自分でやって、それ以外のところは、麻布高校の友人に頼んでやってもらった。器用な友達に、三脚を立ててアングルを決めて、カメラの操作を一通り教えて、回してもらったんです。
――これは「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」(68)のグランプリ作品ですね。
草月シネマテークが「第1回東京実験映画祭」を開催したのが僕が高校2年の時で、その後、草月シネマテークが中心になって「フィルムアート」という雑誌を創刊した。それに合わせて2回目が開催されたので、実験映画祭から名前を変えたんですよ。だから、厳密にいえば映画祭として2回目だけど、名前を変えたからまた第1回ということで「第1回東京フィルムアート・フェスティバル」となったんですね。そこで、グランプリとATG賞と両方をもらいました。
――いま見ても新鮮な映画ですよね。カットが短く、テンポも早く、のっけから様々な映画からのパロディや引用があり、劇中劇も入っている。とても高校生が作った作品とは思えません。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の第一章が「地獄の季節」となっていますが…。
小林秀雄訳のアルチュール・ランボーの『地獄の季節』がすごい好きでした。岩波文庫版が高校生たちのバイブルみたいになっていて、みんな読んでいましたね。星ひとつ(*4)の50円だったし。
この『おかしさに彩られた悲しみのバラード』という映画の成り立ちから話しますと、シナリオはこの映画の途中で出てくる『黄金時代‘68』、劇中劇というか、映画内映画として組み込まれている映画なんですけど、その分しか書いていませんでした。と言うか、そもそも最初は『黄金時代’68』という映画を作ろうとしたんです。ぼくは、映画館ばかり通っていた高校生でしたが、映画を製作するとなると友人に協力を頼まなくてはならないので、急に学校へちゃんと通いはじめた。そして、授業中にシナリオをスタッフやってくれる友人たちに回し読みしてもらい、休み時間になるとみんなで集まって、シナリオのどこをどう直そうかと相談した。そうやって『黄金時代‘68』のシナリオを書いたんだけど、あまり評判が良くなかったんです。
 ――かなり政治的な内容の部分もありますからね。原っぱで「ベトナム戦争ごっこ」をする場面は、ゴダールの引用だとわかりますが、高校生には少し難しいでしょう。
いや、評判が良くなかったというのは、難しいということではなかったんです。政治意識と政治的な主体っていうのかな。その立場の問題なんです。当時の先鋭的な高校生の政治意識はみんな全共闘運動のところまで行ってましたからね。ぼくとしては、一応、反戦運動を問い直すという政治的なメッセージを『黄金時代‘68』というシナリオに込めたつもりでした。例えばベ平連がやっている市民運動は、ベトナムで戦争で行われてる非道に対して、人道的に反対する声を集約していくだけではないか。そういう反戦運動のあり方に対して、それは少し違うと考えていた。やはり自分の置かれている状況から運動を始めなくてはいけないのではないか、と。その頃には東大や早稲田大で闘争が起き始めていた頃でした。だから、そのような無媒介的にヒューマニズムで反戦を唱えるというのは違うのではないか、と考えていたわけで、それを、そういうメッセージをそのシナリオに入れて書いたつもりだったんです。でも、みんな、甘いって言うんです。
みんなも同じような事を考えていた。自分たちの置かれた状況から出発することを考えていた。だから、シナリオを検討しているうちに、反戦運動の批判が描かれているだけじゃだめだ、そこで自分たちが主体的に何をするかが描かれていないと仕様がないと、みんな言うんですよ。「映画なんか撮ってる場合じゃない! 今すぐ休み時間に机を積み上げてバリケード封鎖しよう!」とか言いだす奴もいました。やっぱり高みに立った状況批判だけじゃなくて、そのなかでどうすべきなのかということを描かなければだめなんだと、ぼくも自分で書いたものがまだツメが甘いと思ってたし、みんなの批判を真摯に受けとめたんですが、でも、どうしたらいいか分からず困ってしまったんです。へたをすると、安易なプロパガンダに流れてしまう。困った、困った、と。その時ひらめいたんですね。このような状況そのものを映画にしたらいいんじゃないか、ということにぼくは気づきました。映画が降りて来たんですね。この時が映画が降りて来た初めての経験です。それが春休みのはじまる直前でした。「分かった!任せてくれ!だいたい構想はできたから」と言って、とにかく朝の集合場所と時間だけ決めて、その日の撮影分のシナリオは当日の朝までに書いて渡すという形で納得してもらい、高校2年から3年になる春休みに、とにかく撮りはじめたのが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』なんです。1968年という政治的な状況があって、アメリカという帝国主義国家によってベトナム戦争が行われていて、ぼくたちが生まれ育った日本という国家はそれに協力している。そのなかで自分たちは何をしたらいいのか分からない。映画を撮るにしてもどんな映画を撮ったらいいのか分からない。それでも映画だけは撮った!というのがこの映画に込められたメッセージだと思います。だからこのメッセージは自分たちにも突きつけられた。高校生としての自分たちの置かれた位置は、国家の構成員を育成する教育機関のレールの上を走っている、走らされているだけということは分かっていた。だから、レールを走り続けてその先の大学まであえて行くのかという問いが、みんな、この映画を撮る事によって突きつけられてしまった。だから大学へ行かなかったのがぼくを含めて何人かいました。
――かなり政治的な内容の部分もありますからね。原っぱで「ベトナム戦争ごっこ」をする場面は、ゴダールの引用だとわかりますが、高校生には少し難しいでしょう。
いや、評判が良くなかったというのは、難しいということではなかったんです。政治意識と政治的な主体っていうのかな。その立場の問題なんです。当時の先鋭的な高校生の政治意識はみんな全共闘運動のところまで行ってましたからね。ぼくとしては、一応、反戦運動を問い直すという政治的なメッセージを『黄金時代‘68』というシナリオに込めたつもりでした。例えばベ平連がやっている市民運動は、ベトナムで戦争で行われてる非道に対して、人道的に反対する声を集約していくだけではないか。そういう反戦運動のあり方に対して、それは少し違うと考えていた。やはり自分の置かれている状況から運動を始めなくてはいけないのではないか、と。その頃には東大や早稲田大で闘争が起き始めていた頃でした。だから、そのような無媒介的にヒューマニズムで反戦を唱えるというのは違うのではないか、と考えていたわけで、それを、そういうメッセージをそのシナリオに入れて書いたつもりだったんです。でも、みんな、甘いって言うんです。
みんなも同じような事を考えていた。自分たちの置かれた状況から出発することを考えていた。だから、シナリオを検討しているうちに、反戦運動の批判が描かれているだけじゃだめだ、そこで自分たちが主体的に何をするかが描かれていないと仕様がないと、みんな言うんですよ。「映画なんか撮ってる場合じゃない! 今すぐ休み時間に机を積み上げてバリケード封鎖しよう!」とか言いだす奴もいました。やっぱり高みに立った状況批判だけじゃなくて、そのなかでどうすべきなのかということを描かなければだめなんだと、ぼくも自分で書いたものがまだツメが甘いと思ってたし、みんなの批判を真摯に受けとめたんですが、でも、どうしたらいいか分からず困ってしまったんです。へたをすると、安易なプロパガンダに流れてしまう。困った、困った、と。その時ひらめいたんですね。このような状況そのものを映画にしたらいいんじゃないか、ということにぼくは気づきました。映画が降りて来たんですね。この時が映画が降りて来た初めての経験です。それが春休みのはじまる直前でした。「分かった!任せてくれ!だいたい構想はできたから」と言って、とにかく朝の集合場所と時間だけ決めて、その日の撮影分のシナリオは当日の朝までに書いて渡すという形で納得してもらい、高校2年から3年になる春休みに、とにかく撮りはじめたのが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』なんです。1968年という政治的な状況があって、アメリカという帝国主義国家によってベトナム戦争が行われていて、ぼくたちが生まれ育った日本という国家はそれに協力している。そのなかで自分たちは何をしたらいいのか分からない。映画を撮るにしてもどんな映画を撮ったらいいのか分からない。それでも映画だけは撮った!というのがこの映画に込められたメッセージだと思います。だからこのメッセージは自分たちにも突きつけられた。高校生としての自分たちの置かれた位置は、国家の構成員を育成する教育機関のレールの上を走っている、走らされているだけということは分かっていた。だから、レールを走り続けてその先の大学まであえて行くのかという問いが、みんな、この映画を撮る事によって突きつけられてしまった。だから大学へ行かなかったのがぼくを含めて何人かいました。
 ――創作の秘密と言いますか、一番お聞きしたかったところに入ってきていると思います。一章、二章という風に繋がっていきますが、撮影は章ごとに行なったんですか?
そうです。順番に撮っていました。そういうシナリオ無しのような撮り方をすると順撮りしてかないと分からなくなってしまうので。頭のなかでいろいろな映画の記憶が繋がっていってね、それを整理していかなければならなかったんです。劇中劇にあたる『黄金時代‘68』の部分はルイス・ブニュエルの『黄金時代』からの引用というか本歌取りなんです。朝鮮人の少年のリンチのシーンがありますが、あれは大島渚の『絞首刑』からの引用ですね。大島さんの60年代後半の映画も、創造社になってからの『白昼の通り魔』からはすべてリアルタイムで見ていますね。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』では、そのリンチされた朝鮮人の少年が逃げるところまでは事前に考えていました。その後はトリュフォーの『大人は判ってくれない』のラストシーンのように浜辺で撮ろうと考えていました。本当のラストシーンの「僕たちはこの夏に映画をつくった」というところは、大林宣彦の『いつか見たドラキュラ』の終わり方のパロディですね。
編集作業はひとりでやりました。ラッシュで編集を始めてプリントを焼くまでに、4月から7月まで4ヶ月かかっていますね。まあ、そこまでひとりでやったのだから、間違いなく僕の作品だといえますが、そこにいたるまでの製作プロセスを考えれば麻布の友人たちとの総力戦じゃないですか。現像は市ヶ谷に読売現像所といういいラボがあって、普段はニュース映画しかやってないようなところなんですが、法政大学の映研などがよく使っていたところです。志村喬と森繁久彌を足して割ったような、森田さんという凄くいいおじさんがいました。その後の作業手順をすべて教わりました。「ラッシュ編集をしてくれば、ネガ編は格安でしてあげるよ」と言ってくれて、プリントをあげて、それに磁気コーティングをして、ぼくたちがオープンリールテープに宅録した音源を微調整して入れてくれました。賞をもらった後にプリントを何本か作ることになってからも、シネテープから音ネガを作って焼いた方が安いということになって、その作業もその読売現像所でやってくれました。ラボがそこまでやってくれるというのは考えられない事です。ニュース映画を中心にやっていた所だったんでそれができたんでしょうが、ラッキーでした。
――創作の秘密と言いますか、一番お聞きしたかったところに入ってきていると思います。一章、二章という風に繋がっていきますが、撮影は章ごとに行なったんですか?
そうです。順番に撮っていました。そういうシナリオ無しのような撮り方をすると順撮りしてかないと分からなくなってしまうので。頭のなかでいろいろな映画の記憶が繋がっていってね、それを整理していかなければならなかったんです。劇中劇にあたる『黄金時代‘68』の部分はルイス・ブニュエルの『黄金時代』からの引用というか本歌取りなんです。朝鮮人の少年のリンチのシーンがありますが、あれは大島渚の『絞首刑』からの引用ですね。大島さんの60年代後半の映画も、創造社になってからの『白昼の通り魔』からはすべてリアルタイムで見ていますね。『おかしさに彩られた悲しみのバラード』では、そのリンチされた朝鮮人の少年が逃げるところまでは事前に考えていました。その後はトリュフォーの『大人は判ってくれない』のラストシーンのように浜辺で撮ろうと考えていました。本当のラストシーンの「僕たちはこの夏に映画をつくった」というところは、大林宣彦の『いつか見たドラキュラ』の終わり方のパロディですね。
編集作業はひとりでやりました。ラッシュで編集を始めてプリントを焼くまでに、4月から7月まで4ヶ月かかっていますね。まあ、そこまでひとりでやったのだから、間違いなく僕の作品だといえますが、そこにいたるまでの製作プロセスを考えれば麻布の友人たちとの総力戦じゃないですか。現像は市ヶ谷に読売現像所といういいラボがあって、普段はニュース映画しかやってないようなところなんですが、法政大学の映研などがよく使っていたところです。志村喬と森繁久彌を足して割ったような、森田さんという凄くいいおじさんがいました。その後の作業手順をすべて教わりました。「ラッシュ編集をしてくれば、ネガ編は格安でしてあげるよ」と言ってくれて、プリントをあげて、それに磁気コーティングをして、ぼくたちがオープンリールテープに宅録した音源を微調整して入れてくれました。賞をもらった後にプリントを何本か作ることになってからも、シネテープから音ネガを作って焼いた方が安いということになって、その作業もその読売現像所でやってくれました。ラボがそこまでやってくれるというのは考えられない事です。ニュース映画を中心にやっていた所だったんでそれができたんでしょうが、ラッキーでした。
 ――プリントは2種類あったということですか。音楽はエリック・ドルフィーからビートルズまで、さまざまな楽曲を使っていますね。
ええ、好きな音楽を入れました。受賞式のパーティーで武満徹さんに怒られましたけどね。音楽には著作権があるんだといわれて。ATG賞をもらったので新宿文化で上映する予定だったのだけど、著作権料を到底払い切れないということで上映できなくなってしまった。そうしたら、武満徹さんが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』用に音楽を作り直してあげるって、言ってくれたんです。でも、断っちゃったんですよ(笑)。
――何で断ったりするんですか、もったいない!
若さゆえ、と言うか、ロック少年だったので、クラシックの武満徹とロックのビートルズを差別化する意識があったんでしょうね。僕が映画のなかで使ったビートルズの曲よりも良い曲を武満さんが作れるのか、みたいな。まあ、メチャメチャとんがっていましたから。でも武満さんは全然クラッシックというような領域意識のある人ではなかったんですね。非常にフラットでオルタナティブな人だった。後になって武満さんにお願いすればよかったと悔やまれました。亡くなられた今思いますと、それこそ弟子入りして譜面の清書でもさせてもらえばよかったという感じですよね。若いということにはそういう二面性がありますね。
これは後の話ですが、『東京战争戦後秘話』のとき、武満さんが音楽を担当することになり「原クン、どういう音楽が欲しいかね」と聞いてきてくれたんです。僕がシナリオを書いた映画でしたから。僕はその時に「ビートルズの『ストロベリーフィールズ・フォーエバー』にしましょう」と言ったんです。武満さんはとても喜んで「僕もビートルズは大好きだよ」といって、そのような曲を作ってきてくれました。でも、それは後で考えるともう少し複雑な話です。どうやら大島渚さんが武満さんに「原クンがシナリオ書いているから、音楽のことも原クンに直接相談してもらった方がいいだろう」と言ったようなんです。大島さんが武満さんに「音楽はビートルズでいきましょう」なんて言えば、武満さんは怒っちゃいますよね。僕が言ったから通った話なんです。その辺は、大島さんは裏でちゃんと計算していて、そういう人の使い方がうまい監督なんですね。黒澤明の『乱』で武満さんが音楽を担当したとき、黒澤さんに「マーラーのような音楽でいきたい」と言われて、しかもそのマーラーを聴かされて、武満さんが怒ったというのは有名な話ですけど、選手の力をすべて引き出して勝つ試合をする監督という意味では、大島さんは黒澤さんよりも優れていましたね。
――プリントは2種類あったということですか。音楽はエリック・ドルフィーからビートルズまで、さまざまな楽曲を使っていますね。
ええ、好きな音楽を入れました。受賞式のパーティーで武満徹さんに怒られましたけどね。音楽には著作権があるんだといわれて。ATG賞をもらったので新宿文化で上映する予定だったのだけど、著作権料を到底払い切れないということで上映できなくなってしまった。そうしたら、武満徹さんが『おかしさに彩られた悲しみのバラード』用に音楽を作り直してあげるって、言ってくれたんです。でも、断っちゃったんですよ(笑)。
――何で断ったりするんですか、もったいない!
若さゆえ、と言うか、ロック少年だったので、クラシックの武満徹とロックのビートルズを差別化する意識があったんでしょうね。僕が映画のなかで使ったビートルズの曲よりも良い曲を武満さんが作れるのか、みたいな。まあ、メチャメチャとんがっていましたから。でも武満さんは全然クラッシックというような領域意識のある人ではなかったんですね。非常にフラットでオルタナティブな人だった。後になって武満さんにお願いすればよかったと悔やまれました。亡くなられた今思いますと、それこそ弟子入りして譜面の清書でもさせてもらえばよかったという感じですよね。若いということにはそういう二面性がありますね。
これは後の話ですが、『東京战争戦後秘話』のとき、武満さんが音楽を担当することになり「原クン、どういう音楽が欲しいかね」と聞いてきてくれたんです。僕がシナリオを書いた映画でしたから。僕はその時に「ビートルズの『ストロベリーフィールズ・フォーエバー』にしましょう」と言ったんです。武満さんはとても喜んで「僕もビートルズは大好きだよ」といって、そのような曲を作ってきてくれました。でも、それは後で考えるともう少し複雑な話です。どうやら大島渚さんが武満さんに「原クンがシナリオ書いているから、音楽のことも原クンに直接相談してもらった方がいいだろう」と言ったようなんです。大島さんが武満さんに「音楽はビートルズでいきましょう」なんて言えば、武満さんは怒っちゃいますよね。僕が言ったから通った話なんです。その辺は、大島さんは裏でちゃんと計算していて、そういう人の使い方がうまい監督なんですね。黒澤明の『乱』で武満さんが音楽を担当したとき、黒澤さんに「マーラーのような音楽でいきたい」と言われて、しかもそのマーラーを聴かされて、武満さんが怒ったというのは有名な話ですけど、選手の力をすべて引き出して勝つ試合をする監督という意味では、大島さんは黒澤さんよりも優れていましたね。
 ――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の章のタイトルが入るときに、イラストレーションを使っていますね。
あれはビアズレーが好きな室井伸二クンという友人が描いてくれたんです。デザインのプロになって、今は自分でデザイン事務所やっています。とにかく、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、審査員の方も観客もみんなおもしろがってくれました。
――原さんの著書『見たい映画のことだけを』に「映画の肉体」という言葉がありますが、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、まさに映画の肉体を持った「眼の映画」ですよね。物語でぐいぐい引っ張るのではなく、映像で惹きつける視覚的要素の強い映画です。
実はぼくは、『バラード』を撮った後、仕事をして家を出たかったということもあって、東京フィルムアート・フェスティバルの審査員だった松本俊夫さんに頼んで『薔薇の葬列』の演出部につけてもらったことがあるんですが、たとえば、松本俊夫さんにしても、ゴダールやレネが良いと言っていても、自分で劇映画を撮るとなるとシナリオをちゃんとあげて、スタッフをちゃんと従えてシナリオどおりに撮ることになってしまう。それに初めてのスタッフ、キャスト同士が多くて、そうするとコミュニケーションは言葉で行き交う領域だけになってしまい、シナリオを中心に言語で了解できる領域でやりとりしてしまう。撮影という作業が段取りになってしまう。すると映画が肉体を持たなくなってしまうんですね。そういうことを感じました。その後、溝口健二と小津安二郎を集中的に見ました。二人とも頑固に自分のスタイルを守り通しているんですが、それはシャーマニズムではないかと思いました。巫女として映画の神様を降ろしているんだと。それが映画の肉体だと思って「映画の肉体」という文章を書きました。おそらく溝口さん、小津さんのスタッフは、そういうことが分かっていて、一緒に祈祷していたんでしょうね。そういう意味では、「映画の肉体」は、無意識的な部分でスタッフが如何に映画の神様を降ろすというシャーマニズム的部分を共有できるかという問題かもしれない。『バラード』はけっこう追いつめられた状況で作ってましたから、それができたのかもしれない。
――『おかしさに彩られた悲しみのバラード』の章のタイトルが入るときに、イラストレーションを使っていますね。
あれはビアズレーが好きな室井伸二クンという友人が描いてくれたんです。デザインのプロになって、今は自分でデザイン事務所やっています。とにかく、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、審査員の方も観客もみんなおもしろがってくれました。
――原さんの著書『見たい映画のことだけを』に「映画の肉体」という言葉がありますが、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は、まさに映画の肉体を持った「眼の映画」ですよね。物語でぐいぐい引っ張るのではなく、映像で惹きつける視覚的要素の強い映画です。
実はぼくは、『バラード』を撮った後、仕事をして家を出たかったということもあって、東京フィルムアート・フェスティバルの審査員だった松本俊夫さんに頼んで『薔薇の葬列』の演出部につけてもらったことがあるんですが、たとえば、松本俊夫さんにしても、ゴダールやレネが良いと言っていても、自分で劇映画を撮るとなるとシナリオをちゃんとあげて、スタッフをちゃんと従えてシナリオどおりに撮ることになってしまう。それに初めてのスタッフ、キャスト同士が多くて、そうするとコミュニケーションは言葉で行き交う領域だけになってしまい、シナリオを中心に言語で了解できる領域でやりとりしてしまう。撮影という作業が段取りになってしまう。すると映画が肉体を持たなくなってしまうんですね。そういうことを感じました。その後、溝口健二と小津安二郎を集中的に見ました。二人とも頑固に自分のスタイルを守り通しているんですが、それはシャーマニズムではないかと思いました。巫女として映画の神様を降ろしているんだと。それが映画の肉体だと思って「映画の肉体」という文章を書きました。おそらく溝口さん、小津さんのスタッフは、そういうことが分かっていて、一緒に祈祷していたんでしょうね。そういう意味では、「映画の肉体」は、無意識的な部分でスタッフが如何に映画の神様を降ろすというシャーマニズム的部分を共有できるかという問題かもしれない。『バラード』はけっこう追いつめられた状況で作ってましたから、それができたのかもしれない。
 ※以上の写真は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
『自己表出史 早川義夫編』
――高校は卒業されたんですか。
高3のときの担任の先生が、いい人だったというか、理解があったので卒業はさせてくれました。大学受験も考えましたが、とにかく受験勉強をしていなかったし、僕が受けるときは東大闘争で東大の入試が中止になった年でした。それで、親も息子が大学へ行って学生運動をやるよりは、まだ映画でもやっていてくれる方がいいと判断したんです。麻布高校では学園闘争はありませんでしたが、都立大付属高校には、反戦高協という中核派の拠点ができていました。その翌年の69年になると、高校まで学生組織がおりて来たんですよ。ほとんど学校へは行かずに、松本俊夫さんの『薔薇の葬列』でフォースの助監督を経験したのが高3の三学期だったんです。松本さんに「もう大学行かないことに決めて、映画の仕事してみたいのでつけて下さい」と頼んだ。松本さんは僕が商業映画に関しては何も知らなくて戦力にならないだろうということで、ちゃんとした仕事をくれなかった。『薔薇の葬列』の現場では、サード助監督までいれば充分だったので、フォース助監督の仕事なんてほとんど無かったんです。現場では、カメラを置く度にファインダーを覗かせてもらっていた(笑)。そのことが照明部から大顰蹙を買いました。スタッフはプロフェッショナルで、カメラマンが鈴木達夫さん、照明もちゃんとした劇映画のスタッフでした。現場では、モブ(群衆)シーンで若いのが必要なときに、友だちに電話しまくって、集めてくるような仕出し屋のような仕事をしていました。『薔薇の葬列』は時間軸が交錯する迷宮的な構造を持っている映画ですが、現場では、松本俊夫ともあろう作家がただシナリオ通りに撮っているのが不満でした。それで納得できなくて「これはこう撮った方がいいんじゃないですか」みたいなことを言った。監督に意見するフォース助監督ということで、スタッフの人たちから顰蹙を買いました。とにかく、照明部がいちばんきつかったかな。
高校を卒業する前後でもうひとつ忙しくしていたと言うか、動いていたことがありまして、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を上映したいと言ってきた高校生たちがいて、彼らも映画を撮っていたんです。彼らと連絡取っているうちに「全国高校映画連盟」というのが出来ていった。ちょっとまた川喜多さんたちのシネクラブ研究会の話になりますが、その頃、シネクラブ研究会の百回記念に、鈴木清順全作品の連続上映を企画して、川喜多さんが日活にフィルムを借りに行ったら、拒否され、おまけに、うちにはそんな映画青年たちに人気のあるような芸術映画を撮るような監督は要らないということで、清順さんが日活を首になったという事件がありました。それからシネクラブ研究会が母体となって、鈴木清順問題共闘会議が発足したんです。清順共闘は、週に一度、撮影所の助監督や独立プロの監督やプロデューサーなどが中心に集まって、松田政男さんや河原畑寧さんなどの批評家、足立正生さんなんかも常連で、清順さんの不当解雇問題だけでなくて、当時の映画界を取り巻くあらゆる問題を取り上げて話し合っていたんです。そこにもぼくはというか、『バラード』に主演した瀬川元秀クンなんかも一緒に顔を出すようになった。戦後初めて騒乱罪が適用された10・21の国際反戦デーで国学院の映画研究会の当日の記録映像がその騒乱罪を立件するための証拠物件として警察に差し押さえられたという事件があって、国学院の映研が清順共闘で報告すると言うんで、ぼくたちも話を聞きに行ったんですけど、闘争を記録する事が闘争だみたいな感じで、大学生ってバカだなと思ったこともあって、高校生たちの映画のレベルの方が圧倒的に高いんですね。変に左翼かぶれしてないんで、作品として自立しているわけ。ぼくたちの置かれている状況が感覚的に描かれているわけ。それもあって、「全国高校映画連盟」の結成にはかなり力を注ぎました。松本さんのところでも助監督してたので、忙しかったですね。それこそ学校へ行っている暇もなかった。でも、卒業はさせてもらったんです。
※以上の写真は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』
『自己表出史 早川義夫編』
――高校は卒業されたんですか。
高3のときの担任の先生が、いい人だったというか、理解があったので卒業はさせてくれました。大学受験も考えましたが、とにかく受験勉強をしていなかったし、僕が受けるときは東大闘争で東大の入試が中止になった年でした。それで、親も息子が大学へ行って学生運動をやるよりは、まだ映画でもやっていてくれる方がいいと判断したんです。麻布高校では学園闘争はありませんでしたが、都立大付属高校には、反戦高協という中核派の拠点ができていました。その翌年の69年になると、高校まで学生組織がおりて来たんですよ。ほとんど学校へは行かずに、松本俊夫さんの『薔薇の葬列』でフォースの助監督を経験したのが高3の三学期だったんです。松本さんに「もう大学行かないことに決めて、映画の仕事してみたいのでつけて下さい」と頼んだ。松本さんは僕が商業映画に関しては何も知らなくて戦力にならないだろうということで、ちゃんとした仕事をくれなかった。『薔薇の葬列』の現場では、サード助監督までいれば充分だったので、フォース助監督の仕事なんてほとんど無かったんです。現場では、カメラを置く度にファインダーを覗かせてもらっていた(笑)。そのことが照明部から大顰蹙を買いました。スタッフはプロフェッショナルで、カメラマンが鈴木達夫さん、照明もちゃんとした劇映画のスタッフでした。現場では、モブ(群衆)シーンで若いのが必要なときに、友だちに電話しまくって、集めてくるような仕出し屋のような仕事をしていました。『薔薇の葬列』は時間軸が交錯する迷宮的な構造を持っている映画ですが、現場では、松本俊夫ともあろう作家がただシナリオ通りに撮っているのが不満でした。それで納得できなくて「これはこう撮った方がいいんじゃないですか」みたいなことを言った。監督に意見するフォース助監督ということで、スタッフの人たちから顰蹙を買いました。とにかく、照明部がいちばんきつかったかな。
高校を卒業する前後でもうひとつ忙しくしていたと言うか、動いていたことがありまして、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を上映したいと言ってきた高校生たちがいて、彼らも映画を撮っていたんです。彼らと連絡取っているうちに「全国高校映画連盟」というのが出来ていった。ちょっとまた川喜多さんたちのシネクラブ研究会の話になりますが、その頃、シネクラブ研究会の百回記念に、鈴木清順全作品の連続上映を企画して、川喜多さんが日活にフィルムを借りに行ったら、拒否され、おまけに、うちにはそんな映画青年たちに人気のあるような芸術映画を撮るような監督は要らないということで、清順さんが日活を首になったという事件がありました。それからシネクラブ研究会が母体となって、鈴木清順問題共闘会議が発足したんです。清順共闘は、週に一度、撮影所の助監督や独立プロの監督やプロデューサーなどが中心に集まって、松田政男さんや河原畑寧さんなどの批評家、足立正生さんなんかも常連で、清順さんの不当解雇問題だけでなくて、当時の映画界を取り巻くあらゆる問題を取り上げて話し合っていたんです。そこにもぼくはというか、『バラード』に主演した瀬川元秀クンなんかも一緒に顔を出すようになった。戦後初めて騒乱罪が適用された10・21の国際反戦デーで国学院の映画研究会の当日の記録映像がその騒乱罪を立件するための証拠物件として警察に差し押さえられたという事件があって、国学院の映研が清順共闘で報告すると言うんで、ぼくたちも話を聞きに行ったんですけど、闘争を記録する事が闘争だみたいな感じで、大学生ってバカだなと思ったこともあって、高校生たちの映画のレベルの方が圧倒的に高いんですね。変に左翼かぶれしてないんで、作品として自立しているわけ。ぼくたちの置かれている状況が感覚的に描かれているわけ。それもあって、「全国高校映画連盟」の結成にはかなり力を注ぎました。松本さんのところでも助監督してたので、忙しかったですね。それこそ学校へ行っている暇もなかった。でも、卒業はさせてもらったんです。
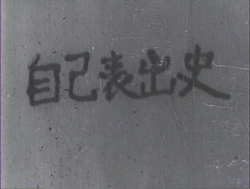 ――『自己表出史 早川義夫編』の話に入りましょうか。
卒業した後、やっぱり「全国高校映画連盟」の関係で、ドキュメンタリー映画作家の野田真吉さん(*5)の息子の亘真幸(わたりまさゆき)クンと友達になりました。それで野田真吉さんの家へよく遊びに行っていた。当時の野田さんは神奈川ニュースで仕事をしたり、新日鉄などの企業PRフィルムを作ったりしていました。野田さんには息子のように可愛がられました。遊びに行く度に、仕事部屋に通してくれていろんな映画の話をしてくれました。帰りには、「この本読むといいよ」と本を貸してくれたり、「このフィルムを使いなよ」と仕事で余った16ミリフィルムをくれました。現像も仕事の企業PRフィルムを現像するときに、一緒に現像してやるよ、という言う事で、次に行く時には、ラベルに野田プロダクション『自己表出史』と書いて撮影済みフィルムを持っていって現像までしてもらいました。そういうわけで、野田真吉さんがこの映画をプロデュースしてくれたようなものなんです。
――元々、ジャックスの音楽が好きだったんですか。
ええ、そうです。いつどこでジャックスの音楽と出会ったかは定かではないんですが、日本語のバンドとしては、ビートルズやストーンズに匹敵する唯一のバンドだと思って、とにかくジャックスの映画を撮ってみたいと思ったんです。それで、やっぱり、それも「全国高校映画連盟」のつながりなんですけど、詩人・福間健二さんの弟の福間雄三クンと仲良くなりました。福間雄三クンは日野高校にいたんですが、8ミリで私的で詩的、ワタクシ的でポエチックな素晴らしい映画を撮っていて、彼とぼくとが「全国高校映画連盟」をまとめあげる中心人物のようになっていった。それで、組織の旗揚げに全国高校映画祭をやろうかみたいな相談で、ずいぶん雄三クンの家に行って泊めてもらったりしたこともあって、福間健二さんと知り合いになったんですけど、福間健二さんは、若松孝二監督の若松プロに出入りしていました。ジャックスのリーダー、早川義夫さんも若松監督の映画に出演したり、『腹貸し女』のサウンドトラックを担当したりして、若松プロと付き合いがあった。それで福間健二さんに早川さんを紹介してもらったんです。
――『自己表出史 早川義夫編』の話に入りましょうか。
卒業した後、やっぱり「全国高校映画連盟」の関係で、ドキュメンタリー映画作家の野田真吉さん(*5)の息子の亘真幸(わたりまさゆき)クンと友達になりました。それで野田真吉さんの家へよく遊びに行っていた。当時の野田さんは神奈川ニュースで仕事をしたり、新日鉄などの企業PRフィルムを作ったりしていました。野田さんには息子のように可愛がられました。遊びに行く度に、仕事部屋に通してくれていろんな映画の話をしてくれました。帰りには、「この本読むといいよ」と本を貸してくれたり、「このフィルムを使いなよ」と仕事で余った16ミリフィルムをくれました。現像も仕事の企業PRフィルムを現像するときに、一緒に現像してやるよ、という言う事で、次に行く時には、ラベルに野田プロダクション『自己表出史』と書いて撮影済みフィルムを持っていって現像までしてもらいました。そういうわけで、野田真吉さんがこの映画をプロデュースしてくれたようなものなんです。
――元々、ジャックスの音楽が好きだったんですか。
ええ、そうです。いつどこでジャックスの音楽と出会ったかは定かではないんですが、日本語のバンドとしては、ビートルズやストーンズに匹敵する唯一のバンドだと思って、とにかくジャックスの映画を撮ってみたいと思ったんです。それで、やっぱり、それも「全国高校映画連盟」のつながりなんですけど、詩人・福間健二さんの弟の福間雄三クンと仲良くなりました。福間雄三クンは日野高校にいたんですが、8ミリで私的で詩的、ワタクシ的でポエチックな素晴らしい映画を撮っていて、彼とぼくとが「全国高校映画連盟」をまとめあげる中心人物のようになっていった。それで、組織の旗揚げに全国高校映画祭をやろうかみたいな相談で、ずいぶん雄三クンの家に行って泊めてもらったりしたこともあって、福間健二さんと知り合いになったんですけど、福間健二さんは、若松孝二監督の若松プロに出入りしていました。ジャックスのリーダー、早川義夫さんも若松監督の映画に出演したり、『腹貸し女』のサウンドトラックを担当したりして、若松プロと付き合いがあった。それで福間健二さんに早川さんを紹介してもらったんです。
 ――ジャックスの音楽性は、それまでのグループサウンズとは全然違いますよね。もとはフォーク・ミュージックですが、有名な「マリアンヌ」という曲では、サイケデリックなギターソロが入っていたり、早川さんの情念的なヴォーカルであったり、日本語ロックの草分けの存在として現在も評価が高いバンドですね。
ジャックスはザ・タイガースなどに比べると、圧倒的にビートルズやストーンズに近いロック的な音楽性です。作詞・作曲も自分たちの手で担当しています。ザ・タイガースや、テンプターズでは、かまやつひろしが多少は自分で曲を書いていたみたいですが、やはり作曲は、すぎやまこういちなんかが担当していて、歌謡曲の人がロックっぽい曲を作っていたわけです。グループサウンズの音楽はロックと言っても、ビートルズやストーンズのような「ロック」とは全然違うのです。ロックの要素が入った歌謡曲といった感じで、美空ひばりの「真っ赤な太陽」なんかと同じですよ。本牧にはゴールデンカップスという上手いバンドもいましたが、彼らはR&Bのカバーをちゃんとやっていましたが、さほどオリジナリティーはなかった。そのような意味で、ジャックスが日本できちんと自分たちのロックをやっていた唯一のバンドに思えました。
――早川義夫さんがジャックスを解散したときに、撮りはじめたんですか。
早川さんに会って「ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいんですけど」と言ったら、「ああ、ジャックスは解散しましたよ」と返された。これからはソロでやっていくというので、「じゃ、それを撮らせて下さい」と言って撮り始めたんです。アルバムを製作しているときの早川さんのURCレコードの事務所での様子、ライヴステージ、それに新宿の街を歩いている姿などを撮影しました。
――ジャックスの音楽性は、それまでのグループサウンズとは全然違いますよね。もとはフォーク・ミュージックですが、有名な「マリアンヌ」という曲では、サイケデリックなギターソロが入っていたり、早川さんの情念的なヴォーカルであったり、日本語ロックの草分けの存在として現在も評価が高いバンドですね。
ジャックスはザ・タイガースなどに比べると、圧倒的にビートルズやストーンズに近いロック的な音楽性です。作詞・作曲も自分たちの手で担当しています。ザ・タイガースや、テンプターズでは、かまやつひろしが多少は自分で曲を書いていたみたいですが、やはり作曲は、すぎやまこういちなんかが担当していて、歌謡曲の人がロックっぽい曲を作っていたわけです。グループサウンズの音楽はロックと言っても、ビートルズやストーンズのような「ロック」とは全然違うのです。ロックの要素が入った歌謡曲といった感じで、美空ひばりの「真っ赤な太陽」なんかと同じですよ。本牧にはゴールデンカップスという上手いバンドもいましたが、彼らはR&Bのカバーをちゃんとやっていましたが、さほどオリジナリティーはなかった。そのような意味で、ジャックスが日本できちんと自分たちのロックをやっていた唯一のバンドに思えました。
――早川義夫さんがジャックスを解散したときに、撮りはじめたんですか。
早川さんに会って「ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいんですけど」と言ったら、「ああ、ジャックスは解散しましたよ」と返された。これからはソロでやっていくというので、「じゃ、それを撮らせて下さい」と言って撮り始めたんです。アルバムを製作しているときの早川さんのURCレコードの事務所での様子、ライヴステージ、それに新宿の街を歩いている姿などを撮影しました。
 ――構想としては、ライヴ映画を撮る予定だったそうですね。早川さんの『かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう』(69)のアルバム制作過程とライヴを撮影して、両方を合わせていわゆる音楽映画を作ろうとした、というわけでは勿論ないんですよね?
そう。ライヴの撮影も、ちゃんと一曲全部を撮影するというような撮り方ではなかった。まあ、演奏しているところをそのまま撮るなんて考えられなかったんですね。フィルムがもったいなくてと言うか、映像は映像として見る音楽、眼の音楽なんだから音楽に従属すべきじゃないと考えていた。最初、ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいと思った時も、リチャード・レスターの撮った『ビートルズがやってくるヤア!ヤア!ヤア!』みたいなものを漠然と考えていました。だから、69年の10・21国際反戦デーの街頭デモとか、当時の色々な要素を映画のなかに入れ込みながら、全体を早川さんの歌とインタビューで繋げば、それで映画として成立するではないか、という直観がありました。『自己表出史 早川義夫編』では、これといってモデルにした映画はありません。『バラード』とはまったく違う作り方でした。撮影した素材と録音したテープから構成した映画です。撮影は野田真吉さんの息子の亘クンが担当してくれて、ぼくとカメラを持った彼と2人で動いていました。
早川さんへのインタビューは、早川さんの自宅へうかがって、そのときはカメラを持たずにテープレコーダーだけで一日がかりでインタビューを録音しました。その早川さんの声をバックに、早川さんが銀座を歩いている映像や当時撮影していた映像を当て嵌めていきました。
それと『自己表出史 早川義夫編』の前に、何本か撮ろうとして撮れなかった映画企画が何本かあった。『自己表出史 早川義夫編』の序章には、「理絵の巻」という短編が組み込まれています。高校生の女の子が、学校の屋上で売春をするストーリーです。高校という空間そのものを否定するような映画を作りたかったんです。女子高生が屋上でキスしたり、男の子と絡みあったりする姿を撮影し、それにオーネット・コールマンの「ロンリー・ウーマン」というジャズ・ミュージックを重ねました。そのテーマでは、足立正生が『噴出祈願 15歳の売春婦』という傑作を作っていますがね。
――構想としては、ライヴ映画を撮る予定だったそうですね。早川さんの『かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう』(69)のアルバム制作過程とライヴを撮影して、両方を合わせていわゆる音楽映画を作ろうとした、というわけでは勿論ないんですよね?
そう。ライヴの撮影も、ちゃんと一曲全部を撮影するというような撮り方ではなかった。まあ、演奏しているところをそのまま撮るなんて考えられなかったんですね。フィルムがもったいなくてと言うか、映像は映像として見る音楽、眼の音楽なんだから音楽に従属すべきじゃないと考えていた。最初、ジャックスのドキュメンタリーを撮りたいと思った時も、リチャード・レスターの撮った『ビートルズがやってくるヤア!ヤア!ヤア!』みたいなものを漠然と考えていました。だから、69年の10・21国際反戦デーの街頭デモとか、当時の色々な要素を映画のなかに入れ込みながら、全体を早川さんの歌とインタビューで繋げば、それで映画として成立するではないか、という直観がありました。『自己表出史 早川義夫編』では、これといってモデルにした映画はありません。『バラード』とはまったく違う作り方でした。撮影した素材と録音したテープから構成した映画です。撮影は野田真吉さんの息子の亘クンが担当してくれて、ぼくとカメラを持った彼と2人で動いていました。
早川さんへのインタビューは、早川さんの自宅へうかがって、そのときはカメラを持たずにテープレコーダーだけで一日がかりでインタビューを録音しました。その早川さんの声をバックに、早川さんが銀座を歩いている映像や当時撮影していた映像を当て嵌めていきました。
それと『自己表出史 早川義夫編』の前に、何本か撮ろうとして撮れなかった映画企画が何本かあった。『自己表出史 早川義夫編』の序章には、「理絵の巻」という短編が組み込まれています。高校生の女の子が、学校の屋上で売春をするストーリーです。高校という空間そのものを否定するような映画を作りたかったんです。女子高生が屋上でキスしたり、男の子と絡みあったりする姿を撮影し、それにオーネット・コールマンの「ロンリー・ウーマン」というジャズ・ミュージックを重ねました。そのテーマでは、足立正生が『噴出祈願 15歳の売春婦』という傑作を作っていますがね。
 ――他にはどのような映画企画があったんですか。
大江健三郎の「セブンティーン」という小説をモチーフにした映画を撮ろうとして、友だちを集めて、キャストも決めて、シナリオなしで撮影を始めました。モチーフにしているだけなので、大江さんの許可を得たわけではないですが。ところが、撮影したフィルムを現像してみたら、カメラの水平軸が全部傾いていたんです。使ったボレックスのカメラのファインダーとプリズムがズレていた。かっちりとした劇映画を撮ろうとしていたので、それで嫌になって中止してしまった。そうしたら、亘君がアリフレックスを持ってきてくれた。とにかく早川義夫を撮り始めて、それまで撮ったフィルムで使える分を『自己表出史 早川義夫編』に入れていったんです。
――この辺りで、原さんの音楽性の確立についてお聞きしたいですね。
早川義夫さんが一番の先生ですよ。早川さんにインタビューへ行ったら、早川さんは全然レコードを持っていなかったんです。ビートルズの古いアルバムが自宅に何枚か置いてあっただけ。その頃の流行のロック、たとえばジミヘンやクリーム、ストーンズやドアーズも持っていない。早川さんにどうしてか聞いたら「他の人の音楽はあまり聴かない」と言うんです。「どうやって作曲をするんですか」と尋ねると、映画の中のインタビューでも答えていますが「僕は作曲の仕方を知らないから、なるべく他の人の音楽を聴かないようにしていると、すると段々とメロディーが湧いて来る。他の音楽を聴くとそれしか浮かんでこなくなっちゃうから、とにかく他の音楽を聴かずに、湧いて来るのを待つ」という方法論を教えてくれた。コード進行をコピーしたり、またコード進行を決めてから曲を作る事もしないと言うんです。「それをやると他人の真似になるから、とにかく音楽は聴かない方がいいよ」と言うんです。そうして、僕の作曲スタイルも決まりました。「早川さんみたいにすればいいんだ」と思ったんです。『初国知所之天皇』のために、半年くらいヒッチハイクをしながら日本列島を撮影していたとき、ほとんどテレビも見ないしラジオも聞かなかったんですが、ピアニカだけは持ち歩いていました。それをリュックの中に入れておいて、ピアニカで浮かんだメロディーをひたすらノートに書きつづる形で作曲をするようになりました。その後、そのメロディーにコードをつけていったんです。
――他にはどのような映画企画があったんですか。
大江健三郎の「セブンティーン」という小説をモチーフにした映画を撮ろうとして、友だちを集めて、キャストも決めて、シナリオなしで撮影を始めました。モチーフにしているだけなので、大江さんの許可を得たわけではないですが。ところが、撮影したフィルムを現像してみたら、カメラの水平軸が全部傾いていたんです。使ったボレックスのカメラのファインダーとプリズムがズレていた。かっちりとした劇映画を撮ろうとしていたので、それで嫌になって中止してしまった。そうしたら、亘君がアリフレックスを持ってきてくれた。とにかく早川義夫を撮り始めて、それまで撮ったフィルムで使える分を『自己表出史 早川義夫編』に入れていったんです。
――この辺りで、原さんの音楽性の確立についてお聞きしたいですね。
早川義夫さんが一番の先生ですよ。早川さんにインタビューへ行ったら、早川さんは全然レコードを持っていなかったんです。ビートルズの古いアルバムが自宅に何枚か置いてあっただけ。その頃の流行のロック、たとえばジミヘンやクリーム、ストーンズやドアーズも持っていない。早川さんにどうしてか聞いたら「他の人の音楽はあまり聴かない」と言うんです。「どうやって作曲をするんですか」と尋ねると、映画の中のインタビューでも答えていますが「僕は作曲の仕方を知らないから、なるべく他の人の音楽を聴かないようにしていると、すると段々とメロディーが湧いて来る。他の音楽を聴くとそれしか浮かんでこなくなっちゃうから、とにかく他の音楽を聴かずに、湧いて来るのを待つ」という方法論を教えてくれた。コード進行をコピーしたり、またコード進行を決めてから曲を作る事もしないと言うんです。「それをやると他人の真似になるから、とにかく音楽は聴かない方がいいよ」と言うんです。そうして、僕の作曲スタイルも決まりました。「早川さんみたいにすればいいんだ」と思ったんです。『初国知所之天皇』のために、半年くらいヒッチハイクをしながら日本列島を撮影していたとき、ほとんどテレビも見ないしラジオも聞かなかったんですが、ピアニカだけは持ち歩いていました。それをリュックの中に入れておいて、ピアニカで浮かんだメロディーをひたすらノートに書きつづる形で作曲をするようになりました。その後、そのメロディーにコードをつけていったんです。
 ――早川さんと原さんは、最近でもお付き合いあるんですか。
早川さんの『たましいの場所』というエッセイ集があるんだけど、それが素晴らしい話ばかりで、特に明治生まれのお母様の臨終のエピソードなどは涙無しには読めないんですが、そのエピソードを中心に映画にしたいという思いがあるんで、連絡を取り合っています。もう、シナリオもあがっています。早川さんは川崎で書店をなさった後、90年代に店をたたんでまた活発に音楽活動をしています。いまも作詞・作曲を自分でやっていますが、復活してからの新曲がすごく良いんですよ。ヴォーカルのスタイルは変わっていませんね。
――タイトルの「自己表出史」という言葉は、吉本隆明から来たんですか。
そうです。『言語にとって美とは何か』です。一人の個の深いところを突き詰めていくと、普遍性ではないけれども、何か本質的なものにぶつかる。早川さんでいえば、すべての音楽を聴かないで、降りるのを待つという姿勢がまさに彼の「自己表出」だと思いました。ビートルズを聴いて、それを真似してみようとなると一種の指示表出になってしまいますからね。
――この映画の一つの魅力は、当時、一種の祝祭空間と化していたという新宿駅周辺の雰囲気をドキュメントしているところです。1500人が逮捕された新宿デモの騒乱、10・21の国際反戦デーを撮影していたのは、創造社の大島渚のグループと原さんだけだったんですよね。
新宿の街は、学生運動のセクトやゲリラで溢れていました。あの映画における一つの成果は、1969年のあの日を映像で記録したことかもしれない。駐車していた車が次々に横倒しにされて、炎上し、その炎が、雨に濡れた道路やずらりと並ぶ機動隊の盾に反射していました。夜遅くまで、そんな光景をカメラに収めていきました。早川さんの「作曲しているともう日常じゃ無くなるんだよ」というコメントをバックに、この10・21の映像をぶつけたんです。早川さんがインタビューで話してくれたことが、その映像ともマッチして、時代の雰囲気を伝えるのに効果を上げたんだと思います。また当時は、東京の風景が急速に変わっていく時期でした。東京オリンピックの後にどんどん路面電車がなくなっていきました。そんな街の風景を記録している面もあります。
ぼくたちは大島渚さん、足立正生さん、仙元誠三さんらに街角で会いました。大島渚さんの創造社の撮影クルーは、二班にわけて撮影していたようです。もう一班は、田村孟さん、吉岡康弘さん、戸田重昌さんの3人。僕は大島さんたちの班に出くわしました。大島さんも10・21の撮影に来ているのは自分たちだけだろう、創造社だけだろうと思っていたらしく、僕たちが来ていたのですごく喜んでいました。そんなこともあって、僕が脚本を書いて大島渚さんが監督した『東京战争戦後秘話』へと繋がっていったんです。
――早川さんと原さんは、最近でもお付き合いあるんですか。
早川さんの『たましいの場所』というエッセイ集があるんだけど、それが素晴らしい話ばかりで、特に明治生まれのお母様の臨終のエピソードなどは涙無しには読めないんですが、そのエピソードを中心に映画にしたいという思いがあるんで、連絡を取り合っています。もう、シナリオもあがっています。早川さんは川崎で書店をなさった後、90年代に店をたたんでまた活発に音楽活動をしています。いまも作詞・作曲を自分でやっていますが、復活してからの新曲がすごく良いんですよ。ヴォーカルのスタイルは変わっていませんね。
――タイトルの「自己表出史」という言葉は、吉本隆明から来たんですか。
そうです。『言語にとって美とは何か』です。一人の個の深いところを突き詰めていくと、普遍性ではないけれども、何か本質的なものにぶつかる。早川さんでいえば、すべての音楽を聴かないで、降りるのを待つという姿勢がまさに彼の「自己表出」だと思いました。ビートルズを聴いて、それを真似してみようとなると一種の指示表出になってしまいますからね。
――この映画の一つの魅力は、当時、一種の祝祭空間と化していたという新宿駅周辺の雰囲気をドキュメントしているところです。1500人が逮捕された新宿デモの騒乱、10・21の国際反戦デーを撮影していたのは、創造社の大島渚のグループと原さんだけだったんですよね。
新宿の街は、学生運動のセクトやゲリラで溢れていました。あの映画における一つの成果は、1969年のあの日を映像で記録したことかもしれない。駐車していた車が次々に横倒しにされて、炎上し、その炎が、雨に濡れた道路やずらりと並ぶ機動隊の盾に反射していました。夜遅くまで、そんな光景をカメラに収めていきました。早川さんの「作曲しているともう日常じゃ無くなるんだよ」というコメントをバックに、この10・21の映像をぶつけたんです。早川さんがインタビューで話してくれたことが、その映像ともマッチして、時代の雰囲気を伝えるのに効果を上げたんだと思います。また当時は、東京の風景が急速に変わっていく時期でした。東京オリンピックの後にどんどん路面電車がなくなっていきました。そんな街の風景を記録している面もあります。
ぼくたちは大島渚さん、足立正生さん、仙元誠三さんらに街角で会いました。大島渚さんの創造社の撮影クルーは、二班にわけて撮影していたようです。もう一班は、田村孟さん、吉岡康弘さん、戸田重昌さんの3人。僕は大島さんたちの班に出くわしました。大島さんも10・21の撮影に来ているのは自分たちだけだろう、創造社だけだろうと思っていたらしく、僕たちが来ていたのですごく喜んでいました。そんなこともあって、僕が脚本を書いて大島渚さんが監督した『東京战争戦後秘話』へと繋がっていったんです。
 ※以上の写真は『自己表出史 早川義夫編』
[注]
*4 岩波文庫は、消費税が導入された1989年までは、定価を金額ではなく星印の数で表示していた。当時は星印一つあたり50円だった。
*5 野田真吉 1916年愛媛県生まれ。早稲田大学在学中中原中也に私淑、詩作を始める。卒業後、東宝の前身だったP.C.L.に入社。文化映画部に配属され40年監督に昇進。ほどなく召集され敗戦まで陸軍に所属。戦後、東宝に復帰し、東宝争議に参加し、49年退社。日本記録映画作家協会結成の中心的な役割を担う。その一方、大島渚、吉田喜重らの「映画批評の会」、安部公房、島尾敏雄らの「現在の会」、花田清輝、佐々木基一らの「記録芸術の会」、長谷川龍生、黒田喜夫、関根弘らの「現代詩の会」などに関わり、『忘れられた土地』(58)『マリン・スノー』(60)『モノクロームの画家 イブ・クライン』(64)などを発表。64年、松本俊夫、土本典昭、黒木和雄、小川紳介とともに「映像記録の会」を結成。67年、「杉並シネクラブ」を結成。その交流の広さから、様々なジャンルの人々から相談を受け、ジャンルを超えて人々を結び付けた、戦後の前衛的な文化を創出した核たる人物のひとりである。代表作に『冬の夜の神々の宴 遠山の霜月祭』(70)『ゆきははなである 新野の雪まつり』(80)『生者と死者のかよい路 新野の盆おどり・神送りの行事』(91)の「民俗神事芸能三部作」がある。また、大島渚監督『愛のコリーダ』(76)の撮影現場をドキュメントしており、おでん屋の店主として出演もしている。1993年没。
「おかしさに彩られた悲しみのバラード」
1968年/16mmフィルム/12分/モノクロ
監督:原將人
第1回フィルムアート・フェスティバル グランプリ&ATG賞
「自己表出史 早川義夫編」
1970年/16mmフィルム/29分/モノクロ
監督:原將人 撮影:亘真幸
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人公式サイト
【原将人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原将人監督とゲストによるトークあり
詳細 http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図 http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★gmail.com ※★を@にしてご入力ください
※以上の写真は『自己表出史 早川義夫編』
[注]
*4 岩波文庫は、消費税が導入された1989年までは、定価を金額ではなく星印の数で表示していた。当時は星印一つあたり50円だった。
*5 野田真吉 1916年愛媛県生まれ。早稲田大学在学中中原中也に私淑、詩作を始める。卒業後、東宝の前身だったP.C.L.に入社。文化映画部に配属され40年監督に昇進。ほどなく召集され敗戦まで陸軍に所属。戦後、東宝に復帰し、東宝争議に参加し、49年退社。日本記録映画作家協会結成の中心的な役割を担う。その一方、大島渚、吉田喜重らの「映画批評の会」、安部公房、島尾敏雄らの「現在の会」、花田清輝、佐々木基一らの「記録芸術の会」、長谷川龍生、黒田喜夫、関根弘らの「現代詩の会」などに関わり、『忘れられた土地』(58)『マリン・スノー』(60)『モノクロームの画家 イブ・クライン』(64)などを発表。64年、松本俊夫、土本典昭、黒木和雄、小川紳介とともに「映像記録の会」を結成。67年、「杉並シネクラブ」を結成。その交流の広さから、様々なジャンルの人々から相談を受け、ジャンルを超えて人々を結び付けた、戦後の前衛的な文化を創出した核たる人物のひとりである。代表作に『冬の夜の神々の宴 遠山の霜月祭』(70)『ゆきははなである 新野の雪まつり』(80)『生者と死者のかよい路 新野の盆おどり・神送りの行事』(91)の「民俗神事芸能三部作」がある。また、大島渚監督『愛のコリーダ』(76)の撮影現場をドキュメントしており、おでん屋の店主として出演もしている。1993年没。
「おかしさに彩られた悲しみのバラード」
1968年/16mmフィルム/12分/モノクロ
監督:原將人
第1回フィルムアート・フェスティバル グランプリ&ATG賞
「自己表出史 早川義夫編」
1970年/16mmフィルム/29分/モノクロ
監督:原將人 撮影:亘真幸
原將人(映画作家)インタビューPART1 少年時代~高校時代
原將人公式サイト
【原将人全映画上映 Vol.1】
『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68)
『自己表出史・早川義夫編』(70)
2010年7月30日(金)19時より
茅場町ギャラリーマキにて
原将人監督とゲストによるトークあり
詳細 http://johnfante.up.seesaa.net/image/A.pdf
地図 http://www.gallery-maki.com/map/
予約・お問い合わせ 上映委員会(金子)
kanekoyou★gmail.com ※★を@にしてご入力ください