3月5日から17日に渡り開催された、大阪アジアン映画祭(以下OAFF)。第6回を迎えた今年度からは
コンペティション部門が新設され、才能の発掘の場としての在り方がより高まった。複数の会場で同時並行的に開催されたOAFF。開催期間中、大阪は立体的な映画空間に変貌した。メイン会場の
ABCホールでは、
コンペティション部門の授賞式を含む三つのセレモニーがあり、
コンペティション部門の上映後には毎回、質疑応答が行なわれた。幾つもの国の言語が交錯し、その多様性が祝祭的な雰囲気をより盛り上げていた。
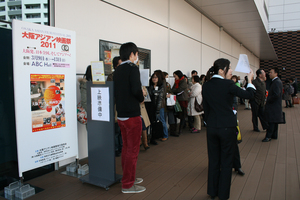
9日のオープニング・セレモニーで上映された
『ハウスメイド(仮題)』(監督:イム・サンス/韓国)は、往年の名作
『下女』(監督:キム・ギヨン/韓国)のリメイク作で、日本公開に先駆けての上映となった。『下女』もサブ会場の
シネ・ヌーヴォで上映された。妻が妊娠中の家庭に若いメイドが雇われた事で、平穏な家庭が内から崩れていくという筋書きや、幾つかのシーンは『下女』から継承されているが、大きな枠組みの他はオリジナルと言っていい。イム監督は記者会見で、
中流階級が台頭し始めた時代を捉えた『下女』に対し、自分は格差がより拡大した現代を描いたと語っていた。その事と絡んでか、劇中、高低差を感じさせる空間演出が頻出する。冒頭の飛び降り自殺シーンや、主な舞台である二階建ての豪邸、人物を仰角で捉えたショットなど。加えて、人物がグラスを手にする仕種も反復されるが、全篇を振り返ればこれは、独立した一個の人間である事の表明であるのが分かる。ヒロインであるメイドが主人に誘惑されるシーンでも、グラスに入ったワインを飲み干すよう促されるが、ここで彼女は、女としての喜びを露わにしていたのだ。更には、一家の幼い娘、ナミの眼差し。冒頭の飛び降り自殺シーンでは、救命士に向かって子供が遺体を指さすカットもあり、欲望渦巻く大人たちの惨劇を見つめる子供の存在が、倫理的な無言の問いかけとも感じられる。またこれは、専ら男女の情念に焦点を合わせていた『下女』との違いでもある。
 『ハウスメイド』
『ハウスメイド』
『下女』では、子供たちの綾とりや、
女工たちの働く紡績工場、下女が働く家の妻が内職に使うミシン、と「糸」の系列が見られ、家庭の幸福と労働の辛苦を一本の糸で結んでいた。悪戯っぽく舌を出す癖のある子供っぽい下女が、彼女にその仕事を斡旋した女友達の行動に刺激されて主人を誘惑するという「女」への変貌や、下女と妻の立場が逆転する展開など、倒錯的な相互関係が描かれる。その反面、最後にはその倒錯性さえも逆転し、全てをパロディにしてしまう所に『下女』の保守性がある。一方『ハウスメイド』が用意した逆転劇は、『下女』の倒錯性に比べるとストレートな表現だ。だがラストシーンは、観客により開かれた多義的なものになり得ており、既存の道徳に回収されない現代性が感じられる。イム監督は、ヒロイン役に選んだ
チョン・ドヨンについて質問された際、美容整形が盛んな韓国の事情を挙げ、「皆、同じ病院で施術されているのか、どれも同じような顔で」と笑い、彼女にはそれと違う個性があると語っていた。この点は劇中に於いても、顔に金をかけられるはずもないメイドの素朴さとして表れ、主人が彼女に欲望を覚える動機としても機能していたように思える。
イム監督は、作品についての質問の半分は『下女』に関するものだとか、批評家からはリメイク作としての出来を酷評されていると、笑いながら話していたが、確かに、脚本の巧みな設計という点では『下女』に一日の長はある。『下女』の、それほど裕福ではない家庭に雇われた下女が、家に紛れ込んだ鼠のように内側から家庭を蝕んでいく、生活感の滲む生々しさや、モノクロ映像の醸し出す禍々しい情念など、その強烈な個性は『ハウスメイド』には継承されていない。夫のピアノ教師という職や、妻の内職といった労働が描かれていた『下女』とは異なり、夫婦があくせく働く様子など
微塵も見せない『ハウスメイド』の家庭は、メイドとの経済格差がより大きく設定されているため、情念の正面からのぶつかり合いは起こり難い。時代が変われば、描かれるべきドラマも変わるのだろう。その一方、
ボーヴォワールの「
第二の性」を読む妻が、夫に物心両面で依存している様を描いた
ジェンダー論的視点も見逃せない。
 『ハウスメイド』
『ハウスメイド』
三つのセレモニーで上映された特別招待作品は、さすがにそれぞれ完成度の高い堂々たるものだったが、
コンペティション部門の10作品は、いかにも「審査」されるのを待ち構えているような、挑戦的であったり若々しかったりする作品が大半だった。授賞式で登壇した、審査委員の
ミルクマン斉藤氏は、この種の映画祭で評価されがちなアート性のみならず、エンターテインメント性も同等に評価の対象としたと語っていたが、10作品を振り返ると、概ね、所謂「アート系」の作品には完成度という点で隙の見えるものが目立ち、エンターテインメント作品はそつなく仕上がっている傾向が見られた。
主演の台湾スター目当てなのか、女性客が大勢押しかけていた
『一万年愛してる』(監督:北村豊晴/台湾)。11日は平日の午前からの上映という事もあってか、熟女の方々で大盛況。上映前に壇上で挨拶をした監督にも声援が飛び、映画のベタなギャグさえよく受けていた。上映後の質疑応答では監督からプレゼント・クイズとして、主人公の父親の職業は何かという出題があったのだが、それを「整体師」と当てた女性には驚かされた。実はそこは編集でカットされた部分なのだが、劇中の主人公の台詞からの推理で見事に正解。
 『一万年愛してる』
『一万年愛してる』
観客の熱の入りよう
からして、観客投票による「観客賞」は『一万年...』が獲るだろうと予想したが、実際その通りの結果となった。尤も、そうしたファン的熱狂を差し引いて、作品自体の完成度で言えば、他のエンターテインメント系の作品と比べて特に出来がいいわけではなく、
『アンニョン!君の名は』(監督:バンジョン・ピサンタナクーン/タイ)の方が一段上である。『アンニョン...』は、最初は傲慢で無神経に見えた青年が、ヒロインとの交流を経ていく内に魅力的に見えてき、最後には彼を応援する気にさせてくれる。130分という、娯楽作としてはやや長尺とも思える上映時間も、エピソードの積み重ねによって丁寧にラストシーンの感動を用意しているという意味で、決して冗長ではない。タイ人男女が異郷・韓国を巡る冒険性は、特別招待作品の
『単身男女』(監督:ジョニー・トー/香港)が「ガラス越しのパフォーマンス」というワンア
イデアを過剰なまでに発展させたのと同じく(車窓や携帯端末のカメラを通した演出もその変奏だ)、シンプルな形で新鮮味を用意している。それと比べると『一万年...』は、「期限三ヶ月の恋愛」というア
イデアを活かしきれていないのが残念だ。例えば『
探偵物語』の謎解きのように、それ自体は大した内容でなくとも、何か課題を与えればタ
イムリミットも活きたはずなのだが。日本の曲「時の過ぎゆくままに」が、
沢田研二の歌声と詞とが相俟っての艶かしさとはかけ離れた、ストレートなラブソングとしてカバーされるシーンは聴かせてくれるが、作品自体も素直に過ぎた感がある。
 『アンニョン!君の名は』
『いつまでもあなたが好き好き好き』(監督:ウィー・リーリン/シンガポール)
『アンニョン!君の名は』
『いつまでもあなたが好き好き好き』(監督:ウィー・リーリン/シンガポール)は、エンターテインメント性とアート性を程よく混合させた点では、最もバランスがとれている。ヒロインのジョイが、結婚式のプロモーション・ビデオで共演した音楽教師ジンにストーカー的につきまとう姿を通して、幻想と現実を交錯させる。
ヒッチコックの『めまい』では、主人公の偏執を誘う鬼火のように緑色が使われていたが、『いつまでも…』はヒロインの恋愛妄想に寄り添うような青色が目に鮮やかだ。ジョイがジンの写真を入れている額や、ジョイの部屋の内装、ビデオの中の衣装をそのまま現実世界でも着ているジョイの青いドレス等々。ビデオの中でジョイが、青空を描いた傘をさしているシーンもあるが、ラストシーンでは、上方にティルトしたカメラが、どこか暗い青空を捉える。虚実の曖昧なラストに関して現地
シンガポールでは、そのシーンを真に受け、疑問を呈する観客も多かったという。だが、劇中のジョイが歌う「主題歌は挿入歌にできる。撮った映画の結末は変えられる」という歌詞は、本作が自己言及的な
メタフィクションでもある事を明確に語っている。
 『いつまでもあなたが好き好き好き』
『いつまでもあなたが好き好き好き』
当初の予定では85分のはずが、直前の編集作業で109分となり、その形ではOAFFが世界初公開となった
『リベラシオン』(監督:アドルフォ・アリックス・ジュニア/フィリピン)。だが、単に冗長さを増しただけに思える。日本の敗戦を信じず、長年フィリピンの山中に潜伏し続けた
日本兵の物語で、
スティーブン・ソダーバーグの『チェ』二部作や、
ガス・ヴァン・サントの『
パラノイドパーク』辺りを髣髴とさせる、淡々としたタッチによる演出。だが、ショットが弱い。「敵」を意識しながら森に潜む緊張感や、食糧の確保等、
日本兵の生活が充分に演出されていない。現地女性との交流にまつわるディテールの積み重ねが薄い。故に、主人公が最後、迎えに来た上官に向けて「この戦争の勝者は誰ですか。この戦争は正しかったんですか」と訴える台詞にも、時間の蓄積に耐え続けた肉体から発せられる説得力が生じない。一緒に迎えに来た兄を演じた役者が、台詞を酷い棒読みにしているのには鼻白まされるし、主人公が部下と相撲に興じるシーンなど、いかにも外国人監督が考えた
日本兵像という印象だ。投降を促すビラが森に降ってくるシーンの反復が、単調な繰り返しの域を出ず、「時間」を描き得ていない事にも不満を覚える。冒頭の、灯の明かりだけを頼りに洞窟を進むシーンで、徐々に
玉音放送が聞こえる演出はいいのだが。
 『リベラシオン』
『リベラシオン』
何よりまずタイトルの響きに惹かれる
『マジック&ロス』(監督:リム・カーワイ/日本・マレーシア・韓国・香港・フランス)には、『息もできない』での共演が鮮烈だったヤン・イクチュンとキム・コッピが再び共演している。『息もできない』の「動」に対して本作は、どこか『
去年マリエンバートで』を髣髴とさせもする「静」の映画。キャストの杉野希妃はプロデューサーも兼ねており、彼女のプロデュース作品の中から、OAFFには
『歓待』(監督:深田晃司/日本)と
『少年少女』(監督:太田信吾/日本)も出品されていた。不可思議さとロマンティックな美しさを感じさせるタイトル通りの作風で、潮の香りと仄かな官能が漂う、虚無的なバカンス映画といったところだ。時の静止を感じさせる白い彫像の向こうに見える浜辺での、カラフルなビキニ姿でビーチボールを投げあう
若い女二人のショットは、作品の雰囲気を象徴している。そのミスマッチ感と叙情性。だが既にこのショット
からして、構図や
色彩設計が徹底した美意識で引き締められきれていない。カメラに接近してきたヤンの赤い半ズボンが画面を覆ったり、キムが杉野の歯ブラシで洗面所を掃除し始めたり、突拍子も無い出来事による驚きが所々に用意されているのは捨て難いが、緻密さと狂気がまだ足りない。時おり杉野が見せる、さり気ない仕種であるが故の艶っぽい姿はよいが、その色香が作品世界を不穏さで充たすには至らない。杉野とキムの唐突な人格交替や、原色の赤と闇の暗さが毒々しいショットなども、作り手の体液のように滲み出したイマジネーションというより、デビッド・リンチ風の不条理映画という「スタイル」を試してみたような印象だ。プロットに合理的な説明などは要らないが、不条理を力業で押し通す映像の質感が欲しい。エンドロール後の、杉野が部屋で電話をとるとノイズが発せられる「不気味さ」の演出も、リンチのようにチープな手作り感によって独特の触感を実現し得る作家ならともかく、半端に手を出すとただチープでしかなくなる。
 『マジック&ロス』
『マジック&ロス』
とはいえ、映画祭中、数多くのキャストやスタッフが登壇した中にあって、杉野は壇上に最も華を添えた存在ではあった。11日のウエルカム・セレモニーでゲストらが勢揃いして登壇した際に、杉野が司会者から「プロデューサーで主演も務められた……」と紹介されると、一同の代表として舞台中央に立っていた
桃井かおりが、身を乗り出して杉野の姿を確認していたのが印象的だった。「来るべき才能賞」の審査でも、杉野の名は挙がっていたようだが、審査委員長の
行定勲監督からは、「プロデューサーとしての自覚が欠けている」、「来るべき才能というにはまだ弱い」と指摘があり、今後への期待も込めて今回は見送られたようだった。彼女に「今後成功する可能性がある」、「ぜひ韓国に来て仕事をしてほしい」と激励を送った審査委員のキム・デウ監督からは、「女性としてもプロデューサーとしても一皮剥ける」という理由で、「不倫をしなさい」とセクハラ紛いの助言も為されたが、その言わんとするところは、漠然とだが了解できる。『マジック...』に関して言えば、感情に直に突き刺さるような強さが欠けていて、浮ついたイメージの展開に終始している嫌いがある。端から見込みのない作品ではないだけに、その不徹底さには隔靴掻痒の感があった。
 『マジック&ロス』
『マジック&ロス』
妙な作風という点では『マジック...』以上の
『遭遇』(監督:イム・テヒョン/韓国)。その、やたらとカメラを手ぶれさせたり、急なズームアップを行なったりして「リアル」を演出する、近ごろ流行りの撮影法には些か食傷気味なのだが、いかにも低予算な映画の撮影現場を物語の舞台としつつ、そこに非現実的な要素を挿入し、更にそれをユーモアではぐらかすという微妙な匙加減には心地よく翻弄された。劇中の、撮影用に宇宙人のキグルミを着てきた男など、その言動はごく普通だが、遂に一度もそのキグルミを脱がないので、その中身が誰なのかという点に、一抹の疑わしさを保ち続けるのが面白い。劇中の撮影現場と同様に、本作の撮影自体も即興的に行なわれたようだが、その選択は諸刃の剣だった。脈絡のない思いつきが画面に驚きをもたらしている箇所もあったが、反面、終盤で劇中の監督ジュンホの過去にまつわるベタな救済劇に収束していく点では、無軌道さに徹さず安直な物語に回収させる弱さが覗く。宇宙人の大きく黒い目が、ジュンホの妹が落ちたと思しき井戸の丸い暗闇と符合させられるのはまだしも、イム監督が思いつきで撮ったという、ジュンホが土を掘るシーンまでも、後づけで安易に理由づけが為されてしまうのが興をそぐ。脚本が練られていないせいで、誰でも即席で思いつくような
クリシェに映画が奪われてしまった観がある。加えて、ドキュメンタリー風の撮影は、カメラが透明な視点とならず、それ自体の身体性が観客の眼前にチラつくせいで、臨場感からはむしろ遠のいてしまう。それでいながら、ジュンホの内面に寄り添うような物語を描く方へ向かうので、表現方法と内容とに齟齬が生じている。質疑応答で監督は、客席から投げかけられた「幼い頃に死んだ妹の幻影が、成人女性の姿で現れるのはなぜか」という問いに、自然な思いつきだとか、
インパクトを重視したとか説明していたが、やはりもう少し考えて撮るべきだっただろう。観客が映像をどう観るかが殆ど計算されていないのは無謀に過ぎる。
 『遭遇』
『遭遇』
グランプリ受賞作となった
『恋人のディスクール』(監督:デレク・ツァン、ジミー・ワン/香港)は、些か棒読み口調で「うまくまとめ上げている」と評したい作品。劇中の四つの物語は、『
恋人までの距離(ディスタンス)』
風の会話劇として演出された第一話に始まり、コメディタッチのメルヘン風、青春映画風、ラブサスペンス風、と趣向を変えていくが、どれも既視感のある「…風」の演出を並べている印象。この監督らが、どのような作品でも手堅く演出し得る優秀さを示したのは認めるし、画面を眩しい光が充たすショットや、人物間に漂う距離感の切なさなど、全篇に通底するスタイルも感じられはするものの、全体の印象としては、小手先の器用さだけが目立つ。冒頭の導入部では、恋愛感情の神経生理学的な解説を行なった後、「科学で恋は説明できない。だから、様々な恋愛物語を見てみよう」と促して本篇に入る。CGを使用したこの導入部は、各話がそれぞれの仕方で叙情性を醸し出していた本篇とも齟齬があるし、結局、本篇が、「こういう類いの映画も撮れますよ」というサンプル集の域を出ない事を予告していたようにも思えてしまう。尤も、内気な
メガネッ娘がメルヘンな空想を繰り広げるキュートな物語が含まれていたり、見栄えのいい映像で雰囲気を作り上げ、人の頭を混乱させない程度の複雑さでプロットを設計していたりと、或る種の
文化系女子には受けそうな作品ではある。こうした作品を器用に撮る才能に何の価値も無いとは言わないが、グランプリという形でわざわざ肯定してやる必要があったのだろうか。
 『恋人のディスクール』
『恋人のディスクール』
一方、『恋人...』と共に最後まで審査の対象になっていたらしい
『雨夜 香港コンフィデンシャル』(監督:マリス・マルティンソンス/ラトビア・香港)は、そつのない『恋人...』とは対照的な、奇妙なタッチの作品だ。一見すると『マジック...』や『遭遇』の方が変則的にも思えるが、独特の世界観を映像として構築し得ている点では、本作が最も推せる。舞台は香港。義兄のマッサージ店に勤める日本人女性・雨夜と、イギリス人男性ポールを両輪として展開する物語は、時間軸が交錯していながらも、過去と現在の区別が曖昧で、しかも「曖昧な描写である」という事自体を明確にしないので、殆どの観客は混乱させられるだろう。本作の前に観た『
リベラシオン』が上映直前に編集を終えたのを聞かされたせいもあって、本作も編集作業が完了していないのではないかとさえ感じてしまった。だが、確かに観客に対して親切な編集ではないが、シーンとシーン、カットとカットの間から、雨夜とポールの記憶の層が現れるに従って、登場人物の表情や言動が、その意味合いを変化させていく驚きがある。この驚きは、過去と現在が完全にフラットに描かれている事で、却ってより強められるのだ。淡々と日々を送って見える登場人物たちが、実は観客が了解していたのとは別の層の時間を生きていた事の驚き。本作の真の被写体は、風景でも人物でもなく、それらを通して垣間見られる「時間」だったのかもしれない。雨夜の夫が古い掛時計を修理するシーンでは、扉が開かれた時計の内側からのショットがあり、恰も、古時計に保存されてきた「時間」の側からの「主観ショット」のようにも感じられた。「編集が不親切だ」という一言で片付けられてしまいかねない危うさは確かに残るが、そうした、世界との関係が脱臼したような在り方が、ひとつの新しい時空間をもたらしてもいる。バイキング形式のような多彩さが却って平板な印象を与える『恋人...』は、それなりに万人受けがしそうだが、『雨夜...』の不親切さの方が遥かに潔く、好ましく思える。
雨夜を演じた
桃井かおりは、
ABCホールでの上映に際して壇上に現れ、上述した時間軸の曖昧さにも触れつつ、監督の作風について、訳が分からない所はあるが、表現したいものがあって作っている事が伝わってくる、と評していたが、本作の印象として的確な表現だ。雨夜という女性についても、桃井自身の想像で人物像を膨らませていたようだが、作品自体も、映像の裏を自由に読める、余白の多い作りになっている。壇上の桃井は、カーテンの陰からひょっこり顔を覗かせたり、作品について熱心に語ったりと、終始ご機嫌な様子だった。会場には彼女を知らぬ人などおそらくいなかっただろうが、その天衣無縫さには、初めて見た人でもすぐにファンになってしまっただろう。
 『雨夜 香港コンフィデンシャル』
コンペティション
『雨夜 香港コンフィデンシャル』
コンペティション部門出品作は概ねアート系作品に難があると先に述べたが、それは、エンターテインメントは描くべきドラマの骨子が予め明確で、そこに幾つか新鮮味のあるア
イデアをちりばめていけば事が済むのに対し、アート系作品はそうした根幹部分から作り上げる必要があるからだろう。だが、「…風」のスタイルを未消化なままなぞった演出法や、奇抜なア
イデアを思いついてもそれを貫かず、既存の物語に回収してしまう作品が目立ち、作者の内的な衝動の徹底を感じさせる、強い作品は少なかった。皆、小利口な形で「映画」を知りすぎてしまっているのだ。そうした中、描きたいものがあって作られている事が最も明確に伝わってきたのは、
『彼が23歳だった時』(監督:アタヌ・ゴーシュ/インド)。
ベンガル地方を舞台に、保守的な家庭に囚われた青年を主人公にしつつも、
ソーシャル・ネットワークを介した男女の出会いといった現代性を盛り込んでもいる。やはり表現行為は、抑圧というものが明確に感じられる場所でこそ、凝縮された密度を持ち得るのだろうか。だが、主人公が医師という地位を脱して芸術家になろうとする姿を「解放」の表現として描くのは、彼が芸術にかける心情や、その才能の有無を描いていないせいもあるが、「芸術家=自由」という構図が自明視されている点に違和感を覚える。
ステレオタイプな道徳に対抗するイメージそのものが、幾分
ステレオタイプなのだ。対して、
コスモポリタンな世界観を有した『雨夜…』は、抗うべき価値観も何もない、宙を浮遊するような曖昧さを生きる現代の感性をよく体現していた。ガラス張りのロープウェイのシーンは、それを象徴している。
 『彼が23歳だった時』
『彼が23歳だった時』
13日の、各賞の授賞式をメインとしたクロージング・セレモニーの後、
『カイト』(監督:アヌラーグ・バス/インド・メキシコ・アメリカ)の上映前に、駐大阪インド
総領事館総領事としてヴィカス・スワラップ氏が挨拶に立った。氏は『スラムドッグ$ミリオネア』の原作者でもあり、その事に彼が言及すると会場からどよめきが起こった。最近のインド映画について、「三時間、空調の効いた場所で夢想に耽るだけではなく、娯楽性と芸術性を両立させた作品が作られている」と語り、「映画『スラムドッグ…』について訊かれた際、私はいつも“ハリウッドの空の下で作られた
ボリウッド映画”と言ってきましたが、これからご紹介する『カイト』は“
ボリウッドの空の下で作られたハリウッド映画”です」と『カイト』につなぐ。最後に壇上に立った、タレント・DJのサニー・フランシス氏は、普段からテレビ等で見せている通りの関西弁の喋りで『カイト』を紹介。いかにも大阪のインド人らしく、与えられた短い時間をフル活用したマシンガン・
トークで捲し立て、会場を沸かせて去っていった。『カイト』は、この二氏の紹介の通り、筋骨隆々の美男子と、セクシーな美女の完璧な容姿や、カー
チェイス・シーンでいちいち花火のように火柱が立ち、曲芸のようにパトカーが宙に舞うなど、ここまでセンターに寄せますかと言いたくなるほどに娯楽作のオーソドクシーを徹底させている。さすがにハリウッドでも、ここまでの直球は投げないだろう。その華美さや、それと対照的なラストの
厭世観など、我々が想像するインドらしさという点では、或る意味『彼が23歳...』以上だろう。この二本のインド映画は、インドでの上映形式に倣い、途中で5分間の休憩が入った。上映前のアナウンスでその事が告げられたとき、客席からは笑い声が湧いていたが、実際に休憩が入った際は、席を立ってトイレか何かに立つ観客も何人かいて、それなりに活用されており、束の間のインド時間が流れていた。
 『カイト』
*後編に続く
『カイト』
*後編に続く
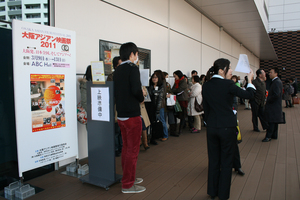 9日のオープニング・セレモニーで上映された『ハウスメイド(仮題)』(監督:イム・サンス/韓国)は、往年の名作『下女』(監督:キム・ギヨン/韓国)のリメイク作で、日本公開に先駆けての上映となった。『下女』もサブ会場のシネ・ヌーヴォで上映された。妻が妊娠中の家庭に若いメイドが雇われた事で、平穏な家庭が内から崩れていくという筋書きや、幾つかのシーンは『下女』から継承されているが、大きな枠組みの他はオリジナルと言っていい。イム監督は記者会見で、中流階級が台頭し始めた時代を捉えた『下女』に対し、自分は格差がより拡大した現代を描いたと語っていた。その事と絡んでか、劇中、高低差を感じさせる空間演出が頻出する。冒頭の飛び降り自殺シーンや、主な舞台である二階建ての豪邸、人物を仰角で捉えたショットなど。加えて、人物がグラスを手にする仕種も反復されるが、全篇を振り返ればこれは、独立した一個の人間である事の表明であるのが分かる。ヒロインであるメイドが主人に誘惑されるシーンでも、グラスに入ったワインを飲み干すよう促されるが、ここで彼女は、女としての喜びを露わにしていたのだ。更には、一家の幼い娘、ナミの眼差し。冒頭の飛び降り自殺シーンでは、救命士に向かって子供が遺体を指さすカットもあり、欲望渦巻く大人たちの惨劇を見つめる子供の存在が、倫理的な無言の問いかけとも感じられる。またこれは、専ら男女の情念に焦点を合わせていた『下女』との違いでもある。
9日のオープニング・セレモニーで上映された『ハウスメイド(仮題)』(監督:イム・サンス/韓国)は、往年の名作『下女』(監督:キム・ギヨン/韓国)のリメイク作で、日本公開に先駆けての上映となった。『下女』もサブ会場のシネ・ヌーヴォで上映された。妻が妊娠中の家庭に若いメイドが雇われた事で、平穏な家庭が内から崩れていくという筋書きや、幾つかのシーンは『下女』から継承されているが、大きな枠組みの他はオリジナルと言っていい。イム監督は記者会見で、中流階級が台頭し始めた時代を捉えた『下女』に対し、自分は格差がより拡大した現代を描いたと語っていた。その事と絡んでか、劇中、高低差を感じさせる空間演出が頻出する。冒頭の飛び降り自殺シーンや、主な舞台である二階建ての豪邸、人物を仰角で捉えたショットなど。加えて、人物がグラスを手にする仕種も反復されるが、全篇を振り返ればこれは、独立した一個の人間である事の表明であるのが分かる。ヒロインであるメイドが主人に誘惑されるシーンでも、グラスに入ったワインを飲み干すよう促されるが、ここで彼女は、女としての喜びを露わにしていたのだ。更には、一家の幼い娘、ナミの眼差し。冒頭の飛び降り自殺シーンでは、救命士に向かって子供が遺体を指さすカットもあり、欲望渦巻く大人たちの惨劇を見つめる子供の存在が、倫理的な無言の問いかけとも感じられる。またこれは、専ら男女の情念に焦点を合わせていた『下女』との違いでもある。
 『ハウスメイド』
『下女』では、子供たちの綾とりや、女工たちの働く紡績工場、下女が働く家の妻が内職に使うミシン、と「糸」の系列が見られ、家庭の幸福と労働の辛苦を一本の糸で結んでいた。悪戯っぽく舌を出す癖のある子供っぽい下女が、彼女にその仕事を斡旋した女友達の行動に刺激されて主人を誘惑するという「女」への変貌や、下女と妻の立場が逆転する展開など、倒錯的な相互関係が描かれる。その反面、最後にはその倒錯性さえも逆転し、全てをパロディにしてしまう所に『下女』の保守性がある。一方『ハウスメイド』が用意した逆転劇は、『下女』の倒錯性に比べるとストレートな表現だ。だがラストシーンは、観客により開かれた多義的なものになり得ており、既存の道徳に回収されない現代性が感じられる。イム監督は、ヒロイン役に選んだチョン・ドヨンについて質問された際、美容整形が盛んな韓国の事情を挙げ、「皆、同じ病院で施術されているのか、どれも同じような顔で」と笑い、彼女にはそれと違う個性があると語っていた。この点は劇中に於いても、顔に金をかけられるはずもないメイドの素朴さとして表れ、主人が彼女に欲望を覚える動機としても機能していたように思える。
イム監督は、作品についての質問の半分は『下女』に関するものだとか、批評家からはリメイク作としての出来を酷評されていると、笑いながら話していたが、確かに、脚本の巧みな設計という点では『下女』に一日の長はある。『下女』の、それほど裕福ではない家庭に雇われた下女が、家に紛れ込んだ鼠のように内側から家庭を蝕んでいく、生活感の滲む生々しさや、モノクロ映像の醸し出す禍々しい情念など、その強烈な個性は『ハウスメイド』には継承されていない。夫のピアノ教師という職や、妻の内職といった労働が描かれていた『下女』とは異なり、夫婦があくせく働く様子など微塵も見せない『ハウスメイド』の家庭は、メイドとの経済格差がより大きく設定されているため、情念の正面からのぶつかり合いは起こり難い。時代が変われば、描かれるべきドラマも変わるのだろう。その一方、ボーヴォワールの「第二の性」を読む妻が、夫に物心両面で依存している様を描いたジェンダー論的視点も見逃せない。
『ハウスメイド』
『下女』では、子供たちの綾とりや、女工たちの働く紡績工場、下女が働く家の妻が内職に使うミシン、と「糸」の系列が見られ、家庭の幸福と労働の辛苦を一本の糸で結んでいた。悪戯っぽく舌を出す癖のある子供っぽい下女が、彼女にその仕事を斡旋した女友達の行動に刺激されて主人を誘惑するという「女」への変貌や、下女と妻の立場が逆転する展開など、倒錯的な相互関係が描かれる。その反面、最後にはその倒錯性さえも逆転し、全てをパロディにしてしまう所に『下女』の保守性がある。一方『ハウスメイド』が用意した逆転劇は、『下女』の倒錯性に比べるとストレートな表現だ。だがラストシーンは、観客により開かれた多義的なものになり得ており、既存の道徳に回収されない現代性が感じられる。イム監督は、ヒロイン役に選んだチョン・ドヨンについて質問された際、美容整形が盛んな韓国の事情を挙げ、「皆、同じ病院で施術されているのか、どれも同じような顔で」と笑い、彼女にはそれと違う個性があると語っていた。この点は劇中に於いても、顔に金をかけられるはずもないメイドの素朴さとして表れ、主人が彼女に欲望を覚える動機としても機能していたように思える。
イム監督は、作品についての質問の半分は『下女』に関するものだとか、批評家からはリメイク作としての出来を酷評されていると、笑いながら話していたが、確かに、脚本の巧みな設計という点では『下女』に一日の長はある。『下女』の、それほど裕福ではない家庭に雇われた下女が、家に紛れ込んだ鼠のように内側から家庭を蝕んでいく、生活感の滲む生々しさや、モノクロ映像の醸し出す禍々しい情念など、その強烈な個性は『ハウスメイド』には継承されていない。夫のピアノ教師という職や、妻の内職といった労働が描かれていた『下女』とは異なり、夫婦があくせく働く様子など微塵も見せない『ハウスメイド』の家庭は、メイドとの経済格差がより大きく設定されているため、情念の正面からのぶつかり合いは起こり難い。時代が変われば、描かれるべきドラマも変わるのだろう。その一方、ボーヴォワールの「第二の性」を読む妻が、夫に物心両面で依存している様を描いたジェンダー論的視点も見逃せない。
 『ハウスメイド』
三つのセレモニーで上映された特別招待作品は、さすがにそれぞれ完成度の高い堂々たるものだったが、コンペティション部門の10作品は、いかにも「審査」されるのを待ち構えているような、挑戦的であったり若々しかったりする作品が大半だった。授賞式で登壇した、審査委員のミルクマン斉藤氏は、この種の映画祭で評価されがちなアート性のみならず、エンターテインメント性も同等に評価の対象としたと語っていたが、10作品を振り返ると、概ね、所謂「アート系」の作品には完成度という点で隙の見えるものが目立ち、エンターテインメント作品はそつなく仕上がっている傾向が見られた。
主演の台湾スター目当てなのか、女性客が大勢押しかけていた『一万年愛してる』(監督:北村豊晴/台湾)。11日は平日の午前からの上映という事もあってか、熟女の方々で大盛況。上映前に壇上で挨拶をした監督にも声援が飛び、映画のベタなギャグさえよく受けていた。上映後の質疑応答では監督からプレゼント・クイズとして、主人公の父親の職業は何かという出題があったのだが、それを「整体師」と当てた女性には驚かされた。実はそこは編集でカットされた部分なのだが、劇中の主人公の台詞からの推理で見事に正解。
『ハウスメイド』
三つのセレモニーで上映された特別招待作品は、さすがにそれぞれ完成度の高い堂々たるものだったが、コンペティション部門の10作品は、いかにも「審査」されるのを待ち構えているような、挑戦的であったり若々しかったりする作品が大半だった。授賞式で登壇した、審査委員のミルクマン斉藤氏は、この種の映画祭で評価されがちなアート性のみならず、エンターテインメント性も同等に評価の対象としたと語っていたが、10作品を振り返ると、概ね、所謂「アート系」の作品には完成度という点で隙の見えるものが目立ち、エンターテインメント作品はそつなく仕上がっている傾向が見られた。
主演の台湾スター目当てなのか、女性客が大勢押しかけていた『一万年愛してる』(監督:北村豊晴/台湾)。11日は平日の午前からの上映という事もあってか、熟女の方々で大盛況。上映前に壇上で挨拶をした監督にも声援が飛び、映画のベタなギャグさえよく受けていた。上映後の質疑応答では監督からプレゼント・クイズとして、主人公の父親の職業は何かという出題があったのだが、それを「整体師」と当てた女性には驚かされた。実はそこは編集でカットされた部分なのだが、劇中の主人公の台詞からの推理で見事に正解。
 『一万年愛してる』
観客の熱の入りようからして、観客投票による「観客賞」は『一万年...』が獲るだろうと予想したが、実際その通りの結果となった。尤も、そうしたファン的熱狂を差し引いて、作品自体の完成度で言えば、他のエンターテインメント系の作品と比べて特に出来がいいわけではなく、『アンニョン!君の名は』(監督:バンジョン・ピサンタナクーン/タイ)の方が一段上である。『アンニョン...』は、最初は傲慢で無神経に見えた青年が、ヒロインとの交流を経ていく内に魅力的に見えてき、最後には彼を応援する気にさせてくれる。130分という、娯楽作としてはやや長尺とも思える上映時間も、エピソードの積み重ねによって丁寧にラストシーンの感動を用意しているという意味で、決して冗長ではない。タイ人男女が異郷・韓国を巡る冒険性は、特別招待作品の『単身男女』(監督:ジョニー・トー/香港)が「ガラス越しのパフォーマンス」というワンアイデアを過剰なまでに発展させたのと同じく(車窓や携帯端末のカメラを通した演出もその変奏だ)、シンプルな形で新鮮味を用意している。それと比べると『一万年...』は、「期限三ヶ月の恋愛」というアイデアを活かしきれていないのが残念だ。例えば『探偵物語』の謎解きのように、それ自体は大した内容でなくとも、何か課題を与えればタイムリミットも活きたはずなのだが。日本の曲「時の過ぎゆくままに」が、沢田研二の歌声と詞とが相俟っての艶かしさとはかけ離れた、ストレートなラブソングとしてカバーされるシーンは聴かせてくれるが、作品自体も素直に過ぎた感がある。
『一万年愛してる』
観客の熱の入りようからして、観客投票による「観客賞」は『一万年...』が獲るだろうと予想したが、実際その通りの結果となった。尤も、そうしたファン的熱狂を差し引いて、作品自体の完成度で言えば、他のエンターテインメント系の作品と比べて特に出来がいいわけではなく、『アンニョン!君の名は』(監督:バンジョン・ピサンタナクーン/タイ)の方が一段上である。『アンニョン...』は、最初は傲慢で無神経に見えた青年が、ヒロインとの交流を経ていく内に魅力的に見えてき、最後には彼を応援する気にさせてくれる。130分という、娯楽作としてはやや長尺とも思える上映時間も、エピソードの積み重ねによって丁寧にラストシーンの感動を用意しているという意味で、決して冗長ではない。タイ人男女が異郷・韓国を巡る冒険性は、特別招待作品の『単身男女』(監督:ジョニー・トー/香港)が「ガラス越しのパフォーマンス」というワンアイデアを過剰なまでに発展させたのと同じく(車窓や携帯端末のカメラを通した演出もその変奏だ)、シンプルな形で新鮮味を用意している。それと比べると『一万年...』は、「期限三ヶ月の恋愛」というアイデアを活かしきれていないのが残念だ。例えば『探偵物語』の謎解きのように、それ自体は大した内容でなくとも、何か課題を与えればタイムリミットも活きたはずなのだが。日本の曲「時の過ぎゆくままに」が、沢田研二の歌声と詞とが相俟っての艶かしさとはかけ離れた、ストレートなラブソングとしてカバーされるシーンは聴かせてくれるが、作品自体も素直に過ぎた感がある。
 『アンニョン!君の名は』
『いつまでもあなたが好き好き好き』(監督:ウィー・リーリン/シンガポール)は、エンターテインメント性とアート性を程よく混合させた点では、最もバランスがとれている。ヒロインのジョイが、結婚式のプロモーション・ビデオで共演した音楽教師ジンにストーカー的につきまとう姿を通して、幻想と現実を交錯させる。ヒッチコックの『めまい』では、主人公の偏執を誘う鬼火のように緑色が使われていたが、『いつまでも…』はヒロインの恋愛妄想に寄り添うような青色が目に鮮やかだ。ジョイがジンの写真を入れている額や、ジョイの部屋の内装、ビデオの中の衣装をそのまま現実世界でも着ているジョイの青いドレス等々。ビデオの中でジョイが、青空を描いた傘をさしているシーンもあるが、ラストシーンでは、上方にティルトしたカメラが、どこか暗い青空を捉える。虚実の曖昧なラストに関して現地シンガポールでは、そのシーンを真に受け、疑問を呈する観客も多かったという。だが、劇中のジョイが歌う「主題歌は挿入歌にできる。撮った映画の結末は変えられる」という歌詞は、本作が自己言及的なメタフィクションでもある事を明確に語っている。
『アンニョン!君の名は』
『いつまでもあなたが好き好き好き』(監督:ウィー・リーリン/シンガポール)は、エンターテインメント性とアート性を程よく混合させた点では、最もバランスがとれている。ヒロインのジョイが、結婚式のプロモーション・ビデオで共演した音楽教師ジンにストーカー的につきまとう姿を通して、幻想と現実を交錯させる。ヒッチコックの『めまい』では、主人公の偏執を誘う鬼火のように緑色が使われていたが、『いつまでも…』はヒロインの恋愛妄想に寄り添うような青色が目に鮮やかだ。ジョイがジンの写真を入れている額や、ジョイの部屋の内装、ビデオの中の衣装をそのまま現実世界でも着ているジョイの青いドレス等々。ビデオの中でジョイが、青空を描いた傘をさしているシーンもあるが、ラストシーンでは、上方にティルトしたカメラが、どこか暗い青空を捉える。虚実の曖昧なラストに関して現地シンガポールでは、そのシーンを真に受け、疑問を呈する観客も多かったという。だが、劇中のジョイが歌う「主題歌は挿入歌にできる。撮った映画の結末は変えられる」という歌詞は、本作が自己言及的なメタフィクションでもある事を明確に語っている。
 『いつまでもあなたが好き好き好き』
当初の予定では85分のはずが、直前の編集作業で109分となり、その形ではOAFFが世界初公開となった『リベラシオン』(監督:アドルフォ・アリックス・ジュニア/フィリピン)。だが、単に冗長さを増しただけに思える。日本の敗戦を信じず、長年フィリピンの山中に潜伏し続けた日本兵の物語で、スティーブン・ソダーバーグの『チェ』二部作や、ガス・ヴァン・サントの『パラノイドパーク』辺りを髣髴とさせる、淡々としたタッチによる演出。だが、ショットが弱い。「敵」を意識しながら森に潜む緊張感や、食糧の確保等、日本兵の生活が充分に演出されていない。現地女性との交流にまつわるディテールの積み重ねが薄い。故に、主人公が最後、迎えに来た上官に向けて「この戦争の勝者は誰ですか。この戦争は正しかったんですか」と訴える台詞にも、時間の蓄積に耐え続けた肉体から発せられる説得力が生じない。一緒に迎えに来た兄を演じた役者が、台詞を酷い棒読みにしているのには鼻白まされるし、主人公が部下と相撲に興じるシーンなど、いかにも外国人監督が考えた日本兵像という印象だ。投降を促すビラが森に降ってくるシーンの反復が、単調な繰り返しの域を出ず、「時間」を描き得ていない事にも不満を覚える。冒頭の、灯の明かりだけを頼りに洞窟を進むシーンで、徐々に玉音放送が聞こえる演出はいいのだが。
『いつまでもあなたが好き好き好き』
当初の予定では85分のはずが、直前の編集作業で109分となり、その形ではOAFFが世界初公開となった『リベラシオン』(監督:アドルフォ・アリックス・ジュニア/フィリピン)。だが、単に冗長さを増しただけに思える。日本の敗戦を信じず、長年フィリピンの山中に潜伏し続けた日本兵の物語で、スティーブン・ソダーバーグの『チェ』二部作や、ガス・ヴァン・サントの『パラノイドパーク』辺りを髣髴とさせる、淡々としたタッチによる演出。だが、ショットが弱い。「敵」を意識しながら森に潜む緊張感や、食糧の確保等、日本兵の生活が充分に演出されていない。現地女性との交流にまつわるディテールの積み重ねが薄い。故に、主人公が最後、迎えに来た上官に向けて「この戦争の勝者は誰ですか。この戦争は正しかったんですか」と訴える台詞にも、時間の蓄積に耐え続けた肉体から発せられる説得力が生じない。一緒に迎えに来た兄を演じた役者が、台詞を酷い棒読みにしているのには鼻白まされるし、主人公が部下と相撲に興じるシーンなど、いかにも外国人監督が考えた日本兵像という印象だ。投降を促すビラが森に降ってくるシーンの反復が、単調な繰り返しの域を出ず、「時間」を描き得ていない事にも不満を覚える。冒頭の、灯の明かりだけを頼りに洞窟を進むシーンで、徐々に玉音放送が聞こえる演出はいいのだが。
 『リベラシオン』
何よりまずタイトルの響きに惹かれる『マジック&ロス』(監督:リム・カーワイ/日本・マレーシア・韓国・香港・フランス)には、『息もできない』での共演が鮮烈だったヤン・イクチュンとキム・コッピが再び共演している。『息もできない』の「動」に対して本作は、どこか『去年マリエンバートで』を髣髴とさせもする「静」の映画。キャストの杉野希妃はプロデューサーも兼ねており、彼女のプロデュース作品の中から、OAFFには『歓待』(監督:深田晃司/日本)と『少年少女』(監督:太田信吾/日本)も出品されていた。不可思議さとロマンティックな美しさを感じさせるタイトル通りの作風で、潮の香りと仄かな官能が漂う、虚無的なバカンス映画といったところだ。時の静止を感じさせる白い彫像の向こうに見える浜辺での、カラフルなビキニ姿でビーチボールを投げあう若い女二人のショットは、作品の雰囲気を象徴している。そのミスマッチ感と叙情性。だが既にこのショットからして、構図や色彩設計が徹底した美意識で引き締められきれていない。カメラに接近してきたヤンの赤い半ズボンが画面を覆ったり、キムが杉野の歯ブラシで洗面所を掃除し始めたり、突拍子も無い出来事による驚きが所々に用意されているのは捨て難いが、緻密さと狂気がまだ足りない。時おり杉野が見せる、さり気ない仕種であるが故の艶っぽい姿はよいが、その色香が作品世界を不穏さで充たすには至らない。杉野とキムの唐突な人格交替や、原色の赤と闇の暗さが毒々しいショットなども、作り手の体液のように滲み出したイマジネーションというより、デビッド・リンチ風の不条理映画という「スタイル」を試してみたような印象だ。プロットに合理的な説明などは要らないが、不条理を力業で押し通す映像の質感が欲しい。エンドロール後の、杉野が部屋で電話をとるとノイズが発せられる「不気味さ」の演出も、リンチのようにチープな手作り感によって独特の触感を実現し得る作家ならともかく、半端に手を出すとただチープでしかなくなる。
『リベラシオン』
何よりまずタイトルの響きに惹かれる『マジック&ロス』(監督:リム・カーワイ/日本・マレーシア・韓国・香港・フランス)には、『息もできない』での共演が鮮烈だったヤン・イクチュンとキム・コッピが再び共演している。『息もできない』の「動」に対して本作は、どこか『去年マリエンバートで』を髣髴とさせもする「静」の映画。キャストの杉野希妃はプロデューサーも兼ねており、彼女のプロデュース作品の中から、OAFFには『歓待』(監督:深田晃司/日本)と『少年少女』(監督:太田信吾/日本)も出品されていた。不可思議さとロマンティックな美しさを感じさせるタイトル通りの作風で、潮の香りと仄かな官能が漂う、虚無的なバカンス映画といったところだ。時の静止を感じさせる白い彫像の向こうに見える浜辺での、カラフルなビキニ姿でビーチボールを投げあう若い女二人のショットは、作品の雰囲気を象徴している。そのミスマッチ感と叙情性。だが既にこのショットからして、構図や色彩設計が徹底した美意識で引き締められきれていない。カメラに接近してきたヤンの赤い半ズボンが画面を覆ったり、キムが杉野の歯ブラシで洗面所を掃除し始めたり、突拍子も無い出来事による驚きが所々に用意されているのは捨て難いが、緻密さと狂気がまだ足りない。時おり杉野が見せる、さり気ない仕種であるが故の艶っぽい姿はよいが、その色香が作品世界を不穏さで充たすには至らない。杉野とキムの唐突な人格交替や、原色の赤と闇の暗さが毒々しいショットなども、作り手の体液のように滲み出したイマジネーションというより、デビッド・リンチ風の不条理映画という「スタイル」を試してみたような印象だ。プロットに合理的な説明などは要らないが、不条理を力業で押し通す映像の質感が欲しい。エンドロール後の、杉野が部屋で電話をとるとノイズが発せられる「不気味さ」の演出も、リンチのようにチープな手作り感によって独特の触感を実現し得る作家ならともかく、半端に手を出すとただチープでしかなくなる。
 『マジック&ロス』
とはいえ、映画祭中、数多くのキャストやスタッフが登壇した中にあって、杉野は壇上に最も華を添えた存在ではあった。11日のウエルカム・セレモニーでゲストらが勢揃いして登壇した際に、杉野が司会者から「プロデューサーで主演も務められた……」と紹介されると、一同の代表として舞台中央に立っていた桃井かおりが、身を乗り出して杉野の姿を確認していたのが印象的だった。「来るべき才能賞」の審査でも、杉野の名は挙がっていたようだが、審査委員長の行定勲監督からは、「プロデューサーとしての自覚が欠けている」、「来るべき才能というにはまだ弱い」と指摘があり、今後への期待も込めて今回は見送られたようだった。彼女に「今後成功する可能性がある」、「ぜひ韓国に来て仕事をしてほしい」と激励を送った審査委員のキム・デウ監督からは、「女性としてもプロデューサーとしても一皮剥ける」という理由で、「不倫をしなさい」とセクハラ紛いの助言も為されたが、その言わんとするところは、漠然とだが了解できる。『マジック...』に関して言えば、感情に直に突き刺さるような強さが欠けていて、浮ついたイメージの展開に終始している嫌いがある。端から見込みのない作品ではないだけに、その不徹底さには隔靴掻痒の感があった。
『マジック&ロス』
とはいえ、映画祭中、数多くのキャストやスタッフが登壇した中にあって、杉野は壇上に最も華を添えた存在ではあった。11日のウエルカム・セレモニーでゲストらが勢揃いして登壇した際に、杉野が司会者から「プロデューサーで主演も務められた……」と紹介されると、一同の代表として舞台中央に立っていた桃井かおりが、身を乗り出して杉野の姿を確認していたのが印象的だった。「来るべき才能賞」の審査でも、杉野の名は挙がっていたようだが、審査委員長の行定勲監督からは、「プロデューサーとしての自覚が欠けている」、「来るべき才能というにはまだ弱い」と指摘があり、今後への期待も込めて今回は見送られたようだった。彼女に「今後成功する可能性がある」、「ぜひ韓国に来て仕事をしてほしい」と激励を送った審査委員のキム・デウ監督からは、「女性としてもプロデューサーとしても一皮剥ける」という理由で、「不倫をしなさい」とセクハラ紛いの助言も為されたが、その言わんとするところは、漠然とだが了解できる。『マジック...』に関して言えば、感情に直に突き刺さるような強さが欠けていて、浮ついたイメージの展開に終始している嫌いがある。端から見込みのない作品ではないだけに、その不徹底さには隔靴掻痒の感があった。
 『マジック&ロス』
妙な作風という点では『マジック...』以上の『遭遇』(監督:イム・テヒョン/韓国)。その、やたらとカメラを手ぶれさせたり、急なズームアップを行なったりして「リアル」を演出する、近ごろ流行りの撮影法には些か食傷気味なのだが、いかにも低予算な映画の撮影現場を物語の舞台としつつ、そこに非現実的な要素を挿入し、更にそれをユーモアではぐらかすという微妙な匙加減には心地よく翻弄された。劇中の、撮影用に宇宙人のキグルミを着てきた男など、その言動はごく普通だが、遂に一度もそのキグルミを脱がないので、その中身が誰なのかという点に、一抹の疑わしさを保ち続けるのが面白い。劇中の撮影現場と同様に、本作の撮影自体も即興的に行なわれたようだが、その選択は諸刃の剣だった。脈絡のない思いつきが画面に驚きをもたらしている箇所もあったが、反面、終盤で劇中の監督ジュンホの過去にまつわるベタな救済劇に収束していく点では、無軌道さに徹さず安直な物語に回収させる弱さが覗く。宇宙人の大きく黒い目が、ジュンホの妹が落ちたと思しき井戸の丸い暗闇と符合させられるのはまだしも、イム監督が思いつきで撮ったという、ジュンホが土を掘るシーンまでも、後づけで安易に理由づけが為されてしまうのが興をそぐ。脚本が練られていないせいで、誰でも即席で思いつくようなクリシェに映画が奪われてしまった観がある。加えて、ドキュメンタリー風の撮影は、カメラが透明な視点とならず、それ自体の身体性が観客の眼前にチラつくせいで、臨場感からはむしろ遠のいてしまう。それでいながら、ジュンホの内面に寄り添うような物語を描く方へ向かうので、表現方法と内容とに齟齬が生じている。質疑応答で監督は、客席から投げかけられた「幼い頃に死んだ妹の幻影が、成人女性の姿で現れるのはなぜか」という問いに、自然な思いつきだとか、インパクトを重視したとか説明していたが、やはりもう少し考えて撮るべきだっただろう。観客が映像をどう観るかが殆ど計算されていないのは無謀に過ぎる。
『マジック&ロス』
妙な作風という点では『マジック...』以上の『遭遇』(監督:イム・テヒョン/韓国)。その、やたらとカメラを手ぶれさせたり、急なズームアップを行なったりして「リアル」を演出する、近ごろ流行りの撮影法には些か食傷気味なのだが、いかにも低予算な映画の撮影現場を物語の舞台としつつ、そこに非現実的な要素を挿入し、更にそれをユーモアではぐらかすという微妙な匙加減には心地よく翻弄された。劇中の、撮影用に宇宙人のキグルミを着てきた男など、その言動はごく普通だが、遂に一度もそのキグルミを脱がないので、その中身が誰なのかという点に、一抹の疑わしさを保ち続けるのが面白い。劇中の撮影現場と同様に、本作の撮影自体も即興的に行なわれたようだが、その選択は諸刃の剣だった。脈絡のない思いつきが画面に驚きをもたらしている箇所もあったが、反面、終盤で劇中の監督ジュンホの過去にまつわるベタな救済劇に収束していく点では、無軌道さに徹さず安直な物語に回収させる弱さが覗く。宇宙人の大きく黒い目が、ジュンホの妹が落ちたと思しき井戸の丸い暗闇と符合させられるのはまだしも、イム監督が思いつきで撮ったという、ジュンホが土を掘るシーンまでも、後づけで安易に理由づけが為されてしまうのが興をそぐ。脚本が練られていないせいで、誰でも即席で思いつくようなクリシェに映画が奪われてしまった観がある。加えて、ドキュメンタリー風の撮影は、カメラが透明な視点とならず、それ自体の身体性が観客の眼前にチラつくせいで、臨場感からはむしろ遠のいてしまう。それでいながら、ジュンホの内面に寄り添うような物語を描く方へ向かうので、表現方法と内容とに齟齬が生じている。質疑応答で監督は、客席から投げかけられた「幼い頃に死んだ妹の幻影が、成人女性の姿で現れるのはなぜか」という問いに、自然な思いつきだとか、インパクトを重視したとか説明していたが、やはりもう少し考えて撮るべきだっただろう。観客が映像をどう観るかが殆ど計算されていないのは無謀に過ぎる。
 『遭遇』
グランプリ受賞作となった『恋人のディスクール』(監督:デレク・ツァン、ジミー・ワン/香港)は、些か棒読み口調で「うまくまとめ上げている」と評したい作品。劇中の四つの物語は、『恋人までの距離(ディスタンス)』風の会話劇として演出された第一話に始まり、コメディタッチのメルヘン風、青春映画風、ラブサスペンス風、と趣向を変えていくが、どれも既視感のある「…風」の演出を並べている印象。この監督らが、どのような作品でも手堅く演出し得る優秀さを示したのは認めるし、画面を眩しい光が充たすショットや、人物間に漂う距離感の切なさなど、全篇に通底するスタイルも感じられはするものの、全体の印象としては、小手先の器用さだけが目立つ。冒頭の導入部では、恋愛感情の神経生理学的な解説を行なった後、「科学で恋は説明できない。だから、様々な恋愛物語を見てみよう」と促して本篇に入る。CGを使用したこの導入部は、各話がそれぞれの仕方で叙情性を醸し出していた本篇とも齟齬があるし、結局、本篇が、「こういう類いの映画も撮れますよ」というサンプル集の域を出ない事を予告していたようにも思えてしまう。尤も、内気なメガネッ娘がメルヘンな空想を繰り広げるキュートな物語が含まれていたり、見栄えのいい映像で雰囲気を作り上げ、人の頭を混乱させない程度の複雑さでプロットを設計していたりと、或る種の文化系女子には受けそうな作品ではある。こうした作品を器用に撮る才能に何の価値も無いとは言わないが、グランプリという形でわざわざ肯定してやる必要があったのだろうか。
『遭遇』
グランプリ受賞作となった『恋人のディスクール』(監督:デレク・ツァン、ジミー・ワン/香港)は、些か棒読み口調で「うまくまとめ上げている」と評したい作品。劇中の四つの物語は、『恋人までの距離(ディスタンス)』風の会話劇として演出された第一話に始まり、コメディタッチのメルヘン風、青春映画風、ラブサスペンス風、と趣向を変えていくが、どれも既視感のある「…風」の演出を並べている印象。この監督らが、どのような作品でも手堅く演出し得る優秀さを示したのは認めるし、画面を眩しい光が充たすショットや、人物間に漂う距離感の切なさなど、全篇に通底するスタイルも感じられはするものの、全体の印象としては、小手先の器用さだけが目立つ。冒頭の導入部では、恋愛感情の神経生理学的な解説を行なった後、「科学で恋は説明できない。だから、様々な恋愛物語を見てみよう」と促して本篇に入る。CGを使用したこの導入部は、各話がそれぞれの仕方で叙情性を醸し出していた本篇とも齟齬があるし、結局、本篇が、「こういう類いの映画も撮れますよ」というサンプル集の域を出ない事を予告していたようにも思えてしまう。尤も、内気なメガネッ娘がメルヘンな空想を繰り広げるキュートな物語が含まれていたり、見栄えのいい映像で雰囲気を作り上げ、人の頭を混乱させない程度の複雑さでプロットを設計していたりと、或る種の文化系女子には受けそうな作品ではある。こうした作品を器用に撮る才能に何の価値も無いとは言わないが、グランプリという形でわざわざ肯定してやる必要があったのだろうか。
 『恋人のディスクール』
一方、『恋人...』と共に最後まで審査の対象になっていたらしい『雨夜 香港コンフィデンシャル』(監督:マリス・マルティンソンス/ラトビア・香港)は、そつのない『恋人...』とは対照的な、奇妙なタッチの作品だ。一見すると『マジック...』や『遭遇』の方が変則的にも思えるが、独特の世界観を映像として構築し得ている点では、本作が最も推せる。舞台は香港。義兄のマッサージ店に勤める日本人女性・雨夜と、イギリス人男性ポールを両輪として展開する物語は、時間軸が交錯していながらも、過去と現在の区別が曖昧で、しかも「曖昧な描写である」という事自体を明確にしないので、殆どの観客は混乱させられるだろう。本作の前に観た『リベラシオン』が上映直前に編集を終えたのを聞かされたせいもあって、本作も編集作業が完了していないのではないかとさえ感じてしまった。だが、確かに観客に対して親切な編集ではないが、シーンとシーン、カットとカットの間から、雨夜とポールの記憶の層が現れるに従って、登場人物の表情や言動が、その意味合いを変化させていく驚きがある。この驚きは、過去と現在が完全にフラットに描かれている事で、却ってより強められるのだ。淡々と日々を送って見える登場人物たちが、実は観客が了解していたのとは別の層の時間を生きていた事の驚き。本作の真の被写体は、風景でも人物でもなく、それらを通して垣間見られる「時間」だったのかもしれない。雨夜の夫が古い掛時計を修理するシーンでは、扉が開かれた時計の内側からのショットがあり、恰も、古時計に保存されてきた「時間」の側からの「主観ショット」のようにも感じられた。「編集が不親切だ」という一言で片付けられてしまいかねない危うさは確かに残るが、そうした、世界との関係が脱臼したような在り方が、ひとつの新しい時空間をもたらしてもいる。バイキング形式のような多彩さが却って平板な印象を与える『恋人...』は、それなりに万人受けがしそうだが、『雨夜...』の不親切さの方が遥かに潔く、好ましく思える。
雨夜を演じた桃井かおりは、ABCホールでの上映に際して壇上に現れ、上述した時間軸の曖昧さにも触れつつ、監督の作風について、訳が分からない所はあるが、表現したいものがあって作っている事が伝わってくる、と評していたが、本作の印象として的確な表現だ。雨夜という女性についても、桃井自身の想像で人物像を膨らませていたようだが、作品自体も、映像の裏を自由に読める、余白の多い作りになっている。壇上の桃井は、カーテンの陰からひょっこり顔を覗かせたり、作品について熱心に語ったりと、終始ご機嫌な様子だった。会場には彼女を知らぬ人などおそらくいなかっただろうが、その天衣無縫さには、初めて見た人でもすぐにファンになってしまっただろう。
『恋人のディスクール』
一方、『恋人...』と共に最後まで審査の対象になっていたらしい『雨夜 香港コンフィデンシャル』(監督:マリス・マルティンソンス/ラトビア・香港)は、そつのない『恋人...』とは対照的な、奇妙なタッチの作品だ。一見すると『マジック...』や『遭遇』の方が変則的にも思えるが、独特の世界観を映像として構築し得ている点では、本作が最も推せる。舞台は香港。義兄のマッサージ店に勤める日本人女性・雨夜と、イギリス人男性ポールを両輪として展開する物語は、時間軸が交錯していながらも、過去と現在の区別が曖昧で、しかも「曖昧な描写である」という事自体を明確にしないので、殆どの観客は混乱させられるだろう。本作の前に観た『リベラシオン』が上映直前に編集を終えたのを聞かされたせいもあって、本作も編集作業が完了していないのではないかとさえ感じてしまった。だが、確かに観客に対して親切な編集ではないが、シーンとシーン、カットとカットの間から、雨夜とポールの記憶の層が現れるに従って、登場人物の表情や言動が、その意味合いを変化させていく驚きがある。この驚きは、過去と現在が完全にフラットに描かれている事で、却ってより強められるのだ。淡々と日々を送って見える登場人物たちが、実は観客が了解していたのとは別の層の時間を生きていた事の驚き。本作の真の被写体は、風景でも人物でもなく、それらを通して垣間見られる「時間」だったのかもしれない。雨夜の夫が古い掛時計を修理するシーンでは、扉が開かれた時計の内側からのショットがあり、恰も、古時計に保存されてきた「時間」の側からの「主観ショット」のようにも感じられた。「編集が不親切だ」という一言で片付けられてしまいかねない危うさは確かに残るが、そうした、世界との関係が脱臼したような在り方が、ひとつの新しい時空間をもたらしてもいる。バイキング形式のような多彩さが却って平板な印象を与える『恋人...』は、それなりに万人受けがしそうだが、『雨夜...』の不親切さの方が遥かに潔く、好ましく思える。
雨夜を演じた桃井かおりは、ABCホールでの上映に際して壇上に現れ、上述した時間軸の曖昧さにも触れつつ、監督の作風について、訳が分からない所はあるが、表現したいものがあって作っている事が伝わってくる、と評していたが、本作の印象として的確な表現だ。雨夜という女性についても、桃井自身の想像で人物像を膨らませていたようだが、作品自体も、映像の裏を自由に読める、余白の多い作りになっている。壇上の桃井は、カーテンの陰からひょっこり顔を覗かせたり、作品について熱心に語ったりと、終始ご機嫌な様子だった。会場には彼女を知らぬ人などおそらくいなかっただろうが、その天衣無縫さには、初めて見た人でもすぐにファンになってしまっただろう。
 『雨夜 香港コンフィデンシャル』
コンペティション部門出品作は概ねアート系作品に難があると先に述べたが、それは、エンターテインメントは描くべきドラマの骨子が予め明確で、そこに幾つか新鮮味のあるアイデアをちりばめていけば事が済むのに対し、アート系作品はそうした根幹部分から作り上げる必要があるからだろう。だが、「…風」のスタイルを未消化なままなぞった演出法や、奇抜なアイデアを思いついてもそれを貫かず、既存の物語に回収してしまう作品が目立ち、作者の内的な衝動の徹底を感じさせる、強い作品は少なかった。皆、小利口な形で「映画」を知りすぎてしまっているのだ。そうした中、描きたいものがあって作られている事が最も明確に伝わってきたのは、『彼が23歳だった時』(監督:アタヌ・ゴーシュ/インド)。ベンガル地方を舞台に、保守的な家庭に囚われた青年を主人公にしつつも、ソーシャル・ネットワークを介した男女の出会いといった現代性を盛り込んでもいる。やはり表現行為は、抑圧というものが明確に感じられる場所でこそ、凝縮された密度を持ち得るのだろうか。だが、主人公が医師という地位を脱して芸術家になろうとする姿を「解放」の表現として描くのは、彼が芸術にかける心情や、その才能の有無を描いていないせいもあるが、「芸術家=自由」という構図が自明視されている点に違和感を覚える。ステレオタイプな道徳に対抗するイメージそのものが、幾分ステレオタイプなのだ。対して、コスモポリタンな世界観を有した『雨夜…』は、抗うべき価値観も何もない、宙を浮遊するような曖昧さを生きる現代の感性をよく体現していた。ガラス張りのロープウェイのシーンは、それを象徴している。
『雨夜 香港コンフィデンシャル』
コンペティション部門出品作は概ねアート系作品に難があると先に述べたが、それは、エンターテインメントは描くべきドラマの骨子が予め明確で、そこに幾つか新鮮味のあるアイデアをちりばめていけば事が済むのに対し、アート系作品はそうした根幹部分から作り上げる必要があるからだろう。だが、「…風」のスタイルを未消化なままなぞった演出法や、奇抜なアイデアを思いついてもそれを貫かず、既存の物語に回収してしまう作品が目立ち、作者の内的な衝動の徹底を感じさせる、強い作品は少なかった。皆、小利口な形で「映画」を知りすぎてしまっているのだ。そうした中、描きたいものがあって作られている事が最も明確に伝わってきたのは、『彼が23歳だった時』(監督:アタヌ・ゴーシュ/インド)。ベンガル地方を舞台に、保守的な家庭に囚われた青年を主人公にしつつも、ソーシャル・ネットワークを介した男女の出会いといった現代性を盛り込んでもいる。やはり表現行為は、抑圧というものが明確に感じられる場所でこそ、凝縮された密度を持ち得るのだろうか。だが、主人公が医師という地位を脱して芸術家になろうとする姿を「解放」の表現として描くのは、彼が芸術にかける心情や、その才能の有無を描いていないせいもあるが、「芸術家=自由」という構図が自明視されている点に違和感を覚える。ステレオタイプな道徳に対抗するイメージそのものが、幾分ステレオタイプなのだ。対して、コスモポリタンな世界観を有した『雨夜…』は、抗うべき価値観も何もない、宙を浮遊するような曖昧さを生きる現代の感性をよく体現していた。ガラス張りのロープウェイのシーンは、それを象徴している。
 『彼が23歳だった時』
13日の、各賞の授賞式をメインとしたクロージング・セレモニーの後、『カイト』(監督:アヌラーグ・バス/インド・メキシコ・アメリカ)の上映前に、駐大阪インド総領事館総領事としてヴィカス・スワラップ氏が挨拶に立った。氏は『スラムドッグ$ミリオネア』の原作者でもあり、その事に彼が言及すると会場からどよめきが起こった。最近のインド映画について、「三時間、空調の効いた場所で夢想に耽るだけではなく、娯楽性と芸術性を両立させた作品が作られている」と語り、「映画『スラムドッグ…』について訊かれた際、私はいつも“ハリウッドの空の下で作られたボリウッド映画”と言ってきましたが、これからご紹介する『カイト』は“ボリウッドの空の下で作られたハリウッド映画”です」と『カイト』につなぐ。最後に壇上に立った、タレント・DJのサニー・フランシス氏は、普段からテレビ等で見せている通りの関西弁の喋りで『カイト』を紹介。いかにも大阪のインド人らしく、与えられた短い時間をフル活用したマシンガン・トークで捲し立て、会場を沸かせて去っていった。『カイト』は、この二氏の紹介の通り、筋骨隆々の美男子と、セクシーな美女の完璧な容姿や、カーチェイス・シーンでいちいち花火のように火柱が立ち、曲芸のようにパトカーが宙に舞うなど、ここまでセンターに寄せますかと言いたくなるほどに娯楽作のオーソドクシーを徹底させている。さすがにハリウッドでも、ここまでの直球は投げないだろう。その華美さや、それと対照的なラストの厭世観など、我々が想像するインドらしさという点では、或る意味『彼が23歳...』以上だろう。この二本のインド映画は、インドでの上映形式に倣い、途中で5分間の休憩が入った。上映前のアナウンスでその事が告げられたとき、客席からは笑い声が湧いていたが、実際に休憩が入った際は、席を立ってトイレか何かに立つ観客も何人かいて、それなりに活用されており、束の間のインド時間が流れていた。
『彼が23歳だった時』
13日の、各賞の授賞式をメインとしたクロージング・セレモニーの後、『カイト』(監督:アヌラーグ・バス/インド・メキシコ・アメリカ)の上映前に、駐大阪インド総領事館総領事としてヴィカス・スワラップ氏が挨拶に立った。氏は『スラムドッグ$ミリオネア』の原作者でもあり、その事に彼が言及すると会場からどよめきが起こった。最近のインド映画について、「三時間、空調の効いた場所で夢想に耽るだけではなく、娯楽性と芸術性を両立させた作品が作られている」と語り、「映画『スラムドッグ…』について訊かれた際、私はいつも“ハリウッドの空の下で作られたボリウッド映画”と言ってきましたが、これからご紹介する『カイト』は“ボリウッドの空の下で作られたハリウッド映画”です」と『カイト』につなぐ。最後に壇上に立った、タレント・DJのサニー・フランシス氏は、普段からテレビ等で見せている通りの関西弁の喋りで『カイト』を紹介。いかにも大阪のインド人らしく、与えられた短い時間をフル活用したマシンガン・トークで捲し立て、会場を沸かせて去っていった。『カイト』は、この二氏の紹介の通り、筋骨隆々の美男子と、セクシーな美女の完璧な容姿や、カーチェイス・シーンでいちいち花火のように火柱が立ち、曲芸のようにパトカーが宙に舞うなど、ここまでセンターに寄せますかと言いたくなるほどに娯楽作のオーソドクシーを徹底させている。さすがにハリウッドでも、ここまでの直球は投げないだろう。その華美さや、それと対照的なラストの厭世観など、我々が想像するインドらしさという点では、或る意味『彼が23歳...』以上だろう。この二本のインド映画は、インドでの上映形式に倣い、途中で5分間の休憩が入った。上映前のアナウンスでその事が告げられたとき、客席からは笑い声が湧いていたが、実際に休憩が入った際は、席を立ってトイレか何かに立つ観客も何人かいて、それなりに活用されており、束の間のインド時間が流れていた。
 『カイト』
*後編に続く
『カイト』
*後編に続く