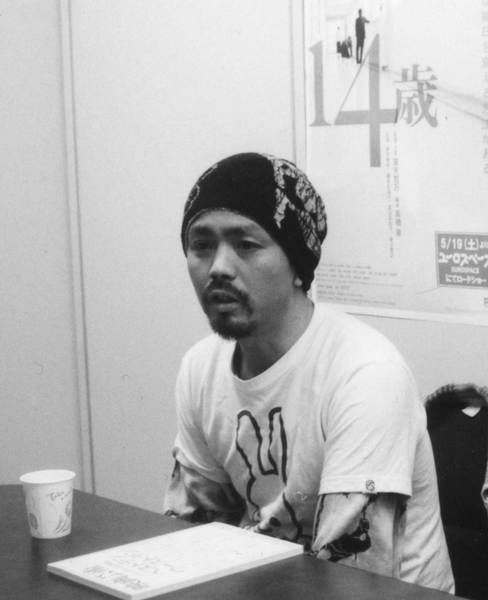2004年のぴあフィルムフェスティバル(PFF)でグランプリと準グランプリを独占した映像ユニット「群青いろ」の高橋泉と廣末哲万は、一本の商業作品も作らないまま日本の映画界に確固たる存在感を示したと言える。PFFグランプリ受賞作の『ある朝スウプは』(03)では、新興宗教に救済を求める主人公の男と、恋愛によって男を救済しようとする恋人との葛藤を描ききり、準グランプリ受賞作の『さよなら さようなら』(03)では自殺サイトに集う現代人の病理を抉った。続いて製作した自主映画『鼻唄泥棒』(05)は、犯罪被害者の遺族による加害者の制裁という題材を基に、犯罪加害者の人権を鋭く問いかける問題作だ。こうして常に社会的なテーマと対峙しようとする姿勢は、等身大映画ばかりが溢れる現在の日本映画界で明らかに異彩を放っている。
この二人がぴあのスカラシップ作品として製作した初の商業映画『14歳』(監督:廣末哲万、脚本:高橋泉)が今月19日からユーロスペースで公開される。初めての商業作品に気負いはなかったのか、なぜ今14歳という題材を選んだのか、撮影時の裏話や今後の活動も含めて、同世代の編集スタッフが聞いた。
「14歳は何にでもなれる」
――この『14歳』はPFFのスカラシップ作品ということですが、どのようにして製作が決まったんですか。
廣末 基本的にはPFFで入選した作品の監督を対象にスカラシップ用の脚本を募るんですね。その後、出資者による面接などで作品のプレゼンみたいなことをして、最終的に映画化する脚本を決めるという流れになっています。
――高橋さんが『ある朝スウプは』でグランプリ、廣末さんが『さよなら さようなら』で準グランプリを獲っていますから、スカラシップには2本の脚本を応募する権利があったんじゃないですか。
廣末 そうですね。権利はあったんですけど、2人で1本しか出しませんでした。
――そのときに応募した脚本は、今回の撮影に使った脚本と同じものだったんでしょうか。
廣末 いや、全然違いますね。
高橋 スカラシップに応募した脚本の段階では、大人から見た14歳はほとんど描かれていませんでした。大人も一応、話の中には登場していたんですが、メインはあくまでも14歳の子供だったんです。
――今回、『14歳』という映画を作りたいと思った動機はなんだったんですか。
高橋 まず、14歳を描きたいという初期衝動があったんですね。それで自分が14歳のときのことを必死に思い出しながら、それよりもっとキツい14歳の日常を描こうとしたんです。さらに、大人になった14歳も並行して描けないかということで、完成した映画のような形になっていきました。
――14歳という年齢にこだわったのは、その時期に何か特別な体験があったからですか。
高橋 14歳を描きたいと思った衝動は、やっぱり自分が14歳のときに体験したことや、そのときの感情に根ざしたものですね。ただ普通に生きていると、14歳が起こした事件のことなんかも耳にしますから、そういうことの影響も多少はあったと思います。でも、基本的には自分が14歳のときの感情を優先して脚本を書きました。
――14歳を描く動機となった高橋さん自身の体験というのはどういうものなんですか。
高橋 映画で言えば、冒頭の彫刻刀のシーンなんかはそのまま僕の実体験なんですけど…。ちょうど中学生時代の杉野(榎本宇伸)が立っている場所に僕がいて、教室の中で女の子が男の教師に怒られていたんですね。それで、その教師が廊下へ出てきたら、女の子もふわぁっと飛び出してきて、彫刻刀でガッとやったという。
――つまりトップシーンのイメージがかなり鮮明にあって、そこから脚本を書き出していったと。
高橋 そうですね。
――今回の脚本を作るに当たって14歳の子供たちに取材したりしたんでしょうか。
高橋 してないですね。基本的に映画のなかの子供たちの感情は、自分がその年代のときに抱いた感情を使っています。
――なぜ13歳や15歳ではなく、14歳でなければいけなかったんでしょう。
廣末 体とかいろいろな部分が未熟ななかで、内面的な感情だけはどんどん熱を持ってふくらんできている時期で、僕自身、とても不安定だったという感覚が今でも残っているんですね。なんでもやっちゃえるというか、何にでもなれるという意味で、特別な時期だったと思うんです。
高橋 実際にオーディションをやってみて、14歳の子って他の年齢の子供たちと明らかに違うんですよ。正直なところ、最初はどうして14歳なのか、その年代をピンポイントで描く必要があるのかという思いが自分にも多少あったんです。でもオーディションで直接子供たちに会ってみたら、12歳と14歳、15歳と14歳の子供では全然違う。12歳~15歳という僅かな年齢差で、これだけ人種が違うのかというぐらいに違っていたんです。
――今回映画に出演されている子供たちも14歳の子が多いんですか。
廣末 ほぼそうですね。
――オーディションでは子供が持っている14歳的な要素を重視したということでしょうか。
廣末 というより、作品で描かれているような感情や感覚を持っている子を選びましたね。
(c)PFFパートナーズ2006
「14歳をわかったように描いたら嘘になる」
――かつて14歳だった大人が今の14歳とどう向き合っていくのかということが映画のテーマだとすると、そのわりに今の14歳を描いている比重が大きいように感じました。
高橋 そのことは脚本の段階でも結構指摘されました。本来の作り方で言うと、子供の人数を増やせば必ず、それぞれの子供の感情やストーリーを最終的に回収しなければいけない。なぜ映画の中にその子が存在していたのかを理由付けする必要が出てきます。だけど僕は、暗い子が二人いたら明るい子が一人いるというようなバランスがないのがリアルな14歳だと思うんです。バランスのいいものにしたら、ただのオハナシにしかならないだろうと。だから、その子の感情やストーリーを回収できなくてもいいから、そのまま映画の中に存在して、突っ走って、何も変わらないまま終わってほしいという考えがありました。大人の感情やストーリーは少し回収しなくちゃいけないかなと思ったんですけど、子供の方を回収したら嘘になっちゃうんですよね。
――高橋さんの中には、例えば問題のない生徒や教師を置こうという考えはなかったんでしょうか。
高橋 それはなかったですね。もしかすると廣末君がエキストラカットや説明カットを撮らないのと似ているのかもしれません。例えば暗い子供を描くために、対照的な存在として明るい子供を配置するという脚本作りのセオリーがありますけど、そういうやり方は好きじゃない。暗い子供を描きたいなら、暗い子供を書けばいいじゃないですか。対照的な存在を配置するとか緩急を付けるとか、そういう嫌らしさは商業映画の脚本でやっているので(笑)、僕らの脚本を書くときはそうじゃなくていいやと。
――『ある朝スウプは』ではカップルが別れる最後の場面で「私たち他人なんだね」という、わりと突き放したセリフを言わせているのに対して、『14歳』では廣末さん演じる杉野がピアノを教えている大樹(染谷将太)に「お前らと本気で向き合ってくれる大人なんて殆どいないんだよ!」と言ったあと、続けて「それでもお前が僕に何かを求めるなら僕はそれに応えてやるよ。お前らが何を考えてるのかはもう思い出せないけど、僕に出来ることがあるならやってやるよ」という言葉を口にします。『14歳』のこのセリフは、『ある朝~』と違って対象にかなり踏み込んだセリフだと思いますが、この変化は時間の経過によるものなんですか。
高橋 時間はあまり関係ないよね?
廣末 そうですね。
高橋 もしかしたら次の作品ではまた突き放すかもしれないし、それはわからないですけど…。やっぱり対象が違うということが大きいですね。でもべつに対象が子供だからというわけではなく、たまたまコミュニケーションしようとする相手がそういう言葉を引き出したということだと思います。
――今は大人になれない人が増えているという実感があります。ちょうど映画の中に登場する杉野や深津(並木愛枝)、小林(香川照之)のように、子供を前にするとどう振舞っていいのかわからない。そういうところが僕にもあって、そんな人間が先ほど挙げたようなセリフを子供に面と向かって口にすることはかなり覚悟がいることだと思います。その覚悟はどのようにして生まれたものなんでしょうか。
廣末 あのシーンに関しては、廣末君が言いたいことを言ってくれと高橋さんから託された感じでした。もしかしたら、そういうことは初めてかもしれないですけど、今回は自分の言いたいことを、恥ずかしいけれどもぶちまけてみようと思ったんです。実際に僕が一人の少年と向き合ったときに何が言えるかと考えてみたら、ああいう言葉になっちゃったんですけど。
――そのセリフにもあるように、この映画は今の14歳がわからないという立場で作られていると思いますが、そう割り切るのはなかなか難しいことですよね。
高橋 ナマの14歳を描くことには降参しました。それをわかったように描くと、やっぱり嘘になってしまうので。
――それで稿を重ねるうちに大人を描く比重が大きくなったということなんですか。
高橋 そうですね。
――大樹が母親に性的な興奮を覚えるという描写がありますよね。彼にそういう設定を与えた意図はなんだったんでしょうか。
高橋 そこは第一稿の流れのままで行ってしまった部分もあるんです。ああいうことは虐待の一種としてあるらしいんですよ。それを入れたいという思いがあって、その名残がああいう形になったと。
――つまり母親が息子を性的に虐待していたということですか。
高橋 元々はそうですね。
――お二人の映画は今回の作品に限らず、常に社会的なテーマとがっぷり四つに組んで作られている印象がありますが、その原動力はどこから来ているんでしょうか。
高橋 どうなんでしょうね。社会っていうのはどこかにあるようなものではなくて、自分の生きている場所が社会なわけですから、その社会とはがっぷり四つに組んで生きている感覚がありますけど…。だから原動力というよりも、自分が普段感じていることをそのまま映画にしてみたら、社会とがっぷり四つの感じになっていたということなんだと思います。
――映画を作るために自分の外側にあるものを取り入れている感覚ではないんですね。
高橋 そうですね。
しんどかった二人での脚本作り
――今回、高橋さんから14歳の映画を作ろうと言われたとき、廣末さんはどう思われたんですか。
廣末 やりたい!と思いました(笑)。14歳の映画を作りたいという話は前々から二人でしていたので、とうとうそれを作るときが来たなと。
――脚本を作る過程で廣末さんが意見を出すようなこともあったんでしょうか。
廣末 そういうディスカッションをしたのはスカラシップ作品に選ばれてからで、応募する前の脚本には口を出していません。プロデューサーも入って意見交換をする段階になって初めて、僕も脚本のことに意見を言うようになったという感じです。
――これまでにも高橋さんが書かれた脚本を廣末さんが監督していますが、廣末さんは脚本作りにどう関わっていたんですか。
廣末 僕が監督をする場合には、脚本作りを始める前に僕が描きたいものを、高橋さんにはある程度断片的に伝えてあって、それを高橋さんが脚本にしてくれるので、脚本を書き始めたら口を出すことはありません。
――高橋さんは、自分が監督をする場合と廣末さんが監督をする場合とで、脚本の書き方が違ったりするんでしょうか。
高橋 それはやっぱり違います。例えば、廣末君の映画では狭いフレームでかなり細かい演出をしたりするんですね。そういうところが、最終的な形になったときに僕が演出する場合とは違う熱を孕んでくるんです。その違いがある程度想定できる分だけ、脚本の書き方も変わってきます。
――『ある朝スウプは』のときには、設定を与えて役者さんに演じてもらってから、脚本に書き起こしたという話を伺いました。高橋さん自身が演出する場合、そういう形で脚本を作っていく場合もあるんでしょうか。
高橋 あのときはたまたまですね。普段は一人で脚本を作ります。
――今回、脚本作りの面で商業作品であるがゆえの苦労はなかったですか。
高橋 プロデューサーが脚本作りに入ってくるのは、普段、商業映画の脚本を書いているときと同じなので、べつに違和感はありませんでした。逆に、廣末君と一緒に脚本を書き直していくというのが初めての経験だったので、そっちの方が新鮮というか、正直しんどかった(笑)。今までは脚本は一つの作品として完成させて、それを基に廣末君がまた別の作品を生むという感覚だったので、脚本も一稿で終わっていたんです。でも今回は大勢のスタッフが関わっているから、現場で脚本を大きく変えることはできない。それで廣末君と一緒に脚本を詰める必要があったんですけど、なかなかやっぱり難しいですね(笑)。
廣末 うん。難しい(笑)。
高橋 感覚は似通ってはいますけど、それをすり合わせていく作業っていうのは、ある種、変な作家性のぶつかり合いみたいなことにもなっちゃいますから。
――脚本作りで二人の意見が一番対立したところはどこだったんですか。
高橋 やりにくかったというだけで、対立はしてないです。基本的に撮るのは廣末君ですから、廣末君が必要ないと言えば、そこは僕も潔く切っちゃいますし。もちろん気持ちのうえでは「これをなくしちゃっていいのか?」と思うこともないわけじゃないですけど(笑)、監督のイメージになければ無理に残しても意味がないですからね。
――今関わっている商業作品も含めて、高橋さんの脚本にある社会性みたいなものが、商業性と折り合わないケースはありませんか。
高橋 それはないですね。喩えは悪いですが、松本人志さんがアメリカ人を笑わせに行くという企画が昔あって、アメリカ人の笑いっていうのは日本人の笑いの60%ぐらいなんですね。要するに、ちょっとだけ感覚が古い。だけど60%の力でネタを作っても通用しないから、60%のものを100%の力で作るっていう言い方を松本人志さんがしてたんですよ。それと同じで、商業映画の中で自分のやりたいことを100%やろうとするとおかしくなってしまうので、少し熱を落としたものを100%の力で作るっていうふうに割り切っています。だから、特に問題が起きることはないですね。
――廣末さんとの活動で自分のやりたいことを100%やりながら、商業映画の脚本は仕事と割り切って書いているということですね。
高橋 そうです。もちろん商業映画の脚本も本気でやりますけど(笑)。
廣末 死活問題だからね(笑)。
(c)PFFパートナーズ2006
バックショットは「過去からの視点」
――お二人の映画としては今回が初めての商業作品ということになると思います。何かそれに伴う苦労はありませんでしたか。
廣末 やっぱり初めてフィルムで撮ったということが一番大きかったですね。カメラマンにアングルを任せるということも初めての経験だったんですが、よほどの信頼関係がない限り、そういうやり方は成立しないのかなと思いました。
――今回のカメラマン(橋本清明)は熊切和嘉監督の『鬼畜大宴会』(98)や『空の穴』(01)なども担当されている方ですが、個人的な関係があって依頼されたわけではないんですか。
廣末 いえ、ぴあの方で連れて来てくださった方ですね。
――カメラマンとのやり取りには苦労した部分もあったんですか。
廣末 そうですね。そのシーンを何カットに割るか、どこからどこまでをワンカットに収めるかということは指示したんですが、あまり細かいことまで言ってしまうと現場が行き詰ってしまうだろうと思って、カメラのアングルまでは指示しなかったんです。だから、そういう部分で踏み込めないもどかしさというのは少しありましたね(笑)。
――今回の映画では、背後からのカットや足だけのカットなど、顔を外したカットが多いですが、その狙いはどんなところにあったんでしょうか。
廣末 バックショットに関しては、「過去からの視点」ということを意識して使いました。「今」というのはものすごい勢いで過ぎ去っていくんですけど、そうやって通り過ぎた過去っていうのはすぐ真後ろで自分のことを見ているような気がしていたんですね。そういう「過去からの視点」を意識してバックショットを多用しました。それから、人の足元や手元のカットを多用したのは、一発で状況がわかってしまう画よりも、観客の想像をかき立てたるような画を使いたかったからですね。
――回想前のシーンでも、背後から引きの画で撮ったりしているので、最初に映画を観たときは多少混乱しましたが、そういう狙いがあったんですね。
高橋 たしかに本来なら顔のアップがあってから回想にいくことが多いですよね(笑)。
――『14歳』も含めて、廣末さんの映画ではエキストラカットや説明カットが殆ど使われていませんが、そういう段取り的なというか、説明的なカットを使うのが嫌いなんですか。
廣末 僕は自分で編集もやるんですが、たとえ現場でそういうカットを撮っていても、なぜか編集の段階で邪魔になるんですね。そういうカットを入れると、自分のリズムに合わなくなってしまうんです。
――『さよなら さようなら』では畳みかけるような編集が印象的でしたが、今回の映画ではわりとゆっくりしたリズムで画を繋いでいました。
廣末 それはカメラが1台しかないという物理的なことも影響しています。最初はどう撮ろうかと悩んでいたんですが、義務教育を受けていた期間を僕は途方もなく長い時間に感じていたので、14歳の退屈な時間を映画でも感じてもらおうと思い直して、のんびりとしたリズムの映画にしたんです。
――フィルムだったせいで、細かい編集作業ができなかったという面もあったんですか。
廣末 今回はラッシュ(撮影した映像を全て観る試写のこと)をビデオで撮影して、自分でその映像を編集させてもらいました。編集マンの方にはその通りにフィルムを繋いでもらったので、フィルムで撮ったからといって、そのことは編集には影響していません。
――またフィルムで撮りたいという思いはありませんか。
廣末・高橋 一切ないですね(笑)。
廣末 撮影のセッティングにあんなに時間がかかるとは思いませんでした。
――カメラマンとのやり取りが難しかったという話がありましたが、逆にある部分を人に任せることによって見えてきたものはありませんでしたか。
廣末 自主映画では今回のようなキャストが揃うことはないので、その部分に関してはとても満足しています。
――子役を演出することに苦労は感じませんでしたか。
廣末 オーディションでは約500人のなかから、この映画で描かれるような感覚を持っている子供を探したんですが、それぞれの役にぴったりの子が面白いように見つかったんです。だから、現場でもその子が持ってるものをそのまま出してくれればいいという感じで、基本的に演出することはなかったですね。
――香川さんや藤井(かほり)さん、渡辺(真起子)さんといったベテランの役者さんに対してはどのように演出されていたんですか。
廣末 今回は僕らが大好きだったり、尊敬している役者さんに出てもらうことができたんですが、そういう方は何も言わなくてもやってくれるみたいで(笑)。だから、「ここはもう少し弱く」とか演技の強弱のことしか言ってなかったような気がします。内面的な部分の演出というのは特にしませんでしたね。そこはもう、役者さんの領分ですから。
――そこまで役者さんを信頼できるのは、自分が役者をしているということとも関係しているんでしょうか。
廣末 そうですね。
廣末哲万
確信した映画作りの方向性
――次回作の予定はあるんでしょうか。
廣末 昨日、ちょうど一本撮影が終わって、これから編集作業に入るところです。次は高橋さんの監督で一本撮って、その次は僕の監督で撮ってというところまでは決まっています。次にこういうものがやりたいというよりは、次はこういう感情を描きたいという感じで考えるので、具体的にどういう形になるかまではわかりませんが。
――昨日撮影が終わったという作品は、どういう内容なんですか。
廣末 それは50代の母親と27歳ぐらいでニートをしている息子の話なんですけど、コミュニケーションが失われた状態から二人の関係性が回復していくという内容ですね。長さ的には1時間半ぐらいのものになると思います。
高橋 面白いっすよ(笑)。
――その作品はぴあとは関係ないんですか。
高橋 完全な自主映画ですね。
――自主映画では、仲間同士の意見が合わなくて途中で空中分解してしまうようなこともありますよね。お二人の場合は最初の頃からスムーズな意見のやり取りができていたんでしょうか。
廣末 意見の交換というよりも、最初の頃は映画を作ることに夢中になっていて、出来上がったものをお互いに見せ合うような関係でした。それを観て、こういうことがやりたかったんだとわかっていくにつれ、だんだん信頼関係のようなものが出来ていったという感じですね。
――これまでに「群青いろ」が解散の危機を迎えたりしたことはなかったんですか(笑)。
廣末 PFFに応募して2年連続で落選したときは、二人のやりたいことを見失いかけて、その頃にそういう危機が一瞬だけありました(笑)。まぁ大丈夫だよって言って、やり続けましたけど。
――今回、一緒に商業作品に取り組んでみて、お互いの知らなかった一面を垣間見るようなことはありましたか。
高橋 廣末君は本当にシステムに興味がないんだなということがよくわかりましたね。元々そういうことは感じていたんですが、時期が来れば必ず別のステップに踏み出すだろうと思っていたんです。でも実際にそのステップを踏んでみて、そういうことに興味がないということがはっきりした(笑)。だから逆に、これからの活動の方向性が見えたということはあります。
――システムと言うのは、例えば今回のスカラシップ作品を足がかりに商業映画に手を伸ばしていこうとか、そういう意味ですか。
高橋 それもありますし、さっき話に出たような映画作りの方法もそうですね。エキストラカットや説明カットを使わないとか。やっぱり自分たちが作るものに誰か他の人が口を出すというのが嫌なんですよね。それはちょっとのことでも、もしかすると耐えられないかもしれないというぐらいの気持ちを…廣末君は持ってるみたいですよ。
廣末 え?! 今、高橋さんの話をしてたんでしょう(笑)。
高橋 (笑)だから廣末君にここをこうしてほしいと言われるのと、外部の人から言われるのとでは全然違います。
――それでは今回の経験を経て、これからも二人で一緒に作りたいものを作っていこうと確信したわけですね。
高橋 そうですね。もう人の手は借りないと(笑)。
廣末 あまり、人の手は借りないと(笑)。
高橋 あまりね(笑)。作ったものをいろんな人を宣伝してくれたりするのはありがたいんですけど、作るまではあまり人の手を借りたくないなと。
――逆に自主映画として映画を作り続けることの壁もあると思います。
廣末 でも、脚本の段階でロケーション的に無理なところがあれば、高橋さんがすぐに書き直してくれますからね。ただ、演じてくれる人たちに肩身の狭い思いをさせてしまうというのが辛いところです。
高橋 昨日も、駅と区民センターみたいなところでゲリラ撮影をしたんですよ。そうすると役者さんたちも気が気じゃない。そういうのも、少しお金を払えば簡単に解決するじゃないですか。だから、それぐらいのお金はあったらいいなと思いますね。あとはやっぱりもう一度、香川さんみたいな役者さんたちと一緒にやりたいという思いはありますけど、今のところは大丈夫です。
『14歳』
監督:廣末哲万 脚本:高橋 泉
プロデューサー:天野真弓 撮影:橋本清明 照明:清水健一 録音:林 大輔
美術:松塚隆史 音楽:碇 英記 編集:普嶋信一 監督助手:松村真吾
出演:並木愛枝、藤井かほり、渡辺真紀子、香川照之、牛腸和裕美、染谷将太、
小根山悠里香、笠井薫明、夏生さち
5月19日より渋谷ユーロスペースにて公開
『14歳』公式サイト
http://www.pia.co.jp/pff/14sai/
(c)PFFパートナーズ2006