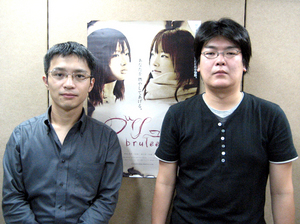10月25日から渋谷ユーロスペースでレイト公開される『ブリュレ』は、連続放火事件をきっかけに再会した双子の姉妹が日本を縦断して逃避行を続けながら互いを求め合おうとする、愛についての物語です。そしてこの映画は、自主制作ながらも全国各地でのロケを敢行した渾身の作であると同時に、2005年7月に120分版として一旦完成された後、スタッフの尽力により3年がかりで劇場公開にまで漕ぎつけた労作でもあります。
監督の林田賢太さんは日本映画学校の在学中に監督した作品で第4回インディーズ・ムービーフェスティバルのグランプリを受賞した新鋭。また、撮影を務めた早坂伸さんは『青 chong』(01)や『BORDER LINE』(03)という李相日監督の作品を始めとして、近年では『リアル鬼ごっこ』(07/柴田一成監督)や『トワイライトシンドローム デッドクルーズ』(08/古澤健監督)などの作品でも活躍しています。
今回はこの2人をお相手に『ブリュレ』の見所を伺いながら、プロ・アマ混成スタッフによる自主制作映画の新たな可能性を探ってみました。
(取材・構成:平澤竹識)
左:早坂 伸(撮影)、右:林田賢太(監督)
プロ・アマ混成スタッフによる自主制作映画の可能性
――お二人は日本映画学校の同級生なんですよね。
林田 そうですね。最近『ブラブラバンバン』(08)という映画を撮った草野陽花が僕と同じ脚本ゼミにいて、彼が卒業制作を撮った時に、僕がプロデューサーで、早坂が撮影部のチーフをやっていたんです。
――卒業後にお互いの仕事ぶりを意識したりすることはありませんでしたか。
林田 僕は脚本で彼は撮影だから進んでいる道も違うし、そういう意識はあまりありませんでしたね。
早坂 李相日、草野陽花の他に『童貞をプロデュース。』(07)の松江哲明も映画学校の同期なんですよ。
――在学中は互いに切磋琢磨しあうような雰囲気だったんでしょうか。
林田 大阪芸大出身の方達みたいに、みんなで一緒にメジャーになるぞっていう感じではなかったですね。
早坂 李も草野も松江も林田もみんな我が強いですから、連帯して一緒に何かをやるということはないでしょう(笑)。でも結果的に、みんなが独力でそれぞれに道を切り拓いているっていうのはすごいなと思いますね。
――林田さんは、映画学校在学中は脚本コースに在籍していたということですが、その当時から監督志望だったんですか。
林田 自分の中での目標は監督になることだったんですけど、映画学校在学中に脚本の面白さにも目覚めまして。卒業後も講師だった池端俊策さんのアシスタントにつくことになったので、まずは脚本家としてキャリアをスタートすることになったんです。
――今回の『ブリュレ』は、映画学校在学中に撮られた『東京フリーマーケット』(01)がインディーズムービーフェスティバルでグランプリを受賞したことがきっかけで生まれたということですが、企画が動き出したのはいつ頃だったんですか。
林田 双子の女の子の話にしようということで、オーディション誌で双子を募集したのが2003年の秋。それから30組ぐらいのオーディションをして、中村梨香・美香に主演が決まったのは2004年の春でした。撮影は2004年の夏を経て、本格的に始動したのが2005年の3月から7月頃までですね。
――ちなみに早坂さんが合流したのはいつ頃だったんでしょう。
早坂 2004年の夏にプロデューサーから電話をもらったんですけど、その時は別の作品についていて参加できなかったんです。だから、合流したのはメインの撮影が始まる5日前とかでしたね。その前に林田から電話があって「自主映画やるのにカメラマンがいないんだけど」って言うから、「どれぐらいやんの? 5日? 1週間? 10日?」って聞いたら「1月半」って言われて絶句しました(笑)。ちょうどその時は唯野未歩子監督の『三年身籠る』(06)という作品でチーフをやってましたし、自主映画で1ヶ月半というのは普通ならありえない(笑)。
林田 ハハハハ。
早坂 僕も生活しなきゃいけないので即答できないですよね、その時は妻も妊娠中でしたから(笑)。それで、夏に撮った素材と台本を見せてほしいと伝えたんですが、その素材を見た時にカメラマンとして中村姉妹を撮ってみたいなと思ったんです。やっぱり17歳と20歳とでは全然違いますから、この佇まいは今しか撮れないなと。
――プレスを見ると、監督と早坂さんの間で「商業作品ではできないことをやろう」というコンセンサスがあったようですが、自主映画の『ブリュレ』に参加したのは、そういう思いもあったからなんですか。
早坂 商業作品ではできないことをやりたいというのは僕が普段から思っていることなんです。例えば、『青 chong』と『BORDER LINE』という李相日の二つの作品がありますが、『青 chong』では天候が悪かったり、人が多すぎたりしたら撮影をしなかった。自主映画なら、そういうことができるんです。でも『BORDER LINE』はPFFのスカラシップ作品で、れっきとした商業映画ですから、スケジュールも11日間と決められています。だから設定は北海道でも、実際に北海道で撮影したのは3日ぐらいしかありません。撮影中はずっと雨が降っていたんですけど、それが狙いじゃなくても撮影を止めるわけにはいかない。結局、その差なんですね。『ブリュレ』も商業映画として撮ろうとしたら、10日ぐらいの撮影期間で、九十九里とか伊豆辺りへ行って終わりになると思います。現行の70分バージョンでは削られてしまったシーンも多いですが、『ブリュレ』に映っている土地の風景というのは実際にその場所へ行かなければ撮れないものですから、それがあるかないかでは画面の贅沢さが全然違いますよね。普段は、決められた予算とスケジュール内に収めるというのが僕の最大の仕事なので、商業作品ではきちんとその枠内で撮りますけど、それでは満たされない部分がいつもある。そういう意味で、今回のような自主作品は非常に魅力的な“場所”なんですよ。
――自主映画では制約の少ないぶんだけ、やりたいことができると。
早坂 例えば、左にカメラを向けてセッティングをしていても、光の加減が変わってきて、やっぱり右にカメラを向けたほうがいいと思うことがあるんです。でも、商業作品でそういう変更をしようとしたら、全てのセッティングを変えなくてはいけないし、各部のスタッフから反論も出る。自分が右にカメラを向けたほうが絶対に良くなると思っていてもそうなんです。ところが、これが5人ぐらいの撮影チームなら、そういう変更も可能になります。やっぱり現場でいいと思った絵のほうが上がりもいいし、現場でよくないと思った絵は上がってきたものもよくないんです。だから、現場で納得できる絵を撮るっていうのはとても大切なことなんですよ。そういう意味では、自主映画なら現場で納得いくまでこだわることができる。もちろん照明が足りないとか、そういう機材面での乏しさがありますけど、それを補うだけの自由さが得られるという。
――たしかに『ブリュレ』の画面には自主映画っぽい貧しさがないですね。ロケーションへのこだわりもすごいと思いました。シナリオを書いた時から、全国各地の風景を映画の中に取り込んでいきたいという狙いがあったんでしょうか。
林田 それはありました。先ほどの早坂の話ではないですが、ある予算やスケジュールを組んでしまうと、やれることって限られてしまうんですね。例えば、撮影期間は3日でロケ場所は全て部屋の中とか、そういう形になりかねない。だから、どうせ自分のお金で作るんだし、素直にやりたいことをやろうと。それが全国各地でロケ撮影をするってことだったんです。後からバカだったなぁと気付くわけですけど(笑)。
早坂 運転するほうの身にもなってみろっていう感じですよね(笑)。林田は免許を持ってないんです。そのくせ、朝4時に今から竜飛岬に行くとか言うわけですよ。延々5時間ぐらい運転して、着いたらすぐに撮影。それが終わってからまた5時間運転ですから、もう地獄ですよ(笑)。
林田 撮影の効率は非常に悪い。それは効率よりも他のものを優先したかったからなんです。でも、もし僕がプロデューサーだったら、監督に即クビと言ってますね(笑)。
自主映画を一般公開する方法
――撮影現場は実際にどうでしたか?
林田 本当に多くの方々に助けられたんですが、特に地方の撮影ではそのことを実感できました。メインのロケ地である秋田県能代市では、貧しい撮影隊を見るに見かねたのか、映画を応援する会を作ってくださって、様々な協力をしていただきました。寝泊りするところも廃校を借りましたし、お米もいただいて、本当に合宿映画ですよね。時には地元の方がキリタンポを作りに来てくださったり。それを秋田・京都・広島と旅しながら撮影していくわけです。だから、皆さんの愛情をたくさんもらって出来上がった映画なんですよ。
――当初、この作品は120分あったそうですが、今回ユーロスペースでの上映にあたって70分にまで編集しているそうですね。
林田 2005年の7月のインディーズムービーフェスティバルで120分版を上映した時は、上映の10日ぐらい前まで撮影をしているような状況だったので、ブラッシュアップしきれていない部分があったんです。
早坂 だから、その後に僕も編集に対する意見書のようなものを書いて林田に渡したりしましたね。
林田 自分で編集しているので、どうしても切れない部分があるんですよ。だからその後の編集だけで数ヶ月はかかっています。さらにそこからオールアフレコで音を付け直して、それにもかなり時間がかかりましたね。
――2005年に一旦上映してから、今回ユーロスペースで公開されることになったわけですが、その間にはどういう経緯があったんでしょうか。
林田 2006年12月に90分版を完成させて、2007年5月にロケでお世話になった秋田県能代市へ持っていって完成披露という形でお披露目しました。それと前後して、劇場での一般公開に向けて配給会社に営業を始めたという流れでした。
早坂 2007年の頭ぐらいから配給会社に持ち込んでいましたが結果に結びつかなかった。それで僕が当時お世話になっていたゼアリズエンタープライズさんに「力になっていただけないでしょうか?」という感じで作品を観てもらったら、配給に協力してくださることになって。
林田 それから劇場側との交渉が始まったんです。僕はブリュレの公開はユーロスペースでと熱望していました。いろんな作品に巡り会うことができた大好きな映画館なんですよ。だからそこから自分の作品をスタートさせたいと。それで公開が決まったのは今年の5月頃ですね。
――これは個人的な見解なんですが、以前は作家性の強い映画を撮っていた監督もどんどん大作を撮るようになってきて、今は個性的な作品が少なくなってる印象があります。でも例えば井土紀州監督の『ラザロ』のように、作り手が配給までした作品が話題になるということがもっと起きてくれば、映画を巡る環境が豊かになるんじゃないかなという気がするんです。そういう意味で、自主制作で劇場公開までこぎつけた『ブリュレ』の方法論は後進の作家にも学ぶべきところがあると思うんですが。
早坂 それも一理あると思いますが、配給や宣伝の現場を見てしまうと、そもそも企画の立て方が変わってくると思うんですよ。まず大事なのは、内容が一言で説明できる作品なのかどうか。例えば『七人の侍』(54)なら「貧しい農民達がメシの食えない侍を雇う話」というようにコンセプトが明確ですよね。そうじゃないと劇場側に売り込むのは難しいし、自力で興行まで持っていくことはできないと思います。
双子の純愛に託された思い
――『ブリュレ』はジャンル映画ではなく、いわゆる人間ドラマになるわけですが、一卵性双生児の姉妹がいて、そのうちの一人が放火癖を持っているという設定は、人間ドラマとしては虚構性が高いように感じます。監督自身は虚構(フィクション)というものに何か強い思い入れがあるんでしょうか。
林田 今でこそ、ライトノベルとかアニメとか虚構性の高い物語世界というものが広く需要されるようになりましたけど、この映画を企画した5年前は「映画はリアルであればあるほどいい」みたいな風潮がありました。でも僕自身は脚本を書いていたこともあって、嘘でもいいから“物語を信じたい”という思いが強かった。そういう映画が原体験にあるからだと思います。リアルかもしれないけど、六畳一間で男女がコソコソやってるみたいな映画は嫌だったんです。
――双子という設定を持ってきたのはなぜだったんですか。
林田 ある時、双子が写っている写真を見て惹きつけられるものがあったんですね。シンメトリーなビジュアルだけではなくて“絶対なる結びつき”を感じたんです。人間関係が希薄と言われている中、それが時代と合わせ鏡になるのではないかと直感しました。理屈じゃなく……だから映画にしたいと思ったのかもしれません。そんな中から、双子の片方が心ののろしとして放火を繰り返している、もう片方の子がその火を消しにくる、という大枠のストーリーが形づけられていきました。
――現実的なことで言うと実際には、警察に追われているという状況などがあると思うんですが。
林田 試写をご覧になられた評論家の方に「日本の警察をなめちゃいかん」と言われました。当初のシナリオでは『テルマ&ルイーズ』(91)のように、警察の追っ手から逃げるという状況をかなり描き込んでいたんです。そういう外的状況に追い詰められていくなかで、双子の絆が離れそうになったり深まったりするというラブストーリーを書いていました。でも、彼女たちにのめり込んでいけばいくほど、関係性を描くことに集約したんです。
――脚本家としてキャリアを積まれてきたわりには、話の辻褄を合わせることには頓着していない印象を受けました。
林田 たとえば脚本のセオリーとして、まず建物の外観にナレーションをかぶせて、その中で起こっているドラマを見せていくという段取りを習うわけですね。もちろん仕事の時にはそういうセオリーを踏まえて脚本を書くんですけど、いざ自分で撮るとなると普段それに縛れているぶん、セオリーとかは結構どうでもよくなってしまうんですよね。この脚本は仕事で書いていたら絶対通らないし、というか怒られます(笑)。
――早坂さんは今回のような物語を撮影するに当たって、どういうアプローチを考えていたんでしょうか。
早坂 二人の生態を捉えられるように、なるべく客観的に撮りたいなとは思っていました。だから、基本的にはフィックスの画面で、カメラに近い目線もほとんどありません。普通のドラマだと、レンズの脇に拳を出して役者さんに「目線ください」なんてやるんですけど、今回の映画ではそういうことはほとんどやってないんです。
――カメラのレンズに人物の目線が近づかないことで、どういう効果が出るんでしょうか。
早坂 押しつけがましい感じがなくなりますよね。個人的にも、ケン・ローチの映画のようにカメラのでしゃばらない撮影が好きなんです。だから今回の映画では、カメラの存在をいかに消すかというのをテーマにして撮っています。
――フィックス撮影の与える効果というのも同じようなものなんでしょうか。
早坂 画面が動かないので、カメラの存在感は消えますよね。観客も自分の見たいところを見ていられるから押しつけがましさもない。フィックスの画面で観客を飽きさせないためには奥行きのあるライティングとフレームを作る必要がありますけど、その部分には自信があるんです。
――この物語では双子の周りにいる人達も、味覚障害のパティシエとか足を骨折したキックボクサーとかキャラクターの造形が変わってますね。
林田 何か欠落している人間が好きなんですね。普通に考えたら、味覚障害のパティシエなんて「ダメじゃん」て感じなんですけど(笑)、そういう人間に惹かれるんです。
早坂 ヒロインに好意を持ってる同級生の男の子も、放火をやめさせようとするんじゃなくて消防士になろうとする(笑)。一般的な感覚からはズレてるけど、僕は好きですね。「(火を)つけてもいいよ。おれが消すから」っていう。
林田 それが絶対的な愛ってことだと思うんですよね。母なるというか、神なるというか、なんでも許してしまう。双子の愛というのもそういうことなんですけど。
――その思いには、今の世の中に対するメッセージも込められているんでしょうか。
林田 そんな大げさなものではなくて、要するに「好き」ってそういうことじゃない?みたいなことですね。言葉にすると恥ずかしいですけど(笑)。
――そういう意味で言うと、この映画は「本当の愛は血のつながりの中にしか成立しえない」というメッセージにも読みとれますよね。
林田 たしかに映画では双子という特殊な関係性の中で愛を描いているけれども、自分としては普遍的なラブストーリーを作ったつもりなんです。だから、映画を観に来てくれた人が「自分と恋人」とか「自分と家族」とか、“大切な人”との関係に置き換えて見ていただければと思っています。
――早坂さんからも、この映画の見所を教えていただけますか。
早坂 今、プロとアマチュアの差ってないんですよね。劇場にかかってしまえば、『ブリュレ』と『躍る大捜査線』は一緒なわけで、製作費が100万円だろうが10億円だろうが変わりはない。そういう意味で、『ブリュレ』が日本映画というものを幅広く捉えてもらうきっかけになればいいなと思います。自分としては今後も、その二つのフィールドを自由に行き来していたいんです。カメラマンという枠に閉じ込もらずに、できることは何でもやるという、もの作りの基本的な姿勢に立ち戻りたい。お金だけが目的なら何もこんなに割りの悪い仕事をする必要はないわけですからね。
スタッフ・キャストのショートインタビュー
三坂知絵子(プロデューサー)
「わたしは、第1回インディーズムービー・フェスティバル(インフェス)でグランプリを受賞した北村龍平監督のインフェス援助作品『VERSUS -ヴァーサス-』でヒロインを演じさせていただいたご縁で、インフェスのボランティアスタッフをするようになって、そのつながりで林田監督と知り合いました。最初に脚本を読んだ段階では“この作品をどう具現化したらいいんだろうか”ともやもやしていたのですが、オーディションで中村美香・梨香姉妹に出会った瞬間、ブワーッとイメージが広がって、映画が立体としてせまってくるように感じました。俳優としてではなくプロデューサーとして映画に関わってみて改めて実感したことは、映画は、お客さまに観ていただいてはじめて映画として完成するんだ、ということですね。『ブリュレ』は旅する映画でもありますし、観客の方にもぜひ双子と一緒に70分旅をしてもらいたいと思っています。笑って泣けて感動できる、というような商業映画ではないので、ストーリーも、どこに行き着くのか不安なまま話が進みますから、観ているほうも本当に不安になっちゃうかも知れないですけれども(笑)。でも、そこには若い俳優たちのこの時期ならではの揺らぎや美しさや輝きや、作り手の強い思いが焼き付いていると思うので、そこを是非観ていただきたいですね」
平林鯛一(出演)
「撮影中の思い出としては、チーム全員で千葉の駅前に停めた車の中で寝て、朝は駅のトイレで歯を磨いたり、そういうことが印象に残ってますね。小田原まで行ったのに撮影が中止なんてこともありましたけど(笑)、不満は全然なかったです。現場はスタッフ全員が良いものを作ろうという雰囲気で、穏やかな中にも締めるところは締めるという緊張感がありました。監督もワンカットワンカットをスタッフと相談しながら、かなりこだわって撮影していて、1カットを1日かけて撮影した日もあったぐらいです。『ブリュレ』はいろんな見方ができる映画だと思います。ヒロインの2人がいろんな障害を越えて自分の思いを遂げる、そういう話として見てみると、何か目標を持って頑張っている人が勇気をもらえたりする作品なんじゃないかなと思います」
『ブリュレ』
監督・脚本:林田賢太
撮影:早坂 伸
製作・配給:シネバイタル
配給協力:ゼアリズエンタープライズ
2008年/日本/カラー/DV撮影 HDCAMマスター/16:9ワイド(1:1.78)/71分
(C)2008CINEVITAL
10月25日(土)より渋谷ユーロスペースにてレイトロードショー!
公式サイト http://www.brulee-movie.com
《イベント情報》
■初日舞台挨拶 10 月25 日(土)上映前
中村美香/中村梨香(主演)、平林鯛一(出演)、早坂伸(撮影)、林田賢太(脚本・監督)
■“映画をつくろう”トーク 11 月4 日(火)上映後
林田賢太(脚本・監督)、早坂伸(撮影)、三坂知絵子(プロデューサー)、佐々木友紀、松本准平
10 月29 日(水)、11 月5 日(水)、11 月12 日(水)開場時・劇場入口にて
■映画公開記念写真展 「ブリュレ」
10月20日(月)~11月14日(金) ユーロスペースロビーにて
■映画公開記念テイクアウトメニュー「ブリュレ」
10月25日(土)~11月14日(金) カフェPrologue(ユーロスペースのビル1F)