映芸ダイアリーズの一員でもある
深田晃司監督の新作『歓待』の東京公開が4月23日から始まりました。本作は
東京国際映画祭のある視点部門で作品賞を受賞、主演女優の杉野希妃さんがプロデューサーを務めていることや、劇団「
青年団」の俳優とのコラボレーションによっても話題となっています。
「
青年団」の演出部に所属しながら、自主映画と商業映画の狭間で映画を撮り続けてきた深田さんは他方で、本サイトの連載「映画と労働を考える」の執筆や、こまば
アゴラ映画祭の企画など、映画状況への関わりも継続的に行なっています。そんな彼の新作は、どんな意図のもとに企画され、演出され、撮影されたのでしょうか。映画の舞台裏も含めて根掘り葉掘り聞いてみました。
(取材・構成:平澤竹識)
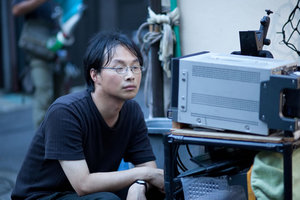 ――『歓待』は「輪転」という短編シナリオが元になっていて、その執筆過程でぼくも読ませてもらっていたわけですが、まず『輪転』を書くことになった経緯と、そこでやろうとしていたことが何だったのか、聞かせてもらえますか。
深田
――『歓待』は「輪転」という短編シナリオが元になっていて、その執筆過程でぼくも読ませてもらっていたわけですが、まず『輪転』を書くことになった経緯と、そこでやろうとしていたことが何だったのか、聞かせてもらえますか。
深田 元々、「淵に立つ」という長編の企画があったんです。印刷業を営む男の家に幼馴染と名乗る男がやって来る、彼は主人公とはある犯罪の共犯者で、彼だけが罪を被って刑務所に入ったという経緯がある。だから、その男が転がり込んできたときに主人公も弱みがあるから断れない。共同生活が始まるなかで、主人公と奥さんと娘の間にある悲劇が起きるという話を考えていました。二年ぐらい前に映画にしたいなと思ってたんですけど、当然、予算も集まらないだろうというときに、友人から、予算集めの
パイロット版を作るためにもVIPO(映像産業振興機構)を利用したらいいんじゃないかという助言を受けたんです。
VIPOの応募規定が30分の短編企画なので、「淵に立つ」の前半部分、印刷所を営む男のところによそ者が来て・・・というところだけを短編に書き直して、応募したんですよ。30分に縮めるに当たって、元々暗い話だったのが、喜劇調の話に変わっていきました。その「輪転」というシナリオをVIPOに出したら書類審査は通って、最終審査のワークショップで落ちたんです。コンチクショウと思って、合格した人たちよりも先に映画を完成させて、面白いことを証明してやろうと。
その時期にたまたま、『歓待』のプロデューサーである小野光輔さん、杉野希妃さんと知り合っていまして、「輪転」のシナリオを読んでもらったら、ぜひやろうという話になったんです。ただ、やっぱり短編だと興行が難しいから長編にしましょうということで、『歓待』に形を変えていきました。つまり、もともと
長編映画だったものを、一度短編にして、また長編に広げたらまったく別の映画になっていたという感じです。「淵に立つ」は今後またやりたいんですけど。
――「淵に立つ」が「輪転」になり『歓待』に変遷していくなかで、闖入者の男が主人公とほぼ関わりのない人物に変わり、なおかつ男が「共同体」というテーマを背負ったキャラクターへと変化しています。
深田 「淵に立つ」になくて「輪転」や『歓待』にあるのは、終盤で主人公の家にいろんな人物が押し寄せてくるという展開です。それは
マルクス兄弟の『オペラは踊る』(35)にあるような、狭い船室にどんどん人が入ってきて、しかも普通に会話をしているというギャグが、最初のイメージとしてあったからなんです。ただ結果として、出来上がった映画はリアリズム寄りになったので、あそこまで
スラップスティックな感じにならなかったのは残念に思ってます。だから、元々「共同体による異物の排除」というテーマが先にあって、ああいう展開になったというよりは、最初にああいう映像的なイメージを実現したいというところから始まっていたんです。
――「輪転」と『歓待』のシナリオを読み比べてみると、大きい改変は、主人公の奥さんが後妻という設定に変わり、出戻りの小姑という存在が新たに加わっていることですよね。それから、町内会の存在がクローズアップされています。
深田 「輪転」を書いていた頃は、もう少し家族の話という形で考えていました。その関係性が変化しながら、それでも続いていかざるをえないというイメージを核にしてたんです。それが長編の『歓待』に変わっていく過程で、クランクインの半年ぐらい前だったと思いますけど、それまで背後に隠れていた「共同体による異物の排除」というテーマが表に出てきたんです。それで、町内会の人たちが公園の美化運動と称して
ダンボールハウスを撤去しようと行政に要望を出しているという伏線が生まれてきました。
――『歓待』では、後妻である夏希(杉野希妃)の孤立感と、闖入者である加川(古舘寛治)が背負っている共同体の問題について書き込まれているように感じます。つまり、夏希と幹夫(山内健司)が抱える家族の問題と、加川が担っている共同体の問題が拮抗するような形に変更されている。そこで思うのは、家族の話と共同体の話、それぞれのバランスはどうなのか? 両方、中途半端じゃないの? という批判がありうるんじゃないかということなんですが。
深田 映画を見てくれた人の感想を聞く限り、そういった批判はあまり出ていないように思います。ぼくとしては、どちらか一方のテーマが目立たないようにしたつもりなので、見る人によってどちらの問題に目を向けるかというのは全然違ってくるんじゃないでしょうか。あれを夫婦や家族の話と捉えた人にとっては、共同体の問題が裏テーマとして見えてくるだろうし、共同体の話と捉えた人にとっては、家族の問題が裏テーマとして見えてくる。そのバランスはどちらかが主でどちらかが従というのではなく、重層的にできたんじゃないかなと思います。まあ、どちらの問題に対しても答えを出しているわけではないので、そういったものを受け取りたいと思うお客さんは物足りないと感じるかもしれません。それは仕方がないと割り切っています。
――ただ、脚本の構造としては、終盤、逃げた加川の噂話をしてる町内会のオバサンたちに幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う、あのセリフが共同体の問題に対する映画としての答えになってるわけですよね。夫婦の問題についても、夏希が逃げたインコの問題をどう処理したかというところに、一つの答えを提示してたんじゃないですか。
深田 そうですね。一本の映画として、一応の句点、ピリオドは打ってるつもりです。
――あのラストシーン、夏希が逃げたピーちゃんと同じ色のインコを買ってきて、幹夫から「いいのか、それで?」と言われますよね。それに対する夏希の「いいんじゃない? 忘れるわよ、すぐ」というセリフはどんなふうにでも解釈できると思うんです。例えば、後妻である夏希自身に対する自己肯定とも受け取れますよね。
深田 あれは「輪転」のシナリオから変わっていない、当初から決めていた終わり方です。ぼくが思う良いラストシーンというのは、自分の伝えたい意図をどれだけ伝えられるか、その正確さによって決まるというよりも、それを見た人のなかでどれだけ解釈が豊かに広がるかということのほうが重要なんですね。だから、ああいうラストシーンになったんです。
もちろん、作り手として作っていく過程で考えていたことはあります。最初にあのラストシーンを書いたときは、記憶も変わっていくし、価値観や財産みたいなものもどんどん移ろっていく。多くの人がその過程にすら気づかないまま変化しているのに、そこで何が本物なのか、何が偽物なのかということに拘るのは虚しいじゃないかという思いで書いてました。
――だから、当初のタイトルは「輪転」で、輪転機のある印刷所を舞台にしたんですね。
深田 そうなんです。どうしようもなく変わっていってしまう世界で生きざるをえないんだから、一時の価値観や関係性の真偽に拘っていてもしょうがないんじゃないかと。
これは最近思うんですけど、結局、何が本物で何が偽物かというときに、それを区別する「審美眼」があるわけですよね。その審美眼をまず疑いたいという思いもあったんだなということに、映画を公開してから気づきました。本物と偽物を区別する審美眼によって権力と差別が生まれる。でも、何が本物で偽物かというのは実は誰にも分からない。にもかかわらず、それがある権力を持って「偽物」と言われるものを排除してしまう。そういうあり方自体を疑ったほうがいいという思いもあったような気がします。否定するというよりも、とりあえず疑う、という感じで。夏希は後妻で、夏希と娘は血の繋がった親子ではない。けれども、最後に「偽物」のインコを買ってきて、それを「忘れるわよ、すぐ」と言うことで、そういう家族のあり方に対して諦めに近い肯定をするということですよね。
 ――本物と偽物という視点は意外でした。ぼくは、家族の話と共同体の話を結びつけるのは、やはり「他者」についての問題、他者をいかにして受け入れるのか、という問題だと思って見てたんですよ。
深田
――本物と偽物という視点は意外でした。ぼくは、家族の話と共同体の話を結びつけるのは、やはり「他者」についての問題、他者をいかにして受け入れるのか、という問題だと思って見てたんですよ。
深田 それは、この映画の核になってると思います。
――だから、本物と偽物ということは全く意識しなかったんですが、その話を聞いていて思ったのは、加川という男は最初から最後まで正体不明のままですよね。どうしてあの家族に狙いをつけて、あの家に大勢の外国人を連れてきたのか、その動機と目的は明かされない。そういう描き方と、今の本物偽物という視点のあり方は、どこかで結びつきがあるんでしょうか。
深田 ぼくも今、話しながら考えてるところがあるので、それが結びついてるかどうか、すぐに否定も肯定もできないんですけど、加川の正体については、シナリオを書いてる最中も、それを明らかにしなければいけないと思った瞬間はありませんでした。もちろん、映画を作っていく過程で、いろんな人から「加川って何なの?」と言われるので(笑)、その裏設定は考えていたんですけど、明示する必要性はないと。そもそもある明確な意図を持って、一つのゴールに向かって生きてる人はそうはいないと思うんですよ。生活は小さな目的の積み重ねであっても、ある明確な行動原理を持って、大きな目的のために人生があるというのは、まさに“フィクションの嘘”だと思います。だから、ぼく自身が物語を作るときはそういう人物造型に興味を持てないんです。加川というキャ
ラクターは
トリックスター的なポジションにいるので、たしかに目立つ存在ではあるんですけど、そこにぼく自身はあまり違和感を持っていませんでした。ただ、現場では特にいろんな人から質問されたので、かなり
理論武装はしましたね、「いや、彼は革命家なんです」とか(笑)。
――ぼくなんかの感覚で言うと、不可解な出来事とか不可解な人物は、最終的にその全容が明らかにされなきゃいけない、みたいなドラマツルギーのお約束があるような気がしちゃうんですね。だから、加川の背景や動機は描かなくていいと思い切れたのが不思議なんですが、そう判断するに当たって何か参照した作品があったんですか。
深田 安部公房の「友達」という戯曲に似ているとよく言われるんですけど、ぼくは不勉強ながらその戯曲を読んだことも芝居を見たこともないので何とも言えません。戯曲で言えばむしろ
イプセンの『人形の家』を意識してます。あと、『テオレマ』(68)ともよく比較されますね。
パゾリーニは大好きなんで、映画はもちろん見てるんですけど、シナリオを書いてる間は全く意識していませんでした。『テオレマ』は
パゾリーニのなかでも人の繋がりが観念的すぎるというか、図式的すぎる気がしてあまり好きじゃないんです。
あの加川と
アナベル夫婦のえたいの知れなさに一番近いと思えるのは、
つげ義春の「李さん一家」という漫画に出てくる夫婦なんですよ。主人公の家にいきなり住み着いてしまうあの夫婦にしても、目的や動機はよく分からないじゃないですか。でも、彼らはそこを自分たちの居住空間として選んでしまう。ぼくはあの不可解さのほうがリアルだなと思うんです。
――あれは結局、どういうところに落ち着く話でしたっけ?
深田 どこにも落ち着かないですよ。主人公が一家に振り回されていくんですよね。湯あたりで倒れた奥さんを運ぶのを手伝わされたりとか、家庭菜園のキュウリを勝手に持って行かれたりとか。で、最後に「あの一家はまだ住んでます」というところで終わる。
ドラマツルギーのあるなしに関わらず、そういう不条理感のほうがリアルだなと思っていました。
逆に、ぼくがある種の映画を見ていて退屈に感じる瞬間というのは、本来、人間も世界も非常に不可解で、不条理に満ちているはずなのに、そこにあたかも合理的な流れがあるかのように見せかけてしまう脚本家の手捌きが見えるときです。もちろん、脚本家の仕事を否定してるわけじゃありません。結局、脚本の「てにをは」みたいなものに縛られすぎると、そういうことが起きるんだと思います。世界がどうあるか、を考える以前に、脚本とは、映画とはこうあるべきだ、という観念が優先されてしまう。それをベースにして、ある人物の行動原理や全体の構成が作られてしまうのは問題があるんじゃないかという気がします。
――でも一方で、脚本の「てにをは」が杜撰な映画も数多くあります。だから、「てにをは」を踏まえたうえで、そこからはみ出すものを掴まえる努力をすべきだということですよね。
深田 もちろん、僕もまだまだそれを勉強中ですし、脚本を書くうえでの技術があるという大前提に立っての話ですよね。やっぱりそれが現代においてフィクションを作るうえでの態度だと思うんですよ。ベタな例えですけど、かつて前衛と呼ばれていた
ピカソにしても、最初に基本となる絵画理論やデッサンを学んだうえで、それを壊しながら「世界はこう見えてもいいんじゃないか」という形で描いていった。それが二十世紀初頭の話なわけですからね。脚本の「てにをは」というのは、
ピカソが壊したデッサン程度のものじゃないかなという気がします。デッサンが大事だというのは大前提だけれども、それがゴールでは全くないということですよね。
――もう少しシナリオの話を伺いたいんですが、『歓待』の完成台本を読むと「第一幕」「第二幕」「第三幕」と分けられています。これは戯曲の体裁ですよね?
深田 いや、構成が考えやすくなるから単純に目安として書き込んでるだけなんです。あれは戯曲じゃなくて、シド・フィールドなんですよ。
――ああ、そっちですか。
深田 シド・フィールドが、映画というのは起承転結の四幕じゃなくて、実は三幕が基本なんだと言っていて、その教えは律儀に守っていたりします。三幕物として構想して、最終的に三幕じゃなくなることもあるんですけど、自分のなかで構成を考えやすくなるという理由から、強引に三幕で規定しちゃうんですね。なんか、さっき言ってることと矛盾してるみたいですけど(笑)。
――それは面白い話ですよね。シド・フィールドが書いてることは脚本の「てにをは」じゃないですか。深田さんもそこは押さえたうえで、そこで囚われちゃいけないと言ってるわけでしょう。
深田 学生時代に脚本書こうと思って、全然分かんねえやと。それで、とりあえずシド・フィールドを読むってことをやってたんで・・・。そのやり方を否定する人たちも多いし、その通りにやって面白い映画になる保証は全然ないんだけど、映画を三幕物として捉えるというのは、単純に考えやすいからいつもやってますね。
 ――あと、さっき「諦めに近い肯定」と言ってましたけど、深田さんの映画にはある種の諦観が通底してますよね。そこにとてもシンパシーを感じるんです。安易な希望や救済は描かないという姿勢が一貫していると思います。
深田
――あと、さっき「諦めに近い肯定」と言ってましたけど、深田さんの映画にはある種の諦観が通底してますよね。そこにとてもシンパシーを感じるんです。安易な希望や救済は描かないという姿勢が一貫していると思います。
深田 映画というのは、その作家の世界観がどうしようもなく出てしまうものだと思うので、当然、そこに自分の世界観が反映されてると思うんですけど・・・。実は5月1日に『椅子』(02)という映画を
紀伊國屋ホールで再上映させてもらったんですね。それを2004年に
アップリンク・ファクトリーで上映したときに、作品解説としてテーマのようなものを書いたんですよ。それが、『
ざくろ屋敷』(06)『
東京人間喜劇』(09)『歓待』とも一緒だったんですよね。
そこで何を書いていたかというと、現代の物語=虚構において救済=ハッピー・エンドがいかにして成り立つのか、という問題意識なんです。結局、ぼくにとってはそれが一番の関心事なんですけど、ある物語のなかに障壁――シド・フィールドは「葛藤」と言ってましたけど――が設定されて、登場人物がそれを乗り越えられるか、乗り越えられないかによって、その物語がハッピー・エンドなり悲劇的な結末なりに導かれていく。でも、全てがフィクションであると知り尽くしている現代の観客にとって、それがどれだけリアルに響くんだろうと。そういう物語のほうが、共感を誘いつつ強い
カタルシスを与えると思うんですけど、その共感や
カタルシスの飛距離、というか持続力はすごく短いと思うんですよね。そういった高揚感は、劇場を出た後に家まで持ち帰れるようなものではないような気がするんです。じゃあ、どうしたらスクリーンとお客さんの間にある垣根を越えることができるんだろうと考えました。結局、人が救われるか救われないかなんて誰にも分からない、だけどその可能性は世界に偏在しているわけで、その可能性もひっくるめた世界観をスクリーンにただ投げ出して見せることぐらいだと思うんですよ。現代の物語作家が提示できるせめてものハッピー・エンドは倫理的にもそういうものじゃないかという気がします。
ぼくの場合は、それが上手くできていないということが、常に新作を作るうえでのモチベーションになっていて、たぶん『歓待』のラストにあるインコのくだりも、そういうところから発想されたんじゃないかなと思います。やっぱり物語が救済に至るまでに努力が介在しないほうが好きなんですよね。努力して救われたからって何なの?!って思いますから(笑)。
――映芸シネマテークで『東京人間喜劇』を上映させてもらったときに、深田さんが「ダメな人間にもいいところがあるじゃん」というところに救いを見出したくない、その人のパーソナリティに関係なく、全ての人間に救われる権利がある、と言ってたことが印象的でした。
深田 逆に言うと、どんなに聖人君子でも救われないかもしれない。ある人が救われるか救われないか分からないというのは、枝から落ちた木の葉がどこに着地するか分からないというのと同じだと思うんですよ。そこに努力が介在する余地はない。いいことしたからといって救われるわけではないし、悪いことをしても救われてしまう人がいる。一種のペシミズムかもしれないけれども、それが希望とも言えるんじゃないかと思います。
――さっきの審美眼を疑うという話じゃないですけど、とにかく世界をフラットに、ニュートラルに見たいという意志なんですかね。
深田 なんでしょうね。ぼくは映画を作るときに、全ての人間には価値があるんだ、というところから出発できなくて、全ての人間には価値がないんだ、というところからいつもスタートしてしまうんです。そこが何か関係してるのかもしれません。
――話は変わりますけど、深田さんは映芸のサイトで「映画と労働を考える」という連載も書いてますし、「ムービー・ユニオン」という労働組合にも発足メンバーの一人として所属しています。そうした活動が『歓待』という映画に影響したところもあったんでしょうか。
深田 自分としては、そこまで意識的にやってるわけじゃないんです。まず、社会派の映画を作りたいとは全く思ってないですし、基本的には100年後も残るような映画をという思いで作っています。今回は不法滞在の外国人とか浮浪者の問題が分かりやすい形で出てきてるけど、映画にああいうモチーフが必要だとは全く思っていません。ただ、映画というものは現代の社会に生きている人間が、現代の社会に三脚を置いてカメラを向けるわけだから、当然そこで出来上がる映画も、被写体である社会とどこかで繋がっていたほうがいいんじゃないかと思っています。コメディだろうが、恋愛劇だろうが、そこと地続きと考えて作るほうが自然な態度だと思うんです。その現代性というのは100年後には忘れ去られてしまうかもしれないけど、映画の普遍的な面白さはそういう要素と共存できると思うし、それが上手く共存してる映画を作りたいなとは思ってますね。
――やはり、『歓待』の面白さの一つは、家族のプライベートな話が、共同体という社会的な視点で捉え直されているところにあると思うんです。その辺りはどの程度、自覚的だったんですか。
深田 どうなんでしょうね。これはぼくが大阪のシネドライヴに参加したときにも作家たちの間で議論になっていたことなんですけど、映画の作り手が半径30メートル以内でドラマを作ってるんじゃないかと。そういうところへの批判意識を持ってる人は同世代の作り手のなかにもいるみたいなんですが、ぼくも自分の目に映っている世界のなかでだけドラマを作るのはどうなのかなって思うんですよ。
60~70年代の政治闘争の時代を経て、90年代以降にもなると、世の中なんて結局変わらないし、自分たちが生きる大きな目的も持てないし、変革すべき問題もないし・・・みたいな虚無感があったけど、それは本当なんだろうかと。ちょっと見渡してみれば、日本という国には社会問題が山ほどあるんですよね、『歓待』にも繋がる移民、難民の問題もそうですけど、映画の作り手にとって世界はいわば題材の宝庫なんです。だから、そっちに目を向けたほうが面白い映画が作れるじゃないかとは単純に思いますね。
――ぼくは78年生まれですけど、政治運動の挫折も経済発展の限界も知ってるような気になっちゃってるんですよね。だから、自分の実感が全てということになりやすい。それで90年代に、例えば諏訪(敦彦)さんが作るような映画を見て、非常に感化されるわけですよね。「大きな物語」を語らなくてもいいじゃないかって。
深田 それはやっぱり、高度経済成長期なんかに掲げられていた大きな目標、
大きな物語というものが、人生を懸けるほどのものではなかったということが露呈しまったからじゃないですか。実際は知らないですよ、ぼくも80年生まれなんで。ただ、ぼくの実感としても、10代、20代のときにそういった大きな目標というのは持てなかったし、今も持てていない。だから、そもそも
大きな物語なんて必要ない、そんなものはないんだと思っていたほうがいいと思ってるんですね。
例えば、難民や移民の問題にしても、まるで“大きな”問題であるかのように感じてしまうんですけど、細部を見ていけばもっと単純な話なんですよ。普通に生きていたら外国人の友人が出来たりもするわけで、その友人が差別を受けたりする、そこでどうするんだというところまで引き寄せればいい。そうなると、社会的な問題である前に、友人の問題、人間関係の問題になるんですよ。そういうミクロの問題の集積が大きな全体を作っているだけであって、そのミクロの問題を見る前に、大きな問題として語るのは危険だと思います。
 ――この映画における共同体の問題は、小さな物語として、友人関係の問題として語られてるわけですね。だから、最後に幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う。夏希にとって幹夫が他者であるのと同じレベルで、二人にとって加川やアナベルが他者であるということが語られているということですよね。
深田
――この映画における共同体の問題は、小さな物語として、友人関係の問題として語られてるわけですね。だから、最後に幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う。夏希にとって幹夫が他者であるのと同じレベルで、二人にとって加川やアナベルが他者であるということが語られているということですよね。
深田 そうですね。外国人だと価値観が当然違うから、個人と他者との軋轢は起きやすくなると思うんですけど、日本人同士でも価値観の違いによる他者との軋轢はあるわけで、程度が違うだけなんですよね。ただ、外国人の問題となるとえたいの知れない不安感があるから、本来ならコミュニケーションによって解決されるべき問題が、違う仕方で決着されてしまう。例えば、トラブルが起きたら即警察を呼んでしまったり、不動産屋が外国人の入居を断ってしまったり、いろんなところに現われてると思うんですよ。それをもっと、個人と他者の問題として捉え直したほうがいいんじゃないかということですね。
――今の話でかなり納得できました。ただ、聞きながら思ったのは、大きな物語を語っていた時代というのは、国家とか権力とか、いわば制度やシステムを「敵」と見なしていたわけですよね。社会的な問題を個人と他者の問題として捉え直すだけになると、制度やシステム自体がはらむ問題は看過されてしまうことにならないですか。
深田 本来、民主主義である以上、国家のシステムも小さいことの集積で成り立つべきものだと思います。たしかに、国家は巨大な権力であって、国家によって個人が押し潰されてしまうという事態は現在進行形で起きてますよね、司法制度の歪みとか、不透明な政策決定システムの横行とか、いろんな形で起きている。でも、そういった問題も結局は個人個人が問いただしていくしかないと思うんです。
今回の震災で明らかになったのは、
原発という制度を見過ごしてきたのは結局、日本の国民だということですよね。選挙権のある全ての国民が、誰かの犠牲のうえに成り立つ
原発の推進を見過ごしてきた加担者なんですよ。だから、国家が国民と全く関係のないところで暴走していると言う前に、多くの人が選挙権を放棄した結果、与党が是認され、ああいう問題が一見国民と関係ないところで進んでしまったということを忘れてはいけない。だから、国家と個人を切り離してしまう考え方はとても危険だと思います。
これは「映画と労働を考える」にも書きましたけど、じゃあ税金をどう考えるのかというところで、文化予算をもらって何か芸術活動をするということに対して、それは国家からお金をもらってるのかといったら、そうじゃない。その元になっている税金は、「国家のお金」じゃなくて、「みんなのお金」なんですよね。みんなのお金の使い方をみんなで考えましょうというのが結果として政策になる。それは文化予算の使い途に限らず、全ての政策がそうなんですよね。本来、お上から政策が下りてきて、それに従うか反発するかしかないという話じゃなくて、政策決定システムそのものにも個人が絡んでいるわけです。だからまあ、例えば
投票率が90パーセントぐらいになれば、何か見え方が変わってくるんじゃないですかね。今の日本の現状からすると、ものすごく甘っちょろい理想論ですけど。
――演出の話も聞いておきたいんですけど、映芸シネマテークのときに稲川(方人)さんが言っていて、ぼくもなるほどなと思ったのは、『東京人間喜劇』の演出が一貫してないんじゃないかという指摘だったんです。大雑把に言ってしまうと、演出にはフィクショナルなものと、リアリズムのものがあると思いますが、『~人間喜劇』はリアリズムの演出を推し進めつつ、そこで様々な試行錯誤が行われている。その試行錯誤を稲川さんは「一貫性がない」と言ったんだと思います。でも『歓待』を見ると、撮影も俳優の演技も割合パキっとしていて、フィクショナルなほうに寄せられているように感じました。
深田 演出に当たるうえでは、いつも「今回はこういう方針で行こう」と決めてるわけじゃなくて、現場の流れもあるんですけど、まず題材に見合った方法論があるだろうと。題材が違えば、当然、演出のスタイルも違ってくるということがあると思います。
今回に関しては――これは『
ざくろ屋敷』も『
東京人間喜劇』も一貫してるつもりなんですけど――映像的な装飾記号をできるだけ排除したいと思っていました。例えばですが、カメラ位置を低くしてアオリにすると、一見迫力のあるカッコいい映像になるけど、必然性もなくそういう小銭を稼ぐようなことはやらないとか。アオリの絵がダメということではなく、被写体とカメラの関係が濁るようなことはしたくない、ということです。
あるいは、映画的だと思われているアクション、カッコつきの「映画的」なもの、そういったものをできるだけ映画から排除して、それでも残る映画的なものって何だろうということを実践したつもりなんです。だから、時々『歓待』がウエルメイドな映画だと言われることには異論があるんです。ぼくとしては、今の日本映画の状況であれをやることは大きな冒険だと思ってるんですね。・・・すいません、冒険というのは少しカッコつけすぎました(笑)。「試み」だと思ってるんで・・・。
――身も蓋もない質問ですが、それでも残った映画的なものって何だったんですか(笑)?
深田 何なんでしょうね(笑)。ぼくは、それが立ち上がると思って脚本を書いて作ってるんですけど。
――以前、印刷機、輪転機の存在が非常に映画的だと言ってましたよね。そこで言う「映画的」ってどういうことなのか聞いてみたかったんですけど。
深田 そうですよね、「映画的」問題ってあると思うんですけど・・・(笑)。ぼくも「
映画芸術DIARY」に映画評を書くときは「映画的」という言葉をなるべく使わないようにしてるんですけど、それを具体的に言うのは難しいんですよね。
自分は中学3年ぐらいから古典映画を中心に年間数百本とか見るようになって、そのなかで「これは映画的だ」「これは映画的じゃない」という価値判断が出来たような気がしちゃうんですよね。でも、そこで言う「映画的」って上手く
言語化できないんですよ。例えば、
トリュフォーの『あこがれ』(58)という映画で
若い女性が自転車を漕いで坂を下りてくる映像はすごく映画的だなと思って興奮するんですけど、一方で
ビリー・ワイルダーの『七年目の浮気』(55)なんかを見たときに、これは映画的だと思って興奮する瞬間が全く訪れない。それがどうしてなのかというのは上手く
言語化できないんです。
ぼくのなかで無理やり
言語化すると、被写体をモチーフとして捉えられているかどうかなんだと思います。物語を効率良く語っていくための情報でしかない映像か、物語の歯車である以前にカメラの前にあるモチーフとして捉えられている映像かという違いじゃないかなと。
ただ一方で、そうした「映画的」な映像があまりにも記号的に流通してるんじゃないかというのも感じていて。例えば走ってる人間を横移動で撮ると映画的に見える、たしかに映画的な映像の記号として気持ちいいと思うんですけど、そういったものの安易な積み重ねだけで映画が成り立ってしまうことへの危惧も一方にあって、そうした映像を一切入れなくとも、映画が映画的になるということをやろうとしてるんです。でも、そうすると「演劇っぽい」とか「映像でやる意味がない」とか「単調だ」とか言われちゃって、ショボンとしちゃったりするんですけど(笑)。
 ――輪転機が映画的であるというのも、背景に列車が通り過ぎるのと同じように、物語の歯車ではないアクションが自律しているからということになるんですかね。
深田
――輪転機が映画的であるというのも、背景に列車が通り過ぎるのと同じように、物語の歯車ではないアクションが自律しているからということになるんですかね。
深田 ただ、
輪転機に関して思い出されるのはハリウッド映画なわけですよ。『
市民ケーン』(41)もそうですし、多くの
フィルム・ノワールで何か事件が起きると、
輪転機が回って事件を伝える新聞記事が映し出される。だから、蓮實センセイは
ウディ・アレンの『カメレオンマン』(83)は
輪転機の回転速度が遅すぎるからダメだと言ったりするわけですよね。そういうものを見たり読んだりするうちに、「
輪転機、スゲーな」となるわけです(笑)。それで今回、映画を作るうえでの足がかりとして
輪転機を置いたんですけど、「輪転」が『歓待』に変わっていくなかで、
輪転機のイメージは後退しちゃったので、あんまりちゃんと撮れなかったですね。
ロケハンでも印刷所を見つけるのが大変で、スタッフから「これ、
ダンボール工場とかでもいいよね」とか言われて(笑)、たしかに言われてみると、そこが印刷所じゃなきゃいけない理由はもうないなと。タイトルも「輪転」ではなくなってましたから。それで、「見つかんなかったら、
ダンボール工場でもいいよ」とか言ってしまったり。最終的にはとてもいい場所が見つかったものの、もう少し
輪転機で映像的な遊びができたら良かったんですけど、そんな時間的余裕は全然なかったですね。
――もう一つ、演出面のことを伺いたいんですが、今回は日本家屋をいかに撮るかということが、演出上の大きな課題だったんじゃないですか。
深田 仕事場と居間が一続きになってる日本家屋というのは、昔の日本映画のなかによく見かける光景で、ぼくとしては馴染みやすい空間でした。
ただ、日本家屋という空間をどう切り取っていくか、それを考えるうえでぼくはそんなに選択肢があるとは思ってないんです。ぼくが普通に見てきた映画、例えば
成瀬巳喜男が居間をどう撮っていたか、そういうイメージがポンポンと一つの雛形として思い浮かぶんですけど、しかし中古智さんが設計したスタジオの居間とロケセットで見つけてきた居間では全然違うわけですね。ロケセットの家はものすごく狭くて、カメラを置く場所も非常に限られるから、どうしたって同じようには撮れないんですよ。
だから、問題は日本家屋をどう撮るかというよりも、例えばちゃぶ台に座っている人たちをどう撮るか、つまり日本家屋の構造が規定するコミュニケーションのあり方やそこから導き出される身体性のモチーフをどう撮るかという選択にあるんだと思います。
――とはいえ、物語的には共同体のテーマがあるので、仕事場と居間が繋がってるとか、隣の部屋とは襖一枚でしか隔てられていないといった日本家屋の構造が重要だったんじゃないですか。
深田 それは決定的にありますね。ああいう下町の家の特徴は、道と家の入口の間に垣根がないんですよ、壁も塀もない。町内会のオバチャンが「こんちは~」っていきなり入ってこれてしまう。つまり、公共の空間とプライベートな空間がいきなり接続されているわけです。だから、従業員やインク業者、町内会のオバチャンといった外部の人間が、あの印刷所で交じり合う。
あと、居候としてやってきた加川夫婦の生活が主人公夫婦の生活に影響してくるということがやりたかったので、部屋の境界が曖昧であるということも意識してました。幹夫と夏希が寝てる隣の部屋から、
アナベルの喘ぎ声が聞こえてくるシーンとかは特にそうなんですけど。結果的に、日本家屋という舞台が逆に物語を規定するところもありますよね。
――最後に製作体制の話も聞かせてください。深田さんの独自性の一つに、劇団「青年団」の演出部に所属しながら、自主映画とも商業映画とも違う体制で映画を作られているということがあると思います。『東京人間喜劇』はキャストが青年団の俳優でスタッフは身内、いわば自主映画に近かったわけですよね。今回はプロデューサーが付いて、スタッフもプロの方が担当されています。その辺りの体制の変化についてはどう感じましたか。
深田 『歓待』の現場は、撮影監督も助監督もライン・プロデューサーもみんなプロの人たちで、ぼくよりもずっと現場経験が豊富で優秀な方々に支えてもらいました。そのおかげで実質8日間の撮影でも徹夜せずに撮り終えられた。
ただ一方で感じるのは、映像のスタッフのなかで、「映画はこうあるべき」「演技はこうあるべき」という
固定観念はものすごいなと。良くも悪くも、そういうものが染み付いてしまっている。そこを変えていくのは、すごく大変な作業だなというのは感じました。
――いきなり周りのスピードがそこまで上がると、深田さん自身が現場で追い込まれるんじゃないですか(笑)。
深田 いやあ、追い込まれましたよ(笑)。現場は時間との闘いでしたから、NGが2テイクを超え始めると、周りからのプレッシャーがすごいんですよ。「またNG出すつもり?」って。大抵、監督が出す細かいNGなんて、周りから見たら「どこが違うのか分かんない」と言われるぐらいのものですからね(笑)。
「あの芝居もうちょっとタイミング遅くしたいんだけど、言える空気じゃないな、どうしようかな」と思ってたところで、録音さんが「すいません、飛行機の音、入りました」とか言うと、「しょうがないなあ。じゃあ、もう1テイクやろうか」とか言って乗っかるわけです。だから、演出的に直したいところがあるときは、技術部のミスを期待してる自分がいましたね(笑)。
 ――俳優の演出にかけられる時間が短いわけですよね。リハーサルはしたんですか。
深田
――俳優の演出にかけられる時間が短いわけですよね。リハーサルはしたんですか。
深田 今回はいろんな事情から、撮影前のリハーサルもほとんどできなかったんです。とはいえ、
青年団の俳優が演じる役はほとんど当て書きだったし、この俳優さんならこのセリフをここまでのポテンシャルで演じてくれるだろうなという想像はついていました。あと、彼らは時間があると、現場で俳優同士がコミュニケーションを取って演技をどんどん組み立てていってくれるんです。だから、そこまで苦労することはありませんでした。
初めてお仕事する杉野さんとはリハーサル、というかどんな演技をする方なのか、ちゃんと知っておかなくちゃいけなかったんですけど、それができなかったので、シーンごとの優先順位を決めて、大事なところは時間をかけて撮影の合間にリハーサルをやるという形で進めていきました。これは他の監督もやってることだと思うんですけど、そういうふうに時間をなんとかやりくりしてましたね。でもやっぱり、最後のドンチャン騒ぎのシーンなんかは、10分でも15分でも延ばして、狂気に至るところまでやりたいと思っていたので、そこは少し残念に思ってます。
だから、低予算の早撮りというのはまあ、いいものではないなと。やっぱり既存の映画作りのシステムのいいところを継承しつつ、新しい製作システムを提案できるかどうかが重要だと思ってるんですけど、『歓待』ではそこまでは至れなかった。ただ、「
青年団」の俳優たちが出ていることで、日本映画の固定化した演技の慣習というものに対して、こういうあり方もあるよという提案はできるかなと思ってます。
――今回の経験を活かして、次回作では何か新しい形で映画作りができるといいですよね。
深田 今の日本映画の状況が劇的に変わるわけではないし、ぼくはそのなかで映画を作らなくちゃいけないので、次回作ですぐに何か新しいシステムを提案できるとは思っていません。ただ、例えば日本では製作リスクが高すぎることによって、単純に作る側の自由や選択肢が狭められていますよね。キャスティング一つ取っても、この俳優を使わなくちゃいけないとか。脚本も、これじゃ当たらないからマス向けに分かりやすく作り直せとか、原作を使わなくちゃいけないとか。もちろん、そういった制約の中でなおかつ面白い映画を作り上げるプロの監督を尊敬しますし、完全な自由なんてありえませんが、しかし、そういった不自由に対して少しでも自由の領域を広げていくための運動は必要だと思います。
いろいろあると思うんですよ。例えば、外国の資本にもアプローチしていくとか。あるいは、ぼくの立場で言えば「
青年団」には
アゴラ劇場という空間があるので、映画館で少し掛けてDVDにして終わりじゃなくて、もっと数年のスパンで上映を続けていくことも視野に入れていくとか。今できることはそれぐらいしかなくて、あとは本当に
助成金とか全体のシステムを変えていくしかない。自分が今置かれた立場のなかでできることは限られていて、映画のスタッフが直面している犯罪的な労働問題を軽減しながら映画を作っていくこと、映画制作のシステムを変えていくことは、10年、20年かかる作業だと思います。なかなかいっぺんにはできないんですけど、それを並行して進めていければいいですね。
結局、局地戦をいつまでやってもしょうがないと思うんですよ。一般に受け入れられやすい作風でクオリティも高い、そういうものを作って経済的に回していける作家もいると思うんですけど、それもやっぱり局地戦であって、それをいかにして全体に敷衍させていけるかが大事なんですよね。要は、必ずしもマスに受け入れられないけれども支持者がいるという作品をサポートしていけるシステムを作っていかなければいけない。「映画と労働を考える」で紹介しているチケット税による資金の循環もそのためのアイディアのひとつですし、多様な映画を理解してもらうために観客、受け手の意識にも働きかけていく必要がある。例えばフランスでは、インディーズのマイナーな映画をゴールデンタイムの全国区の公共放送で日常的に見ることができる。そういうことは必ずしもありえないことではない。それを不可能だと思ってしまったら、絶対に成り立たないと思います。
――・・・まあ、それに向けて日々活動していくということですね!
深田 なんか最後がずいぶん投げやりに終わらせてないですか? もう疲れたって感じになってますけど(笑)。
映画『歓待』予告編
『歓待』
監督・脚本・編集:
深田晃司
芸術監督:
平田オリザ プロデューサー:杉野希妃
出演:
山内健司 杉野希妃
古舘寛治 ブライアリー・ロング オノエリコ 兵藤公美
配給:和エンタテインメント
2010年/日本/96分/HDCAM/
(C)2010「歓待」製作委員会
公式サイト
http://kantai-hospitalite.com/
〈公開劇場〉
【東京】
ヒューマントラストシネマ渋谷 4月23日
5月11日(水)~13日(金)20:10
5月14日(土)~
20日(金)21:25
池袋シネマロサ 5月21日
5月21日(土)~ 10:30 / 20:30
【大阪】
テアトル梅田 5月14日
5月14日(土)〜 16:30
【京都】
みなみ会館 6月11日
【兵庫】
神戸元町映画館 7月下旬
【群馬】
シネマテークたかさき 夏
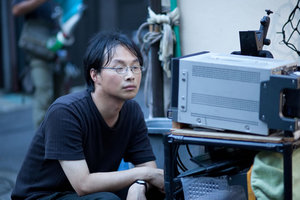 ――『歓待』は「輪転」という短編シナリオが元になっていて、その執筆過程でぼくも読ませてもらっていたわけですが、まず『輪転』を書くことになった経緯と、そこでやろうとしていたことが何だったのか、聞かせてもらえますか。
深田 元々、「淵に立つ」という長編の企画があったんです。印刷業を営む男の家に幼馴染と名乗る男がやって来る、彼は主人公とはある犯罪の共犯者で、彼だけが罪を被って刑務所に入ったという経緯がある。だから、その男が転がり込んできたときに主人公も弱みがあるから断れない。共同生活が始まるなかで、主人公と奥さんと娘の間にある悲劇が起きるという話を考えていました。二年ぐらい前に映画にしたいなと思ってたんですけど、当然、予算も集まらないだろうというときに、友人から、予算集めのパイロット版を作るためにもVIPO(映像産業振興機構)を利用したらいいんじゃないかという助言を受けたんです。
VIPOの応募規定が30分の短編企画なので、「淵に立つ」の前半部分、印刷所を営む男のところによそ者が来て・・・というところだけを短編に書き直して、応募したんですよ。30分に縮めるに当たって、元々暗い話だったのが、喜劇調の話に変わっていきました。その「輪転」というシナリオをVIPOに出したら書類審査は通って、最終審査のワークショップで落ちたんです。コンチクショウと思って、合格した人たちよりも先に映画を完成させて、面白いことを証明してやろうと。
その時期にたまたま、『歓待』のプロデューサーである小野光輔さん、杉野希妃さんと知り合っていまして、「輪転」のシナリオを読んでもらったら、ぜひやろうという話になったんです。ただ、やっぱり短編だと興行が難しいから長編にしましょうということで、『歓待』に形を変えていきました。つまり、もともと長編映画だったものを、一度短編にして、また長編に広げたらまったく別の映画になっていたという感じです。「淵に立つ」は今後またやりたいんですけど。
――「淵に立つ」が「輪転」になり『歓待』に変遷していくなかで、闖入者の男が主人公とほぼ関わりのない人物に変わり、なおかつ男が「共同体」というテーマを背負ったキャラクターへと変化しています。
深田 「淵に立つ」になくて「輪転」や『歓待』にあるのは、終盤で主人公の家にいろんな人物が押し寄せてくるという展開です。それはマルクス兄弟の『オペラは踊る』(35)にあるような、狭い船室にどんどん人が入ってきて、しかも普通に会話をしているというギャグが、最初のイメージとしてあったからなんです。ただ結果として、出来上がった映画はリアリズム寄りになったので、あそこまでスラップスティックな感じにならなかったのは残念に思ってます。だから、元々「共同体による異物の排除」というテーマが先にあって、ああいう展開になったというよりは、最初にああいう映像的なイメージを実現したいというところから始まっていたんです。
――「輪転」と『歓待』のシナリオを読み比べてみると、大きい改変は、主人公の奥さんが後妻という設定に変わり、出戻りの小姑という存在が新たに加わっていることですよね。それから、町内会の存在がクローズアップされています。
深田 「輪転」を書いていた頃は、もう少し家族の話という形で考えていました。その関係性が変化しながら、それでも続いていかざるをえないというイメージを核にしてたんです。それが長編の『歓待』に変わっていく過程で、クランクインの半年ぐらい前だったと思いますけど、それまで背後に隠れていた「共同体による異物の排除」というテーマが表に出てきたんです。それで、町内会の人たちが公園の美化運動と称してダンボールハウスを撤去しようと行政に要望を出しているという伏線が生まれてきました。
――『歓待』では、後妻である夏希(杉野希妃)の孤立感と、闖入者である加川(古舘寛治)が背負っている共同体の問題について書き込まれているように感じます。つまり、夏希と幹夫(山内健司)が抱える家族の問題と、加川が担っている共同体の問題が拮抗するような形に変更されている。そこで思うのは、家族の話と共同体の話、それぞれのバランスはどうなのか? 両方、中途半端じゃないの? という批判がありうるんじゃないかということなんですが。
深田 映画を見てくれた人の感想を聞く限り、そういった批判はあまり出ていないように思います。ぼくとしては、どちらか一方のテーマが目立たないようにしたつもりなので、見る人によってどちらの問題に目を向けるかというのは全然違ってくるんじゃないでしょうか。あれを夫婦や家族の話と捉えた人にとっては、共同体の問題が裏テーマとして見えてくるだろうし、共同体の話と捉えた人にとっては、家族の問題が裏テーマとして見えてくる。そのバランスはどちらかが主でどちらかが従というのではなく、重層的にできたんじゃないかなと思います。まあ、どちらの問題に対しても答えを出しているわけではないので、そういったものを受け取りたいと思うお客さんは物足りないと感じるかもしれません。それは仕方がないと割り切っています。
――ただ、脚本の構造としては、終盤、逃げた加川の噂話をしてる町内会のオバサンたちに幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う、あのセリフが共同体の問題に対する映画としての答えになってるわけですよね。夫婦の問題についても、夏希が逃げたインコの問題をどう処理したかというところに、一つの答えを提示してたんじゃないですか。
深田 そうですね。一本の映画として、一応の句点、ピリオドは打ってるつもりです。
――あのラストシーン、夏希が逃げたピーちゃんと同じ色のインコを買ってきて、幹夫から「いいのか、それで?」と言われますよね。それに対する夏希の「いいんじゃない? 忘れるわよ、すぐ」というセリフはどんなふうにでも解釈できると思うんです。例えば、後妻である夏希自身に対する自己肯定とも受け取れますよね。
深田 あれは「輪転」のシナリオから変わっていない、当初から決めていた終わり方です。ぼくが思う良いラストシーンというのは、自分の伝えたい意図をどれだけ伝えられるか、その正確さによって決まるというよりも、それを見た人のなかでどれだけ解釈が豊かに広がるかということのほうが重要なんですね。だから、ああいうラストシーンになったんです。
もちろん、作り手として作っていく過程で考えていたことはあります。最初にあのラストシーンを書いたときは、記憶も変わっていくし、価値観や財産みたいなものもどんどん移ろっていく。多くの人がその過程にすら気づかないまま変化しているのに、そこで何が本物なのか、何が偽物なのかということに拘るのは虚しいじゃないかという思いで書いてました。
――だから、当初のタイトルは「輪転」で、輪転機のある印刷所を舞台にしたんですね。
深田 そうなんです。どうしようもなく変わっていってしまう世界で生きざるをえないんだから、一時の価値観や関係性の真偽に拘っていてもしょうがないんじゃないかと。
これは最近思うんですけど、結局、何が本物で何が偽物かというときに、それを区別する「審美眼」があるわけですよね。その審美眼をまず疑いたいという思いもあったんだなということに、映画を公開してから気づきました。本物と偽物を区別する審美眼によって権力と差別が生まれる。でも、何が本物で偽物かというのは実は誰にも分からない。にもかかわらず、それがある権力を持って「偽物」と言われるものを排除してしまう。そういうあり方自体を疑ったほうがいいという思いもあったような気がします。否定するというよりも、とりあえず疑う、という感じで。夏希は後妻で、夏希と娘は血の繋がった親子ではない。けれども、最後に「偽物」のインコを買ってきて、それを「忘れるわよ、すぐ」と言うことで、そういう家族のあり方に対して諦めに近い肯定をするということですよね。
――『歓待』は「輪転」という短編シナリオが元になっていて、その執筆過程でぼくも読ませてもらっていたわけですが、まず『輪転』を書くことになった経緯と、そこでやろうとしていたことが何だったのか、聞かせてもらえますか。
深田 元々、「淵に立つ」という長編の企画があったんです。印刷業を営む男の家に幼馴染と名乗る男がやって来る、彼は主人公とはある犯罪の共犯者で、彼だけが罪を被って刑務所に入ったという経緯がある。だから、その男が転がり込んできたときに主人公も弱みがあるから断れない。共同生活が始まるなかで、主人公と奥さんと娘の間にある悲劇が起きるという話を考えていました。二年ぐらい前に映画にしたいなと思ってたんですけど、当然、予算も集まらないだろうというときに、友人から、予算集めのパイロット版を作るためにもVIPO(映像産業振興機構)を利用したらいいんじゃないかという助言を受けたんです。
VIPOの応募規定が30分の短編企画なので、「淵に立つ」の前半部分、印刷所を営む男のところによそ者が来て・・・というところだけを短編に書き直して、応募したんですよ。30分に縮めるに当たって、元々暗い話だったのが、喜劇調の話に変わっていきました。その「輪転」というシナリオをVIPOに出したら書類審査は通って、最終審査のワークショップで落ちたんです。コンチクショウと思って、合格した人たちよりも先に映画を完成させて、面白いことを証明してやろうと。
その時期にたまたま、『歓待』のプロデューサーである小野光輔さん、杉野希妃さんと知り合っていまして、「輪転」のシナリオを読んでもらったら、ぜひやろうという話になったんです。ただ、やっぱり短編だと興行が難しいから長編にしましょうということで、『歓待』に形を変えていきました。つまり、もともと長編映画だったものを、一度短編にして、また長編に広げたらまったく別の映画になっていたという感じです。「淵に立つ」は今後またやりたいんですけど。
――「淵に立つ」が「輪転」になり『歓待』に変遷していくなかで、闖入者の男が主人公とほぼ関わりのない人物に変わり、なおかつ男が「共同体」というテーマを背負ったキャラクターへと変化しています。
深田 「淵に立つ」になくて「輪転」や『歓待』にあるのは、終盤で主人公の家にいろんな人物が押し寄せてくるという展開です。それはマルクス兄弟の『オペラは踊る』(35)にあるような、狭い船室にどんどん人が入ってきて、しかも普通に会話をしているというギャグが、最初のイメージとしてあったからなんです。ただ結果として、出来上がった映画はリアリズム寄りになったので、あそこまでスラップスティックな感じにならなかったのは残念に思ってます。だから、元々「共同体による異物の排除」というテーマが先にあって、ああいう展開になったというよりは、最初にああいう映像的なイメージを実現したいというところから始まっていたんです。
――「輪転」と『歓待』のシナリオを読み比べてみると、大きい改変は、主人公の奥さんが後妻という設定に変わり、出戻りの小姑という存在が新たに加わっていることですよね。それから、町内会の存在がクローズアップされています。
深田 「輪転」を書いていた頃は、もう少し家族の話という形で考えていました。その関係性が変化しながら、それでも続いていかざるをえないというイメージを核にしてたんです。それが長編の『歓待』に変わっていく過程で、クランクインの半年ぐらい前だったと思いますけど、それまで背後に隠れていた「共同体による異物の排除」というテーマが表に出てきたんです。それで、町内会の人たちが公園の美化運動と称してダンボールハウスを撤去しようと行政に要望を出しているという伏線が生まれてきました。
――『歓待』では、後妻である夏希(杉野希妃)の孤立感と、闖入者である加川(古舘寛治)が背負っている共同体の問題について書き込まれているように感じます。つまり、夏希と幹夫(山内健司)が抱える家族の問題と、加川が担っている共同体の問題が拮抗するような形に変更されている。そこで思うのは、家族の話と共同体の話、それぞれのバランスはどうなのか? 両方、中途半端じゃないの? という批判がありうるんじゃないかということなんですが。
深田 映画を見てくれた人の感想を聞く限り、そういった批判はあまり出ていないように思います。ぼくとしては、どちらか一方のテーマが目立たないようにしたつもりなので、見る人によってどちらの問題に目を向けるかというのは全然違ってくるんじゃないでしょうか。あれを夫婦や家族の話と捉えた人にとっては、共同体の問題が裏テーマとして見えてくるだろうし、共同体の話と捉えた人にとっては、家族の問題が裏テーマとして見えてくる。そのバランスはどちらかが主でどちらかが従というのではなく、重層的にできたんじゃないかなと思います。まあ、どちらの問題に対しても答えを出しているわけではないので、そういったものを受け取りたいと思うお客さんは物足りないと感じるかもしれません。それは仕方がないと割り切っています。
――ただ、脚本の構造としては、終盤、逃げた加川の噂話をしてる町内会のオバサンたちに幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う、あのセリフが共同体の問題に対する映画としての答えになってるわけですよね。夫婦の問題についても、夏希が逃げたインコの問題をどう処理したかというところに、一つの答えを提示してたんじゃないですか。
深田 そうですね。一本の映画として、一応の句点、ピリオドは打ってるつもりです。
――あのラストシーン、夏希が逃げたピーちゃんと同じ色のインコを買ってきて、幹夫から「いいのか、それで?」と言われますよね。それに対する夏希の「いいんじゃない? 忘れるわよ、すぐ」というセリフはどんなふうにでも解釈できると思うんです。例えば、後妻である夏希自身に対する自己肯定とも受け取れますよね。
深田 あれは「輪転」のシナリオから変わっていない、当初から決めていた終わり方です。ぼくが思う良いラストシーンというのは、自分の伝えたい意図をどれだけ伝えられるか、その正確さによって決まるというよりも、それを見た人のなかでどれだけ解釈が豊かに広がるかということのほうが重要なんですね。だから、ああいうラストシーンになったんです。
もちろん、作り手として作っていく過程で考えていたことはあります。最初にあのラストシーンを書いたときは、記憶も変わっていくし、価値観や財産みたいなものもどんどん移ろっていく。多くの人がその過程にすら気づかないまま変化しているのに、そこで何が本物なのか、何が偽物なのかということに拘るのは虚しいじゃないかという思いで書いてました。
――だから、当初のタイトルは「輪転」で、輪転機のある印刷所を舞台にしたんですね。
深田 そうなんです。どうしようもなく変わっていってしまう世界で生きざるをえないんだから、一時の価値観や関係性の真偽に拘っていてもしょうがないんじゃないかと。
これは最近思うんですけど、結局、何が本物で何が偽物かというときに、それを区別する「審美眼」があるわけですよね。その審美眼をまず疑いたいという思いもあったんだなということに、映画を公開してから気づきました。本物と偽物を区別する審美眼によって権力と差別が生まれる。でも、何が本物で偽物かというのは実は誰にも分からない。にもかかわらず、それがある権力を持って「偽物」と言われるものを排除してしまう。そういうあり方自体を疑ったほうがいいという思いもあったような気がします。否定するというよりも、とりあえず疑う、という感じで。夏希は後妻で、夏希と娘は血の繋がった親子ではない。けれども、最後に「偽物」のインコを買ってきて、それを「忘れるわよ、すぐ」と言うことで、そういう家族のあり方に対して諦めに近い肯定をするということですよね。
 ――本物と偽物という視点は意外でした。ぼくは、家族の話と共同体の話を結びつけるのは、やはり「他者」についての問題、他者をいかにして受け入れるのか、という問題だと思って見てたんですよ。
深田 それは、この映画の核になってると思います。
――だから、本物と偽物ということは全く意識しなかったんですが、その話を聞いていて思ったのは、加川という男は最初から最後まで正体不明のままですよね。どうしてあの家族に狙いをつけて、あの家に大勢の外国人を連れてきたのか、その動機と目的は明かされない。そういう描き方と、今の本物偽物という視点のあり方は、どこかで結びつきがあるんでしょうか。
深田 ぼくも今、話しながら考えてるところがあるので、それが結びついてるかどうか、すぐに否定も肯定もできないんですけど、加川の正体については、シナリオを書いてる最中も、それを明らかにしなければいけないと思った瞬間はありませんでした。もちろん、映画を作っていく過程で、いろんな人から「加川って何なの?」と言われるので(笑)、その裏設定は考えていたんですけど、明示する必要性はないと。そもそもある明確な意図を持って、一つのゴールに向かって生きてる人はそうはいないと思うんですよ。生活は小さな目的の積み重ねであっても、ある明確な行動原理を持って、大きな目的のために人生があるというのは、まさに“フィクションの嘘”だと思います。だから、ぼく自身が物語を作るときはそういう人物造型に興味を持てないんです。加川というキャラクターはトリックスター的なポジションにいるので、たしかに目立つ存在ではあるんですけど、そこにぼく自身はあまり違和感を持っていませんでした。ただ、現場では特にいろんな人から質問されたので、かなり理論武装はしましたね、「いや、彼は革命家なんです」とか(笑)。
――ぼくなんかの感覚で言うと、不可解な出来事とか不可解な人物は、最終的にその全容が明らかにされなきゃいけない、みたいなドラマツルギーのお約束があるような気がしちゃうんですね。だから、加川の背景や動機は描かなくていいと思い切れたのが不思議なんですが、そう判断するに当たって何か参照した作品があったんですか。
深田 安部公房の「友達」という戯曲に似ているとよく言われるんですけど、ぼくは不勉強ながらその戯曲を読んだことも芝居を見たこともないので何とも言えません。戯曲で言えばむしろイプセンの『人形の家』を意識してます。あと、『テオレマ』(68)ともよく比較されますね。パゾリーニは大好きなんで、映画はもちろん見てるんですけど、シナリオを書いてる間は全く意識していませんでした。『テオレマ』はパゾリーニのなかでも人の繋がりが観念的すぎるというか、図式的すぎる気がしてあまり好きじゃないんです。
あの加川とアナベル夫婦のえたいの知れなさに一番近いと思えるのは、つげ義春の「李さん一家」という漫画に出てくる夫婦なんですよ。主人公の家にいきなり住み着いてしまうあの夫婦にしても、目的や動機はよく分からないじゃないですか。でも、彼らはそこを自分たちの居住空間として選んでしまう。ぼくはあの不可解さのほうがリアルだなと思うんです。
――あれは結局、どういうところに落ち着く話でしたっけ?
深田 どこにも落ち着かないですよ。主人公が一家に振り回されていくんですよね。湯あたりで倒れた奥さんを運ぶのを手伝わされたりとか、家庭菜園のキュウリを勝手に持って行かれたりとか。で、最後に「あの一家はまだ住んでます」というところで終わる。ドラマツルギーのあるなしに関わらず、そういう不条理感のほうがリアルだなと思っていました。
逆に、ぼくがある種の映画を見ていて退屈に感じる瞬間というのは、本来、人間も世界も非常に不可解で、不条理に満ちているはずなのに、そこにあたかも合理的な流れがあるかのように見せかけてしまう脚本家の手捌きが見えるときです。もちろん、脚本家の仕事を否定してるわけじゃありません。結局、脚本の「てにをは」みたいなものに縛られすぎると、そういうことが起きるんだと思います。世界がどうあるか、を考える以前に、脚本とは、映画とはこうあるべきだ、という観念が優先されてしまう。それをベースにして、ある人物の行動原理や全体の構成が作られてしまうのは問題があるんじゃないかという気がします。
――でも一方で、脚本の「てにをは」が杜撰な映画も数多くあります。だから、「てにをは」を踏まえたうえで、そこからはみ出すものを掴まえる努力をすべきだということですよね。
深田 もちろん、僕もまだまだそれを勉強中ですし、脚本を書くうえでの技術があるという大前提に立っての話ですよね。やっぱりそれが現代においてフィクションを作るうえでの態度だと思うんですよ。ベタな例えですけど、かつて前衛と呼ばれていたピカソにしても、最初に基本となる絵画理論やデッサンを学んだうえで、それを壊しながら「世界はこう見えてもいいんじゃないか」という形で描いていった。それが二十世紀初頭の話なわけですからね。脚本の「てにをは」というのは、ピカソが壊したデッサン程度のものじゃないかなという気がします。デッサンが大事だというのは大前提だけれども、それがゴールでは全くないということですよね。
――もう少しシナリオの話を伺いたいんですが、『歓待』の完成台本を読むと「第一幕」「第二幕」「第三幕」と分けられています。これは戯曲の体裁ですよね?
深田 いや、構成が考えやすくなるから単純に目安として書き込んでるだけなんです。あれは戯曲じゃなくて、シド・フィールドなんですよ。
――ああ、そっちですか。
深田 シド・フィールドが、映画というのは起承転結の四幕じゃなくて、実は三幕が基本なんだと言っていて、その教えは律儀に守っていたりします。三幕物として構想して、最終的に三幕じゃなくなることもあるんですけど、自分のなかで構成を考えやすくなるという理由から、強引に三幕で規定しちゃうんですね。なんか、さっき言ってることと矛盾してるみたいですけど(笑)。
――それは面白い話ですよね。シド・フィールドが書いてることは脚本の「てにをは」じゃないですか。深田さんもそこは押さえたうえで、そこで囚われちゃいけないと言ってるわけでしょう。
深田 学生時代に脚本書こうと思って、全然分かんねえやと。それで、とりあえずシド・フィールドを読むってことをやってたんで・・・。そのやり方を否定する人たちも多いし、その通りにやって面白い映画になる保証は全然ないんだけど、映画を三幕物として捉えるというのは、単純に考えやすいからいつもやってますね。
――本物と偽物という視点は意外でした。ぼくは、家族の話と共同体の話を結びつけるのは、やはり「他者」についての問題、他者をいかにして受け入れるのか、という問題だと思って見てたんですよ。
深田 それは、この映画の核になってると思います。
――だから、本物と偽物ということは全く意識しなかったんですが、その話を聞いていて思ったのは、加川という男は最初から最後まで正体不明のままですよね。どうしてあの家族に狙いをつけて、あの家に大勢の外国人を連れてきたのか、その動機と目的は明かされない。そういう描き方と、今の本物偽物という視点のあり方は、どこかで結びつきがあるんでしょうか。
深田 ぼくも今、話しながら考えてるところがあるので、それが結びついてるかどうか、すぐに否定も肯定もできないんですけど、加川の正体については、シナリオを書いてる最中も、それを明らかにしなければいけないと思った瞬間はありませんでした。もちろん、映画を作っていく過程で、いろんな人から「加川って何なの?」と言われるので(笑)、その裏設定は考えていたんですけど、明示する必要性はないと。そもそもある明確な意図を持って、一つのゴールに向かって生きてる人はそうはいないと思うんですよ。生活は小さな目的の積み重ねであっても、ある明確な行動原理を持って、大きな目的のために人生があるというのは、まさに“フィクションの嘘”だと思います。だから、ぼく自身が物語を作るときはそういう人物造型に興味を持てないんです。加川というキャラクターはトリックスター的なポジションにいるので、たしかに目立つ存在ではあるんですけど、そこにぼく自身はあまり違和感を持っていませんでした。ただ、現場では特にいろんな人から質問されたので、かなり理論武装はしましたね、「いや、彼は革命家なんです」とか(笑)。
――ぼくなんかの感覚で言うと、不可解な出来事とか不可解な人物は、最終的にその全容が明らかにされなきゃいけない、みたいなドラマツルギーのお約束があるような気がしちゃうんですね。だから、加川の背景や動機は描かなくていいと思い切れたのが不思議なんですが、そう判断するに当たって何か参照した作品があったんですか。
深田 安部公房の「友達」という戯曲に似ているとよく言われるんですけど、ぼくは不勉強ながらその戯曲を読んだことも芝居を見たこともないので何とも言えません。戯曲で言えばむしろイプセンの『人形の家』を意識してます。あと、『テオレマ』(68)ともよく比較されますね。パゾリーニは大好きなんで、映画はもちろん見てるんですけど、シナリオを書いてる間は全く意識していませんでした。『テオレマ』はパゾリーニのなかでも人の繋がりが観念的すぎるというか、図式的すぎる気がしてあまり好きじゃないんです。
あの加川とアナベル夫婦のえたいの知れなさに一番近いと思えるのは、つげ義春の「李さん一家」という漫画に出てくる夫婦なんですよ。主人公の家にいきなり住み着いてしまうあの夫婦にしても、目的や動機はよく分からないじゃないですか。でも、彼らはそこを自分たちの居住空間として選んでしまう。ぼくはあの不可解さのほうがリアルだなと思うんです。
――あれは結局、どういうところに落ち着く話でしたっけ?
深田 どこにも落ち着かないですよ。主人公が一家に振り回されていくんですよね。湯あたりで倒れた奥さんを運ぶのを手伝わされたりとか、家庭菜園のキュウリを勝手に持って行かれたりとか。で、最後に「あの一家はまだ住んでます」というところで終わる。ドラマツルギーのあるなしに関わらず、そういう不条理感のほうがリアルだなと思っていました。
逆に、ぼくがある種の映画を見ていて退屈に感じる瞬間というのは、本来、人間も世界も非常に不可解で、不条理に満ちているはずなのに、そこにあたかも合理的な流れがあるかのように見せかけてしまう脚本家の手捌きが見えるときです。もちろん、脚本家の仕事を否定してるわけじゃありません。結局、脚本の「てにをは」みたいなものに縛られすぎると、そういうことが起きるんだと思います。世界がどうあるか、を考える以前に、脚本とは、映画とはこうあるべきだ、という観念が優先されてしまう。それをベースにして、ある人物の行動原理や全体の構成が作られてしまうのは問題があるんじゃないかという気がします。
――でも一方で、脚本の「てにをは」が杜撰な映画も数多くあります。だから、「てにをは」を踏まえたうえで、そこからはみ出すものを掴まえる努力をすべきだということですよね。
深田 もちろん、僕もまだまだそれを勉強中ですし、脚本を書くうえでの技術があるという大前提に立っての話ですよね。やっぱりそれが現代においてフィクションを作るうえでの態度だと思うんですよ。ベタな例えですけど、かつて前衛と呼ばれていたピカソにしても、最初に基本となる絵画理論やデッサンを学んだうえで、それを壊しながら「世界はこう見えてもいいんじゃないか」という形で描いていった。それが二十世紀初頭の話なわけですからね。脚本の「てにをは」というのは、ピカソが壊したデッサン程度のものじゃないかなという気がします。デッサンが大事だというのは大前提だけれども、それがゴールでは全くないということですよね。
――もう少しシナリオの話を伺いたいんですが、『歓待』の完成台本を読むと「第一幕」「第二幕」「第三幕」と分けられています。これは戯曲の体裁ですよね?
深田 いや、構成が考えやすくなるから単純に目安として書き込んでるだけなんです。あれは戯曲じゃなくて、シド・フィールドなんですよ。
――ああ、そっちですか。
深田 シド・フィールドが、映画というのは起承転結の四幕じゃなくて、実は三幕が基本なんだと言っていて、その教えは律儀に守っていたりします。三幕物として構想して、最終的に三幕じゃなくなることもあるんですけど、自分のなかで構成を考えやすくなるという理由から、強引に三幕で規定しちゃうんですね。なんか、さっき言ってることと矛盾してるみたいですけど(笑)。
――それは面白い話ですよね。シド・フィールドが書いてることは脚本の「てにをは」じゃないですか。深田さんもそこは押さえたうえで、そこで囚われちゃいけないと言ってるわけでしょう。
深田 学生時代に脚本書こうと思って、全然分かんねえやと。それで、とりあえずシド・フィールドを読むってことをやってたんで・・・。そのやり方を否定する人たちも多いし、その通りにやって面白い映画になる保証は全然ないんだけど、映画を三幕物として捉えるというのは、単純に考えやすいからいつもやってますね。
 ――あと、さっき「諦めに近い肯定」と言ってましたけど、深田さんの映画にはある種の諦観が通底してますよね。そこにとてもシンパシーを感じるんです。安易な希望や救済は描かないという姿勢が一貫していると思います。
深田 映画というのは、その作家の世界観がどうしようもなく出てしまうものだと思うので、当然、そこに自分の世界観が反映されてると思うんですけど・・・。実は5月1日に『椅子』(02)という映画を紀伊國屋ホールで再上映させてもらったんですね。それを2004年にアップリンク・ファクトリーで上映したときに、作品解説としてテーマのようなものを書いたんですよ。それが、『ざくろ屋敷』(06)『東京人間喜劇』(09)『歓待』とも一緒だったんですよね。
そこで何を書いていたかというと、現代の物語=虚構において救済=ハッピー・エンドがいかにして成り立つのか、という問題意識なんです。結局、ぼくにとってはそれが一番の関心事なんですけど、ある物語のなかに障壁――シド・フィールドは「葛藤」と言ってましたけど――が設定されて、登場人物がそれを乗り越えられるか、乗り越えられないかによって、その物語がハッピー・エンドなり悲劇的な結末なりに導かれていく。でも、全てがフィクションであると知り尽くしている現代の観客にとって、それがどれだけリアルに響くんだろうと。そういう物語のほうが、共感を誘いつつ強いカタルシスを与えると思うんですけど、その共感やカタルシスの飛距離、というか持続力はすごく短いと思うんですよね。そういった高揚感は、劇場を出た後に家まで持ち帰れるようなものではないような気がするんです。じゃあ、どうしたらスクリーンとお客さんの間にある垣根を越えることができるんだろうと考えました。結局、人が救われるか救われないかなんて誰にも分からない、だけどその可能性は世界に偏在しているわけで、その可能性もひっくるめた世界観をスクリーンにただ投げ出して見せることぐらいだと思うんですよ。現代の物語作家が提示できるせめてものハッピー・エンドは倫理的にもそういうものじゃないかという気がします。
ぼくの場合は、それが上手くできていないということが、常に新作を作るうえでのモチベーションになっていて、たぶん『歓待』のラストにあるインコのくだりも、そういうところから発想されたんじゃないかなと思います。やっぱり物語が救済に至るまでに努力が介在しないほうが好きなんですよね。努力して救われたからって何なの?!って思いますから(笑)。
――映芸シネマテークで『東京人間喜劇』を上映させてもらったときに、深田さんが「ダメな人間にもいいところがあるじゃん」というところに救いを見出したくない、その人のパーソナリティに関係なく、全ての人間に救われる権利がある、と言ってたことが印象的でした。
深田 逆に言うと、どんなに聖人君子でも救われないかもしれない。ある人が救われるか救われないか分からないというのは、枝から落ちた木の葉がどこに着地するか分からないというのと同じだと思うんですよ。そこに努力が介在する余地はない。いいことしたからといって救われるわけではないし、悪いことをしても救われてしまう人がいる。一種のペシミズムかもしれないけれども、それが希望とも言えるんじゃないかと思います。
――さっきの審美眼を疑うという話じゃないですけど、とにかく世界をフラットに、ニュートラルに見たいという意志なんですかね。
深田 なんでしょうね。ぼくは映画を作るときに、全ての人間には価値があるんだ、というところから出発できなくて、全ての人間には価値がないんだ、というところからいつもスタートしてしまうんです。そこが何か関係してるのかもしれません。
――話は変わりますけど、深田さんは映芸のサイトで「映画と労働を考える」という連載も書いてますし、「ムービー・ユニオン」という労働組合にも発足メンバーの一人として所属しています。そうした活動が『歓待』という映画に影響したところもあったんでしょうか。
深田 自分としては、そこまで意識的にやってるわけじゃないんです。まず、社会派の映画を作りたいとは全く思ってないですし、基本的には100年後も残るような映画をという思いで作っています。今回は不法滞在の外国人とか浮浪者の問題が分かりやすい形で出てきてるけど、映画にああいうモチーフが必要だとは全く思っていません。ただ、映画というものは現代の社会に生きている人間が、現代の社会に三脚を置いてカメラを向けるわけだから、当然そこで出来上がる映画も、被写体である社会とどこかで繋がっていたほうがいいんじゃないかと思っています。コメディだろうが、恋愛劇だろうが、そこと地続きと考えて作るほうが自然な態度だと思うんです。その現代性というのは100年後には忘れ去られてしまうかもしれないけど、映画の普遍的な面白さはそういう要素と共存できると思うし、それが上手く共存してる映画を作りたいなとは思ってますね。
――やはり、『歓待』の面白さの一つは、家族のプライベートな話が、共同体という社会的な視点で捉え直されているところにあると思うんです。その辺りはどの程度、自覚的だったんですか。
深田 どうなんでしょうね。これはぼくが大阪のシネドライヴに参加したときにも作家たちの間で議論になっていたことなんですけど、映画の作り手が半径30メートル以内でドラマを作ってるんじゃないかと。そういうところへの批判意識を持ってる人は同世代の作り手のなかにもいるみたいなんですが、ぼくも自分の目に映っている世界のなかでだけドラマを作るのはどうなのかなって思うんですよ。
60~70年代の政治闘争の時代を経て、90年代以降にもなると、世の中なんて結局変わらないし、自分たちが生きる大きな目的も持てないし、変革すべき問題もないし・・・みたいな虚無感があったけど、それは本当なんだろうかと。ちょっと見渡してみれば、日本という国には社会問題が山ほどあるんですよね、『歓待』にも繋がる移民、難民の問題もそうですけど、映画の作り手にとって世界はいわば題材の宝庫なんです。だから、そっちに目を向けたほうが面白い映画が作れるじゃないかとは単純に思いますね。
――ぼくは78年生まれですけど、政治運動の挫折も経済発展の限界も知ってるような気になっちゃってるんですよね。だから、自分の実感が全てということになりやすい。それで90年代に、例えば諏訪(敦彦)さんが作るような映画を見て、非常に感化されるわけですよね。「大きな物語」を語らなくてもいいじゃないかって。
深田 それはやっぱり、高度経済成長期なんかに掲げられていた大きな目標、大きな物語というものが、人生を懸けるほどのものではなかったということが露呈しまったからじゃないですか。実際は知らないですよ、ぼくも80年生まれなんで。ただ、ぼくの実感としても、10代、20代のときにそういった大きな目標というのは持てなかったし、今も持てていない。だから、そもそも大きな物語なんて必要ない、そんなものはないんだと思っていたほうがいいと思ってるんですね。
例えば、難民や移民の問題にしても、まるで“大きな”問題であるかのように感じてしまうんですけど、細部を見ていけばもっと単純な話なんですよ。普通に生きていたら外国人の友人が出来たりもするわけで、その友人が差別を受けたりする、そこでどうするんだというところまで引き寄せればいい。そうなると、社会的な問題である前に、友人の問題、人間関係の問題になるんですよ。そういうミクロの問題の集積が大きな全体を作っているだけであって、そのミクロの問題を見る前に、大きな問題として語るのは危険だと思います。
――あと、さっき「諦めに近い肯定」と言ってましたけど、深田さんの映画にはある種の諦観が通底してますよね。そこにとてもシンパシーを感じるんです。安易な希望や救済は描かないという姿勢が一貫していると思います。
深田 映画というのは、その作家の世界観がどうしようもなく出てしまうものだと思うので、当然、そこに自分の世界観が反映されてると思うんですけど・・・。実は5月1日に『椅子』(02)という映画を紀伊國屋ホールで再上映させてもらったんですね。それを2004年にアップリンク・ファクトリーで上映したときに、作品解説としてテーマのようなものを書いたんですよ。それが、『ざくろ屋敷』(06)『東京人間喜劇』(09)『歓待』とも一緒だったんですよね。
そこで何を書いていたかというと、現代の物語=虚構において救済=ハッピー・エンドがいかにして成り立つのか、という問題意識なんです。結局、ぼくにとってはそれが一番の関心事なんですけど、ある物語のなかに障壁――シド・フィールドは「葛藤」と言ってましたけど――が設定されて、登場人物がそれを乗り越えられるか、乗り越えられないかによって、その物語がハッピー・エンドなり悲劇的な結末なりに導かれていく。でも、全てがフィクションであると知り尽くしている現代の観客にとって、それがどれだけリアルに響くんだろうと。そういう物語のほうが、共感を誘いつつ強いカタルシスを与えると思うんですけど、その共感やカタルシスの飛距離、というか持続力はすごく短いと思うんですよね。そういった高揚感は、劇場を出た後に家まで持ち帰れるようなものではないような気がするんです。じゃあ、どうしたらスクリーンとお客さんの間にある垣根を越えることができるんだろうと考えました。結局、人が救われるか救われないかなんて誰にも分からない、だけどその可能性は世界に偏在しているわけで、その可能性もひっくるめた世界観をスクリーンにただ投げ出して見せることぐらいだと思うんですよ。現代の物語作家が提示できるせめてものハッピー・エンドは倫理的にもそういうものじゃないかという気がします。
ぼくの場合は、それが上手くできていないということが、常に新作を作るうえでのモチベーションになっていて、たぶん『歓待』のラストにあるインコのくだりも、そういうところから発想されたんじゃないかなと思います。やっぱり物語が救済に至るまでに努力が介在しないほうが好きなんですよね。努力して救われたからって何なの?!って思いますから(笑)。
――映芸シネマテークで『東京人間喜劇』を上映させてもらったときに、深田さんが「ダメな人間にもいいところがあるじゃん」というところに救いを見出したくない、その人のパーソナリティに関係なく、全ての人間に救われる権利がある、と言ってたことが印象的でした。
深田 逆に言うと、どんなに聖人君子でも救われないかもしれない。ある人が救われるか救われないか分からないというのは、枝から落ちた木の葉がどこに着地するか分からないというのと同じだと思うんですよ。そこに努力が介在する余地はない。いいことしたからといって救われるわけではないし、悪いことをしても救われてしまう人がいる。一種のペシミズムかもしれないけれども、それが希望とも言えるんじゃないかと思います。
――さっきの審美眼を疑うという話じゃないですけど、とにかく世界をフラットに、ニュートラルに見たいという意志なんですかね。
深田 なんでしょうね。ぼくは映画を作るときに、全ての人間には価値があるんだ、というところから出発できなくて、全ての人間には価値がないんだ、というところからいつもスタートしてしまうんです。そこが何か関係してるのかもしれません。
――話は変わりますけど、深田さんは映芸のサイトで「映画と労働を考える」という連載も書いてますし、「ムービー・ユニオン」という労働組合にも発足メンバーの一人として所属しています。そうした活動が『歓待』という映画に影響したところもあったんでしょうか。
深田 自分としては、そこまで意識的にやってるわけじゃないんです。まず、社会派の映画を作りたいとは全く思ってないですし、基本的には100年後も残るような映画をという思いで作っています。今回は不法滞在の外国人とか浮浪者の問題が分かりやすい形で出てきてるけど、映画にああいうモチーフが必要だとは全く思っていません。ただ、映画というものは現代の社会に生きている人間が、現代の社会に三脚を置いてカメラを向けるわけだから、当然そこで出来上がる映画も、被写体である社会とどこかで繋がっていたほうがいいんじゃないかと思っています。コメディだろうが、恋愛劇だろうが、そこと地続きと考えて作るほうが自然な態度だと思うんです。その現代性というのは100年後には忘れ去られてしまうかもしれないけど、映画の普遍的な面白さはそういう要素と共存できると思うし、それが上手く共存してる映画を作りたいなとは思ってますね。
――やはり、『歓待』の面白さの一つは、家族のプライベートな話が、共同体という社会的な視点で捉え直されているところにあると思うんです。その辺りはどの程度、自覚的だったんですか。
深田 どうなんでしょうね。これはぼくが大阪のシネドライヴに参加したときにも作家たちの間で議論になっていたことなんですけど、映画の作り手が半径30メートル以内でドラマを作ってるんじゃないかと。そういうところへの批判意識を持ってる人は同世代の作り手のなかにもいるみたいなんですが、ぼくも自分の目に映っている世界のなかでだけドラマを作るのはどうなのかなって思うんですよ。
60~70年代の政治闘争の時代を経て、90年代以降にもなると、世の中なんて結局変わらないし、自分たちが生きる大きな目的も持てないし、変革すべき問題もないし・・・みたいな虚無感があったけど、それは本当なんだろうかと。ちょっと見渡してみれば、日本という国には社会問題が山ほどあるんですよね、『歓待』にも繋がる移民、難民の問題もそうですけど、映画の作り手にとって世界はいわば題材の宝庫なんです。だから、そっちに目を向けたほうが面白い映画が作れるじゃないかとは単純に思いますね。
――ぼくは78年生まれですけど、政治運動の挫折も経済発展の限界も知ってるような気になっちゃってるんですよね。だから、自分の実感が全てということになりやすい。それで90年代に、例えば諏訪(敦彦)さんが作るような映画を見て、非常に感化されるわけですよね。「大きな物語」を語らなくてもいいじゃないかって。
深田 それはやっぱり、高度経済成長期なんかに掲げられていた大きな目標、大きな物語というものが、人生を懸けるほどのものではなかったということが露呈しまったからじゃないですか。実際は知らないですよ、ぼくも80年生まれなんで。ただ、ぼくの実感としても、10代、20代のときにそういった大きな目標というのは持てなかったし、今も持てていない。だから、そもそも大きな物語なんて必要ない、そんなものはないんだと思っていたほうがいいと思ってるんですね。
例えば、難民や移民の問題にしても、まるで“大きな”問題であるかのように感じてしまうんですけど、細部を見ていけばもっと単純な話なんですよ。普通に生きていたら外国人の友人が出来たりもするわけで、その友人が差別を受けたりする、そこでどうするんだというところまで引き寄せればいい。そうなると、社会的な問題である前に、友人の問題、人間関係の問題になるんですよ。そういうミクロの問題の集積が大きな全体を作っているだけであって、そのミクロの問題を見る前に、大きな問題として語るのは危険だと思います。
 ――この映画における共同体の問題は、小さな物語として、友人関係の問題として語られてるわけですね。だから、最後に幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う。夏希にとって幹夫が他者であるのと同じレベルで、二人にとって加川やアナベルが他者であるということが語られているということですよね。
深田 そうですね。外国人だと価値観が当然違うから、個人と他者との軋轢は起きやすくなると思うんですけど、日本人同士でも価値観の違いによる他者との軋轢はあるわけで、程度が違うだけなんですよね。ただ、外国人の問題となるとえたいの知れない不安感があるから、本来ならコミュニケーションによって解決されるべき問題が、違う仕方で決着されてしまう。例えば、トラブルが起きたら即警察を呼んでしまったり、不動産屋が外国人の入居を断ってしまったり、いろんなところに現われてると思うんですよ。それをもっと、個人と他者の問題として捉え直したほうがいいんじゃないかということですね。
――今の話でかなり納得できました。ただ、聞きながら思ったのは、大きな物語を語っていた時代というのは、国家とか権力とか、いわば制度やシステムを「敵」と見なしていたわけですよね。社会的な問題を個人と他者の問題として捉え直すだけになると、制度やシステム自体がはらむ問題は看過されてしまうことにならないですか。
深田 本来、民主主義である以上、国家のシステムも小さいことの集積で成り立つべきものだと思います。たしかに、国家は巨大な権力であって、国家によって個人が押し潰されてしまうという事態は現在進行形で起きてますよね、司法制度の歪みとか、不透明な政策決定システムの横行とか、いろんな形で起きている。でも、そういった問題も結局は個人個人が問いただしていくしかないと思うんです。
今回の震災で明らかになったのは、原発という制度を見過ごしてきたのは結局、日本の国民だということですよね。選挙権のある全ての国民が、誰かの犠牲のうえに成り立つ原発の推進を見過ごしてきた加担者なんですよ。だから、国家が国民と全く関係のないところで暴走していると言う前に、多くの人が選挙権を放棄した結果、与党が是認され、ああいう問題が一見国民と関係ないところで進んでしまったということを忘れてはいけない。だから、国家と個人を切り離してしまう考え方はとても危険だと思います。
これは「映画と労働を考える」にも書きましたけど、じゃあ税金をどう考えるのかというところで、文化予算をもらって何か芸術活動をするということに対して、それは国家からお金をもらってるのかといったら、そうじゃない。その元になっている税金は、「国家のお金」じゃなくて、「みんなのお金」なんですよね。みんなのお金の使い方をみんなで考えましょうというのが結果として政策になる。それは文化予算の使い途に限らず、全ての政策がそうなんですよね。本来、お上から政策が下りてきて、それに従うか反発するかしかないという話じゃなくて、政策決定システムそのものにも個人が絡んでいるわけです。だからまあ、例えば投票率が90パーセントぐらいになれば、何か見え方が変わってくるんじゃないですかね。今の日本の現状からすると、ものすごく甘っちょろい理想論ですけど。
――演出の話も聞いておきたいんですけど、映芸シネマテークのときに稲川(方人)さんが言っていて、ぼくもなるほどなと思ったのは、『東京人間喜劇』の演出が一貫してないんじゃないかという指摘だったんです。大雑把に言ってしまうと、演出にはフィクショナルなものと、リアリズムのものがあると思いますが、『~人間喜劇』はリアリズムの演出を推し進めつつ、そこで様々な試行錯誤が行われている。その試行錯誤を稲川さんは「一貫性がない」と言ったんだと思います。でも『歓待』を見ると、撮影も俳優の演技も割合パキっとしていて、フィクショナルなほうに寄せられているように感じました。
深田 演出に当たるうえでは、いつも「今回はこういう方針で行こう」と決めてるわけじゃなくて、現場の流れもあるんですけど、まず題材に見合った方法論があるだろうと。題材が違えば、当然、演出のスタイルも違ってくるということがあると思います。
今回に関しては――これは『ざくろ屋敷』も『東京人間喜劇』も一貫してるつもりなんですけど――映像的な装飾記号をできるだけ排除したいと思っていました。例えばですが、カメラ位置を低くしてアオリにすると、一見迫力のあるカッコいい映像になるけど、必然性もなくそういう小銭を稼ぐようなことはやらないとか。アオリの絵がダメということではなく、被写体とカメラの関係が濁るようなことはしたくない、ということです。
あるいは、映画的だと思われているアクション、カッコつきの「映画的」なもの、そういったものをできるだけ映画から排除して、それでも残る映画的なものって何だろうということを実践したつもりなんです。だから、時々『歓待』がウエルメイドな映画だと言われることには異論があるんです。ぼくとしては、今の日本映画の状況であれをやることは大きな冒険だと思ってるんですね。・・・すいません、冒険というのは少しカッコつけすぎました(笑)。「試み」だと思ってるんで・・・。
――身も蓋もない質問ですが、それでも残った映画的なものって何だったんですか(笑)?
深田 何なんでしょうね(笑)。ぼくは、それが立ち上がると思って脚本を書いて作ってるんですけど。
――以前、印刷機、輪転機の存在が非常に映画的だと言ってましたよね。そこで言う「映画的」ってどういうことなのか聞いてみたかったんですけど。
深田 そうですよね、「映画的」問題ってあると思うんですけど・・・(笑)。ぼくも「映画芸術DIARY」に映画評を書くときは「映画的」という言葉をなるべく使わないようにしてるんですけど、それを具体的に言うのは難しいんですよね。
自分は中学3年ぐらいから古典映画を中心に年間数百本とか見るようになって、そのなかで「これは映画的だ」「これは映画的じゃない」という価値判断が出来たような気がしちゃうんですよね。でも、そこで言う「映画的」って上手く言語化できないんですよ。例えば、トリュフォーの『あこがれ』(58)という映画で若い女性が自転車を漕いで坂を下りてくる映像はすごく映画的だなと思って興奮するんですけど、一方でビリー・ワイルダーの『七年目の浮気』(55)なんかを見たときに、これは映画的だと思って興奮する瞬間が全く訪れない。それがどうしてなのかというのは上手く言語化できないんです。
ぼくのなかで無理やり言語化すると、被写体をモチーフとして捉えられているかどうかなんだと思います。物語を効率良く語っていくための情報でしかない映像か、物語の歯車である以前にカメラの前にあるモチーフとして捉えられている映像かという違いじゃないかなと。
ただ一方で、そうした「映画的」な映像があまりにも記号的に流通してるんじゃないかというのも感じていて。例えば走ってる人間を横移動で撮ると映画的に見える、たしかに映画的な映像の記号として気持ちいいと思うんですけど、そういったものの安易な積み重ねだけで映画が成り立ってしまうことへの危惧も一方にあって、そうした映像を一切入れなくとも、映画が映画的になるということをやろうとしてるんです。でも、そうすると「演劇っぽい」とか「映像でやる意味がない」とか「単調だ」とか言われちゃって、ショボンとしちゃったりするんですけど(笑)。
――この映画における共同体の問題は、小さな物語として、友人関係の問題として語られてるわけですね。だから、最後に幹夫が「友達の悪口は言わないでください」と言う。夏希にとって幹夫が他者であるのと同じレベルで、二人にとって加川やアナベルが他者であるということが語られているということですよね。
深田 そうですね。外国人だと価値観が当然違うから、個人と他者との軋轢は起きやすくなると思うんですけど、日本人同士でも価値観の違いによる他者との軋轢はあるわけで、程度が違うだけなんですよね。ただ、外国人の問題となるとえたいの知れない不安感があるから、本来ならコミュニケーションによって解決されるべき問題が、違う仕方で決着されてしまう。例えば、トラブルが起きたら即警察を呼んでしまったり、不動産屋が外国人の入居を断ってしまったり、いろんなところに現われてると思うんですよ。それをもっと、個人と他者の問題として捉え直したほうがいいんじゃないかということですね。
――今の話でかなり納得できました。ただ、聞きながら思ったのは、大きな物語を語っていた時代というのは、国家とか権力とか、いわば制度やシステムを「敵」と見なしていたわけですよね。社会的な問題を個人と他者の問題として捉え直すだけになると、制度やシステム自体がはらむ問題は看過されてしまうことにならないですか。
深田 本来、民主主義である以上、国家のシステムも小さいことの集積で成り立つべきものだと思います。たしかに、国家は巨大な権力であって、国家によって個人が押し潰されてしまうという事態は現在進行形で起きてますよね、司法制度の歪みとか、不透明な政策決定システムの横行とか、いろんな形で起きている。でも、そういった問題も結局は個人個人が問いただしていくしかないと思うんです。
今回の震災で明らかになったのは、原発という制度を見過ごしてきたのは結局、日本の国民だということですよね。選挙権のある全ての国民が、誰かの犠牲のうえに成り立つ原発の推進を見過ごしてきた加担者なんですよ。だから、国家が国民と全く関係のないところで暴走していると言う前に、多くの人が選挙権を放棄した結果、与党が是認され、ああいう問題が一見国民と関係ないところで進んでしまったということを忘れてはいけない。だから、国家と個人を切り離してしまう考え方はとても危険だと思います。
これは「映画と労働を考える」にも書きましたけど、じゃあ税金をどう考えるのかというところで、文化予算をもらって何か芸術活動をするということに対して、それは国家からお金をもらってるのかといったら、そうじゃない。その元になっている税金は、「国家のお金」じゃなくて、「みんなのお金」なんですよね。みんなのお金の使い方をみんなで考えましょうというのが結果として政策になる。それは文化予算の使い途に限らず、全ての政策がそうなんですよね。本来、お上から政策が下りてきて、それに従うか反発するかしかないという話じゃなくて、政策決定システムそのものにも個人が絡んでいるわけです。だからまあ、例えば投票率が90パーセントぐらいになれば、何か見え方が変わってくるんじゃないですかね。今の日本の現状からすると、ものすごく甘っちょろい理想論ですけど。
――演出の話も聞いておきたいんですけど、映芸シネマテークのときに稲川(方人)さんが言っていて、ぼくもなるほどなと思ったのは、『東京人間喜劇』の演出が一貫してないんじゃないかという指摘だったんです。大雑把に言ってしまうと、演出にはフィクショナルなものと、リアリズムのものがあると思いますが、『~人間喜劇』はリアリズムの演出を推し進めつつ、そこで様々な試行錯誤が行われている。その試行錯誤を稲川さんは「一貫性がない」と言ったんだと思います。でも『歓待』を見ると、撮影も俳優の演技も割合パキっとしていて、フィクショナルなほうに寄せられているように感じました。
深田 演出に当たるうえでは、いつも「今回はこういう方針で行こう」と決めてるわけじゃなくて、現場の流れもあるんですけど、まず題材に見合った方法論があるだろうと。題材が違えば、当然、演出のスタイルも違ってくるということがあると思います。
今回に関しては――これは『ざくろ屋敷』も『東京人間喜劇』も一貫してるつもりなんですけど――映像的な装飾記号をできるだけ排除したいと思っていました。例えばですが、カメラ位置を低くしてアオリにすると、一見迫力のあるカッコいい映像になるけど、必然性もなくそういう小銭を稼ぐようなことはやらないとか。アオリの絵がダメということではなく、被写体とカメラの関係が濁るようなことはしたくない、ということです。
あるいは、映画的だと思われているアクション、カッコつきの「映画的」なもの、そういったものをできるだけ映画から排除して、それでも残る映画的なものって何だろうということを実践したつもりなんです。だから、時々『歓待』がウエルメイドな映画だと言われることには異論があるんです。ぼくとしては、今の日本映画の状況であれをやることは大きな冒険だと思ってるんですね。・・・すいません、冒険というのは少しカッコつけすぎました(笑)。「試み」だと思ってるんで・・・。
――身も蓋もない質問ですが、それでも残った映画的なものって何だったんですか(笑)?
深田 何なんでしょうね(笑)。ぼくは、それが立ち上がると思って脚本を書いて作ってるんですけど。
――以前、印刷機、輪転機の存在が非常に映画的だと言ってましたよね。そこで言う「映画的」ってどういうことなのか聞いてみたかったんですけど。
深田 そうですよね、「映画的」問題ってあると思うんですけど・・・(笑)。ぼくも「映画芸術DIARY」に映画評を書くときは「映画的」という言葉をなるべく使わないようにしてるんですけど、それを具体的に言うのは難しいんですよね。
自分は中学3年ぐらいから古典映画を中心に年間数百本とか見るようになって、そのなかで「これは映画的だ」「これは映画的じゃない」という価値判断が出来たような気がしちゃうんですよね。でも、そこで言う「映画的」って上手く言語化できないんですよ。例えば、トリュフォーの『あこがれ』(58)という映画で若い女性が自転車を漕いで坂を下りてくる映像はすごく映画的だなと思って興奮するんですけど、一方でビリー・ワイルダーの『七年目の浮気』(55)なんかを見たときに、これは映画的だと思って興奮する瞬間が全く訪れない。それがどうしてなのかというのは上手く言語化できないんです。
ぼくのなかで無理やり言語化すると、被写体をモチーフとして捉えられているかどうかなんだと思います。物語を効率良く語っていくための情報でしかない映像か、物語の歯車である以前にカメラの前にあるモチーフとして捉えられている映像かという違いじゃないかなと。
ただ一方で、そうした「映画的」な映像があまりにも記号的に流通してるんじゃないかというのも感じていて。例えば走ってる人間を横移動で撮ると映画的に見える、たしかに映画的な映像の記号として気持ちいいと思うんですけど、そういったものの安易な積み重ねだけで映画が成り立ってしまうことへの危惧も一方にあって、そうした映像を一切入れなくとも、映画が映画的になるということをやろうとしてるんです。でも、そうすると「演劇っぽい」とか「映像でやる意味がない」とか「単調だ」とか言われちゃって、ショボンとしちゃったりするんですけど(笑)。
 ――輪転機が映画的であるというのも、背景に列車が通り過ぎるのと同じように、物語の歯車ではないアクションが自律しているからということになるんですかね。
深田 ただ、輪転機に関して思い出されるのはハリウッド映画なわけですよ。『市民ケーン』(41)もそうですし、多くのフィルム・ノワールで何か事件が起きると、輪転機が回って事件を伝える新聞記事が映し出される。だから、蓮實センセイはウディ・アレンの『カメレオンマン』(83)は輪転機の回転速度が遅すぎるからダメだと言ったりするわけですよね。そういうものを見たり読んだりするうちに、「輪転機、スゲーな」となるわけです(笑)。それで今回、映画を作るうえでの足がかりとして輪転機を置いたんですけど、「輪転」が『歓待』に変わっていくなかで、輪転機のイメージは後退しちゃったので、あんまりちゃんと撮れなかったですね。
ロケハンでも印刷所を見つけるのが大変で、スタッフから「これ、ダンボール工場とかでもいいよね」とか言われて(笑)、たしかに言われてみると、そこが印刷所じゃなきゃいけない理由はもうないなと。タイトルも「輪転」ではなくなってましたから。それで、「見つかんなかったら、ダンボール工場でもいいよ」とか言ってしまったり。最終的にはとてもいい場所が見つかったものの、もう少し輪転機で映像的な遊びができたら良かったんですけど、そんな時間的余裕は全然なかったですね。
――もう一つ、演出面のことを伺いたいんですが、今回は日本家屋をいかに撮るかということが、演出上の大きな課題だったんじゃないですか。
深田 仕事場と居間が一続きになってる日本家屋というのは、昔の日本映画のなかによく見かける光景で、ぼくとしては馴染みやすい空間でした。
ただ、日本家屋という空間をどう切り取っていくか、それを考えるうえでぼくはそんなに選択肢があるとは思ってないんです。ぼくが普通に見てきた映画、例えば成瀬巳喜男が居間をどう撮っていたか、そういうイメージがポンポンと一つの雛形として思い浮かぶんですけど、しかし中古智さんが設計したスタジオの居間とロケセットで見つけてきた居間では全然違うわけですね。ロケセットの家はものすごく狭くて、カメラを置く場所も非常に限られるから、どうしたって同じようには撮れないんですよ。
だから、問題は日本家屋をどう撮るかというよりも、例えばちゃぶ台に座っている人たちをどう撮るか、つまり日本家屋の構造が規定するコミュニケーションのあり方やそこから導き出される身体性のモチーフをどう撮るかという選択にあるんだと思います。
――とはいえ、物語的には共同体のテーマがあるので、仕事場と居間が繋がってるとか、隣の部屋とは襖一枚でしか隔てられていないといった日本家屋の構造が重要だったんじゃないですか。
深田 それは決定的にありますね。ああいう下町の家の特徴は、道と家の入口の間に垣根がないんですよ、壁も塀もない。町内会のオバチャンが「こんちは~」っていきなり入ってこれてしまう。つまり、公共の空間とプライベートな空間がいきなり接続されているわけです。だから、従業員やインク業者、町内会のオバチャンといった外部の人間が、あの印刷所で交じり合う。
あと、居候としてやってきた加川夫婦の生活が主人公夫婦の生活に影響してくるということがやりたかったので、部屋の境界が曖昧であるということも意識してました。幹夫と夏希が寝てる隣の部屋から、アナベルの喘ぎ声が聞こえてくるシーンとかは特にそうなんですけど。結果的に、日本家屋という舞台が逆に物語を規定するところもありますよね。
――最後に製作体制の話も聞かせてください。深田さんの独自性の一つに、劇団「青年団」の演出部に所属しながら、自主映画とも商業映画とも違う体制で映画を作られているということがあると思います。『東京人間喜劇』はキャストが青年団の俳優でスタッフは身内、いわば自主映画に近かったわけですよね。今回はプロデューサーが付いて、スタッフもプロの方が担当されています。その辺りの体制の変化についてはどう感じましたか。
深田 『歓待』の現場は、撮影監督も助監督もライン・プロデューサーもみんなプロの人たちで、ぼくよりもずっと現場経験が豊富で優秀な方々に支えてもらいました。そのおかげで実質8日間の撮影でも徹夜せずに撮り終えられた。
ただ一方で感じるのは、映像のスタッフのなかで、「映画はこうあるべき」「演技はこうあるべき」という固定観念はものすごいなと。良くも悪くも、そういうものが染み付いてしまっている。そこを変えていくのは、すごく大変な作業だなというのは感じました。
――いきなり周りのスピードがそこまで上がると、深田さん自身が現場で追い込まれるんじゃないですか(笑)。
深田 いやあ、追い込まれましたよ(笑)。現場は時間との闘いでしたから、NGが2テイクを超え始めると、周りからのプレッシャーがすごいんですよ。「またNG出すつもり?」って。大抵、監督が出す細かいNGなんて、周りから見たら「どこが違うのか分かんない」と言われるぐらいのものですからね(笑)。
「あの芝居もうちょっとタイミング遅くしたいんだけど、言える空気じゃないな、どうしようかな」と思ってたところで、録音さんが「すいません、飛行機の音、入りました」とか言うと、「しょうがないなあ。じゃあ、もう1テイクやろうか」とか言って乗っかるわけです。だから、演出的に直したいところがあるときは、技術部のミスを期待してる自分がいましたね(笑)。
――輪転機が映画的であるというのも、背景に列車が通り過ぎるのと同じように、物語の歯車ではないアクションが自律しているからということになるんですかね。
深田 ただ、輪転機に関して思い出されるのはハリウッド映画なわけですよ。『市民ケーン』(41)もそうですし、多くのフィルム・ノワールで何か事件が起きると、輪転機が回って事件を伝える新聞記事が映し出される。だから、蓮實センセイはウディ・アレンの『カメレオンマン』(83)は輪転機の回転速度が遅すぎるからダメだと言ったりするわけですよね。そういうものを見たり読んだりするうちに、「輪転機、スゲーな」となるわけです(笑)。それで今回、映画を作るうえでの足がかりとして輪転機を置いたんですけど、「輪転」が『歓待』に変わっていくなかで、輪転機のイメージは後退しちゃったので、あんまりちゃんと撮れなかったですね。
ロケハンでも印刷所を見つけるのが大変で、スタッフから「これ、ダンボール工場とかでもいいよね」とか言われて(笑)、たしかに言われてみると、そこが印刷所じゃなきゃいけない理由はもうないなと。タイトルも「輪転」ではなくなってましたから。それで、「見つかんなかったら、ダンボール工場でもいいよ」とか言ってしまったり。最終的にはとてもいい場所が見つかったものの、もう少し輪転機で映像的な遊びができたら良かったんですけど、そんな時間的余裕は全然なかったですね。
――もう一つ、演出面のことを伺いたいんですが、今回は日本家屋をいかに撮るかということが、演出上の大きな課題だったんじゃないですか。
深田 仕事場と居間が一続きになってる日本家屋というのは、昔の日本映画のなかによく見かける光景で、ぼくとしては馴染みやすい空間でした。
ただ、日本家屋という空間をどう切り取っていくか、それを考えるうえでぼくはそんなに選択肢があるとは思ってないんです。ぼくが普通に見てきた映画、例えば成瀬巳喜男が居間をどう撮っていたか、そういうイメージがポンポンと一つの雛形として思い浮かぶんですけど、しかし中古智さんが設計したスタジオの居間とロケセットで見つけてきた居間では全然違うわけですね。ロケセットの家はものすごく狭くて、カメラを置く場所も非常に限られるから、どうしたって同じようには撮れないんですよ。
だから、問題は日本家屋をどう撮るかというよりも、例えばちゃぶ台に座っている人たちをどう撮るか、つまり日本家屋の構造が規定するコミュニケーションのあり方やそこから導き出される身体性のモチーフをどう撮るかという選択にあるんだと思います。
――とはいえ、物語的には共同体のテーマがあるので、仕事場と居間が繋がってるとか、隣の部屋とは襖一枚でしか隔てられていないといった日本家屋の構造が重要だったんじゃないですか。
深田 それは決定的にありますね。ああいう下町の家の特徴は、道と家の入口の間に垣根がないんですよ、壁も塀もない。町内会のオバチャンが「こんちは~」っていきなり入ってこれてしまう。つまり、公共の空間とプライベートな空間がいきなり接続されているわけです。だから、従業員やインク業者、町内会のオバチャンといった外部の人間が、あの印刷所で交じり合う。
あと、居候としてやってきた加川夫婦の生活が主人公夫婦の生活に影響してくるということがやりたかったので、部屋の境界が曖昧であるということも意識してました。幹夫と夏希が寝てる隣の部屋から、アナベルの喘ぎ声が聞こえてくるシーンとかは特にそうなんですけど。結果的に、日本家屋という舞台が逆に物語を規定するところもありますよね。
――最後に製作体制の話も聞かせてください。深田さんの独自性の一つに、劇団「青年団」の演出部に所属しながら、自主映画とも商業映画とも違う体制で映画を作られているということがあると思います。『東京人間喜劇』はキャストが青年団の俳優でスタッフは身内、いわば自主映画に近かったわけですよね。今回はプロデューサーが付いて、スタッフもプロの方が担当されています。その辺りの体制の変化についてはどう感じましたか。
深田 『歓待』の現場は、撮影監督も助監督もライン・プロデューサーもみんなプロの人たちで、ぼくよりもずっと現場経験が豊富で優秀な方々に支えてもらいました。そのおかげで実質8日間の撮影でも徹夜せずに撮り終えられた。
ただ一方で感じるのは、映像のスタッフのなかで、「映画はこうあるべき」「演技はこうあるべき」という固定観念はものすごいなと。良くも悪くも、そういうものが染み付いてしまっている。そこを変えていくのは、すごく大変な作業だなというのは感じました。
――いきなり周りのスピードがそこまで上がると、深田さん自身が現場で追い込まれるんじゃないですか(笑)。
深田 いやあ、追い込まれましたよ(笑)。現場は時間との闘いでしたから、NGが2テイクを超え始めると、周りからのプレッシャーがすごいんですよ。「またNG出すつもり?」って。大抵、監督が出す細かいNGなんて、周りから見たら「どこが違うのか分かんない」と言われるぐらいのものですからね(笑)。
「あの芝居もうちょっとタイミング遅くしたいんだけど、言える空気じゃないな、どうしようかな」と思ってたところで、録音さんが「すいません、飛行機の音、入りました」とか言うと、「しょうがないなあ。じゃあ、もう1テイクやろうか」とか言って乗っかるわけです。だから、演出的に直したいところがあるときは、技術部のミスを期待してる自分がいましたね(笑)。
 ――俳優の演出にかけられる時間が短いわけですよね。リハーサルはしたんですか。
深田 今回はいろんな事情から、撮影前のリハーサルもほとんどできなかったんです。とはいえ、青年団の俳優が演じる役はほとんど当て書きだったし、この俳優さんならこのセリフをここまでのポテンシャルで演じてくれるだろうなという想像はついていました。あと、彼らは時間があると、現場で俳優同士がコミュニケーションを取って演技をどんどん組み立てていってくれるんです。だから、そこまで苦労することはありませんでした。
初めてお仕事する杉野さんとはリハーサル、というかどんな演技をする方なのか、ちゃんと知っておかなくちゃいけなかったんですけど、それができなかったので、シーンごとの優先順位を決めて、大事なところは時間をかけて撮影の合間にリハーサルをやるという形で進めていきました。これは他の監督もやってることだと思うんですけど、そういうふうに時間をなんとかやりくりしてましたね。でもやっぱり、最後のドンチャン騒ぎのシーンなんかは、10分でも15分でも延ばして、狂気に至るところまでやりたいと思っていたので、そこは少し残念に思ってます。
だから、低予算の早撮りというのはまあ、いいものではないなと。やっぱり既存の映画作りのシステムのいいところを継承しつつ、新しい製作システムを提案できるかどうかが重要だと思ってるんですけど、『歓待』ではそこまでは至れなかった。ただ、「青年団」の俳優たちが出ていることで、日本映画の固定化した演技の慣習というものに対して、こういうあり方もあるよという提案はできるかなと思ってます。
――今回の経験を活かして、次回作では何か新しい形で映画作りができるといいですよね。
深田 今の日本映画の状況が劇的に変わるわけではないし、ぼくはそのなかで映画を作らなくちゃいけないので、次回作ですぐに何か新しいシステムを提案できるとは思っていません。ただ、例えば日本では製作リスクが高すぎることによって、単純に作る側の自由や選択肢が狭められていますよね。キャスティング一つ取っても、この俳優を使わなくちゃいけないとか。脚本も、これじゃ当たらないからマス向けに分かりやすく作り直せとか、原作を使わなくちゃいけないとか。もちろん、そういった制約の中でなおかつ面白い映画を作り上げるプロの監督を尊敬しますし、完全な自由なんてありえませんが、しかし、そういった不自由に対して少しでも自由の領域を広げていくための運動は必要だと思います。
いろいろあると思うんですよ。例えば、外国の資本にもアプローチしていくとか。あるいは、ぼくの立場で言えば「青年団」にはアゴラ劇場という空間があるので、映画館で少し掛けてDVDにして終わりじゃなくて、もっと数年のスパンで上映を続けていくことも視野に入れていくとか。今できることはそれぐらいしかなくて、あとは本当に助成金とか全体のシステムを変えていくしかない。自分が今置かれた立場のなかでできることは限られていて、映画のスタッフが直面している犯罪的な労働問題を軽減しながら映画を作っていくこと、映画制作のシステムを変えていくことは、10年、20年かかる作業だと思います。なかなかいっぺんにはできないんですけど、それを並行して進めていければいいですね。
結局、局地戦をいつまでやってもしょうがないと思うんですよ。一般に受け入れられやすい作風でクオリティも高い、そういうものを作って経済的に回していける作家もいると思うんですけど、それもやっぱり局地戦であって、それをいかにして全体に敷衍させていけるかが大事なんですよね。要は、必ずしもマスに受け入れられないけれども支持者がいるという作品をサポートしていけるシステムを作っていかなければいけない。「映画と労働を考える」で紹介しているチケット税による資金の循環もそのためのアイディアのひとつですし、多様な映画を理解してもらうために観客、受け手の意識にも働きかけていく必要がある。例えばフランスでは、インディーズのマイナーな映画をゴールデンタイムの全国区の公共放送で日常的に見ることができる。そういうことは必ずしもありえないことではない。それを不可能だと思ってしまったら、絶対に成り立たないと思います。
――・・・まあ、それに向けて日々活動していくということですね!
深田 なんか最後がずいぶん投げやりに終わらせてないですか? もう疲れたって感じになってますけど(笑)。
映画『歓待』予告編
『歓待』
監督・脚本・編集:深田晃司
芸術監督:平田オリザ プロデューサー:杉野希妃
出演:山内健司 杉野希妃 古舘寛治 ブライアリー・ロング オノエリコ 兵藤公美
配給:和エンタテインメント
2010年/日本/96分/HDCAM/
(C)2010「歓待」製作委員会
公式サイト http://kantai-hospitalite.com/
〈公開劇場〉
【東京】
ヒューマントラストシネマ渋谷 4月23日
5月11日(水)~13日(金)20:10
5月14日(土)~20日(金)21:25
池袋シネマロサ 5月21日
5月21日(土)~ 10:30 / 20:30
【大阪】
テアトル梅田 5月14日
5月14日(土)〜 16:30
【京都】
みなみ会館 6月11日
【兵庫】
神戸元町映画館 7月下旬
【群馬】
シネマテークたかさき 夏
――俳優の演出にかけられる時間が短いわけですよね。リハーサルはしたんですか。
深田 今回はいろんな事情から、撮影前のリハーサルもほとんどできなかったんです。とはいえ、青年団の俳優が演じる役はほとんど当て書きだったし、この俳優さんならこのセリフをここまでのポテンシャルで演じてくれるだろうなという想像はついていました。あと、彼らは時間があると、現場で俳優同士がコミュニケーションを取って演技をどんどん組み立てていってくれるんです。だから、そこまで苦労することはありませんでした。
初めてお仕事する杉野さんとはリハーサル、というかどんな演技をする方なのか、ちゃんと知っておかなくちゃいけなかったんですけど、それができなかったので、シーンごとの優先順位を決めて、大事なところは時間をかけて撮影の合間にリハーサルをやるという形で進めていきました。これは他の監督もやってることだと思うんですけど、そういうふうに時間をなんとかやりくりしてましたね。でもやっぱり、最後のドンチャン騒ぎのシーンなんかは、10分でも15分でも延ばして、狂気に至るところまでやりたいと思っていたので、そこは少し残念に思ってます。
だから、低予算の早撮りというのはまあ、いいものではないなと。やっぱり既存の映画作りのシステムのいいところを継承しつつ、新しい製作システムを提案できるかどうかが重要だと思ってるんですけど、『歓待』ではそこまでは至れなかった。ただ、「青年団」の俳優たちが出ていることで、日本映画の固定化した演技の慣習というものに対して、こういうあり方もあるよという提案はできるかなと思ってます。
――今回の経験を活かして、次回作では何か新しい形で映画作りができるといいですよね。
深田 今の日本映画の状況が劇的に変わるわけではないし、ぼくはそのなかで映画を作らなくちゃいけないので、次回作ですぐに何か新しいシステムを提案できるとは思っていません。ただ、例えば日本では製作リスクが高すぎることによって、単純に作る側の自由や選択肢が狭められていますよね。キャスティング一つ取っても、この俳優を使わなくちゃいけないとか。脚本も、これじゃ当たらないからマス向けに分かりやすく作り直せとか、原作を使わなくちゃいけないとか。もちろん、そういった制約の中でなおかつ面白い映画を作り上げるプロの監督を尊敬しますし、完全な自由なんてありえませんが、しかし、そういった不自由に対して少しでも自由の領域を広げていくための運動は必要だと思います。
いろいろあると思うんですよ。例えば、外国の資本にもアプローチしていくとか。あるいは、ぼくの立場で言えば「青年団」にはアゴラ劇場という空間があるので、映画館で少し掛けてDVDにして終わりじゃなくて、もっと数年のスパンで上映を続けていくことも視野に入れていくとか。今できることはそれぐらいしかなくて、あとは本当に助成金とか全体のシステムを変えていくしかない。自分が今置かれた立場のなかでできることは限られていて、映画のスタッフが直面している犯罪的な労働問題を軽減しながら映画を作っていくこと、映画制作のシステムを変えていくことは、10年、20年かかる作業だと思います。なかなかいっぺんにはできないんですけど、それを並行して進めていければいいですね。
結局、局地戦をいつまでやってもしょうがないと思うんですよ。一般に受け入れられやすい作風でクオリティも高い、そういうものを作って経済的に回していける作家もいると思うんですけど、それもやっぱり局地戦であって、それをいかにして全体に敷衍させていけるかが大事なんですよね。要は、必ずしもマスに受け入れられないけれども支持者がいるという作品をサポートしていけるシステムを作っていかなければいけない。「映画と労働を考える」で紹介しているチケット税による資金の循環もそのためのアイディアのひとつですし、多様な映画を理解してもらうために観客、受け手の意識にも働きかけていく必要がある。例えばフランスでは、インディーズのマイナーな映画をゴールデンタイムの全国区の公共放送で日常的に見ることができる。そういうことは必ずしもありえないことではない。それを不可能だと思ってしまったら、絶対に成り立たないと思います。
――・・・まあ、それに向けて日々活動していくということですね!
深田 なんか最後がずいぶん投げやりに終わらせてないですか? もう疲れたって感じになってますけど(笑)。
映画『歓待』予告編
『歓待』
監督・脚本・編集:深田晃司
芸術監督:平田オリザ プロデューサー:杉野希妃
出演:山内健司 杉野希妃 古舘寛治 ブライアリー・ロング オノエリコ 兵藤公美
配給:和エンタテインメント
2010年/日本/96分/HDCAM/
(C)2010「歓待」製作委員会
公式サイト http://kantai-hospitalite.com/
〈公開劇場〉
【東京】
ヒューマントラストシネマ渋谷 4月23日
5月11日(水)~13日(金)20:10
5月14日(土)~20日(金)21:25
池袋シネマロサ 5月21日
5月21日(土)~ 10:30 / 20:30
【大阪】
テアトル梅田 5月14日
5月14日(土)〜 16:30
【京都】
みなみ会館 6月11日
【兵庫】
神戸元町映画館 7月下旬
【群馬】
シネマテークたかさき 夏